一人前の社会人を目指して
- 事業所名
- 株式会社グロップサンセリテ
- 所在地
- 岡山県岡山市
- 事業内容
- サービス業(事務処理業務、データ入力業務、清掃業務、リサイクル業務、テレマーケティング業務)
- 従業員数
- 37名
- うち障害者数
- 30名
障害 人数 従事業務 視覚障害 2 事務処理 聴覚障害 12 データ入力、総務・経理事務、清掃 肢体不自由 11 データ入力、事務処理、清掃、簡易印刷 内部障害 1 データ入力 知的障害 4 リサイクル業務、清掃 精神障害 0 - 目次

1. 障害者雇用の経緯・背景
株式会社グロップサンセリテは、株式会社グロップを親会社とする特例子会社で、2004年1月に設立した。当時、親会社では数名の障害者を雇用していたが、人材派遣業の成長に反比例し、障害者雇用率は低迷。ある年のハローワークの説明会にて、特例子会社という制度を知り、設立への取り組みを始めた。それまでは、パート、アルバイトでの採用しか行っていなかったが、特例子会社を設立するとともに正社員での採用を促進することに成功した。
現在、グロップサンセリテでは30名の障害者が在籍しており、清掃業務、リサイクル業務、事務処理業務、データ入力業務、テレマーケティング業務など多岐に渡る業務に従事している。
2. 障害者の職域拡大
2007年4月、新規事業としてリサイクル事業を開始した。狙いは知的障害者の雇用促進だ。リサイクルセンター立ち上げ以前、親会社では、知的障害者を7名雇用していたのに対し、特例子会社での知的障害者の雇用は清掃業務に従事する2名のみであった。「このままでは、身体障害者の雇用は専門分野で職場提供できるかもしれないが、知的障害者の雇用は停滞してしまう」という担当者の考えのもと、新たな職域を検討しリサイクル事業の立ち上げに至った。
現在、リサイクル事業部は、管理者1名、作業全般に従事する知的障害者3名、事務処理業務を行う視覚障害者1名の計5名で構成している。知的障害者の採用時には「元気があって素直な人」に重点を置き、2007年4月、立石昌寛さん(20歳)と西翔太さん(20歳)を新たに採用。2人は、国立吉備高原職業リハビリテーションセンターの職域開発系職業実務科を卒業後、グロップサンセリテに入社した。
リサイクルセンターでは、社内や取引先から古紙やパンフレットなどを回収後、クリップやホッチキス針の分別、裁断処理を経て、回収業者に引き取ってもらう。引き取られた古紙は、最終的にトイレットペーパーへと形を変えてセンターへ還ってくる。納品後は、グループ各社へ販売、また障害者雇用でお世話になっている関係機関へ配付している。事業の取り組みの中で、まずはトイレットペーパーへ再生したが、今後はメモ用紙、手帳、封筒など多くのリサイクル商品も検討していきたい。
3. 障害者の従事業務
前述の通り、グロップサンセリテでは多岐に渡る業務に従事しているが、今回はリサイクルセンターの立石さんと西さんに焦点をあててみたい。2人の1日の仕事が始まった。朝礼で、センターの管理者の和気さんから1日の予定を聞き、作業に取り掛かる。基本的な業務は、古紙の回収、分別、裁断処理であるが、定期的に回収業者への固形化物の搬出、また、トイレットペーパーの受注時には、納品対応を行う。
まずは、古紙の回収だ。グループ会社の拠点に設置されたリサイクル袋を、車で定期的に回収。古紙が溜まったリサイクル袋を空の袋と交換し、事業所の従業員から受渡表にサインをもらう。リサイクル袋は、満杯になると40kg近くにも及ぶため、若い2人の力は欠かせない。この作業は、2人にとって、多くの事業所の従業員と接点をもつことになるので、コミュニケーションの向上に大いに役立っている。事実、入社当初はぎこちなかった挨拶も、最近では「失礼いたします」、「お疲れさまです」といった言葉が自然に、そして自発的に出るようになった。
リサイクル袋の回収が終わると次は古紙の分別。事業所から回収してきた古紙には、クリップやホッチキスの針が付いているもの、のり付けされたもの、特殊な加工がされているもの、と多種多様。よって、シュレッダーに投入しても良い状態にし、併せて回収業者が引き取ってくれない紙類を排除する。多少雑だが作業スピードの速い立石さんと、丁寧だがゆっくりと作業する西さんの2人はとても対照的。リムーバーと呼ばれるホッチキスを除去する道具の扱い、分別作業後の作業台の状態を比べてみても、良くも悪くも2人の違いは極めて顕著だ。古紙の分別が終わると裁断作業へと移る。機密書類等が含まれている時もあるので、この作業で全ての古紙を裁断し、固形化する。固形化された物が入った大袋は、一定量が溜まると回収業者へ引き取ってもらい、2人の一連の作業工程は完結する。回収時には、吉備高原職業リハビリテーションセンターで訓練したハンドリフトを使っての作業もあり、ここでもセンターでの訓練の成果を存分に発揮してくれている。ただ、ハンドリフトを使っての作業は専ら西さんが行っており、立石さんは「訓練したけれど、あまり得意ではないのです」と言う。得手不得手があるのは当然だが、立石さんも一人前にリフトを使いこなせるよう、和気さんの厳しい指導のもと日々奮闘中だ。

(左)立石昌寛さん
(右)西翔太さん



西さんは、ハンドリフトを使った作業は、お手のものだ

2人とも、とても嬉しそうだった

4. 助成金の活用(知的障害者への安全面での配慮)
リサイクルセンターでは、障害者雇用に取り組むにあたって、各種助成金を多く取り入れた。1つ目は、大型シュレッダーについて、第1種作業施設設置等助成金の認定を受けた。市販の機械にこちらから要望をあげ、非常停止ボタンの追加、ベルトコンベヤー部分への安全カバー取り付け、前方扉へのドアロック機能の3箇所について改造を施した。これにより、より安全な職場環境を提供することができている。また機械作動時は安全靴の着用、首から下げた身分証明書の着脱などをチェックし、業務災害の未然防止を心掛けている。
2つ目は、第2種作業施設設置等助成金の活用だ。家賃の一部の助成を受けることができ、安全で快適な職場環境の形成に注力できている。
3つ目は、リサイクルセンターでの事務処理に必要な設備に、第1種作業施設設置等助成金を活用した。2007年9月に入社した視覚障害者の就労支援のための機器で、具体的には、拡大読書機、PCの拡大ソフト、音声読み上げソフトである。これらの機器が手配できたことによって、視覚障害者の就労を実現することができた。現在では、リサイクルセンターにおける事務処理業務に加え、管理部門の業務全般に至るまで幅広く担当しており、助成金の活用は人材の活用ひいては会社の発展に非常に結びついている。


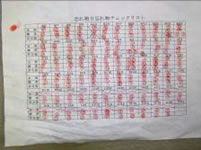
運用開始後は、格段に忘れ物が減った
5. 生活するために必要なこと
立石さん、西さんともに、社会人となり、給与を得ることで自分で自由に使えるお金を持つようになった。入社時にそれぞれのお母さんにも了承をしてもらい、本人が自分のキャッシュカードを保持、管理するようにした。入社して2~3ヶ月が経過した頃、それぞれのお母さんに給料の使い方について聞いてみると、2人とも家に1円もお金を入れていないと言う。立石さんはアパートの家賃をお母さんが支払い、西さんは実家で食費等の費用が掛かっている。2人ともその事実について全く理解できていなかった。働いたお金は全部自分のものになる、といった誤認があったのだろう。
そこで和気さんは2人それぞれに面談を行い、生活するために必要なお金の話を徹底的に叩き込んだ。その後、それぞれのお母さんに職場環境や仕事振りを見学してもらった後の会話の中で、2人に対し、給料の一部をお母さんに渡すように提案した。本人への説明、保護者との連携の甲斐あって、夏頃からは2人ともその時に約束した一定の金額を家に入れるようになった。
「将来的なことを考えた上でプライベートの事も気遣うのが、彼らの真の自立につながり、必ず仕事にも活きてくるはずだ」と和気さんは語る。
6. 一人前の社会人を目指して
グロップグループでは、障害者を特別扱いすることはない。この会社に籍を置くからには全員同じであり、それは2人も当然一緒。彼らは社会人1年目であり、まだまだ未熟だが、それだけ伸びる可能性も当然秘めており、先々は後輩に仕事を教える立場になってほしいと考えている。来たるべきその日が来るまで、少しずつでも成長していってほしいと願い、日々真剣に向き合っている。
20歳になった節目として、2人に今年の抱負を書いてもらった。立石さんは、「公私ともに頑張って一人前の社会人になる」。西さんは、「自分から話しかけることができるように表現力を身につける。仕事と休みのけじめをつける。」これに対し和気さんは「彼らが目標を達成できるように周囲の人間が協力することは不可欠。仕事もプライベートも、出来る限りの指導やサポートをしてやりたい」と2人を応援している。
まだまだ成長途上の2人であるがゆえ、今後の活躍を大いに期待したい。そして、胸を張って一人前の社会人だと言えるよう、また会社にとって必要な人間であるという自信を持てるように成長していってほしい。我々もそのために彼らと共に今後も様々な取り組みを行っていきたい。
執筆者 : 株式会社グロップグループサービス本部 法務課 野村 裕樹
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











