自律&自立を目指して
- 事業所名
- オムロン太陽株式会社
- 所在地
- 大分県別府市
- 事業内容
- 電機機械器具製造(リレーソケット、センサー、スイッチ等の製造)
- 従業員数
- 60名
- うち障害者数
- 36名
(内訳)
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 3 製造工(組立加工、ハンダ工) 肢体不自由 31 製造工(22)、事務(4)、工務(3)、生産技術(2) 内部障害 2 製造工(2) 知的障害 0 精神障害 0 - 目次


1. 事業所の概要(障害者雇用の理念:経営哲学を障害者雇用に結びつけて)
太陽の家の玄関を抜けエレベーターで3階へ、ドアが開くと、前面の壁いっぱいに掲げられた〈オムロンの社憲〉と〈オムロンの経営理念〉に出会う。そこには、『われわれの働きで/われわれの生活を向上し/よりよい社会をつくりましよう』、『社憲を実現する6つの経営の基本精神』;「顧客満足の最大化/たえざるチャレンジ/株主からの信頼重視/個人の尊重/良き企業市民の実践/倫理性の高い企業活動」と書かれている。この社憲に明記している精神の具体的活動こそ、オムロンの「人間尊重の実践と福祉の心」である。障害者とのかかわりは、昭和44年に「サリドマイド児」の義手の開発から始まった。
今回情報を提供して頂いたのは、35年前の授産生時代からの生え抜きである車いすの社長;江藤秀信氏である。ちなみにオムロン太陽株式会社の役職者(課長以上)は全員障害のある者であることも特色である。
障害者を自立した労働者として育成するためにオムロン株式会社と社会福祉法人太陽の家が共同出資してオムロン太陽株式会社が創業したのは昭和47年4月のこと。
「保護より機会を」をモットーに障害者の自立した働く場づくりをすすめる太陽の家の理念に、企業の公器性(社会貢献)を重視する社憲をもつオムロン株式会社の立石一真創業者が共鳴、福祉施設・身障者・民間企業の協力による、わが国初の福祉工場としてスタートした。その後、昭和52年にオムロンの特例子会社としての承認を受けるとともに、より職能的な重度障害者を雇用するために昭和56年第2工場を増設・創業開始する。
バブル崩壊以降、障害者雇用の面でも一次低迷した時期があったが、国際規格のISO9001(品質)、ISO14001(環境)、OHSAS18001(労働安全衛生)の認証を得るとともに、障害者雇用の職場づくりの在り方を見直し、平成16年に平成22年までのグランドデザイン(GD2010)を制定。障害者工場としてのハンディを克服しつつ、オムロングループの中で自律と自立を目指した企業活動を展開中である。
2. 取り組みの内容(能力開発、雇用の促進・定着等のために取り組んだ職場改善の数々)
(1)作業環境・設備への配慮
第2工場では、電気制御機械のパワーリレーを月産15万個製造できる一貫性組み立てラインが、政府の支援とオムロン・生産技術センターの協力で開発・導入された。まだ、職能的重度障害者は大工場では「働けない」というのが一般的な風潮で、ましてやバリアフリーやユニバーサルデザインなどの概念は一般的にはまだ知られていない時代である。
組み立てラインでは残存機能の少ない職業能力から見た重度障害者が働きやすく、安全で効率よく作業できるように各所に工夫がされ、生産ラインの要所要所には、高度な自動機が配置された。例えば、ベルトコンベア(作業台)の高さは、車いすで仕事がしやすいように設計された。また、手の不自由な人にはそれを補完できる装置、全盲の人には聴覚で判断するような仕組みを施すなど重度の身障者でも作業や検査ができるように改善された。
作業環境の面では、工場出入り口の段差をなくし、出入口、廊下の幅、トイレ、エレベーターなどを広くしたり、生産ラインはゆったりと余裕のあるレイアウトにしたりした。各所に設けられている自動ドアは両開き式に、衝突を避けるためコーナーにはカーブミラーが付けられ、電気配線などは当初から埋め込まれた。

(2)足りないところは科学の力で・・・「人と機械のベストマッチング」
オムロン太陽は、創業以来、障害者が労働者として自立できる職場づくりを目指してきた。そのため、オムロングループの他の工場と同様に、利益を追求し、従業員に対しては成果に応じて給与を支給するシステムを採用している。しかし、障害というハンディをクリアし、オムロングループの他の工場並みの生産性や利益を追求するのは、並の努力で無かったと推察するが、徹底討論の末の結論が、「障害者に適した治工具の改善はもとより、健常者に比べて、よりリスクが大きくなる労働災害の徹底した防止を図ることで、安全で快適な職場づくりを目指す」であった。このような、地道で緻密な努力の積み重ねによって一般工場との格差を限りなくゼロに近づけたことは大いに評価できる。
その最たるものが「人と機械のベストマッチング」である。オムロン第2工場で働く人たち一人ひとりの残存機能は厳密に測定され分析された。不自由な足の動作範囲はどうか、微妙な振動音を聞き分ける能力はどうか等である。
各工程ごとに、人間と機械をマッチングする検討がなされ、最終的なライン配置が決められた。その人その人の残存機能を充分に発揮できるシフトが敷かれたのである。当時、第2工場で働く人たちの実に90%(26人)が残存機能の少ない職業能力から見た重度身障者だった。工程の各所にはニーズに応じたさまざまな新しい工夫がされている。
例えば、部品の供給は、レバー操作で在庫棚から自動的に手許へ送られてくる。脳性まひで、左手だけが健常なA氏は、この装置によって部品を組み合わせる作業に専念する。
サリドマイド後遺症のS氏は、不自由な指で器用にリード線を整え、端子台をコイルの上に置く。当初、彼が生産ラインのネックになるのではと、憂慮したのは全くの杞憂だった。彼は、自立を目指して頑張り抜いた。今では導入時から見ると7倍の仕事量をこなせるまでに熟達した。



コイル線を端子台に通す作業は、ポリオと事故後遺症の二人で進める。自動機が半田付けをすると、半田の良否を、両手両足の力が弱く働きも不自由なB氏がテレビで半田づけの状態を観察、チェックする。
デリケートでピンセットを使う工程は、交通事故とポリオの女性二人がスピーディに作業する。組み立てが終わった製品を、超音波洗浄機で自動的に洗浄して、クリーンルームに送る。ここでは、ポリオや事故で足に障害のある二人が調整する。その隣では、脳性まひのC氏が不自由な手でリレーにかぶせるケースをエアー洗浄する。
防音室では、全盲のD史が鋭い聴力で異常なうなりをチェックして、製品の良否を判断する。コンベアで検査へ送られる途中では、検査装置に表示された特性データーを、左右にわずかに残存機能が残っているE氏がタイプライターのキーを打ち、検査データーを作成する。特性検査機によってチェックされた製品は、筋ジストロフィの2人によって、最終の外観検査が行われる。
ここで働く人たちは、不自由ではあっても、残存機能を精一杯ふるっている。多くの人々の温かい協力と、足りないところを助ける科学・技術の力の結晶の姿がある。
常に人と機械のベストマッチングを図り、生産性の向上すなわち御社がめざす「自立」は、平成10年度一人あたりの生産量において、平成15年度比200%の伸び率である。
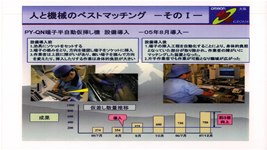
(3)もうひとつの「自律」のために、「フルファンクションをもつ主管工場へ」
オムロン太陽の目指すものに、「人と機械のベストマッチングによる生産性の向上と企業価値の向上」による「自立」と、今一つの「自律」がある。GD2010にはこう書かれている。「生産する商品の一部は、フルファンクションを保有することで、自らが自己完結のマネージメントをする姿(自律)を目指します」。即ち、フルファンクションをもつ主管工場を目指すことで「自立」と「自律」が完結するという計画である。平成15年度は既存設備に手を加えることにより、障害者が機械・設備に合わせて作業をする「製造」のみであったものが、平成17年度には「計画・調達・製造・流通」までに機能アップ、平成19年度には「計画・調達・製造・流通・(一部)技術・QA)」の一部主管工場へ、そして、平成22年には「センシング&コントロール技術を活かし人と機械のベストマッチングの実現により、雇用で人を選ばない設備と技能を体制をもつ会社」を目指している。
3. 今後の課題・展望
(1)21世紀の障害者工場のありたい姿
社会の公器性を具現化しながら世の中へ多くの情報を発信し続け、感心から感動へ一人ひとりが果敢にチャレンジし、ユニバーサル工場に変革させることである。
(2)感心そして感動する工場へ
①一人ひとりの目標が明確になっていて、改善や工夫の履歴が管理されていること。
②ハンディを補う改善や工夫が至る所に見られること。
③一人ひとりが主役になって、生き生きと仕事をして、工場全体の5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)が徹底され労働災害ゼロを目指すこと。
④オムロンのセンシング&コントロール技術が活用されていること。
(3)社員教育の強化で安全・快適な職場づくりが当たり前になること。

執筆者 : 別府大学短期大学部初等教育科教授 佐藤 賢之助
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











