障害者にやりがいを持って働ける職場を
- 事業所名
- 京成ハーモニー株式会社
- 所在地
- 千葉県酒々井町
- 事業内容
- サービス業(鉄道施設およびその周辺の清掃及び植栽管理)
- 従業員数
- 12名
- うち障害者数
- 7名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 7 研修所・車両基地・乗務員の宿泊施設の清掃、植栽管理、名刺作成 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要
| (1) | 創立:2005年3月10日 |
| *障害者多数雇用事業所特例子会社認定 2006年2月1日 | |
| ・資本金:1,000万円 | |
| ・出資会社:京成電鉄株式会社 100% |
| (2) | 事業内容:業務請負・受託 |
| ・グループ企業の関連施設内の清掃 | |
| ・名刺作成 | |
| ・作業衣のクリーニング |
| (3) | 従業員数 | 12名 | (男 9名 女 3名) | |
| ・ うち障害者数 | (知的障害者) | 7名 | (男 6名 女 1名) | |
| (重度知的障害者数) | 4名 | (男 3名 女 1名) |
2. 障害者雇用の経緯・背景
障害者の雇用を社会的使命と自覚するも、親会社である京成電鉄株式会社は鉄道業という、安全性が重視される業種であるために、障害者の雇用に苦慮していた。
一方、障害者の法定雇用率の未達成に加え、さらに、除外率の引き下げが実施されようとしていた情勢のなかで、会社の首脳部が積極的に検討をし、関係機関の指導援助のもと、特例子会社の設立を決定し、下記、理念のもと、京成ハーモニー株式会社を設立した。
【設立理念】
「障害者と健常者との調和、福祉と企業経営の調和、ひいては当社と京成グループが、事業を展開するエリアにお住まいのすべての方々との調和を目指します。」
3. 取り組みの内容
(1)障害者の募集及び採用
創業時の採用は、千葉障害者就職支援キャリアセンターで訓練中の知的障害者から推薦のあった者を2005年10月から3ヶ月トライアル雇用を経て採用した。その後の採用は、他の支援機関を含めた中で幅広く実施している。
| 【採用実績】 | 2006年 1月 | 6名 |
| 2007年 4月 | 1名 | |
| 2008年 2月 | 3名 |
(2)障害者の配置・定着・職場適応
業務配置は、清掃及びクリーニング業務については、全員が当たり、このうち、名刺作成業務は受注があった時に2名が担当している。
特に、作業現場は従業員にこだわりが見られることにより、配置とローテーションに配慮をしている。
なお、作業現場は、大きく分けて、京成電鉄株式会社の3箇所施設と関連企業の1箇所に分散しており、事務所から各作業所まで最長10分の時間を、公道だけでなく踏切のない軌道の横断を含めた移動がある。
このことにより、リーダー(指導員)を、スタッフ(従業員)の前後に配置して安全確保を図っている。
定着については、退職者は創業から現在まで3名である。退職理由は、全員が遠距離通勤の解消を図ることのために、居住地に近い事業所に転職をしたものであり、疾病や職場不適応の者はいない。また、土曜日を作業スキルを向上させるための訓練日としている。
職場適応指導については、日常的な支援機関との連携により、障害者の適性に応じた指導方法について、リーダー間で知識・技能を共有、活用している。
特に、問題等が生じた場合には、外部のジョブコーチ及び社内で障害者職業生活相談員の資格を取得した2名が、指導に当たっている。また、日常的には、「オアシス」及び「ホウレンソウ」を励行していることが、作業現場で触れ合う人たちに好感が持たれ、障害者に対する理解を深めるとともに、スタッフが職場に親しむ効果を生んでいる。
他に、年間業務目標を掲げるとともに、月間重点目標を掲げ、業務遂行に対する意識を高めている。なお、特筆すべきことは、親会社の新入社員研修に、清掃業務(6月)を取り入れ、スタッフと一緒に清掃作業を実施することにより、健常者に障害者の特性について、理解をより深めていること。及び、特別支援学校の教員・生徒ならびに盲学校生徒の実習を積極的に受け入れ、共同作業を実施していることである。
| ※ | 【オアシス】 | ・オ=おはようございます |
| ・ア=ありがとうございます | ||
| ・シ=失礼しました | ||
| ・ス=すみませんでした | ||
| 【ホウレンソウ】 | ・ホウ=報告 | |
| ・レン=連絡 | ||
| ・ソウ=相談 |

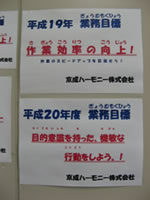
(3)障害者の能力開発
リーダー4名が、スタッフ7名に対してわかりやすく、明確な指示をすることに心がけている。創業時は、作業量の固定化と平準化により、一人ひとりに的確に理解をさせることと、適切にサポートすることに努めた。その後に、ローテーションを取り入れ、現在に至っている。
また、リーダーはスタッフに「励まし」を、スタッフはリーダーに「どんなことでも質問を」をすることを励行している。特に、「オアシス」と「ホウレンソウ」は唱えることでなく、実践すること。教えられたことは手帳に記すことの励行を徹底させている。さらに、リーダー会議は、毎日15分のミーティングを 実施している。また、適宜、支援機関ジョブコーチの助言を得ている。


(4)労働時間
就業時間は9時30分から16時50分である。休憩時間は12時から13時で、実働6時間であるが、作業時間は、10時から16時である。スタッフの特殊性から、作業開始前の点呼や体操及び作業終了後の作業日報の記帳等の時間に配慮している。
(5)定年継続雇用
定年制については、親会社の制度に従い60歳であり、その後は継続雇用を想定している。現在、最年長が36歳であり、近い将来に、スタッフが定年を迎える事例はないが、高年齢者雇用 安定法の趣旨を踏まえた継続雇用の具体的内容の制定が必要である。
(6)健康管理・安全衛生
健康診断については、年2回(3月、9月)実施している。この受診は、作業現場の施設で行われることにより、100%の受診率である。また、受診後は速やかに作業に復帰できる好影響もある。また、季節ごとのレクリェーションは、スタッフの働く意欲を喚起している。
日常的には、作業開始前後の点呼時及び作業日報により、健康状態を把握している。 特に、夏期は飲料水を作業現場に携行させて、水分補給を義務付けている。
安全面については、どこの作業現場にも、必ずリーダーが同行しているために問題はなく、衛生面は極めて良好である。特に、トイレの清掃については、清掃の場所に色彩マークを印し、使用する用具や洗剤・薬剤にも同様にマーク印をすることにより、問違いなく作業が遂行できるように工夫されている。なお、この色彩マークは、クリーニング作業にも応用し、所属毎の仕分けに誤りのないようにしている。

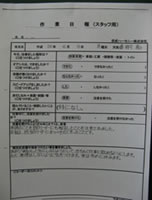





(7)就業環境の整備
食堂、休憩室、更衣室等、極めて清潔に整備されている。なお、これらの整備については、自力で行い、障害者雇用納付金制度に基づく助成金の利用はない。

4. 最後に
(1)今後の課題・展望
課題については、社長も現在の作業エリアでは親会社からの発注可能な業務量に限界があることの認識を持ち、これを踏まえて「新構想」を考えつつも、具体的な構想になっていない。ただし、近い将来に、何らかの形で職域拡大を図り、障害者従業員3~4名程度の増員を画策している。
(2)評価
創業3年であり、知的障害者を雇用する特例子会社である。幹部が、親会社からの出向社員等で構成されており、知的障害者と接する機会が殆どなかったことにより、業務運営のみでなく、日常生活までの対応に苦慮されていることが拝察できるとともに敬意を表するところである。雇用面は、現時点では、限られた支援機関が人的供給源となっているが、今後は、ハローワークを中心に学校関係機関とのきめ細かな連携が必要であり、募集は幅広く行うことが求められる。
一方、受注面では親会社との綿密な連携により危惧することはないと推察するが、障害者雇用は、創業時から1名増の7名である。近い将来に3~4名の雇用が見込まれているが、「新構想」は具体化されていない。しかし、当社は障害者特例子会社であり株式会社でもある。当然利益を求めなければならない。現在の事業運営は、受注は安定しているものの障害者の福祉的要素が色濃い。
福祉から「真の雇用」に脱し、利益を追求することが求められる。そして、利益の拡大が、従業員に安定した収入と安定した雇用が確立され従業員の社会的自立を保証するものである。
執筆者 : 社団法人千葉県雇用開発協会 障害者雇用推進技術顧問 加藤 清彌
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











