障害者雇用により地域貢献を図り、障害者雇用定着を促進する
- 事業所名
- 田中石灰工業株式会社
- 所在地
- 高知県高知市
- 事業内容
- 石灰の採掘・加工・販売・廃棄物リサイクル事業等
- 従業員数
- 80名
- うち障害者数
- 6名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 1 事務 肢体不自由 2 リサイクル資源分別作業 内部障害 0 知的障害 3 リサイクル資源分別作業 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要
| 設立年次:明治27年 | |
| 資本金:2,000万円 | |
| 従業員数:80名 障害者6名 | 知的障害者3名(重度3名) 肢体障害者2名(重度1名) 聴覚障害者1名(重度1名) |
| 事業所・施設: | ・稲生石灰工場 ・大坂山鉱業所 ・円行寺鉱業所 ・高知中間処理センター ・高知エコセンター ・高知プラスチック再生センター ほか、関連会社7社 |
高知県に豊富に埋蔵する良質な石灰石を独自工法で加工して作る「土佐漆喰」の製造・販売メーカーとして明治27年に創業。今年114年目を迎えた。石灰製品は建築用にとどまらず、食品の添加剤、肥料用、各種試薬などの医療用、工業用、公害防止用など,幅広い分野で使われている。昭和30年代からは地下資源の蛇紋岩鉱山の開発に着手し、高炉鉄鋼業の副原料製造を開始している。現在、石灰、鉱産、建設、環境開発の4つの事業部門を持っているが、中でも「資源リサイクル」「適正な廃棄物処理」「環境保全」を事業コンセプトに資源循環型事業を目指す環境開発事業活動は注目されるところである。平成2年設立の廃棄物中間処理施設「高知中間処理センター」に続いて、平成17年9月からはプラスチック製容器包装ゴミをペレットに加工する「高知プラスチック再生センター」が新たに稼働。創業100年を超える資源活用企業として、これからのエコ社会を生きる「グリーンカンパニー」を目指している。
現在、従業員数は80名で、そのうち障害者6名が働いている。勤務先は、本社に聴覚障害者1名と「高知プラスチック再生センター」で、従業員数40名のうち知的障害者3名、肢体障害者2名である。
「高知プラスチック再生センター」は、家庭から出るプラスチック製容器を包装ゴミやスーパーマーケットなどで回収したペットボトル、食品用の白色のトレイ等をプラスチック原料に加工する工場。最終的には錠剤ぐらいの大きさのペレットに加工し、建築資材のウッドデッキや配送用パレットの原料として県外の大手メーカーに出荷している。

2. 企業理念、障害者雇用についての認識
(1)企業理念
私たちは、100年を超える伝統を礎として、地域経済の発展に全力を尽くし、雇用の創出・人材育成に大きく貢献してまいります。
蓄積された経験と技術で、循環型社会形成の一翼を担う事業を展開し、クリーンな環境の保全・構築に邁進いたします。
地場資源の有効利用を企業活動の根幹に、経済の健全な発展に欠かすことのできない製品を研究・開発・創造してまいります。
21世紀を疾駆する、活力と創意にあふれた企業を目指します。
(2)障害者雇用についての考え方
平成17年に完工した「高知プラスチック再生センター」で本格的な障害者雇用の取り組みを始めた。当初は、障害者雇用を考えていなかったが、ハローワーク担当者から知的障害者を紹介され、障害者雇用を検討した。執行役員環境開発部長で、高知プラスチック再生センター長兼任でもある川原さんは「別の事業部門に身体障害者が1名いて、会社としての雇用率の問題はクリアしたが、当初はやはり戸惑いがあった。社長に進言したところ、環境開発事業部として可能ならばやってみるようにと言われ、採用に踏み切った」という。初年度の平成17年度に1名、18年度に2名、19年度に1名を採用している。
その障害者を受け入れるにあたって、雇い入れ1ヶ月前から週に1度、14人の管理職による勉強会を実施した。「それまで私をはじめ、従業員の誰も知的障害者と接したことがなかったので、資料を取り寄せ、どのように対応したらよいのかを勉強した。特別なことではなく、話しかけ方、あいづちの打ち方、『はい』と返事をしても理解していない場合もあるので、何度も根気よく説明をすること、絶対に叱らないこと、うまくできた時は必ず誉めることなどを徹底した」と川原さん。従業員も障害者を受け入れることで、助け合う気持ちが高まったようだという。

3. 取り組み状況
(1)施設・設備などハード面の工夫
障害者のための特別な施設ではないので、特に障害者を対象としたハード面での工夫はしていない。しかし、廃棄物処理施設だけに機械が多く、障害者だけではなく他の従業員にとっても危険は同じ。職場での危険因子を全員で提案して災害防止につなげる「ヒヤリ・ハット活動」も積極的に進めている。
障害者も安全推進者として活動。作業をしながら、ひやり、はっとする場所に気づいたら、即座に提案し、その日のうちに対処法を検討している。これまで滑りやすい床にテープを貼る、ベルトコンベアに覆いを取り付ける等、すでに100件あまりの改善が行われている。障害者と他の従業員どちらにもやさしい職場を目指している。

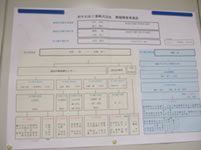
(2)ソフト面の工夫
①雇用管理
<採用>
現在働いている障害者は、ハローワークや高知障害者職業センターの紹介で採用した。現在はフル稼働のため、新たな採用予定は考えていない。
<賃金>
賃金は時給730円。雇用形態は他の従業員と同じく正社員で待遇面は同じ。障害のレベルに応じて配置を考えている。
<労働時間>
勤務時間は、他の従業員と同じく三交代制。①午前8時から午後5時まで②午後4時から午前1時まで③午前12時から午前9時まで。休憩1時間のほか、2時間ごとに休息タイムを設けている。これは集中力が落ちるための休息で、その時間に自分の周囲の掃除をするようにしている。
月160時間以上は残業手当が付く。休日は毎日曜日。但し、原料の増減によって土曜日が半休あるいは全休となる場合もある。
②職場配置
障害者は3カ所ある選別台に配置している。工場内は選別作業員51名、フォークリフト等場内作業員が24名となっている。ここでは、家庭やスーパーマーケットなどから運び込まれた不燃ゴミを機械で粉砕、洗浄、選別、乾燥、溶解し、ペレット等にリサイクルしていく。作業内容的には危険を伴うことも多く、障害者は他の従業員とともに、この選別台に配置されている。
ベルトコンベアの前に立って、流れていくゴミを手で選り分けていく作業だ。障害のレベルに応じて配置を決めるためにまず、トライアル雇用で1週間仕事を体験してもらい、工場の責任者がマンツーマンで指導体制を検討していく。

③教育・訓練
知的障害者を受け入れるにあたって、まず、作業を難易度ごとの3つのランクに区分けし、習得したら次のステップに進んでいけるように工夫しながら、ベテランがつきっきりで指導している。最初のランクでは、選別台でペットボトルだけを取り除く。次のステップでは「残渣(ざんさ)選別台」の前で機械が砕くことができなかった大きなゴミ袋にドライバーで穴をあけて破いたり、大きなレジ袋を取り除いたりする。
難易度の高い作業は、原料選別台の前に立ち機械で選別された原料の中からポリエチレンとポリプロピレン以外の異物を取り除く作業。原料の素材の違いを瞬時に見極めるのは他の従業員でも難しく、どうにかやれるようになるまでは1~2ヶ月、慣れるまでに半年はかかる。知的障害者の場合はやはり、倍近い時間を要するが、訓練の末、難易度の高い3ランクの原料選別台に進んだ知的障害者もいる。
④福利厚生・健康管理
福利厚生など、待遇面は他の従業員と同じである。忘年会などにも参加している。その際には職場の仲間が送り迎えをする。健康管理については、年1回の法定の健康診断を実施している。
⑤地域との連携
地域社会への貢献を柱にしている。障害者の採用についても地域貢献の一つと考えている。障害者雇用にあたっては、ハローワークや高知障害者職業センターと連携している。また、高知プラスチック再生センターが完工した際、地元採用を優先させようと新聞の折り込みチラシを配っている。
⑥助成金や各種支援制度の活用
障害者雇用率は法定雇用率1.8%をはるかに上回り、報奨金を受給している。また、障害者雇用納付金制度に基づく助成金(業務遂行援助者の配置助成金)の支給を受けている。
4. 取り組みの効果
障害者を受け入れたことで、従業員からクレームの声は一切あがっていない。むしろ、予想もしなかった効果もあった。「障害者の方々は、皆さん、性格が明るいので、職場の雰囲気も明るくなっている。まわりのみんなも助け合っていこうという気持ちが高まってきたようで、チームワークが良くなった」と川原さん。従業員同士の絆も強まったようだ。障害者の雇用を始めて3年目となる今年、聴覚障害者を採用。コミュニケーションを取るために従業員全員が手話を覚えようと、職場で手話教室を開催。すでに、お互いにあいさつを手話で交わるようになっている。
平成17年11月に採用となり、入社した細木さんは、重度の知的障害者。しかし、訓練の末、他の従業員とともに原料選別台の前に立って働いている。「仕事は大変ですが、楽しい。ただ、途中休憩の時の掃除が苦手です。以前、働いていたところは合わなくて辞めたこともある。でも、ここはみんなから僕によく話しかけてくれるので嬉しい。ここでなら、ずっと働いていけそうで良かった。家は家族と一緒で、給料の中から少し入れている」という。
細木さんをはじめ、障害者はいずれも高知市内もしくは、その近郊に住んでいて自転車で通勤している。同僚は「細木さんは意外と自分からも話しかけてくれる。最初は障害者ということで、意識をして付き合わないといけないのではないかと身構えていたが、そこまで抵抗がなかった。作業内容はこちらが考えながら指導していかないといけない面もあるけれど、普通の生活では全然意識して接することもない」という。
川原さんによると「障害者の特性としては個人によるが、全般的にうちに来て貰っている人はみんな集中力がある。1日中、まじめにずっと作業をしている。しかも、欠勤もなく遅刻もない」そうだ。


5. 今後の課題、展望等
本格的なエコ社会を迎えて、ますます、産業廃棄物やゴミのリサイクル需要は高まってくる。循環型社会の実現に向けて、地域に根ざした企業活動をしている。当社としては、「高知プラスチック再生センター」に次ぐ、新たなプラントを作りたいと考えている。「計画は未定だが、障害者だけで運営できるような施設づくりが可能なら挑戦してみたい。但し、廃棄物処理は機械が多く、危険でもあるため、知的障害者よりも身体障害者の方の雇用の可能性が高い。将来、障害を持つ人たちの就職先となれたら、地元企業として少しはお役に立てるのではないかと思う」という。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











