①アルバイト生に代えて一般募集により初めて障害者(精神障害者)を雇用
②フルタイム勤務よりも継続勤務
- 事業所名
- 株式会社久美堂
- 所在地
- 東京都町田市
- 事業内容
- 書籍 雑誌・文部科学省検定教科書・教材・文具・OA機器・音楽CD・DVD・TVゲーム・玩具等の販売
- 従業員数
- 120名
- うち障害者数
- 1名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 0 精神障害 1 書籍の検品及び返品 - 目次

1. 事業所の概要
・創業 1945(昭和20)年10月
・設立 1951(昭和26)年 6月(法人に改組し株式会社久美堂設立)
・資本金 2,400万円
・従業員数 120人(男40人・女80人)
・店舗 町田市内ほか計8店
本店・小田急店・四丁目店・旭町店・本町田店・愛川店・多摩境店・伊勢原店
(関連会社)有限会社久美堂外商センター、株式会社久美堂商事
(1)経営方針
屋号の由来である「人はいく久しく美しくあれ」という精神を経営の根幹としている。
「我々は誠意・熱意・創意の三意を以って顧客の信頼に応える」(創業者:故井之上哲夫)の理念のもと、「世の中には、変わってはならないものと、変わらなければならないものがある」との考えから、「本」を基軸として地域との交流を大切にするとともに、常に社員の新たな創意と挑戦する心を大切にしている。(具体的には、「マガジン・ドライブスルー」・「店舗内のイベントスペース」・「ハンディキャップのある人のための店舗の工夫」・「地元作家のための著書常設コーナー」・「自費出版のヘルパー事業」などを積極的に実施してきた。)
(2)組織構成
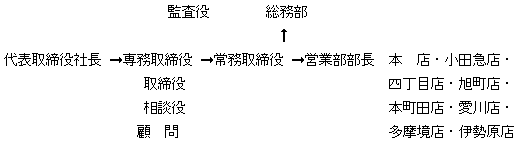
(3)障害者雇用の理念
全く性格も夢も異なる社員一人一人が、幼い頃から持ち続けた自分の夢を実現・達成していくために、社員の創意工夫を大切にする経営を心がけており、障害者の雇用も個人の能力を高めることによって企業の活力になり、本人の目標達成につながるものと考えている。
2. 取り組みの経緯、背景
同社の事業の性格上、雇用の形態は正社員・契約社員・パート社員・アルバイトなどさまざまであり、基本的には本人の希望・能力・適性を見極めて採用・配属・業務の担当を決めている。
障害者雇用については、かねてから検討してはいたが、どのような仕事が良いか、どこの店舗が働ける環境が整っているかなどの課題があり、採用のタイミングを考えていたところ、新店舗出店などたまたま仕事や店舗の雰囲気なども揃うタイミングが合ったので、具体的に雇用に取組むこととなった。
採用当時、アルバイトの代わりを補充する必要があり、高齢者にするという考えもあったが、それでは単にアルバイトの一人に過ぎないという考えもあり、継続的に勤務できる人を採用する前提のもとに障害者を雇用することとした。
基本的には障害の種別は問わないこととし、ハローワークと相談した結果、一般募集により採用することとした。数人の紹介の中から先ず通勤可能範囲かどうかなどにより書類選考を行い、一般の採用試験と同じテストと面接を行ったうえで1名を採用したところ、結果としてたまたま精神障害(かつて企業に勤務経験がある)であった。
3. 取り組みの内容
(1)職場配置
当該社員(以下「本人」、27歳)は、前の勤務先ではバリバリ仕事をしていた人であるが、対面でパニック状態になるなど中途で統合失調症を発症したとのことである。
同社の面接時には全く普通の状態であったが、対面接客が苦手ということでバックヤードの仕事をしてもらうこととした。
(2)従事している業務等
勤務先店舗では、書籍のほか、文具・音楽CD・DVD・TVゲーム・玩具等の販売等も行っているが、本人の担当業務は「書籍の検品と返品」及び「漫画本などのシュリンクパック作業」である。2種類の業務を担当することは本人にとっては「単純作業の繰り返しの疲れ」を緩和する効果があるようである。
① 書籍の検品と返品
「新刊本等の箱出し」時の「納品伝票とのチェック・確認」、「返品本の確認・箱詰め」である。返品する際の書籍等の抜き取りは一般社員が行い、本人は機械によりバーコードなどを読み取り、データをとりながら箱詰めをする作業を行っている。
黙々と一人でこなす仕事で単純作業であり、処理量が多いときは負担になるようであるが、本人には合っているようである。
作業量には波があり、単純平均すればダンボール7~8箱/日×@50冊位。
②漫画本などのシュリンクパック作業
漫画本などの一冊一冊を透明ビニール袋に入れ、「シュリンカー」を通してパッキングする作業である。作業量には波があり、200~400冊/回位。

(3)職場における指導
現勤務先(支店)は昼間6~7人、1~2人休み体制として常時4~5人の規模なので、店長自らが直接指導することとした。
社内(店内)においては、予め本人の居ない場で専務から店長へ、店長から社員へと障害者雇用について説明し、受入れのための環境づくりを行った。
現在は担当業務を一人でできるようになっているが、本人からは「(仕事量・勤務時間)をもう少し減らしてほしい」と店長に要望があった。
(4)家族・関係機関との連携の状況
初期において出勤時間の話し合いなどで店長と連絡があったが、今は全く無い。
現在は3ヶ月ごとにハローワークの指導官が来訪し、本人と店長それぞれに状況のヒアリングをしている。
(5)雇用条件(雇用形態・勤務時間・賃金など)
当初、一般契約社員として採用する予定であったが、面接時に本人から勤務時間が長いことを理由に「パート勤務にしてほしい」との希望があり、現在もパート勤務である。
同社では、事業の性格上、40時間/週を年間で実現するという変形労働時間制を採っており、一般契約社員(半年毎自動更新)は大卒18万円/月、パート社員は800円/時である。
現在の本人の具体的な勤務時間は、9:30~16:00(休憩1:00)、5.5時間/日×4日となっている。
障害のある従業員を一般契約社員と同じ報酬にすると作業効率としては割高であるが、一般社員でも「作業が遅い者は遅い」というのが実態なので割り切っている。
(6)障害者雇用に取り組んで思うこと
①社員の理解が必要であり、事前に社内(店内)に説明をした。
②精神障害についてはオープン(手帳所持)で入社したが、学生時代には研究論文を書き、就職後も研究部門で毎日遅くまで残業しバリバリ仕事をしていたということなので、障害のない人とどこが違うのか判らなかった。
③今の職場は、当人にとっては居心地がよく、パートであれば継続できると思う。
④障害者の雇用については職域開拓が難しい。採用難。雇用管理にコストがかかる。
⑤今後の採用については、高齢者の雇用・再雇用の問題があり、それとの兼ね合いが難しい。60歳定年への対応があり、継続雇用をしなければならないが、そのほかに障害者雇用を進めていく余力には限りがある。
4. 最後に
(1)当社のイメージ
「我々は誠意・熱意・創意の三意を以って顧客の信頼に応える」(創業者:故人)
「人はいく久しく美しくあれ」(社名の由来)
「社員一人ひとりが『ここで働けて良かった』と思える会社に」(社長の経営課題)
「一人一人のエネルギーと夢が企業の力となるように。それが私たちの組織作りです。」
「一人一人が期待し、期待され、期待にこたえることのできる組織でありシステムであることこそ最上のものであると考えます。」という言葉に表されるとおり、当社は人を大切にする経営をモットーとしており、社員の積極的なアイデアにより、各店それぞれに特色のあるサービスを行っている。
(2) 障害者雇用への取り組み
かねてから障害者の雇用を考えてはいたものの、雇用の環境が整わず延引していた。このたびの採用にあたっては、障害の種別についても特にこだわらず「本人次第」とのスタンスである。
当社の事例は、従業員数300人未満の規模で、且つ障害者雇用は初めてという企業における障害者雇用の事例として参考になるが、次の様な課題も挙げられる。
①雇用形態が正社員・契約社員・パート・アルバイトと分かれており、高齢者の雇用・再雇用などとの兼ね合いも考慮しながら障害者雇用をどこにどのように組み入れていくか。特に、本人の作業効率の評価と処遇をどうするかという課題がある。
②店舗が市内に分散しており、しかも共通する業務の集約が難しい状況においては、本人の業務習熟度が上がるにつれて、仕事量の確保も難しくなることが予想されるため、例えば、今後のために他の業務との兼務も検討することも考えられる。
③採用・配属時の店長と現在の店長は替わっており、今後の人事異動による交替時などにおいても本人の定着・継続勤務のためには適切な引継ぎが必要である。
④複数店舗を有しているため、障害の種別を限定せず採用し、それぞれの店舗の特色にあった業務を担当させることによって、更に障害者雇用を進める可能性(余地)はあるが、並行して「障害者雇用についての社内の理解の促進」と「管理者の育成」が必要と思われる。


アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











