障害者が支える環境リーディング・シティ
- 事業所名
- 綾瀬市リサイクル協同組合
- 所在地
- 神奈川県綾瀬市
- 事業内容
- 資源リサイクル業
- 従業員数
- 7名
- うち障害者数
- 5名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 2 空き缶選別作業 精神障害 3 電気製品の分解作業、空き缶選別作業 - 目次


1. 「ヤード方式」で資源を回収・分別
綾瀬市リサイクル協同組合(以下、協同組合)は、1985年、綾瀬市寺尾釜田に約1万㎡の敷地を借用し、設立された神奈川県では第一号となる資源分別回収組合である。代表理事は中嶋敏治氏(株式会社アーム代表取締役)、副理事長は飯室雅海氏(有限会社飯室商店代表取締役)。
作業場には市内の組合員企業5社が回収したリサイクル資源(取扱総数量約6,300t/年)が集められ、紙類や鉄類、非鉄類、ガラス類、プラスチック類などのセクションに解体・選別された後、納品される。
このような、すべての回収物を一ヵ所に集約し、そこで分別する手法は「ヤード方式」と呼ばれ、高品質な製品を安定的に提供できるほか、解体・選別作業を量や処理能力に合わせてコントロールできるのが特徴。他の市区町村ではあまり見られないが、県内で一番初めにリサイクル資源の分別回収を導入した「環境リーディング・シティ」綾瀬市ならではである。
作業場では協同組合の社員7人のほか、シルバー人材センターから3人、組合企業より15人ほどが参加し、約25人が日々の業務を遂行している。
2. 障害者雇用の開始
組合企業の株式会社アームから、湯山真理子さんが事務局員として協同組合に来たのは2003年4月のこと。着任早々、障害者雇用に取り組むことになったという。
「きっかけは、それまで解体作業を担当していた組合員企業の社員が白内障を患い、高齢だったこともあって3月末に退職したことでした。その欠員を補充しなければならなかったのですが、その退職者が知的障害者だったこともあり、同等の解体・選別作業であれば十分できるのではと思ったのです。すぐに綾瀬市に出向き、障害者の雇用について相談しました」
市から県央地域就労援助センターを紹介された湯山さんは中嶋代表理事に相談し、代表理事はじめ組合員全員の賛成を得て、5月より知的障害者2人、精神障害者2人をグループ実習で受け入れることを決定。彼らに小型家電の解体とミックスペーパー(新聞、雑誌、ダンボール以外の紙類)の選別を担当させ、ジョブコーチを付けて状況を見守った。
そして2006年4月、組合として彼ら全員を正社員として雇用すると同時に、他の作業所に通所していた知的障害者を実習を経て1人採用。2007年にも知的障害者と精神障害者の2人を採用している。
現在、障害者を雇用する際には原則1年間の実習を行い、その後、本人が希望すれば社員として受け入れることにしている。
また、2008年度からは綾瀬市他の福祉的就労奨励金や高齢・障害者雇用支援機構(当時)の各種助成金なども受け始めた。新たに支援機関と関係ができたことは、対外的に協同組合の存在を知らせることにもなり、雇用の拡充につながったという成果も出ている。

3. 全員すべての作業ができるように
協同組合で働く障害者は、現在5人。その主な仕事は以下の通りだ。
●掃除機、炊飯器、アイロンなどの小型家電の解体
●容器、包装などプラスチック類の選別(ライン作業)
●アルミの選別(ライン作業)
●ミックスペーパー(新聞、雑誌、ダンボール以外の紙類)の選別
それぞれに得手、不得手があるというが、シルバー人材センターや組合企業のスタッフとともに作業を行い、全員がすべての作業ができるよう指導を受けている。


また、作業には写真入りの作業手順書が用意され、誰でも見れば作業できるようにしてあるのも工夫のひとつだ。
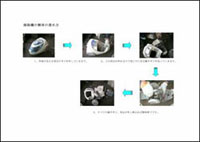
4. 雇用定着のための管理手法
(1)作業管理
作業場に回収されるリサイクル資源の量は「水・木・金曜日は月・火曜日より多い」「雨の日は少ない」など、季節や曜日、天候によって変動する。その状況変化に対応しやすいのが「ヤード方式」のメリットだが、協同組合では回収量を月単位で把握・管理して状況を推測、日々の作業量にメリハリをつけ、なるべくバラツキがないよう調整して作業指示を出している。
また障害のある社員には、作業日報の提出を業務として位置づけ、その日の作業量を数字にしたものを自己申告させている。作業日報にはその日の体調を記す欄もあり、管理者が一人一人の体調変化を認識するためにも役立っている。
(2)個別の管理マニュアルの作成
協同組合では、障害のある社員一人一人ごとに、それぞれの性格や作業時の特性、体調不良時における対処方法などを記したマニュアルを作成し、個別の管理を行っている。
「たとえ管理者が交代しても、それまでと変わらず対応できるような体制が大切だと思います」
湯山さんは、管理姿勢を一貫させることが必要と力説した。
(3)安全管理
作業場の敷地内はフォークリフトやトラックの往来が多いが、交通ルールの厳守、安全確認は全員に徹底し、事故は設立以来24年間ゼロ。
また、障害のある社員には単独では作業を任せず、必ずグループで作業させるほか、職場を離れるときはスタッフに申告し、許可を得てから離れるように指導している。
(4)健康管理と生活管理
障害者雇用では、健康管理や生活管理も重要なポイントだ。
協同組合では、障害のある社員の体調維持のため、1時間の昼休み、10時と15時にとる二度の15分休憩のほかに、1時間ごとに5~10分の休憩をとらせ、その間に日報を書かせている。
また、精神障害のある社員は特に体を壊しやすく早退や休暇が多いため、体調に少しでも不良を感じたときは、必ず事務局や職場のスタッフに報告するよう指示。
その他、精神障害のある社員の月1~2回の通院時間は出勤扱いとし、毎年、全員に健康診断を受けさせるなど、きめ細やかな健康管理を行っている。
「とはいえ、彼らの生活面のあらゆることに目が届いているわけではありません。先日も、最近やけに肥満が進み、仕事も休みがちな社員がいたので、よく観察したんですが、毎日、休憩時間のたびに数本のジュースを飲んでいたんですよ。これはいけないと思って、全員に『ジュース禁止令』を出し、その代わりに職場には無料で飲めるミネラルウォーターを用意しました」
彼等は大好きなジュースを止められたことで不安になり数日休んだ者もいましたが、再び出勤し始め、体調も回復したという。
「働くことで自分のお金を手にし、自由に買い物できるようになるのは良いことで、社会生活の基本になることなのですが・・・」と、湯山さん。
「通勤途中のコンビニで『高カロリーな甘い誘惑』が手軽に手に入るので、この社員の肥満はなかなか解消されません」と、心配も・・・
このように、仕事だけでなく生活のあらゆる面に目を配り、フォローすることが管理者には求められる。
(5)賃金について
障害のある社員に対して、協同組合では給与は時間給で支給(交通費は日額で支給)、賞与は出勤率と実績を考慮して支給している(最低賃金制度の適用除外を申請し、認可されている)。
「慣れた障害者でも、正直、作業能力は健常者の7割程度で、不慣れな場合は3~4割ぐらいです。最低賃金制度を適用すれば、どうしてもそれに見合った作業能力が要求され、知的障害者や精神障害者が働ける職域が健常者や高齢者に奪われることにもなりかねません。ですから私たちは、今後も最低賃金制度除外制度は必要と考えています」
一方で、3ヵ月に1度の面接を行い10月の昇給時期に反映させるほか、作業目標の設定や評価基準、新しい作業業務に携わる仕組みなどの「スキルアップ・プログラム」を実施し、スキルの向上が見られた社員は賃金を上げるなど、能力に応じた賃金体系をめざしている。


5. 課題、そして今後の取り組み
(1)生活保護費との関連
2008年秋、1年間の長い実習を終え、ようやく正社員として採用していた知的障害のある社員の一人が退職してしまった。
「正社員になって半年、これからというときの退職でした。実は彼、親も兄弟も障害があり、それぞれが生活保護を受けて生計を営んでいるのです。そんな家族環境のせいか、本人も額に汗して働くことに大切さを感じていないようでした。『自分も働かないで生活保護を受けるのだ』と、次第に休みがちになっていったのです」
出勤日数が社会保険の必要日数に満たなくなったため、「何かあったら相談に乗るよ」と声をかけ、退職を認めたという。
今、湯山さんは、「問題は社会制度にある」「行政の支援制度が分かりにくい」という中嶋代表理事の言葉も受け、障害者雇用を支援する機関は生活保護費と就業によって得られる賃金との関連を考える必要があると、切に感じている。
(2)障害者雇用職域の拡大
2010年度より綾瀬市では、リサイクル化(固形燃料化)による可燃ゴミの削減に取り組む方針を打ち出している。そこで協同組合では、現在は可燃ゴミである製品プラスチック類、ミックスペーパーに混入されているその他の紙類(コーティング紙、ロウ引き紙、プラスチック付き紙など)の選別を障害者に担当させ、さらなる雇用に結びつけようと検討中だ。まずは新たに障害者の実習を受け入れて2009年度中に方向性を定め、半年から1年後には本格的に作業発注を実現する構えだ。
「回収資源の解体・選別作業はマンパワーを必要としますが、破損などの心配がいらず、また、ノルマがなくおおよその目標で作業量が管理できるので、特性を生かした仕事であると考えています」と意欲を語る湯山さん。
選別作業の増加は、今後も障害者の職域拡大に寄与することができると、協同組合では期待している。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











