高次脳機能障害のある障害者をスタッフとして受け入れる中での、障害特性に配慮した環境整備の取組
- 事業所名
- 株式会社ヴィレッジ・ヴァンガードコーポレーション
- 所在地
- 大阪府大阪市
- 事業内容
- 「遊べる本屋」をキーワードに、書籍、雑貨類、CD・DVD類を複合的に陳列して販売する小売業
- 従業員数
- 195名
- うち障害者数
- 16名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 4 定型書類作成、郵便物仕分け、書類発送準備等の本社内事務、店舗業務 内部障害 0 知的障害 4 清掃、コミックパック、検品、値付け、品出し等の店舗業務 精神障害 8 清掃、コミックパック、検品、値付け、品出し等の店舗業務 - 目次
1. 事業所の概要
独創的に描かれたポップに目を引き店内に入ると、所狭しと書籍や雑貨が陳列されている。他の店では見かけない商品ばかりなので、店内を探索するだけでも十分に楽しむことができる・・・。ここ数年、大型ショッピングセンター内のテナントとして相次いで出店し、若い世代を中心に幅広い年齢層から支持を受けている店舗で、特に休日は買い物客で混雑が絶えない『ヴィレッジ・ヴァンガード』を知らない人は少ないのではないだろうか。平成21年2月現在で、全国で270店舗以上を展開している事業所である。
2. 障害者雇用の経緯、背景
当該事業所においては、本部における名古屋での事務系作業での障害者雇用については早くから取り組んでいた。しかし、各地での相次ぐ出店により事業所規模が急激に拡大する中、障害者雇用率の達成に向けた取り組みとして、店舗スタッフとしての障害者の雇用を積極的に取り組むようになったのである。本部機能がある名古屋地区の店舗において就労支援機関による人的サポートを活用した障害者雇用の取り組みに成果があったため、これまで障害者雇用に取り組んでいなかった関西地区も含めた全国の店舗でも、障害者就業・生活支援センター等の就労支援機関と連携のもとに、障害者雇用を拡げることとしたのである。
ここでは、関西地区での最初の障害者雇用の取り組みであり、また店舗スタッフとして知的障害者に限らず、高次脳機能障害のある障害者にも受け入れが拡がるきっかけとなった梅田ロフト店での事例を紹介する。

3. 当該事例における従事業務、職場配置
梅田ロフト店で働くAさんは、高次脳機能障害。約15年前の交通事故により受傷した。受傷時の後遺症として高次脳機能障害による記憶力や手順を整理する遂行機能障害と、人工股関節が埋め込まれたことにより長距離の歩行には杖が必要な状況となっていた。そのため、就労時の配慮として、複雑な作業工程や判断を要する業務、長時間の立位での業務を避ける必要はあった。
受傷後の15年間は、在宅での生活が続いていたAさんであったが、障害者雇用支援センターとの出会いにより、支援者のサポートを受けながらの企業への就労を目指すこととなった。当初は、体力面を考慮して、事務系作業での就労を検討していたAさんであったが、障害者雇用支援センターで体験的に実習体験を行った喫茶店での業務を通して、接客も含めたサービス業での就労に興味をもつようにもなった。そんなときに、梅田ロフト店での障害者雇用の話が持ち上がったのである。
当該の事業所での店舗での障害者雇用は、これまでは知的障害者の受け入ればかりであった。高次脳機能障害のあるAさんを受け入れるためには店舗での新たな配慮も必要とはなるが、梅田ロフト店での就労に前向きなAさんを受け入れるための、以下で報告するようなサポートを、店舗と就労支援機関の連携のもとに取り組んでいった。
4. Aさんに業務ができるための数々のサポート
(1)アルバイト従業員の教育プログラムをベースに
Aさんの雇用に先立ち、就労支援機関のスタッフが事業所に訪問し、当時の店長にも協力いただきながら業務の一つ一つの洗い出しを行い、梅田ロフト店でのAさんが勤務することを想定した職務分析を行った。当該の事業所にはアルバイト従業員の新人教育プログラムがあることで、この作業には多くの時間を要さなかった。新人のアルバイト従業員が最初に任される業務内容のうち、レジ業務等の煩雑なものを省いて、Aさんにとってわかりやすく、自信をもって取り組むことができる業務を中心に組み立てるようにすればよいからである。
このようにして選び出された一つ一つの業務を伝えていく際には、ジョブコーチの方法論に基づく支援も重要であった。例えば、店舗清掃の業務については、Aさんが判断に困らないように取り組むべき順序を前もって示すこととした。また、一つ一つの作業手順についても、必要な部分については就労支援機関のスタッフがAさんにモデル(見本)を提示しながら、着実に習得してもらうことを心がけた。
(2)バックヤードを整頓することで、全てのスタッフが働きやすく
店舗では、陳列と販売のスペースをできるだけ多く確保することから、必然的にバックヤードのスペースは限られてしまう。商品の入れ替わりが激しい店舗の状況からも、バックヤード内は入れ替えの商品で溢れる状況になりがちであった。バックヤード内で商品整理をすることが多いAさんにとっては、商品の場所を把握できずに混乱の要因となってしまう懸念があった。
当時の店長は、Aさんの受け入れに備えて、バックヤードを整理し、整然と商品を保管できるように環境整備を行った。これまでは、各スタッフの経験による『職人技』によって、商品の場所が理解されていた部分さえもあったのだが、Aさんだけでなく、他のスタッフにとっても仕事がやりやすくなる事業所環境となっていったのである。
(3)スケジュール表の活用はメモリーノートがわりにも
店舗では、一定のキャリアを積んだアルバイトスタッフが日替わりで『リーダー』となり、その日の全スタッフの業務分担を指示する役割を担うこととなっている。当然、Aさんの仕事についても、日ごとに異なる『リーダー』が指示することになるのだが、Aさんが「できる仕事」と「できない仕事」を『リーダー』が把握していなければ、業務内容を指示することもできない。そこで、それぞれの『リーダー』がAさんに業務内容を指示するためのツールとして、スケジュール表を活用することにしたのである。
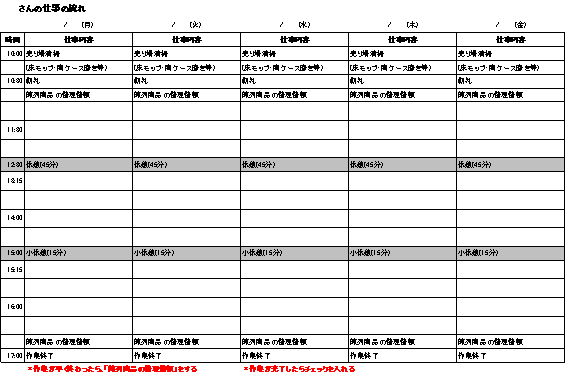
店舗の清掃等で毎日決まっている業務以外の部分において、その日のバックヤードでの作業でAさんに依頼したい業務内容を、業務開始時に書き記しておく。Aさんはスケジュール表を確認しながら、一つ一つの業務に取り組み、指示された時間までに業務が終わった場合でも、業務の途中で時間になった場合も、スケジュール表にAさん自らが結果を書き込むのである。そのことで『リーダー』はAさんの業務の進捗状況を把握することができるとともに、翌日の『リーダー』もAさんが前日までに取り組んできた業務の内容と完了していない業務の有無を踏まえた上で、Aさんの業務内容を検討することができるのである。
スケジュール表は、店舗スタッフにとっては、Aさんに業務指示をする際の合理的なコミュニケーションが可能となる配慮ではあったが、Aさんにとっては次に述べる点でも安定した就労に効果のあるツールとなった。
Aさんは、先にも説明したとおり、交通事故による脳損傷の後遺症による高次脳機能障害も持ちあわせており、記憶の保持にも困難な部分がみられる。そんなAさんに対しては、スケジュール表は、記憶障害を補完するためのメモリーノートのような存在になったのである。スケジュール表には、その日のやるべき業務内容が書き込まれ、業務中のAさんが常に確認できるからである。
仕事にも慣れてきたAさんは、今ではスケジュール表は必ずしも活用していないという。それでも、ときには『リーダー』から口頭で指示された内容を忘れないよう、スケジュール表に記入し、業務に活かしていることもあるとのことである。
(4)受傷の後遺症である体力面にも配慮をして・・・
交通事故の後遺症により長時間の立位作業が困難なAさんに対しては、体力面からも店舗での業務内容に配慮をする必要があった。
具体的には、店舗内の掃除、店内の陳列商品の整理整頓といった立ったまま行う作業と、商品の値付けや本にラップを巻く作業等のバックヤードにおいて座って行う作業を、交互に行うことができるような作業スケジュールが構成できるようにしたのである。写真のように、座ってできる商品である自転車の組み立て作業の後は、店内の整理整頓の業務を行う・・・といった具合である。これによって、朝から夕方まで店内業務に取り組むAさんの体力的な負担は随分と軽減されたようである。
また、休憩時間の設け方についても、配慮がなされた。Aさんの就業時間は、午前10時から午後6時で、その間に1時間の休憩時間が設けられている。そこで、昼食の休憩時間は45分、それとは別に午後3時前後に15分程度の小休憩が取れるように、休憩時間を2つに分けるような柔軟な対応をとったのである。午後の15分間の休憩を設けて、肉体的な疲れが溜まることを軽減できたことは、Aさんが無理なく長時間の業務に取り組めていることの要因の一つとなっている。

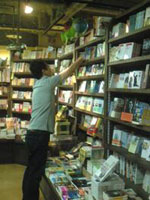
(5)何よりも職場の仲間として受け入れられること
梅田ロフト店に限らず、当該事業所のスタッフはアルバイト従業員が中心ということもあり、従業員の平均年齢は随分と若い。そのため、Aさんとは10歳以上離れている人がほとんどである。
しかし、仕事に対して生真面目に取り組みながらも、ユーモアも随所に織り交ぜるAさんの人柄は、障害者雇用の枠は関係なく、すぐにスタッフに受け入れられた。幾度となくスタッフ間の飲み会にもAさんは参加し、作業の合間でも他のスタッフとの間での冗談のやり取りが頻繁にみられる。事業所側の物理的な配慮があっても、障害者にとって一緒に働く人に受け入れられている実感がなければ、障害者にとって働きやすい環境とはなりえない。Aさんを受け入れる職場の風土があるからこそ、より前向きにAさんは業務に取り組めるのだと思われる。
5. 取り組みを振りかえって
当該事業所では、梅田ロフト店での取り組みの後、関西地区だけでも4名の障害者雇用を新たに実現し、障害者雇用率についても計画どおりに達成している。また、この間の取り組みを踏まえて、さらに障害者雇用の受け入れのない店舗のうちの数店においても、新たな雇用に取り組む予定にしている。
梅田ロフト店での取り組みは、高次脳機能障害のある人が、店舗業務に従事する可能性を持っていることを実証した結果となった。ここでの取り組みを通じた配慮の内容は、障害者が担う業務内容と、現場スタッフから障害者スタッフへの業務指示を「より明確に」「よりわかりやすく」していく取り組みに集約される。
知的障害者等の雇用受け入れの際にも十分に汎用が可能なこれらの取り組みは、基本的ではありながらも重要な、障害者雇用を拡げるための視点といえる。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











