公的機関(国立大学法人神戸大学)における障害者雇用の取り組み
- 事業所名
- 国立大学法人神戸大学
- 所在地
- 兵庫県神戸市
- 事業内容
- 高等教育機関(総合大学としての教育・研究機関)
- 従業員数
- 4,050名
- うち障害者数
- 35名
障害 人数 従事業務 視覚障害 2 大学事務、環境整備 聴覚障害 3 病院業務、教育・研究 肢体不自由 17 大学事務、病院業務、教育・研究 内部障害 3 大学事務 知的障害 10 環境整備(清掃、植木剪定等) 精神障害 0 - 目次


1. 事業所の概要
国際都市神戸に位置する神戸大学は、「異文化との交流」を重視し、国際性豊かな総合大学として発展を続けている。「人文・人間科学系」「社会科学系」「自然科学系」「生命・医学系」の4大学術系列の下に11の学部、13の大学院、1研究環、1研究所と多数のセンターを持つ総合大学である。「知の生命体としての大学」を目指して「異分野との交流」を重視し、教育・研究交流はもちろん、大学の第三の使命である社会貢献のために産学官民連携を積極的に推進することとしている。
神戸大学は、開放的で国際性に富む固有の文化の下、「真摯・自由・協同」の精神を発揮し、人類社会に貢献するため、普遍的価値を有する「知」を創造するとともに、人間性豊かな指導的人材を育成することを使命として掲げている。そして更なる飛躍に向けて、2015年までに研究・教育における「グローバル・エクセレンス」の実現を目指している。
神戸大学は、昭和24年5月に設置された国立大学で、文部科学省に属する国の機関として運営されてきたが、平成15年7月16日に成立した国立大学法人法の施行により平成16年4月1日から公的な性格を有する国立大学法人として組織変更を行った。
2. 障害者雇用の経緯
神戸大学における障害者雇用率は、以前は法定雇用率を上回っていたが、平成16年度から従来の除外職員制度(各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる職員数を算定する際に、一定の範囲の職種に従事する者を控除する制度)による職種の見直しが行われ算定方法が大きく変わった。神戸大学では旧除外職員である職種に従事する職員が多かったため、障害者雇用率は突然急降下し障害者数が一気に11人も不足する事態となった。
これまで、神戸大学における障害者雇用については、特別な施策を講じることはなく、たまたま不幸にして病気や事故などのため、障害者手帳の交付を受けるに至り、その人数が法定雇用率を満たすという状態で推移してきたのが実態であった。
障害者の法定雇用率を下回った直後、兵庫労働局から指導を受け、平成17年1月を始期とする3年間の障害者の雇い入れに関する計画の作成を命じられた。早速、障害者雇用計画の作成に取りかかり、平成17年3月に「障害者雇用3ヶ年計画」を提出した。
その後、法定雇用率を達成するための具体的な計画立案を行い、順次、重度知的障害者の雇用を継続していく中で、平成19年7月に法定雇用率を達成したところである。
3. 障害者の勤務状況
現在、重度知的障害者は、第1班に2名、第2班に4名、第3班に3名、計9名が環境整備員として雇用されているが、環境整備業務としての対象区域は、神戸市灘区六甲台町(六甲台地区)の丘陵地に所在する広大な「神戸大学六甲台・鶴甲キャンパス」の全域が対象であり、3つの班でその受け持ち区域を分けて作業を行っている。
環境整備員として雇用されている重度知的障害者は、各班ごとに各1名配置されているコーディネーター(指導員)から、その日に行う作業内容の指示を受けて、主として建物屋外とその周辺部の清掃を行っている。
勤務時間は、1日6時間、週あたり30時間勤務の非常勤職員として勤務している。重度知的障害者は、神戸市内や宝塚市から電車とバスを乗り継いで通勤している。
キャンパス内に作業グループ専用の休養室を2箇所新設し、休憩時間には指導員と障害者の意思疎通や団欒の場として活用されている。


4. 取り組みの内容
今回の障害者雇用策については、当大学総務部人事課及び施設部施設企画課が中心となって取り組んだ。平成17年3月に「障害者雇用3ヶ年計画」を提出した時点では、どのように対応したらよいか分からず、ハローワークが企画する障害者雇用促進セミナー、工場見学、合同面接会の見学などに参加しながら検討していたところ、ある大学で知的障害者を構内清掃作業員として10人ほど採用したという話を聞き、早速その大学に連絡をとり実現までの経過やノウハウなど色々なことを教えてもらい貴重な情報を得ることができた。
障害者を雇用して行う業務として検討したのは、広大な「神戸大学六甲台・鶴甲キャンパス」の建物屋外と周辺部の清掃及び植木の剪定等を対象とした環境整備業務として位置付け、重度知的障害者の雇用を一つのプロジェクトとして取り組むこととした。
これまで、外注してきた清掃業務の関係書類のすべてについて、知的障害者が出来そうな業務の分析を行い、ある大学の事例を参考に、外回りの清掃作業を中心に抜き出した。(業務内容一覧参照)
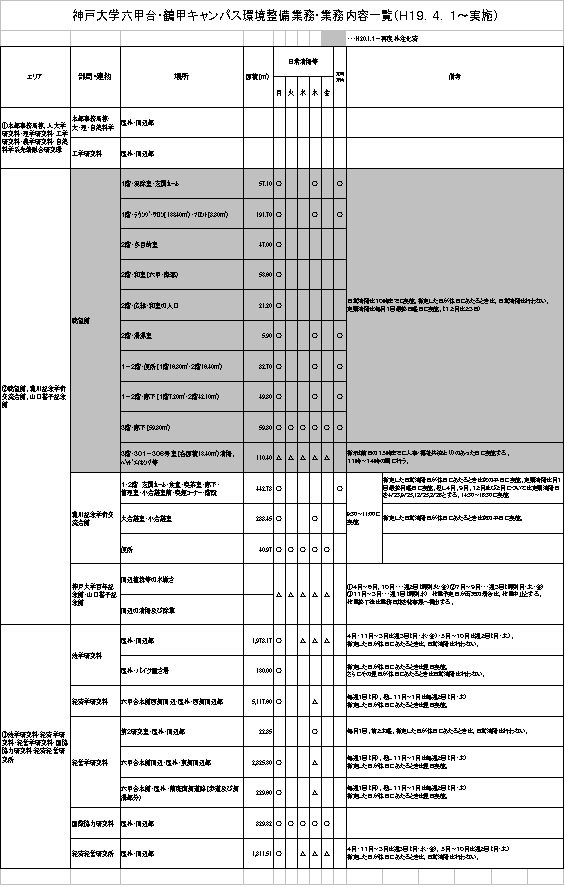
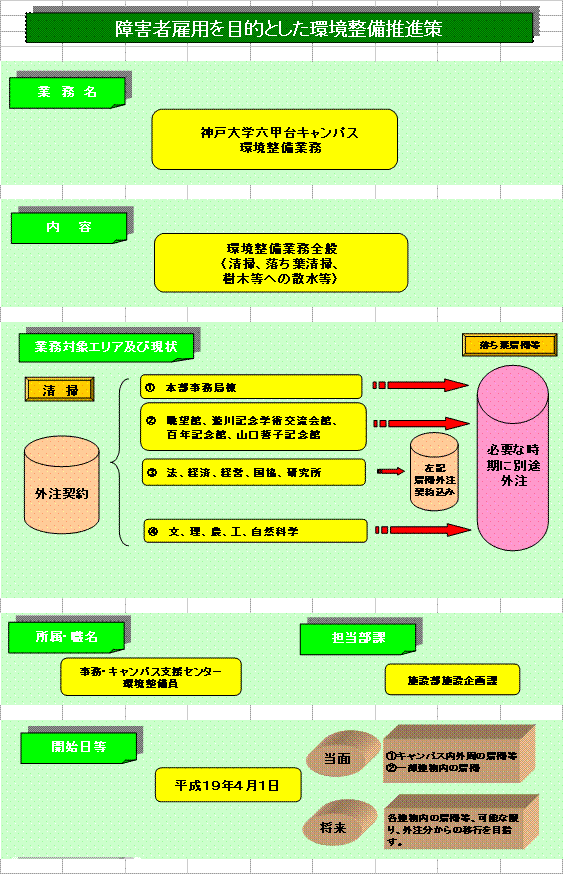
平成18年11月に、具体的な計画を立案し、平成19年4月稼動を目指すこととした。しかし、大学内部の財政事情から「新たな財政支出を伴なわずに行うように」との条件が付された。これまでの外注経費を調べると極めて安価であることがわかり、抜き出した作業量に見合った障害者の雇用人員に必要な人件費を外注経費から転用することができず、少ない人数でのスタートとならざるを得なかった。(環境整備員等の配置計画ご参照)
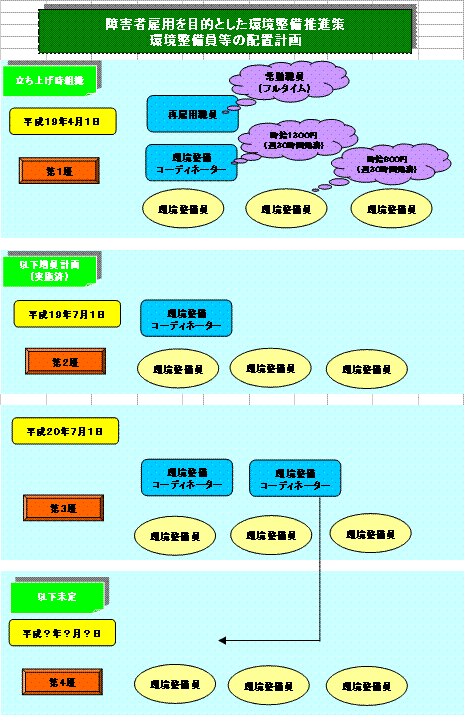
さて、数字の上では何とか雇用に必要な人件費を捻出することができたが、実際にその額を確保するためには、各関連部署と折衝して了承を得なければならなかった。財務部をはじめ関係する10ヶ所ほどの学部等に出向き、それぞれの責任者と会計事務担当者に、「外注を一部取りやめるので、その分を障害者雇用の経費に使わせてほしい」と説明して回った。「そんなこと本当にできるのか?予算を吸い上げる以上は、きっちり清掃をしてもらわないと困りますよ」というような厳しい意見もあったが、年末ぎりぎりに何とかすべての部署の了承を得ることができ、それと同時に、正式に「障害者雇用対策」が神戸大学内のしかるべき会議において了承された。
また、障害者雇用に取り組む中で、ハローワークの担当者には、面接の手配や助成金制度等、常に惜しみないご協力をいただき、平成19年2月に第1回の面接会を開催することができた。その間、当大学内では、施設部を中心に休養室の建設も急ピッチで進み、環境整備員達が着用するユニフォームのデザインや専用の作業靴の選定、清掃用具類の準備など着々と進み、何とか目標どおり、平成19年4月に第1班の誕生というところまでこぎつけることができた。
ここで言えることは、担当者が「必ず実行するんだ」という揺るぎのない熱意を持ち続けること。そして、内外を問わず、できるだけ周囲の人の協力を得ていく。それが障害者雇用を推進していくうえで、大事なポイントの一つではないかと思われる。
立ち上げ時の体制は、環境整備コーディネーター(指導員)1名、環境整備員として重度知的障害者3名、そして最終段階で、その年度末に定年を迎える事務職員の一人が、定年後の再雇用職員として、この作業班のまとめ役及び大学と現場とのつなぎ役として配置され、総勢5名によるスタートとなった。
立ち上げ当初は、外回りの清掃だけでなく、雇用経費を捻出するために、宿泊施設のベッドメイキングといった作業難易度の高いものも外注から回さざるを得ず、そのことが加重な負担となって当初の作業メンバーを苦しめることになった。
また、広大なキャンパスをたった5人で清掃しなければならなかった当初のメンバーの苦労は、筆舌に尽くしがたいものがあった。
ただ、立ち上げた以上、力を合わせてやれる限りのことを精一杯やって、その姿を評価してもらい、その結果として早期に作業班を増やして作業量に見合った体制を築くことが次の目標となった。
その後、平成19年7月に第2班、翌年6月には第3班を設置することができ、今や総勢13名の大所帯としてキャンパス美化に取り組むに至っている。
5. 障害者雇用の効果・メリット
環境整備業務として立ち上げた当初は、「全然綺麗になってないやないか」「ゴミ箱があふれているで」「予算だけ吸い上げておいて何してるねん」など僅かながら批判の声が寄せられていたが、多くの人達は辛抱強く見守っていてくれたので、第2班が入った後は「去年外注していた時よりも綺麗になったよ」とか「皆ホントによく頑張ってるね」と、嬉しい言葉もかけてもらえる機会が増えてきた。また、以前は学生がタバコのポイ捨て等をしていたが、一生懸命清掃している障害者の姿を見て、タバコのポイ捨てはなくなり、「ご苦労さま」と声をかけるようになってきたことが大きな変化である。
また、障害者が徐々に作業にも慣れ時間に余裕ができて、本来作業しなくても良い場所も積極的に清掃するようになり、さらに「建物の中もやりたい」など現場からは更なる意欲的な声も聞かれるようになった。実現の可能性については、十分に見極める必要があるが、いずれは外回りの清掃だけではなく、建物内の清掃についてもできるところから外注を取りやめてみようかと検討しているところである。




6. 障害者等のコメント
(1)障害者及び家族のコメント
雇用した障害者は、就業経験のある人、ない人、年齢も上は60歳を超えている人、下は20歳台前半の人、性別も男性・女性と様々な人が在籍している。皆、出会えば気持ち良く挨拶し、口を揃えて「神戸大学を自分の手で綺麗にしたい」と言ってくれる。また、「もらった給料で、家族に恩返しをしたい」あるいは「将来家を建てたい」と夢を語ってくれる人もいる。皆、定刻の30分前には出勤し、休むこともほとんどなく、一生懸命頑張っている。仕事を覚えるまでには、かなりの時間がかかったのは事実であるが、日々の積み重ねの中で、確実に個々人の作業能力が向上しており、キャンパス美化が想像以上の早さで実現しつつある。
また、障害者の家族については、面接後に合格の連絡をすると「まさか合格できるとは思っていなかった」と皆さんとても喜んでくれるし、「社会的に自立すること」を何よりも強く望んでいることがわかる。
(2)コーディネーターのコメント
障害者雇用の経験がある沖さん(第2班)は、「一人一人それぞれ障害の度合いが違うので個々に対応している」とのこと。また、「カラ返事をする、勝手に行動する、指示事項を忘れるなどの欠点もあるが、繰り返し地道に指導している。障害者が怒られているのを学生が見て興味を持ち、障害者に対して挨拶が多くなってきた。学生のペットボトルやタバコのポイ捨てが以前に比べて少なくなった。マナーが良くなった。教育面で良い結果が生じている」と話す。
「挨拶が出来ない。字が書けない者もいるので、休憩時間等を利用して自分の名前を漢字で書かせたり、数字の1から10までを毎日ノートに書かせたりして覚えるように指導している」とのこと。
7. 障害者雇用計画達成のために進行中のプロジェクト
(1) 平成19年12月より、神戸大学発達科学部附属特別支援学校(旧養護学校)で、卒業生(重度知的障害者)1名を清掃スタッフとして雇用している。卒業生が母校で働く姿を直接在校生に見てもらうことによって、在校生自身が将来社会に出ることをイメージしてもらうための大きな力となる。
また、そのための良きお手本としての役割を担ってもらうというのが大きな目的である。現在、業務もしっかりこなし、また、在校生への良い刺激になっているとの報告を受けている。
(2) 障害者雇用をフィールドとした社会人学生支援強化プログラム
国から助成を受けて、平成20年4月より人間発達環境学研究科というところに、カフェ(喫茶店)を設置して、そこで重度身体障害者(車いす使用)にフロアマネージャーとして活躍してもらっている。そして、このカフェでは、常時3人から4人の知的障害者が喫茶業務を通じた就業訓練を行っている。この取り組みは、将来、国からの助成が途絶えることになったとしても、神戸大学としては継続していきたいと考えている。
8. まとめ
障害者雇用の取り組みをした中で、表に出ない様々なトラブル、ほとんどは人間関係を巡るものだったが、その対応については試行錯誤の繰り返しであった。指導者と環境整備員(障害者)の間で険悪な関係が生じたり、同僚からのちょっとした言葉で心が傷つき翌日出勤できなくなってしまった者がいたり、いずれも結果としては、何とか乗り越えることができたが、障害者雇用について組織として動かしていく難しさを痛感することとなった。
対処方法については、まずトラブルの原因を突き止めること。これが当然のことながら最も重要なことである。コミュニケーションの不足と、コミュニケーションの方法に問題があったことが主な原因であった。当初、指導員は、作業量に見合った人員が確保されていない中で、どう環境整備員のメンバーを指導していったら良いのかに悩み、また、給料をもらって行う以上は、清掃作業をきっちり仕上げなければならない。そういうプレッシャーの中で指導を行っており、作業の担い手である環境整備員は、なかなか思い通りに動いてくれない。作業工程を覚えるのに時間がかかる。そのような状況でお互いストレスがたまり、結果として衝突してしまう。そのような悪循環が生じてしまった。何度も担当部署と現場とが話を重ね、第2班が入るまでは暫定的に外注業者を入れるなどして、清掃業務のサポート体制をとった。
その後、第2班が入ったことで作業負担も大幅に軽減され、また、業務管理担当部署の施設企画課と人事課とで部署を越えた連携体制を深め、そこに現場の指導員も加わってミーティングを行っている。現場の生の声を直接耳にすることは大変大事なことであると思われる。それから、やってみて無理だと思う仕事は、思い切って再び外注に戻すなど、当初の計画を考えれば勇気のいることであったが、迅速かつ柔軟に対処するということも必要なことであると考えている。
障害者雇用率については、今回の取り組みによって達成したところであるが、現在、激変緩和措置として設定されている除外率は、いずれ廃止されることになるので、今後も引き続き障害者雇用を推進していくことが必要であると考えている。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











