特例子会社がグループ会社を啓発し、障害者雇用を推進させている企業
- 事業所名
- 宇部興産株式会社
- 所在地
- 山口県宇部市
- 事業内容
- 化成品・樹脂、機能品・ファイン、建設資材、機械・金属成形、エネルギー・環境の事業分野の各種製品製造等
- 従業員数
- 4,919名
- うち障害者数
- 61名
障害 人数 従事業務 視覚障害 2 ヘルスキーパー 聴覚障害 7 PCオペレータ、機械オペレータ、製本オペレータ 肢体不自由 29 PCオペレータ、製造オペレータ、事務・営業職、技術職 内部障害 13 事務・営業職、技術職 知的障害 9 PCオペレータ、清掃 精神障害 1 経理事務 - 目次

(山口県宇部地区)

1. 事業所の概要
宇部興産株式会社は、創業から100年以上の歴史を有する大手総合化学メーカーであり、国内の工場は、山口県宇部地区の工場群を中心に、千葉、堺、伊佐(山口県)、苅田(福岡県)に広がる。海外ではスペイン、タイなどに化学製品を生産する拠点を設け、国際的な市場でも活発に活動している。当社が関与するグループ会社は全国に約160社を数え、その事業内容は化学、建設資材、機械、運輸、商社などのほか、近年は情報処理、エレクトロニクス、印刷などの分野まで含み、極めて広範囲である。
当社の人事部人事グループの主席部員である西本靖氏と早坂卓氏に話を伺った。
「私ども宇部興産株式会社は、連結経営を重視しており、グループ全体で企業競争力を高めようとしております」
グループ会社とともに経営戦略を立てる大企業としてのスタンスである。
2. 大企業としての社会的責任
(1)障害者雇用を推進する
近年、企業にはその社会的責任(CSR)の一環として、地域社会への貢献も問われる時代となった。この点について伺った。
「当社が地域貢献として重視しているのは、①収益をあげ、国・地方自治体に税金を納めること、②環境への配慮をすること、③雇用(障害者、高齢者等)の推進をすること、の三点が中心です。環境への配慮につきましては、UBEグループ全体で省エネ、燃料転換、廃棄物利用等により、2010年度の二酸化炭素排出量削減目標を12%(1990年度比)としています。障害者雇用の推進につきましても、重要な社会的責任としてとらえ、取り組んでおります。特例子会社である有限会社リベルタス興産が鋭意先導しているところです」
(2)特例子会社がグループ会社を支援する
宇部興産株式会社には、障害者雇用の推進をめざす特例子会社「有限会社リベルタス興産」が設立され、企業としての障害者雇用率を既に達成しているという実績がある(平成19年6月現在で2.06%)。しかしここで歩みを止めることなく、特例子会社で培われた障害者雇用のノウハウをグループ会社に広く提供し、そこでの障害者雇用を進展させようとする取り組みのあることが、宇部興産株式会社の大きな特徴である。
「リベルタス興産の代表取締役社長の有田信二郎氏が、当社人事部と共にグループ会社に声をかけ、平成18年7月に学習会(研修会)を発足させました。この会の名称を“UBEグループ障害者雇用支援ネットワーク”といいます。学習会での情報交換を通し、障害者雇用に向けての企業側の不安感を無くそうという試みです」とのこと。
3. 特例子会社「有限会社リベルタス興産」
有限会社リベルタス興産は、「保護より機会を!」の趣旨のもと、宇部興産株式会社の特例子会社として平成3年に宇部市に誕生した。業務内容としては、まず印刷業務から開始し、平成12年にデジタル業務、平成15年に清掃業務に着手した。平成20年現在で、従業員数40名、障害者26名(その中で重度障害が21名)である。障害の内訳は、身体障害17名(聴覚障害7名、脊髄障害3名、脳性麻痺3名、その他4名)、知的障害9名(その中で自閉症が3名)である。
前述したように、リベルタス興産は、宇部興産株式会社とそのグループ会社における障害者雇用の推進役を担っている。
(1)無知と不安を払拭する
代表取締役である有田信二郎社長に話を伺った。
「特例子会社に障害者を数多く雇用させることで、雇用率を達成させようとする企業は、全国に存在します。ほとんどの障害者雇用を特例子会社が支えるという図式です。これも一つのやり方ですから、私はこれを否定しません。でも、これだけが正しいやり方なのだろうか、という思いが私のなかにあるのです」
特例子会社としての役割は、障害者雇用率の達成のためだけにあるのではない、と有田社長はとらえる。
「障害者雇用を妨げている要因の一つは、企業側にある無知と不安です。障害についての知識が少ないために、雇用に不安を感じ、躊躇してしまうのです。そこで、私たち特例子会社がグループ会社に向けて情報を提供することにより、その無知と不安を解消していけるのではないか、と考えました」
特例子会社で培われた雇用のノウハウを、グループ会社に広く提供することで、ひいてはグループ会社での障害者雇用を進展させていくことが、有田社長の夢である。
「企業が安心して障害者を雇用できる環境を、グループ会社のなかにつくっていきたいのです。企業に提供できる価値を有している障害者は多いのですから」
特例子会社には積極的発信の役割もある、ととらえる有田社長は、次の三つの内容を中心とした発信をこれまで継続してきた。
(2)三つの発信
①グループ会社に向けた学習会の開催
平成20年現在、UBEグループ障害者雇用支援ネットワークが主催する学習会に、現在約20のグループ会社が、2ヶ月に1回のペースで集っている(午前中の1時間半)。
この学習会は、障害者雇用に関する様々な情報について、本音を交えながら研修することを目的としている。リベルタス興産での障害者就労の現場や、特別支援学校(旧名称;養護学校)の授業を見学したり、関係諸機関との連携や助成金制度等について学習したり、雇用事例を発表する活動などを通し、雇用の具体的なノウハウを研修している。
学習会のポイントとして、有田社長は「本音での対話」をあげる。
「本音での対話をしなければ、障害者雇用は絶対進みません。多くの人が、障害者に対する固定観念をもっているのが現実です。一例をあげると、障害のある人には力仕事は無理である、といったとらえです。こうした本音の部分をまず表に出させることが必要です。それらに対して私たちが必要な情報を提供することで固定観念を変化させ、不安や悩みを解消させていきたいのです」
この学習会を開始した当初は、雇用にまつわる不安や悩みを率直に語ることに躊躇する空気が強くあった。しかし、発足からの2年間でこの学習会は10回開催され、グループ会社9社のなかで計13名の障害者雇用を実現させるという結果を生み出した(障害種別は聴覚障害、肢体不自由、知的障害)。これらの新規就労者は、そのほとんどが現在も安定就労している。
「この学習会を開催する前までは、グループ会社のなかでも、障害者雇用に対して否定的な意見が多かったのは事実です。例えば、『うちの会社では障害者雇用は無理です。』『特例子会社のリベルタス興産さんだから障害者雇用ができるのですよ。』といった声を聞いてきました。でも、一人の障害者が雇用につながった時から、次の雇用が展開し始めたのです。『あの人、なかなか仕事ができるね。』『自分の会社にも一人欲しい。』『二人目も欲しい。』といった言葉をグループ会社から聞けるようになり、障害者雇用が進み始めました」
UBEグループ障害者雇用支援ネットワークによる学習会は、着実にその成果を上げつつある。
「一つ一つの雇用事例が成功事例となるようにしたいですね。これからも学習会の取り組みを継続していきたいと思います」と有田社長は語る。
有田社長は、グループ会社に対してのみでなく、地域の一般企業や、事業所見学に訪れた学生、保護者、教師たちにも、自身の熱い思いを伝えている。

②通称「手話ネット」(聴覚障害者遠隔支援システム)の開設
重度の聴覚障害者にとって、その母語は手話であるといわれている。通常の業務については口話や筆談で進めることが可能であっても、込み入った複雑な話題や、感情が介在するような話題では、手話活用の必要度が高くなる。宇部興産株式会社のグループ会社には、そのうちの3社に各1名ずつの聴覚障害者が雇用されているため、手話も活用した相談支援体制づくりが急務である。しかし、各会社に専任手話通訳者を雇用することは容易ではない。そこで、リベルタス興産で現在勤務している専任手話通訳者(1名)の活躍の場を、グループ会社にも広く展開させようとする試みが、平成20年6月に開始された。リベルタス興産とグループ会社とを通信回線でつなぎ、動画と音声によるリアルタイム通訳を行うことで、強固な相談支援体制をつくる取り組みである。


「手話ネットというアイデアは、リベルタス興産の社員のなかから生まれました。パソコンとネットワーク環境さえあれば、5万円程度の出費により、専用ソフトやWebカメラなどの必要機材を備えることができ、動画と音声の送受信が可能になります。宇部興産株式会社は、日本の北から南まで多くの事業所やグループ会社がありますので、このシステムが完備すれば、日本中どこでもリアルタイムでの相談支援が可能になります」
聴覚障害の従業員にとってもグループ会社にとっても、このリアルタイムの相談支援体制は心強い。今後の展開に関係者の熱い視線が注がれている。
③ガイドブックの作成
リベルタス興産では、長年の聴覚障害者雇用の経験をもとに、平成18年から19年にかけて2冊のガイドブックを作成した。「聴覚障がい者雇用支援のために‐豊かな職場生活を願って‐」(全7ページ)と「聴覚障がい者雇用事例集‐豊かな職場生活を願って‐」(全11ページ)である。
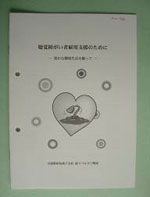

職場内での良好な人間関係を築くためには、円滑なコミュニケーションがその要となる。しかし、聴覚障害は目に見えにくい障害であることを一因として、健常者にはその実態を理解しにくい面があり、予期せぬトラブルによって職場内の人間関係が悪化することがある。そこで、このガイドブックの活用により、会社側が事前に障害特性を理解し、適切な支援を継続することによって、円滑な就労生活の実現することが期待されうる。
これらのガイドブックは、「聞こえない」という状態の解説から始まり、コミュニケーションの方法や職場で役立つ機器類、勤務上のトラブルと解決方法などが、写真などを含めて大変わかりやすく記載されている。グループ会社にとって、心強いガイドブックといえよう。
4. 障害者雇用の知見を明日につなぐ
特例子会社の存在意義を問い、一つの方向性として、持てる知見とノウハウをグループ企業全体へ提供することで、障害者雇用の底上げを図っているユニークな取り組みである。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











