働きやすい職場環境を創り、雇用継続と安定に努める
1. 事業所の概要
昭和38年に池田学園(知的障害児入所施設)が開設認証されて以降、箸蔵山荘、池田療育センター、セルプ箸蔵、障害者支援センターはくあい、永楽荘等が開設され、高齢者ケア総合センターと障害者支援総合センターの2つに分け運営している。平成2年には「箸蔵福祉村」(※1)が設立されるなど、古くから地域で障害者と共に歩んできた経緯がある。現在12事業所、職員数297名となっている。
また、毎年、法人3大イベントとして博愛まつり、ふれあいフェスティバル、理事長杯ソフトボール大会を開催し、施設を利用される方もそうでない方も、共に集い同じ地域で生活し、障害者への理解を深める交流の場として開催している。
(※1)箸蔵福祉村は、各種の福祉施設の設置を機会に利用者と住民との積極的な交流を含め、ボランティア活動等も広めながら、福祉の心豊かな郷土をつくるために平成2年に設置された。
高齢ケア総合センター
| 名称 | 種別 |
|---|---|
| 永楽荘 | 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム |
| 永楽荘デイサービスセンター太陽 | 通所介護事業所 |
| 永楽荘デイサービスセンター月 | 通所介護事業所 |
| 永楽荘デイサービスセンター星 | 通所介護事業所 |
| 永楽荘在宅介護支援センター | 在宅介護支援事業所 訪問介護事業所 訪問入浴介護事業 |
| 永楽荘第一在宅介護支援センター | 在宅介護支援事業所 訪問介護事業所 |
| ケアハウス宝珠 | 軽費老人ホーム |
障害者支援総合センター
| 名称 | 種別 |
|---|---|
| 箸蔵山荘 | 知的障害者更生施設 |
| 池田学園 | 知的障害児施設 |
| 池田療育センター | 知的障害児通園施設 |
| はくあい | 障害者生活支援センター |
| セルプ箸蔵 | 知的障害者通所授産施設 |
| 沿革 | |
| 昭和38年3月1日 | 財団法人池田学園として設立 |
| 昭和43年5月1日 | 箸蔵山荘開設 |
| 昭和52年4月25日 | 社会福祉法人池田博愛会に経営主体変更 |
| 昭和54年4月1日 | 精神薄弱児通園施設池田療育センター開設 |
| 昭和56年4月1日 | 特別養護老人ホーム永楽荘開設 |
| 平成元年4月1日 | 箸蔵山荘 通所部開設(5名)・・・現在(19名) |
| 平成2年4月1日 | グループホーム開設(4名)・・・(現在、現員52名・11ホーム) |
| 平成13年 | 知的障害者通所授産施設 セルプ箸蔵開設 |
| 平成16年 | ジョブコーチ支援事業開始 |
| 平成17年4月1日 | 障害者就業・生活支援センター事業受託 |
| 平成19年4月2日 | ISO9001認証取得 |
2. 障害者雇用の経緯
事業所のある地域には、特別支援学校が近隣にあり、卒業生からの実習受け入れや就労希望が多数ある。しかし、徳島県西部の地域性として、従業員数を56名以上抱えている事業所が約30件程度、200名を越えている事業所も少なく、障害者の受け入れが困難な状況である。
法人の施設関係では組織が大きく、部署別に仕事が細分化されており、障害者が実施できる仕事を単純化することが出来るため雇用に繋がっている。
また、箸蔵地区は、地域に多数の福祉関連施設があり、障害者就業・生活支援センターも存在することや、ホームも充実しているため、障害者に対して就業、生活が一体となった支援体制が整っている。
3. 障害者の従事業務
各事業所では、業務を細分化し、障害者ができる作業を明確にしている。また、一人で業務を行うのではなく、担当職員を配置し、業務支援や指導が行える環境を創っている。下記に障害を持たれている方が実施している業務を紹介する。
○ 高齢ケア総合センター
洗濯・・洗濯機で回し、乾燥機から出てきた衣類をたたむ。タオル類はたたんだ後、所定の場所に片付ける。時間がある場合は、職員の指示により、ゴミ集めや介助員補助を実施している。


調理業務補助、食器などを洗浄し、所定の場所に戻す作業を実施している。


○ 障害者支援総合センター
施設全体の清掃を実施している。掃除機がけ、掃き掃除、拭き掃除、ゴミ集めなどを実施している。


調理補助で食材の皮むきや下処理を行っている。午後からは、食材の仕分け作業を実施している。食材の仕分け作業については、最後に確認は必要であるが、ほぼ一人で仕分け作業が出来るようになった。


4. 取り組みの内容
(1)職場適応訓練の活用
特別支援学校を卒業した方を対象に、職場適応訓練を活用している。この制度を活用することにより、指導員の支援を受けながら、卒業後の雇用に向けて、焦ることなく細かい指導を受けることができている。この期間で、勤務上の課題点や作業環境に適応できているかなどを明確にし、対応の方向付けを行うとともに、本人の仕事に対する不安を解消し、現場スタッフとうちとけるよう働きかけている。
(2)職員配置と教育訓練
障害を持たれている方が従事している業務を、職員とペアで実施している。作業を細分化し、一つ一つ細かく段階的に職員が指導を行っている。このことにより、確実に一つ一つ業務がこなせるようになり、次の段階の業務も覚えやすくなっている。
また、教育訓練で職員月報を活用し、OJTにより指導者との毎日の意思疎通を図っている。
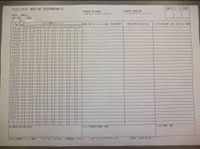
毎月目標を決め、毎日目標に対して取り組みが出来たかを自分で評価している。
また、指導者が毎日確認することにより、本人の悩みや、出来ていないことの早期発見に役立てている。
(3)ホームとの連携
全ての方がホームを利用されている。本人が居住するホームから事業所まで、徒歩5分程度であり、生活面も含めてトラブルや課題が生じた時は、障害者就業・生活支援センター「箸蔵山荘」と連携し、問題解決に当たっている。
また、ホーム職員と事業所が連携することにより、毎日の体調管理や勤務の調整、本人の悩みを早期に解決することができ、仕事の継続性や仕事に対する意識の向上を図っている。本人たちも相談者が増えることにより情緒の安定が図れている。


(4)事例紹介
【事例紹介1】
清掃業務をしているAさんの事例について。
実習から箸蔵山荘にて訓練をする。最初から一日の仕事をするのではなく、勤務時間や勤務形態を段階的に増やすように支援している。作業に関しても、一人で行うのではなく清掃職員とペアで作業することにより、一つ一つの作業手順が詳しく説明でき、作業の習得と安定を図ることができた。このことにより、最初の段階では何をするのでも不安が多く、決まった時間に出勤することができていなかったが、現在では施設の勤務表に従い5時間の勤務をこなしている。
生活面では、まだまだ不安定なところが多く、ホーム職員や障害者就業・生活支援センターと連携を取り、安定して仕事に通えるように生活面から支援している。
【事例紹介2】
厨房補助業務として、食材の仕分け下処理補助をしているBさんの事例について。
Bさんは、他事業所で介護補助や製造業に勤務されていた経験があるが、意思疎通が不十分であることや、会社に不満があり退職されている。母親より障害者就業・生活支援センター「箸蔵山荘」に就業相談があり、同法人の箸蔵山荘と連携を図り、実習を開始する。実習中の課題として、意思疎通が難しいことや、作業を覚えていないことなどが揚げられたが、まじめに仕事に取り組む姿勢が評価され雇用される。このときに、生活面と就業面の一体的な支援を行うためにホームへの入居も同時に勧める。
また、雇用後は雇用定着を図るため、作業の指導責任者を任命し、指導内容を決め引き続き支援を実施している。
指導・援助内容
① 挨拶についての指導
② 仕分け作業についての指導
③ 下処理についての指導
④ 数量確認、点検の仕方についての指導
【事例紹介3】
洗濯業務や介助員補助を行っているCさんの事例について
Cさんの課題として、時間に対しての対応が難しく、マイペースで作業は出来るのだが、急ぐことが出来ず、洗濯物が多いときなどは動きが止まってしまう状態であった。
そのため、通常は一人で行う業務を2名で実施する体制を作り、業務を分担化することにより、時間や量に対しての対応を図った。このことにより、洗濯物の量を見て動きが止まることはなくなり、安定して業務に取り組むことが出来た。
5. さいごに
就労するということは、生活面の土台が出来てこそ、継続していけるということを痛感し、ホームや関係機関との連携が、継続雇用には必ず必要になると感じた。仕事がいくら出来ていても、生活面の少しのゆがみから、継続雇用に繋がらないというケースもたくさんある。
今後、自立支援法の流れの中で、地域移行は進んでいくと思うが、就労を継続していくためには生活面の安定、生活面を安定させるのには、就労(活動)することが必要になってくるのではないかと感じる。この二つの両輪を支えることによって今後の障害者の安定した地域生活が進んでいくのではないだろうか。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











