障害者の就労定着支援システムを活用した事例
~精神障害者の雇用マネジメントへの活用と
メンタルヘルス対策への応用~
- 事業所名
- 株式会社 島津製作所
(法人番号: 6130001021068) - 業種
- 製造業
- 所在地
- 京都府京都市
- 事業内容
- 業務用機械器具製造業
- 従業員数
- 3,253名
- うち障害者数
- 72名
-
障害 人数 従事業務 視覚障害 5 事務 聴覚・言語障害 5 事務、検査 肢体不自由 30 事務、検査、製造補助 内部障害 20 事務、製造補助 知的障害 4 製造補助 精神障害 6 開発、事務 その他の障害 2 事務 - 本事例の対象となる障害
- 精神障害
- 目次
-
 事業所外観
事業所外観1. 事業の概要
明治8(1875)年3月、初代島津源蔵が京都市木屋町二条で、教育用理化学器械の製造に乗り出し、「島津製作所」を創業。息子である二代源蔵の時代に、蓄電池の製造、医療用エックス線装置を開発するなど、事業分野を医療、分析機器へと拡大し、大正6(1917)年9月に「株式会社 島津製作所」(以下「同社」という。)を設立した。以後、精密機械メーカーとして順調に発展。創業者の精神「科学技術で社会に貢献する」を社是に掲げ、最先端技術の開発に挑戦し、さまざまなテクノロジー製品を提供して、医薬・医療・環境・エネルギー・半導体・素材など幅広い産業の発展に貢献してきた。
今日では、資本金266億円、連結売上3,425億円(2017年3月期)と業界有数の大企業へと成長し、「分析・計測機器」、「医用機器」、「航空機器」、「産業機器」の4分野を中心とした事業を展開している。さらには、「人と地球の健康への願いを実現する」の経営理念のもと、新エネルギー開発支援や、病気の超早期診断・新薬開発の支援など、最先端の科学技術で社会のニーズに応えるべく新たな事業にも取り組んでいる。
2. 障害者雇用の経緯と取組の背景
本稿の作成に当たっては、同社の障害者雇用に関して中心的役割を担っている本社人事部マネージャーの境浩史氏(以下「境氏」という。)への取材に基づき取りまとめている。
(1)障害者雇用の経緯
同社は以前から障害のある従業員を雇用していたが、2010年ごろは障害者雇用に関するいくつかの課題を抱えていたため、積極的に進めてはいなかった。その理由は、入社後にメンタル面で不調をきたす従業員(以下、「メンタル不調者」とする。)が多くみられたこと、障害のある者が行える業務には制約があるという固定概念や、雇用管理に対する不安感や負担感があったことなどである。そのため、特例子会社を置かず、障害者雇用の担当者も不在で、これといった戦略もないまま、各部門の人材需要に合った障害者をそのつど新規採用するという状況であった。
しかしその後、障害のある従業員の定年退職や自己都合退職が相次ぎ、障害者の実雇用率が急速に低下した。2014年6月には実雇用率は1.66%に下がり、ハローワークから指導を受けるまでになった。そこで、法定雇用率達成と雇用管理を担う障害者雇用専任者を置くこととなり、以前に障害者雇用を担当していた境氏に白羽の矢が立った。2014年10月に人事部へ転属した境氏は、ハローワークの紹介で障害者就職面接会や各支援機関のセミナーなどに積極的に参加し、多くの障害者と触れ合う機会を設け、"適材適所の雇用"を目指して採用活動を行った。その結果、2年間で24名のさまざまな障害をもつ人材を新規に採用し、2016年3月には、当時の法定雇用率2.0%を超えるまでに雇用率は回復した。2018年10月現在の実雇用率は2.31%となっている。
(2) 精神障害者受け入れと新たな課題
2014年10月から2年間で新規に採用した障害のある従業員24名のうち4名が精神障害のある者であったが、ここで「精神障害者の雇用管理」という新たな課題に直面する。境氏が以前に障害者雇用を担当していた2005年ごろは、精神障害のある従業員は在籍しておらず、そのマネジメントは未経験であった。そのため、雇用管理における留意点や配慮事項は明確化されておらず、発生した課題への対応が後手に回ることが多かった。また、精神障害のある従業員本人・配属先の担当者(上司など)・人事部との間の連携がうまくとれなかったことも、的確なマネジメントができなかった要因の一つである。
筆者も、同社に限らず精神障害者の就労継続は難しいということを聞くことがある。障害者職業総合センターの調査によると、障害別にみた就職1年後の定着率は、身体障害60.8%、知的障害68.0%、精神障害49.3%、発達障害71・5%であり、精神障害は他の障害に比べて低い結果になっている(障害者職業総合センター調査研究報告書No.137「障害者の就業状況等に関する調査研究」)。
境氏はこの当時を振り返って「障害者の面接会などに参加しても、精神障害の方の応募は確実に増えており、全体の8割ぐらいを占めることもありました。これからますます精神障害者の就労数が増えていく中で、"就労の継続"が大きな課題だと感じました。そして、精神障害者の職場定着のためにどのような対応が必要だろうかと頭を悩ませていました」と話す。

人事部マネージャー 境 浩史 さん(3)メンタル不調者の増加
もうひとつの課題はメンタル不調者の増加であった。境氏によるとメンタル面の不調に悩む従業員も以前に比べて増加しているという。同社従業員約3,200名のうち、在職中にメンタル疾患を発症し、長期欠勤や休職、あるいは休職・復職を繰り返している人は少なくない。「病名や症状で最も多いのはうつ状態で、そのほかにも、うつ病、適応障害、双極性障害(そううつ病)などさまざまであり、精神障害者保健福祉手帳を取得している者もいる。また、休職までには至らなくても、メンタル不調で保健スタッフに相談している人が数パーセントいる」と話す。境氏は、2014年に人事部に転属になるまで事業部でメンタルヘルス不調者対応などに従事していたこともあり、障害者雇用の推進とあわせて、このメンタル不調者に対するフォローの重要性も感じていた。
同社のメンタルヘルス対応は、人事部の健康安全センターで行っており、社内診療所に常駐する産業医、保健師、看護師、臨床心理士(専任)と、人事担当者や管理監督者らが連携をとって行っている。こうした本格的なメンタルヘルス対策を始めたのは2010年ごろからで、臨床心理士による社内カウンセリングや、嘱託契約の精神科の産業医による面談、さらには外部のEAPサービス(Employee Assistance Programの略で、企業のためのメンタルヘルスサービス)と契約するなど、多方面からのサポート体制を整えている。しかしそれでも、新規のメンタル不調者、再発者ともに年々増加傾向にあった。
(4) SPISとの出合いと導入
このような状況のなか、2016年8月、境氏は京都障害者雇用企業サポートセンター(京都市が独自に設置した企業向け支援機関)が主催の障害者雇用に関する勉強会に参加し、精神障害者の就労定着支援システム「SPIS」と出合う。(SPISは、「Supporting People to Improve Stability」 の略で、読み方は「エスピス」。)
SPISは、精神障害者・発達障害者向けに開発されたマネジメントツールで、日報をWeb化したものである。精神障害や発達障害のある従業員が、心身のコンディションを自己評価して発信し、企業の担当者(上司や人事部門など)や専門家(臨床心理士など外部支援者)とリアルタイムに情報共有することで、円滑なコミュニケーションを図るとともに、不調予防や早期の対応を可能にするものである。記録された内容は上司らが随時チェックし、相談・助言などを行うほか、外部支援者も助言できるシステムになっている(外部支援者は社外の専門機関や臨床心理士などの識者などである)。
SPISの詳細や導入に関しては、その普及などを行っている特定非営利活動法人全国精神保健職親会のホームページを、開発経過などについてはSPISののホームページを参照されたい(各リンク先は以下に掲載)。
全国精神保健職親会のSPISのHP https://www.vfoster.org/spis.html#a2
SPISのHP https://www.spis.jp/
境氏は、2回の勉強会に出席し、SPISへの理解を深めていくなかで、SPISは精神障害のある従業員の職場定着に有効であると同時に、メンタル不調者の対応にも効果が期待できるのではないかと考えた。そこで、社内調整(健康安全センターなどとの調整)を行い、同社では2016年11月からSPISを導入することとした。
3. 取組の内容
(1) SPISの特色と進め方
ア.SPISの特色
・クラウドサービスを活用した日報管理システムである。
・日報データを三者(障害のある従業員及びメンタル不調者(以下「当事者」という。)・企業の担当者・外部支援者)で共有でき、相互
に働きかけができる。
・パソコンやスマートフォンで簡単に入力でき、いつでもどこでも確認できる。
・画一的な評価項目でなく、当事者が症状に合わせて自由に設定できる。
・自由記載できるコメント欄があり、直接対面で話すことが苦手な人でも伝えやすい。
・グラフ表示や色分けによって、好不調の波を「見える化」できる。
イ.SPISの進め方
(ア)準備として、Web上の日報形式のフォームに、当事者が生活面・仕事面などで気になるポイント(例「睡眠の質」「気分の浮き沈
み」「不安を感じる」など)を評価項目として設定する。項目数は自由だが、6~7項目が標準。あとから増減も可能。
(イ)設定した評価項目について「良い」から「悪い」まで4段階で自己評価し毎日記録する。コメント欄には、体調、気分、仕事や仲間
との関わりなど、日々の出来事や感情を自由に記録する。
(ウ)日報データは、当事者・企業の担当者(上司など)・外部支援者の三者で共有。コメントへの返信も可能なので、随時コメントを返
す。
(エ)自己評価の推移をグラフ化することで、体調・精神面のアップダウンが一目瞭然となり、職場担当者や外部支援者は必要に応じて声
掛けやサポートなど早めの対応を行う。
(オ)グラフをもとに定期的な振り返りを行うほか、産業医による面談の際にはグラフをプリントアウトして持参することで資料として活
用可能。
SPISの入力画面
(2) SPISの実施事例(トライアル実施)
同社では、精神障害のある従業員に対して行う前に、SPISをメンタル不調者に対してトライアル(試行)として実施した。ここではその事例を示す。
ア.トライアルの概要
(ア)利用者:Aさん(東京支社勤務)
・適応障害で約10か月間休業し、6か月前に復職した。
・回復途上にあるが、体調や気分に不安定な状態が続いている。
・月1回、臨床心理士のカウンセリングを受けている。
・自分のことを「見てほしい、理解してほしい」という思いが強い。
(イ)実施状況
人事部からAさんとその上司にSPISの内容を説明し、トライアル実行に関して承諾を得る。AさんがSPISを始めてみようと思った理
由は、「SPISを通して上司や支援者に常に見守られていることが、復調への追い風になる」と感じたからだという。
評価項目は、「寝つきが悪い」「気分が良い・悪い」「集中して取り組めたか」など、生活面、社会面、作業面で6項目を設定した。
そして、Aさんの直属の上司が「職場担当者」に、健康安全センターの臨床心理士と人事部管理職(境氏ほか)が「外部支援者」とな
り、情報を共有しつつマネジメントを行った(同社では社外の専門家は活用せず、職場担当者とは異なるラインとして人事部が外部支援
者と関わっている。)。
情報共有を始めると、Aさんは日々の評価項目のチェックのほか、コメント欄に仕事上の悩みや、旅行、趣味、勤務外の過ごし方な
ど、プライベート面についても事細かに発信していった。そして、スタートから5か月目の産業医面談で、「そろそろSPISやめましょう
か」と言われたが、Aさん本人がもう1か月の継続を希望し、6か月で卒業(終了)した。
イ.トライアルの結果
Aさんは、SPISを活用して、「見守られていることによる安心感」があったという。それが勤務状況やメンタル状況の安定につながっていったと考えている。また、日々の状態を記録していくことにより、自己理解が深まったという。「職場担当者」である上司とすれ違いが多く、顔を合わせる機会が少ないなかでも「タイムリーに状況把握ができ、Aさんへのアドバイスや仕事上のフォローがスムーズ、かつタイミングよくできた」という感想を持ったそうだ。本社(京都)で「外部支援者」として情報を共有していた境氏も「本社にいても東京支社でのAさんの様子を知ることができ、SPISの効果を実感することができた」と話す。
こうしたAさんの実施結果を踏まえ、同社ではSPISの対象者を増やして実施することとした。次に拡大して取り組んだ状況と効果について示す。
(3)拡大した取組の概況と効果、課題
ア.取組の効果
Aさんに加え、精神障害のある従業員3名とメンタル不調者2名、合計5名の利用者を新たに増やし、現在までに6名がSPISを活用した。6名のSPIS活用を通して明確になった効果は以下のとおりである。
[当事者]
・体調の波や気持ちなど、直接言葉では伝えにくいことも発信できる。
・職場での障害理解が進み、コミュニケーションが活性化される。
・日々症状を記録することで自分の体調変化に気づき、体調が悪化してもリカバリーが早くなる。
[職場担当者]
・情報共有を通して趣味や生活習慣などもわかり、当事者への理解が深まる。
・好不調の波がわかるので、早めの対応や業務面での配慮ができる。
・当事者が困っていること、苦しんでいることなどが把握でき、的確に対応できる。
・休職中や離れた場所にいても、様子がわかる。
同社では、休職中の対応として、これまでは月1回、上司が電話やメールで様子を聞いていたが、SPISでは体調なども踏まえながら随
時の入力とした。
・上司のコミュニケーション能力向上や成長につながる。(詳細は次項「イ.波及効果」に記載)
[外部支援者(人事部管理職など)]
・離れた場所にいても当事者の状況がわかり、不調の兆候を早期にキャッチして対応することができる。
[人事部(SPIS導入に関する評価)]
・本社は、甲子園球場4.5個分の広大な敷地で、建物も40棟以上ある。当事者と離れた場所にいても状況を瞬時に把握できる。また、距離
的に離れた事業所の従業員のデータもリアルタイムに共有でき、一元管理が可能である。
・導入により、三者の情報共有とコミュニケーションは図られ、当事者の体調や就労の安定につながった。不調の兆しも早めに気づき、早
期に対応することもできた。
イ.波及効果
「思わぬ波及効果もありました。SPISは上司の成長にもつながるんです」と境氏は言う。そして、女性部下の「職場担当者」になったある上司のエピソードを話してくれた。
SPISを始めた女性部下が、勇気をもって初めてのコメントを書いた時、その上司はやや否定的なきついコメントを返してしまった。すると、そのコメントを見た外部支援者から上司のもとに「彼女は今までそれが言えなかったからSPISを始めたのです。当事者の気持ちを汲んで対応しましょう」とアドバイスが届いた。その上司はタテ社会で育った男性で、これまでもきつい口調によって無自覚に部下を傷付けることがあった。SPISを使う中でその上司は、自分の言い方がきつかったことに気づき、自ら話し方教室とアンガーマネジメント研修に通い、人との接し方を変える努力をした。その結果、部署内の雰囲気が大きく改善されたという。
ウ.SPIS活用の留意点
SPIS活用にあたって最も重要なことは、「当事者の特性を考慮した対応」を心がけることである。具体的には以下のような点である。
(ア)SPISは雇用する側が強制するものではなく、当事者の意志を尊重したうえで始めるものである。「自分のことを見てほしい」という
タイプの人もいれば、「監視されているようだ」と感じる人もいるので、特性を考慮して取り入れる。あえて強制はしない。
(イ)「職場担当者」は慎重に選ぶ。メンタル不調者の場合、その原因が職場の人間関係にあることも多いので、必ずしも「職場担当者」
=「業務上の上司」と限定せず、当事者に決めてもらう。(例:直属の上司との関係にストレスを感じる場合は、さらに上の上司や総
務系の立場の人などにする。)なお、直属の上司以外を選任した場合は、直属の上司にはSPISのことを一切知らせないよう配慮する。
(ウ)「当事者のコメントには"必ず"返信する」というルールにはしない。必ずとなれば職場担当者も負担になるので、ルール上は「週
1回は返信する」として、「普段は書ける時に書く」ようにする。
(エ)メンタル不調者の場合、SPISを卒業する時期を見極める。「寛解(病状改善または回復)」状態を迎えたらSPISを切り上げる決断
も重要である。SPISに依存して、「ネット上でしか気持ちが伝えられない」ということがないよう医師や臨床心理士と相談し、個々
の状況に応じてやめる時期を決める。
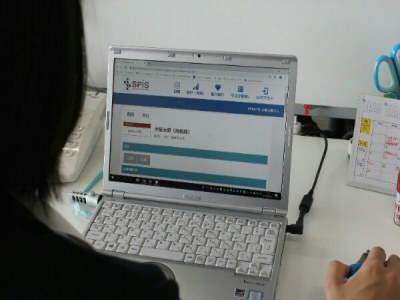
SPIの活用風景4. 今後の課題とまとめ
(1) 今後の課題
同社では、今後、同社の業務に即してSPISの機能に独自の改善を加え、さらに使いやすくすることを検討している。(例:その日の評価[良い・悪い]を所属部署内で共有可能にする。職場担当者らがコメントを返さない場合でも、ちゃんと見ていることが当事者に伝わるよう「既読」の機能を付加する、など)
また並行して、「障害者に対しての理解を深めるよう、全従業員に向けての啓蒙活動を行い『誰もが働きやすい職場づくり』を推進し、ダイバーシティを実感できる社内風土を実現していきたい」と境氏は言う。
(2) まとめ
SPIS導入前、同社では、在職中の社員がメンタル疾患を発症し、休職と復職を繰り返したり、就業困難となって突然退職するなど、業務が混乱したという前例があった。そのため、「精神の障害は突然調子が悪くなるので、雇用が難しい」というネガティブな思い込みがあった。
しかし、SPIS導入から約2年、6名の活用体験を通して、毎日の記録データを分析することで、調子が上下する傾向や、不調の兆しが把握できるようになった。つまり、「精神の障害は突然調子が悪くなる」のではなく、その前兆があることをSPISの活用を通して認識することができた。不調の兆候を早めにキャッチし、体調悪化を予想することができれば、先手の対応が可能になり、雇用する側にとっても、当事者にとっても、安心して働ける環境づくりができることもわかり、社内の理解も進んできつつある。
境氏は、「うまくいっている事例というより、鋭意努力中という段階です」と話す。確かに同社の事例だけで一般的な効果を論じることはできないかもしれない。しかし、障害のある従業員が社内で必要なコミュニケーションをとり、自身の体調管理面での意識・スキルを向上するとともに、事業所側でも障害のある従業員とその上司と人事部、そして外部の専門家が連携をとり、従業員の心身の健康管理をサポートしていくことは、職場定着にとって非常に重要なことであり、SPISがそのための有効なツールである可能性を同社の取組は示している。
2018年4月の法定雇用率の改定で、精神障害者が雇用義務の対象に加わったことに伴い、今後、働く精神障害者の数はますます増加していくことが予想される。同社の取組が精神障害者の雇用と職場への定着、そしてメンタルヘルスへの対策として他の事業所の参考となるものと取材を終えて筆者は強く感じた。執筆者:藤原 幸子
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











