知的障害者の教育機関における合理的配慮事例
- 事業所名
- 合理的配慮事例・2019221
- 業種
- 教育、学習支援業、うち除外率設定業種
- 従業員数
- 347人
- 職種・従事作業
- 学内の清掃作業
- 障害種別
- 知的障害
- 障害の内容・特性
就労上の課題 - 抽象的な概念の理解が苦手であり、日程変更や作業変更等の認識に時間がかかる。
意思疎通のためのコミュニケーション面や日常生活等の管理に配慮が必要である。
募集・採用時の合理的配慮
面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること
本事例の対象者(以下「対象者」という。)は障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)の支援を受けており、採用面接時に、支援センターの支援員の同席を得た。支援員の同席により対象者は緊張することなく面接に臨めるとともに、対象者の障害特性や就労上の配慮について説明を受けることができた。
その他の配慮
対象者の適性や就労状況、職場環境等が双方ともに確認できるように、採用前に「障害者短期職場実習制度」を活用した(同制度は県の制度で障害者一人につき日額1,800円の委託料が企業に支払われる。対象者の場合は10日間実施)。
また、実習段階から採用後にかけて地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)のジョブコーチ支援を利用した。
採用後の合理的配慮
業務指導や相談に関し、担当者を定めること
1.対象者は学内の清掃作業を担当する部署に配属した。清掃作業はグループで行うもので、グループは障害のある職員4名で編成している。
2.障害特性に配慮し、指示する人が変更になることで混乱がないように担当者を総務課長に定め、指示、報告・連絡・相談が一元的に対応できるようにした。また対象者が所属する作業グループのリーダーには業務用の携帯電話を携行させ、現場で何か問題が起きたとき等には、すぐに連絡が取れるようにした。
3.作業開始・終了時には必ず清掃作業グループ(障害のある職員4名)全員と総務課長でミーティングを行い、一日のスケジュールの確認や翌日の確認をすることで、不安無く、スムーズに作業が行えるようにした。また、グループのリーダー、副リーダーを毎日交代制で行い、問題があればグループのリーダーや副リーダーに報告・連絡・相談し、それでも解決しない場合は、総務課長へ連絡する体制とした。また早急な対応が必要な場合は、すぐに個別もしくは全員でのミーティングを行い、解決へ向けた体制もとっている。
4.口頭での質問、相談が苦手な者もいるため、業務日報を活用することで、相談や問題の吸い上げを行い、早期に解決できるようにしている。
本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと
1.個人別に月始めに目標を立て、月末にはその目標が達成できたか振り返りを行うことで達成度と改善すべき点を把握し、次のステップにつなげるようにした。
2.口頭での質問、相談が苦手な者もいるため、支援センターの提案により「業務日報」を作成し、就寝時間や起床時間、朝の体調や朝食について把握することで体調管理をしながら、一日の振り返りや目標の達成度をもとに作業内容や作業量を検討していった。
図等を活用した業務マニュアルを作成する、業務指示は内容を明確にし、一つずつ行う等作業手順を分かりやすく示すこと
1.誰がやっても作業にばらつきがないように、また本人が何度も作業確認できるように県の支援事業を活用して視覚的にも分かりやすい障害特性を配慮した作業手順書を作成した。県の事業は障害のある従業員に応じたマニュアル等を作成した企業に助成するもので、本事例の事業所も100,000円の助成を受けている。この作業手順書の活用により作業の確実性の向上等につながっている。
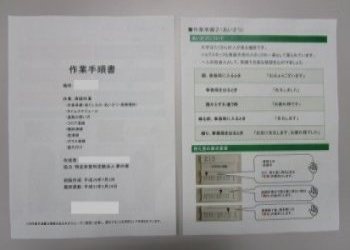

2.視覚的に理解しやすく、うっかりミス等をなくすための工夫として、注意事項や指示事項を付せんに記載し休憩室の壁に掲示したり、日頃から気を付けて欲しい事柄などについても関係する場所に掲示するなどして、作業開始前等に確認できるようにした。
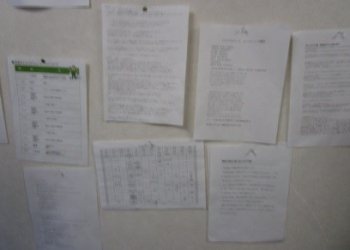
また、各清掃用具に番号をつけ、それぞれが決めた番号がついた清掃用具等を使用することで、対象者の忘れ物がないように工夫した。


出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること
1.業務日報の中に、就寝時間や起床時間、朝の体調や朝食について記入してもらうことで、これまでの経過や当日の体調を把握するとともに、体調に関する対象者の意識付けや振り返りを行った。
2.通院や休暇、早退等に対しては、すぐに対応ができるような体制としているが、事前に連絡を受ける等、特段の配慮を必要とすることはなく勤務ができている。
3.清掃作業チーム用の休憩場所が確保されており、テーブルとイスの他に脚を伸ばせるようにじゅうたん敷きのスペースを作り、身体を休めリラックスできるような環境を整備した。
4.休憩場所にポットや冷蔵庫等も準備し昼食が取れるようにしているとともに、スケジュール表や各連絡事項を掲示して午後からの仕事の確認ができるようにしている。
本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること
何か問題が生じた場合は、清掃作業グループと担当者である総務課長とミーティングを行うが、その際に障害特性等の理解を促すために情報共有がなされている。また法人本部内でも情報共有がなされ、緊急時の対応ができるような体制となっている。
また、学生への周知はしていないが、挨拶を交わす等のなかで自然と理解されているところである。
その他の配慮
1.障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、ハローワーク等、多くの支援機関と連携することで、対象者に対して、より迅速で適正な問題解決がなされる体制とした。
2.職場実習中から採用した後も職業センターのジョブコーチ支援を活用することで、対象者への指示出しの仕方や対象者の就業上の特性が理解できたとともに対象者を含めた面談等を重ねていくことで対象者が安心して就労ができるようにした。
3.対象者が安定した就労ができるように、家族を含む各支援機関を交えて日常生活の様子や健康管理等の情報の交換・共有できる会議を設けた。
4.日々、充実した就労生活をおくり職場定着がなされるように、問題が発生した場合には、すぐに総務課長と対象者を含めた清掃作業グループが解決のためのミーティングを開ける体制とした。
5.障害特性に配慮し抽象的な指示ではなく、具体的で明確な指示を心掛けるとともに、常にコミュニケーションを図りながら、風通しの良い職場環境作りを心掛けた。
6.道具が違うことによる混乱や不安がなく、安心して作業が行えるように、職場実習期間中から就労移行事業所で使用していた清掃用具と同じ仕様の道具を準備した。
7.業務日誌のコメント欄に総務課長が必ず記入することで、相談事や問題等を早期に把握するとともにコミュニケーションを図った。
障害者への配慮の提供にあたり、障害者と話し合いを行った時期・頻度等の配慮提供の手続きの詳細
1.職場実習中に障害者職業センター(ジョブコーチ)、就業・生活支援センターや就労移行支援事業所等の支援機関から、対象者の就労上の特性について説明を受けたり、特性を踏まえた指示出しや雇用管理上の具体的な配慮方法に関わる会議を設けた。
2.採用後も各支援機関と定期的に会議を設けるとともに、家族や生活支援施設とも必ず面談の機会を設け、生活上の特性を把握することで、雇用管理に役立てている。
3.月に1度の定期面談等において、対象者から配慮事項等に関する意見を聴取し、必要に応じて支援機関への相談等も含め情報を共有しながら修正をしている。
配慮を受けている障害者の意見・感想等
・わからないことがあれば、すぐに総務課長に連絡できるので、安心して作業が行える。
・グループで作業をしているので、助け合いながら作業ができる。
・交代制でリーダ-をやっているので、責任感が持てるようになった。
・問題発生時には、全員でミーティングを行い、解決していけるのでとても良い。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











