仕事に人を合わせるのではなく、
人に仕事を合わせることで、成果をあげている事例
- 事業所名
- 株式会社はくばく
(法人番号: 50900001012072) - 業種
- 製造業
- 所在地
- 山梨県中央市
- 事業内容
- 市販用、業務用含め、穀物の加工品である6事業(精麦、雑穀、和麺、穀物茶、穀粉、精米)を展開している。
- 従業員数
- 390名
- うち障害者数
- 9名
-
障害 人数 従事業務 肢体不自由 3名 総務、検査、製造現場の包装 内部障害 1名 物流 知的障害 3名 物流セットアップ 精神障害 2名 物流セットアップ - 本事例の対象となる障害
- 肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害
- 目次
-
 事業所外観
事業所外観1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業内容
食の本質が問われる現在、株式会社はくばく(以下「同社」という。)は、主食の満足が育む、健康で心豊かな食生活の提案と、穀物の世界をリードしていくためのさまざまな事業展開をしている。より多くの人に穀物を食べてもらうために、機能性とおいしさを工夫することで世代を超えて愛される味わいを追求しており、次の事業を行っている。
ア 精麦(健康機能性素材としての大麦の魅力)
イ 雑穀(「大地の恵み」を手軽においしく)
ウ 和麺(品質と風味にこだわりぬいた味)
エ 麦茶(香り豊かな自然飲料)
オ 穀粉(便利で良質、様々な用途に)
カ 米(お米と一緒に、健康で安心な食生活をお届けする)
(2)経営方針
同社は「穀物の感動的価値を創造し、人々の健康と豊かな食生活を実現する。」を理念として掲げている。健康に生きるための最も理想的な食のあり方については様々な研究がなされており、そのなかでは穀物を中心とした、かつての日本人の食も注目された。それは、「ヘルシーフードピラミッド」を生み、それを参考に2005年、厚生労働省と農林水産省が共同で「食事バランスガイド」を発表した。 同社は創業以来、穀物のおいしさに取り組み、これからも新しい食のニーズに応え、穀物の新たな可能性を深めていくことを事業の基本的考え方としている。
ちなみに、社名の「はくばく」とは"白麦"を意味しており、創業以来、同社は麦の会社である。コーポレートシンボルは五穀が世界に広がる様を描いており(「事業所外観」を参照)、その五穀とは「米、大麦、小麦、あわ、そば」である。これらの「はくばく」流五穀は同社が創業以来深いかかわりを持ってきたものばかりである。
そして同社は自社を「The Kokumotsu Company」と定義しているが、それは、今までの歴史と、これからの人々の理想の食の提供に大いなるかかわりを持つという決意の表明である。穀物についての知見を深め、新しい価値の提供を通して、「The Kokumotsu Company」を実現していくことを目指している。
(3)組織構成
同社は、管理本部(総務人事部、経営管理部、品質保証部、購買部)、市場戦略本部(商品戦略部、開発部、海外事業部、カスタマーダイレクト部)、生産本部(中央工場、富士川工場、南湖工場)、物流部、営業本部(営業推進部、広域流通部、関東支店、関西支店、業務用販売部)から成っている。
(4)障害者雇用の理念
同社は、「The Kokumotsu Company」として、「穀物の感動的価値を創造し、人々の健康と豊かな食生活を実現する」という企業理念のもと、日々の事業活動を通じて社会の持続的な発展に貢献できるよう取り組んでいる。その中で、会社全体で「子育て支援」と「ワーク・ライフ・バランス」推進のために改善を進め、社員全員が「働きがいのある働きやすい企業」と思えるような企業を目指している。また、地域社会の一員として、地域の住民に認められ、社会から存在を期待される会社を目指し、より豊かな生活と社会づくりに貢献するための活動をしている。そうした理念や取組をベースに、企業の社会的責任(CSR)の一環として、「コーポレート・ガバナンス」を定めている。それが、次の、「はくばくコンプライアンス宣言」(以下「宣言」という。)である。
<はくばく コンプライアンス宣言>
1. 法令・諸規則の順守
業務上必要なあらゆる法令、社会ルール、当社の諸規則について、その趣旨を理解し、その順守に努めます。
2. 健全な社会常識と倫理感覚
お客様及び広く社会から信頼される食品メーカーとして、健全な社会常識と倫理感覚を保持できるよう不断の研鑽に努めます。
3. 適切な情報開示・説明
提供する商品・サービスの内容や当社の経営情報について正しく開示し、説明します。
4. 適切な情報管理
業務上知り得た個人情報について法令等に従って適正に取り扱います。
5. 公正、公平な取り扱い
全てのお客様の公正、公平な取り扱いを確保します。
6. 公私のけじめ
業務遂行に当たって、常に公私の別を考えて行動します。
7. 人権の尊重
人権を尊重し、差別やハラスメントの発生防止に取り組みます。
すなわち、障害者雇用の理念とすると、「ワーク・ライフ・バランス」や、「働きがいある働きやすい企業」、並びに「地域貢献」、「ダイバーシティ」、「インクルージョン」の実現を目指すことが上げられる。
(5)取組のきっかけ
障害者雇用の取組の背景には上記(4)の理念があるが、直接のきっかけは、昭和51年に障害者の法定雇用率が義務化されたことにある。これを契機として、宣言にあるとおり、法令順守並びに人権尊重の精神に基づき、障害者法定雇用率を達成すべく障害者雇用への取組を開始した。
本稿では同社の障害者雇用について、担当部門である管理本部総務人事部部長の鰻池さん、総務人事部人事課の望月さんに伺った内容をもとに紹介する。
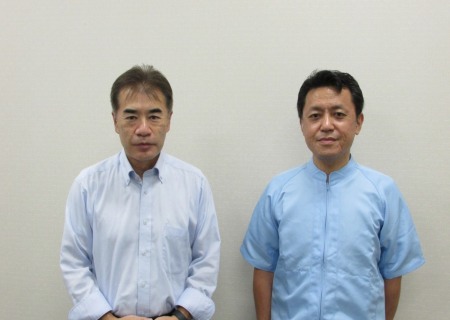 管理本部総務人事部部長の鰻池さん(右)、同部人事課の望月さん(左)
管理本部総務人事部部長の鰻池さん(右)、同部人事課の望月さん(左)2. 障害者の従事業務と職場配置
(1)労働条件と従事業務
ア 労働条件
・雇用期間:新たに障害者を採用する場合には有期(6か月)の雇用契約であるが、原則として契約更新することとしており、ほとんどの人が定年の60歳程度までは継続雇用している。その後も本人の希望などによっては、65歳までの雇用も可能である。また、本人の希望や勤務状況によっては正社員に登用することもある。障害のある社員の中には正社員在職中に障害者となった者もあるが、その場合には正社員としている。
有期契約の場合の主な労働条件は以下のとおりである。
・就業場所:本社工場内
・就業時間:9時から16時の6時間の勤務(パート勤務)が基本であるが、本人の希望や状況に応じて8時半から17時半の8時間フルタイ
ム勤務になることがある。
・賃金:最低賃金からスタートする時給制。年1回の見直しにより昇給あり。賞与あり
・人事評価:パート勤務の場合はないがフルタイム勤務の場合はあり、昇給、賞与に反映
・退職金:なし
・福利厚生:パート・有期雇用労働法の施行に即して、令和2年9月より、特別休暇の適用を開始した。
イ 従事業務
冒頭の一覧表にあるように、肢体不自由のある社員は総務、検査、包装、物流に従事し、内部障害のある社員は物流に従事している。知的障害のある社員と精神障害のある社員は、物流部門のセットアップ業務に従事している。セットアップ業務は、商品の詰め合わせを行なったり、包装やラベル貼りなどの手作業であり、物流を支える仕事である。いずれの業務でも障害のある社員と障害のない社員が一緒に働いている。
(2)職場配置
この「職場配置」、並びに次の「3.取組の内容と効果」以降については、主に、知的障害のある社員と精神障害のある社員について述べるものである。
労務管理上の工夫とも重なるが、仕事に人を合わせるのではなく、人に仕事を合わせるようにしている。したがって、原則として、「できない仕事はやらせない」配置を心掛けている。だからこそ、例えば、最初は物流セットアップを担当していても、本人が成長し、できることが広がることにより、現場のラインに入るような他の仕事を割り当てることもある。3. 取組の内容と効果
(1)労務管理の工夫
ア スムーズな採用に向けた関係機関の利用
ハローワークはもとより、地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)、並びに障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)の支援を得て、障害者を採用している。特に、地域に根差した支援センターの支援は、非常に丁寧で効果的であり、採用において大いに助けられている。なお、ハローワークのトライアル雇用制度も活用している。
なお、現在のところ直接採用に結び付いていないが、特別支援学校在校生の職場実習を受け入れており、実習を契機とする採用も期待できるところである。
イ 労働条件の柔軟性
本人の希望や仕事ぶり、体調の状況に応じて、パート勤務からフルタイム勤務への変更が可能となっており、実績もある。
ウ 仕事の割り当て
上記「2. 障害者の従事業務と職場配置」の「(2)職場配置」でも触れたが、まず「人に仕事を合わせる」を基本に、仕事を割り当てている。始めは「正確性」を重視し、正確な作業ができるようになったら、「速さ」を求めるような目標設定、指導をしている。なお、障害のない社員と一緒に仕事をすることで、障害のある社員の困難なことを周囲がカバーすることにより、働きやすい職場環境を作っている。
エ 指導・教育・訓練
障害のある社員が理解しやすいように、指導者(管理者)を固定するようにしている。また、年齢に関係なく、先に就職した障害のある社員が後輩を指導し、面倒を見るようにして、より身近な教育を実現している。さらに、職業センターの助言により「ナビゲーションブック」(「注」参照)を活用し、ジョブコーチの支援も受けている。このナビゲーションブックは、指導などにおいて極めて有効と感じている。また、障害特性に応じた作業マニュアルも作成しており、写真を多く取り入れ、見やすいものに工夫している。
注)「ナビゲーションブック」は、障害者が自身の体験などをもとに、自らの特徴やセールスポイント、障害特性、職業上の課題、職場で配慮してほしいことなどをまとめ、事業主に説明する際に使用する資料。
(2)取組の効果
現在働いている障害のある社員は一様に、「長く勤めたい、仕事がおもしろい、やりがいを感じる」と周りに話しており、就労実態としても、定年年齢程度まで働く者が大半である。職場になじんでいる者も多く、障害のある社員の多くが社内行事にも積極的に参加している。また、毎年アビリンピックに出場している者もいるなど、会社全体のモチベーションを高める効果を上げている。そして、取組の総合的な成果として、障害者法定雇用率の達成につながっている。
障害のある社員が配属された職場は特に、障害者雇用について好意的に受けとめている。というのも、障害者を含めたいろいろな仲間を受け入れることで、柔軟な働き方を実現し、安全にもつながるからである。さらには、管理者の人間的な成長や、指導者としての育成にも役立っている。
4. 今後の展望と課題
(1)展望
今後も、スムーズな採用を実現し、人に仕事を合わせる配置を心掛けることで定着率を向上させ、会社と社員がともに豊かになり、結果として障害者法定雇用率を達成し続けることを目指している。
(2)課題
会社としては、障害のある社員と接する管理職のスキル不足を感じている。例えば、重度障害の場合どのように対応するのかなどはまだまだ不十分な点があるように感じている。今後を見据え、管理者の研修が重要かつ不可欠と考えている。したがって、特に、部門長向けの研修を検討したいと考えている。
(3)障害者雇用に取り組む企業へのアドバイス
障害者雇用だからといって特別なことはなく、必要以上に意識しないことが、かえって良い結果につながる。また、会社や担当者だけで悩まずに、遠慮なく関係機関の支援を受けることも効果的である。特に、職業センターと支援センターの活用は、障害者の採用前から採用後に至るまで、障害者雇用をスムーズに進める際に有用である。
(4)最後に~筆者から~
同社は、「コーポレート・ガバナンス」にある「人権の尊重」を背景に、障害者法定雇用率の達成を目標として、「ワーク・ライフ・バランス」や、「働きがいのある働きやすい企業」、並びに「地域貢献」、「ダイバーシティ」、「インクルージョン」を実現している。その取組は、障害者雇用に本音で向き合っている様子が伝わってくるものである。障害者雇用を必要以上に意識することなく、自然なものとして受け入れ、一歩一歩着実に地に足をつけて取り組むことで、成果をあげているのが印象的である。
執筆者:雨宮労務管理事務所 所長 雨宮隆浩
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











