障害者雇用に学び、障害者雇用を「あたりまえ」に
- 事業所名
- ニップンドーナツ九州株式会社
(法人番号: 2310002000642) - 業種
- サービス業
- 所在地
- 長崎県長崎市
- 事業内容
- 飲食店経営
- 従業員数
- 147名
- うち障害者数
- 6名
-
障害 人数 従事業務 内部障害 1名 ドーナツ製造及び接客業務 知的障害 5名 ドーナツ製造及び接客業務、調理業務 - 本事例の対象となる障害
- 内部障害、知的障害
- 目次
-
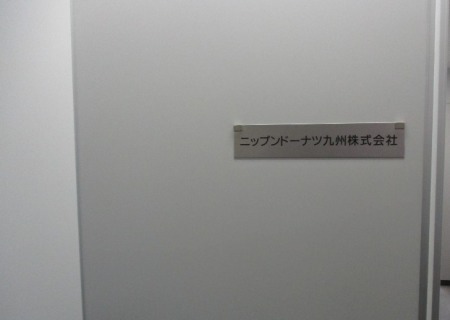 本部入り口
本部入り口1. 事業所の概要
ニップンドーナツ九州(以下「同社」という。)は昭和32(1957)年に創業の有限会社ウミノを前身とする。平成25(2013)年にニップンドーナツ九州株式会社へ商号変更し、現在に至る。従業員数は現在147名。主な事業は、喫茶飲食店経営、ミスタードーナツのフランチャイズ(FC)事業、タリーズコーヒーFC事業。
令和3(2021)年に、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度「もにす認定制度」で、長崎県内初の認定を、長崎労働局より受ける。
本稿は、同社の障害者職業生活相談員である取締役経営管理本部長(以下「本部長」という。)への取材をもとに、障害者雇用の取組を紹介するものである。
2. 障害者の従事業務と職場配置
(1)知的障害のある社員 5名
・ドーナツ店内でのドーナツ製造及び接客業務 1名
・ドーナツ店内での接客業務 2名
・ドーナツ店内での全業務 1名
・カフェ店内でのメイン調理業務 1名
(2)内部障害のある社員 1名・ドーナツ店内でのドーナツ製造及び接客業務 1名
3. 取組の内容と効果
(1)募集・採用、正社員登用などの取組
採用は、特別支援学校の在校生については職場実習を受け入れた上で行うほか、ハローワークからの紹介者についても職場実習を受け入れ、行っている。
職場実習時から、特別支援学校(以下「支援学校」という。)やハローワークをはじめ、地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)、障害者就業・生活支援センターなど(特別支援学校以下を総称して「支援機関」という。)と連携し、採用後の雇用継続を見据えた対応を行うよう努めている。支援機関と常に情報を共有し、障害のある社員の雇用前からの経緯を理解し、企業と支援機関が連携して対応するほうが、それぞれの状況で単発で対応するより効果的であり、企業も支援者も安心できる。また関係者が頻繁にコミュニケーションをとり連絡しやすい関係になっていることも課題の早期発見や解決にとって非常に大切と同社は考えている。
なお、同社では障害のある社員を採用した際は、まずは短時間のパートタイム契約からスタートする。これは、社会に緩やかに慣れていくことに重きを置いているからである。
正社員への登用制度を設けており、正社員を募集する際は、ハローワークなどで募集するとともに社内向けにも告知するが、障害の有無を問わず募集し選考を行う。直近の募集でも、社内告知を見た障害のある社員が「自分も応募できるのか」との意欲を持ち応募。選考の結果、この4月から2名の正社員登用に至った。登用が円滑に行えた背景には、採用後の短時間勤務時において、着実に経験を積む様子を、本部長が店舗を巡回した際などに詳細に把握していたことがある。なお、正社員登用の検討の際は、勤務時間や職責などの負担が増すことから、本人が重圧で潰れずに次のステップに行けるかを慎重に見極めており、場合によっては、もう一年間短時間勤務を経験してからチャレンジするよう会社から促すなど、本人にとってよりよい雇用であるように配慮し、慎重な対応を行っている。
(2)重視している取組の具体例と効果
ア 職場実習の活用
各支援機関と連携し職場実習(以下「実習」という。)はできるだけ回数を多く、また長い期間を設定し就労の際に障害者本人の負担を軽減すべく行われている。
例えば支援学校の実習については、一般的な実習は前期2週間、後期2週間の期間設定だが、同社では支援学校側へ回数や期間の拡大を提案している。高等部1年時には「働くとはこういう感じなんだ」ということを体験し理解することを目的に、あまり難解なことには触れずに前期・後期とも2週間実施する。2年時には卒業後の就労を意識して前期・後期とも1週間をプラスした3週間実施する。3年時には来春の就職を目指し、前期では2週間をプラスした4週間を実施期間とし、後期では2週間の実施に加え、同社への就職が内定した生徒については、もう一回、3週間の実習を行うことを提案している。3年時の2回目の実習は秋に行われることから、実習終了から翌春の入社までには数か月の期間があるが、そこからいきなり職業生活に入る困難さを軽減したいと考えるからである。
そうした取組の効果としては、実習機会・期間が多いほうが、会社側もしっかりと対応でき、課題や解決方法も多く発見できること、また同社での就労につながった時にも、把握してきた課題が多ければ多いほど、留意点が最初から多く分かり、現場での受け入れが円滑であること、そして、障害のある社員本人にとっても、会社側から長期間にわたり対応してもらってきたことにより戸惑いや負担感が少なく、安心して働けることにつながっているなどが挙げられる。
イ 障害者雇用についての社内の理解と必要な知識を得るための取組
同社では、同社の障害者雇用に関する方針や、障害特性や特性に応じた対応方法に関する知識などをすべての社員が理解するための取組にも力を入れている。
具体的には、社員向けの説明会を定期的に開催し、本部長自ら、障害者雇用について説明を行っている。また、新しい社員が入社した場合にも個別に説明の機会を持つなど、同社の障害者雇用に対する取組や考え方が、常に薄まることなく、全店舗にいきわたるように努めている。
また説明の際には社員が理解しやすいように、支援機関発行のガイドブックや雇用マニュアルを配付している。ガイドブックなどは、職業センターなどから入手しており、特に高齢・障害・求職者雇用支援機構発行の障害種類別のマニュアルコミック版は、初めて関わる社員からの評判も良い。
また、社員が支援機関を見学する機会の確保も重視している。特に支援学校の見学会へは、企業向けのものに限らず、全店舗の責任者が順繰りに参加することとしている。実際に支援学校ではどのような教育がなされているかを知った上で生徒達(実習生)の行動を理解すること、また現場の空気感(様々な障害のある生徒の真剣に学ぶ姿や教員の熱心な指導ぶりなど)を知ることにより、障害者雇用への理解が各段に深まる効果があり、そういった現場の見学には、できる限り社員が参加できるようにしている。
また、同社の障害者雇用の取組は、現在本部長が中心となり進めているが、企業として、取組の継続が可能となる人材育成こそが命題の一つと捉えており、本部長の後継者の育成にも注力している。
ウ 障害者雇用を会社全体の成長につなげるための取組
障害のある社員と障害のない社員が共に働くことで、障害のない社員のレベルアップや現場責任者のスキルアップができるように工夫し会社全体の成長につなげるための取組にも力を入れている。
各店舗の障害のある社員と店長などの現場責任者を定期的に集め、勉強会を開催している。勉強会では、参加する障害のある社員(以下「参加者」という。)が、現場責任者と一緒にパワーポイントで資料を事前に作成し、それを用いて、ほかの参加者へ、自分の働く店舗の紹介と、店長の紹介(ここが一番盛り上がるとのこと)、また「こんなことができるようになった」もしくは「今こんなことをやっています」ということをそれぞれ報告する。報告は参加者を中心に行い、現場責任者や勉強会運営側はそれを見守る。毎回、参加者は皆一様に緊張しているが、上手に報告する者もでてきている。そして、勉強会の最後では、参加者に対し会社から、人前でもじもじしないで話すことも、ドーナツやオムライスを作るとか、接客をするという現場での仕事とはまた別に、社会人として大切なことであると伝えている。
参加者の感想としては、「あの人があそこまでできるようになっているんだ」、「じゃあもっと頑張ろう」であるとか、素朴に「すごい」というものが多い。模範となる先輩が、他店舗にいることがわかるだけで、就労継続や技能向上などに向けた意欲につながる様子が見られる。また現場責任者などの店舗の社員たちも、日々の営業の中ではなかなか把握が難しい参加者本人の状態や、達成できた事柄を改めて確認でき、またそれを現場で生かすことができる。
以上のように、取組の効果として、障害のある社員自身が、仕事の見直しや確認を行うことができ、自己理解になり目標も持つことができるとともに、現場責任者などにとってもレベルアップにつながっている。
4. 今後の展望と課題
今後の展望と課題について、本部長は以下のように話す。
「障害者雇用をもっと『あたりまえ』のものにしていきたい。障害の種類を問わず、障害者の方が、飲食店の現場で働いていることが、特段の説明を行わなくとも、普通のこととなるように。これが展望であり、課題でもある。
そのためにも、理想としては、全店舗において、1人以上の障害者が、普通に働いている環境にもっともっとしていきたいし、一緒に働く社員には、今よりもっと理解が深まるよう、継続して働きかけを行っていきたい。」
また、本部長にお話しいただいたなかで、同社の障害者雇用の取組を支える理念の一つである「障害者雇用に学ぶ」ということを、非常に感じ取れる内容のお話があったことから以下に紹介し、本稿の結びとする。
「飲食店の業界で、店舗を構えて営業するところには、当然ながらそこに店長などの責任者がおり、責任者にとって重要なことの一つは、人を理解し、まとめていくリーダーシップだと考える。時代は変わってもその重要性は変わらず、今の時代に見合うリーダーシップが必要になり、それにはいろいろな人を理解し見識を養い、その見識を広げていくことが肝要である。その観点においても、障害者の方と一緒に働くことは、社員教育、とりわけ店長教育の中でも必要不可欠な要素と考える。会社都合ではなく、本人の立場に立ち、障害者の方たちに業務を理解していただきそれができるようになっていくステップ、教える側が省略せず粘り強く何度でも教えるということが大切な基本である。障害者の方たちに業務を教える過程では、これらの基本的なことを、きちんと行うということを、特に強く意識するようにさせている。だから教える側が緊張し工夫する。そして教える側が勉強になる。そのことを常に理解し取り組むことで、現場責任者のみならず会社全体において、責任感やスキルが向上することは確かである。ものの見方として、今まで当然と思っていたことが当然ではないこと、今の教え方がベストとは限らないということを、少しでも気づくことが本当に重要。本部長である私もいまだに毎日、こんな表現や工夫があったのかなど、勉強になることが多々ある。障害者雇用を通じて、日々『会社側が勉強させていただいている』との思いを新たにしている。」
執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
長崎支部 高齢・障害者業務課
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











