企業理念に沿って目的意識を持ち、
決して無理することなく自然に取り組んでいる事例
- 事業所名
- 旭陽電気株式会社
(法人番号: 4090001011059) - 業種
- 製造業
- 所在地
- 山梨県韮崎市
- 事業内容
- 半導体製造装置・情報通信機器製造
- 従業員数
- 396名(旭陽電気325名、旭陽エンジニアリング71名)
- うち障害者数
- 10名(旭陽電気7名、旭陽エンジニアリング3名)
-
障害 人数 従事業務 聴覚・言語障害 2名 ハーネス製作、製品梱包 肢体不自由 1名 管理職 内部障害 1名 ハーネス検査 精神障害 1名 部材管理 発達障害 5名 装置組立、図面整備、製品梱包、他 - その他
- 障害者職業生活相談員
- 本事例の対象となる障害
- 聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害、精神障害、発達障害
- 目次
-
 事業所外観(韮崎工場)
事業所外観(韮崎工場) 事業所外観2(宮城工場)
事業所外観2(宮城工場)1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
ア 事業内容
旭陽電気株式会社(以下「同社」という。)では電子部品(ケーブル・ハーネス)の設計から製造までの業務を行っており、さらにはEMS(ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICE:電子機器製造受託サービス)業務として、顧客企業からの受託による電子機器製品を製造している。
また、社会インフラ整備業としては、河川・ダムの防災機器、顔認証情報設備等の情報機器の販売・施工を行っている。
事業拠点は、本社・本社工場(韮崎市)のほか、韮崎工場、甲府工場、宮城工場がある。
さらに、同社のグループ会社である旭陽エンジニアリング株式会社(以下「エンジニアリング社」という。)では、技術者育成、人材派遣、請負製造など様々な事業を展開している。
そして、同社とエンジリアニング社の両社は障害者雇用についての取組を連携して進めていることから、冒頭の従業員数等は両社の状況について紹介している。このあと紹介する障害者雇用の取組も、両社に共通する取組である。イ 同社の経営方針等
(ア)「企業理念」
電気を繋ぐ技術とものづくりで、社会の進歩を支える。
(イ)「KYOKUYO2025経営方針」※2025年1月に更新
①「次」の成長に向けて
・顧客へのビヨンドパートナーとしての提案
・省人化・自動化・システム化のDXの強化
・人的資本力(賃金、ウェルビーング)の更なる向上
②ネットゼロ ロードマップ作成と活動始動
③「まち」に展開。地域と共に。
(ウ)「WELL LABO」
同社の取組として、ウェルビーング事業「WELL LABO(ウェルラボ)」がある。
同社では、自社の行動規範の1つに「まずは、自分が幸せになる」を掲げている。ここでいう「幸せ」とは、HAPPYのような感情による幸せの
ことだけでなく、WHOが定義する「幸せ=Well-being」(身体的にも精神的にも社会的にも良い状態)が重要だと考えている。会社は「人」でできている。その一人ひとりが幸せか、不幸せかで、会社のアウトプットは全く違った結果になる。社員各人が、まずは自分が
幸せ(Well-being)になることで、仕事だけでなく、家族や友人など周囲に対して、良い影響が出るはずである。そう考えると、社員全員を幸せ
にすることは、会社という枠組みを越えて、関係する多くの人の幸せを、連鎖的に生み出すことにつながると考えることができる。そのための
取組がWELL LABO事業である。(エ) WELL LABO事業とは
社員を「幸せ(Well-being)」にするために、「心と身体の健康」、「働きやすさ」、「人材成長」の3つの観点で推進する様々な事業の総称である。
(オ) WELL LABOの名称
幸せの形は、人により様々である。この事業を通し、社員一人ひとりが「自分の幸せの形」を研究する機会となればと思い、【WELL=幸せ】【LABO
=研究室】とした。ウ 組織構成
WELL LABO事業は、社内の各拠点・各部門で横断的に担当者を定め、組織的に取り組んでいる。具体的には、総務本部、事業本部、韮崎工場、宮城工場、品質保証部、社会インフラ事業部と、エンジニアリング社により組織し、取り組んでいる。
エ 障害者雇用の理念
同社では、全ての社員に陽があたり、活躍できる機会を与え、全員が輝けることを目指している。障害者雇用についても同様で、各人の障害の特性や配慮すべき点を考慮し、輝けることを目指している。そして、障害のある社員もない社員も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現したいと考えている。それは、すなわち、前述の「(ウ)「WELL LABO」で紹介した行動規範、「まずは、自分が幸せになる」を実現することであると考えている。
(2)障害者雇用の経緯
同社では、障害者の法定雇用率の達成を意識した障害者雇用に以前から取り組んできた。そうした同社が、より積極的に障害者雇用に取り組むようになったきっかけは、約1年前に、「WELL LABO」の観点で障害者雇用のあるべき姿を再検討したことである。
検討の結果、「障害者の法定雇用率をノルマと思うことが間違いである」という結論に至り、その視点で社内を見たところ、以下のような実態に気が付いたからである。
・(職場でのトラブルや障害者の離職等について)障害者に原因があるというような一方的な見方をしがちであった。
・採用後のフォローができていなかった。
・障害者本人にストレスがかかっていた。
・障害の特性等について、まわりの社員の理解が進んでいなかった。
・障害者の雇用について、お荷物、おしつけとの感じ方があった。
同社は、こうした状況を改善することが経営理念等の上から必要と考えた。そして、障害者雇用は同社の重要な経営課題であり、不可欠な取組として位置付け、より積極的な取組を始めた。
次に、同社における障害者雇用の状況や取組等について紹介する。なお、下のお二人は、今回お話を伺った同社専務取締役の金山さんと、人材派遣課・教育支援担当課長の河邉さんである。
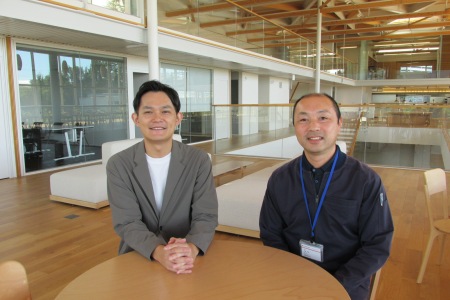 取締役の金山さん(左)、人材派遣課・教育支援担当課長の河邉さん(右)
取締役の金山さん(左)、人材派遣課・教育支援担当課長の河邉さん(右)2. 障害者の従事業務と職場配置
(1)労働条件
・雇用期間:有期雇用から始め、無期雇用に転換も可能。
・就業場所:韮崎工場、宮城工場、客先(請負製造)
・勤務時間:基本的には8時間のフルタイムだが、当人の希望により時短勤務も可能
・賃金:障害の有無に関係なく共通の給与規定を適用
・通勤方法:自家用車、公共交通機関
(2)従事業務の内容
主に、管理職、ハーネス製作、製品梱包、ハーネス検査、部材管理、装置組立、図面整備等である。
 製品梱包作業の様子
製品梱包作業の様子 ハーネス検査作業の様子
ハーネス検査作業の様子 部材管理作業の様子
部材管理作業の様子 図面整備作業の様子
図面整備作業の様子3. 取組の内容と効果
(1)労務管理の工夫(設備面も含む)
ア 採用について
(ア)業務の切り出し
各部署に障害者雇用に関するアンケートを実施し、業務を切り出すことで、適材適所に取り組んだ。アンケートの設問は次のとおりである。
「会社全体で障害者雇用を進める時に、自分の部署を除いてどこの部署のどういう仕事だったら障害者を雇用しやすいと考えますか?」
金山さんたちのお話だと、アンケートに「自分の部署を除いて」としたのは、各部署に先立ち、特定の部署で試行的にアンケートを行ったが、その際にはその表現はなかった。そして、先入観もあってか、回答には「うちには障害者ができる仕事はないです」等の否定的なものが少なくなかった。そうしたことから、客観的(岡目八目的)に業務を切り出すための工夫として加えたとのことである。工夫の効果があってか、様々な意見、提案があり、業務の切り出しに参考となったそうである。
(イ)高等支援学校新卒採用及び職場実習の実施
採用は高等支援学校からの新卒者を中心に行っている。山梨県・宮城県にある高等支援学校へ求人活動を行っており、在学中からの職場実習(以下「実習」という。)を受け入れている。山梨では、桃花台学園3年生の生徒が令和6年6月と10月に。宮城では、岩沼高等学園、小牛田高等学園、仙台みらい高等学園、各校2年生の生徒が令和6年10月に3週間の実習を行った。
(ウ)助成金の活用トライアル雇用助成金を活用した。
イ 労務管理について
(ア)専任の担当者(障害者支援員)の配置
「障害者雇用の経緯」で把握された課題(社内の理解、サポート体制等)への取組をスタートした。取組を中心的に担う社員を「障害者支援員」(以下「支援員」という。)として選任した(支援員は本社総務本部に所属しており、本社工場、韮崎工場、甲府工場、宮城工場もカバーしている)。支援員は、企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)、障害者職業生活相談員の資格などを有しており、障害者雇用に係る各種の取組を主導している。
(イ)定期及び早期の面談実施
支援員による面談シートを活用した定期面談の実施により、状況や課題を早期に把握し、課題の早期解決を図っている。特に、課題の予兆が出始めたら、早めの面談で課題解決につなげており、その際、最も重要なのは、面談のきっかけとなる予兆に関する周囲の社員からの連絡である。
(ウ)山梨障害者職業センターとの連携
山梨障害者職業センター(以下「職業センター」という。)との連携も取っている。例えば、遅刻、あるいは就業時間のギリギリに出社する日や、タイムカード打刻忘れが頻繁にあるような場合には、職業センターのジョブコーチと同社のジョブコーチ(支援員)が連携して、本人との面談を通じて「健康管理」と「生活管理」の重要性理解のための支援等を行い、改善につなげたことがある。
(エ)障害者雇用の理解の促進障害者に接する機会が少なかった人は、障害の特性や配慮事項等に対する知識が不足せざるを得ない。また、障害者の特性等も一人ひとり異なるので、一律に理解・対応することも難しい。「障害者雇用の経緯」で把握された社内の理解不足等は、そうしたことが背景にあると思われた。
障害者雇用を進めるためには、障害特性や障害者との接し方についての社内の理解の促進を図ることが必要とされた。
そのため、まず、監督職を対象に、障害や障害者についての基礎知識、障害者雇用に対する理解促進、障害のある人との接し方についての研修をスタートし、現在も開催している。その際に重要と考えているのは、障害についての知識を学ぶということにとどまらず、「障害」を「個人の違い(多様性)」として理解し、多様性に応じた接し方をしていくことである。
(オ)総務関係のデジタル化
総務の手間を省き、障害者雇用等の業務に注力できるよう、勤怠管理システム(商品名KING OF TIME)、人事賃金管理システム(商品名マネーフォワード)を導入した。システムの導入により総務部門の省力化が進み、障害雇用により注力することにつながった。
(2)取組の効果
上記(1)の各取組により、次のような効果が認められると同社では考えている。
・障害者の実雇用率が上がっている。
・職場の生産性が上がっている。(管理職の意識の向上、職場からのクレームの減少、
職場のストレスの減少)
・採用に苦労することがなくなった(支援学校と連携することで、応募者が確保できる)。
(3)障害のある社員・上司のお話
取材の中で、障害のある社員(以下「本人」という。)と、その上司の方からお話を聞くことができた。
本人は、現在担当している仕事を説明してくれた上で、「定年までこの会社にずっと勤めたい。」と話をされており、働きやすい職場であることが伝わってきた。
また、直属の上司である製造2課の堀川課長からは、「いろいろな苦労は絶えないが、職場に障害のある社員がいることで、職場環境や業務進捗状況に気を配るようになった。その結果、周りがよく見え、職場の皆さんの人となりがよく分かるようになった。また、障害のある社員はみな生真面目であり、大変貴重である。その生真面目さを活かすには、周りが障害を理解することが、不可欠と思う。」とのことだった。
他の上司の方からも、「今後、是非、機構の障害者雇用事例リファレンスサービスを活用し、他社の取組を参考にしたい。」との意見も聞かれ、上司の皆さんが障害者雇用に意欲的であることがよく分かった。
 お話を伺った製造2課課長の堀川さん
お話を伺った製造2課課長の堀川さん4. 今後の展望と課題
今後の同社の障害者雇用について、同社専務の金山さんと担当課長の河邉さんに伺った。
(1)課題
取組を始めてから一年程度だが、一定の成果をあげることができており、更なる障害者雇用を進めるためには、次のような課題、即ち改善すべき点があると同社では考えている。
・宮城工場での雇用人数拡大。
現在は山梨県内の事業場での雇用が主であるので、宮城工場での障害者雇用の拡大を図る。
・女性の雇用人数拡大。
製造業ということもあって、会社全体の社員構成は男性が多い。障害のある社員についても同様。更なる障害者雇用に向け、職域・職種の拡大等が必要と考えている。
・社員全体の障害者雇用への理解促進。
これまでの取組により、社内の理解は進んできた。しかし、職域・職種、就業場所の拡大には更なる社内の理解が必要と考えている。
(2)対策・展望上記(1)課題の対策として、次の取組を実施、並びに予定している。
・高等支援学校より、女子生徒を令和7(2025)年度新卒採用。
・令和8(2026)年度以降の新卒採用に向けて、高等支援学校の職場実習生を受け入れており、今後も継続を予定。(※受入状況 宮城工場:3年生3名(男子3名)、2年生1名(男子1名))
・監督職(主任・リーダー)への理解促進研修を実施しており、今後も年1回程度、定期的に研修を実施する予定。
以上であるが、近い将来の展望として、障害者を中心とした部署、いわゆる特例子会社的な部署を、社外ではなく社内に立ち上げることで、より一層、社員一人ひとりが幸せになる仕組みとして実現させたいと考えている。
(3)障害者雇用に取り組む企業へ、専務の金山さんからのアドバイス
まず言えることは、知識があり観察力がある者を、障害者雇用の担当者として配置することである。遠回りのように感じられるかもしれないが、一番の近道と思われる。配置が難しい場合は、とにかく教育が重要であり、研修の機会を設けることが有効と考える。社員全員がリテラシーを持ち、人間関係を作ることができれば、障害者雇用の実現に近づくことができる。ただし、「何のためにするのか」という目的意識を持たなければ、本当の効果は得られないと考える。自社の場合、経営方針等にある、「社員が幸せになる(Well-being)」を追求する過程で、無理することなく目的意識が醸成され、現在の障害者雇用を実現できたものである。言い換えると、理念なき取組では、成果は上がらなかったかもしれない。即ち、障害者雇用に取り組む前に、経営方針等に立ち返り、社員一人ひとりが目的意識を持ちながら臨むことが大切ではないだろうか。
(4)最後に
訪問して筆者がまず感じたことは、なんと雰囲気の良い会社だろうということである。
環境も素晴らしく、うらやましく思えたほどである。この会社であれば、障害の有無にかかわらず、社員一人ひとりが働きやすいのではないかと予想していたが、話を伺っているうちに、それは確信へと変わった。特に印象に残っているのは、専務さんから伺った「雇用率はノルマと思っているのが間違い」という話である。これこそ、まさにパラダイム転換であり、「会社の理念に沿って社員がどうすべきかに立ち返る」との考えから自然と生まれたものなのであろう。したがって、あらためて、企業理念や目的意識の重要性を再認識させられた。
訪問を終えて、気分が高揚すると同時に、温かさや、さわやかさを感じながら、会社を後にした。また訪問したいと思わせるほどの会社の雰囲気と取組内容であった。
執筆者:雨宮労務管理事務所
所長 雨宮 隆浩
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











