独法研究機関のきめ細かな障害者雇用
- 事業所名
- 独立行政法人産業技術総合研究所つくば本部
- 所在地
- 茨城県つくば市
- 事業内容
- 学術・開発研究機関
- 従業員数
- 3,937名
- うち障害者数
- 84名
障害 人数 従事業務 視覚障害 3 研究・技術補助ほか 聴覚障害 5 一般事務、研究・技術補助ほか 肢体不自由 38 一般事務、研究・技術補助ほか 内部障害 15 一般事務、研究・技術補助ほか 知的障害 10 事務補助、環境整備 精神障害 13 一般事務、研究・技術補助、環境整備ほか - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)概要
産業技術総合研究所は、2001年4月に、旧通商産業省工業技術院の15研究所と計量研修所が統合・再編されて誕生した。ライフサイエンス、情報通信・エレクトロニクス、ナノテクノロジー・材料・製造、環境・エネルギー、地質、標準・計測の6分野という多様な産業技術の研究を目的としたわが国最大級の公的研究機関であり、国の安全・安心の確保および産業競争力の強化に資する研究の推進、さらには新産業創出への貢献という大きな役割を担っている。
本部は東京及びつくばにあり、北海道から九州までの全国9ヶ所に地域センターを配している。
当研究所で雇用されている84人のうち、身体障害者、精神障害者は全国の各部署に所属しており、健常者と同様に、その部署が責任をもって雇用管理、指導教育等を行っている。なお、バリアフリー推進室からのフォローとして職業生活等に関する相談窓口を設けている。
今回は、知的障害者、発達障害者から構成される「つくば本部能力開発部門バリアフリー推進室チャレンジドチーム」の活動を中心にご紹介する。
(2)障害者雇用の経緯
平成18年1月に障害者雇用3ヵ年計画を立てる。当時の障害者雇用率は、0.57%。計画開始から1年半を経過した平成19年6月は、1.04%と、それなりにがんばったが、法定雇用率には遠くおよばなかった。そこで平成20年3月、全所的に障害者の雇用を促進するため、つくば本部の能力開発部門に新たな組織である「バリアフリー推進室」を設置し、年内の法定雇用率2.1%達成を目指した。さらに同年6月には、知的障害者の雇用を促進するため、同推進室においてチャレンジドチームを編成した。
チャレンジドチームを編成した時点で、計画開始から2年半を経過していたが、当時の障害者雇用率は1.46%。残り半年で、目標である法定雇用率の達成までは0.64%の不足となっていた。
ここからバリアフリー推進室がフル稼働し、本部や地域センターの各部署の協力を得ながら障害者向けの仕事を探した。その結果、一気に障害者雇用が進み、3ヵ年計画の終了時には、障害者雇用率2.14%と、目標としていた法定雇用率2.1%を達成することができた。さらに平成21年6月1日現在の障害者雇用率は2.71%となっている。
能力開発部門バリアフリー推進室運営スタッフ(写真下)は、関根英二室長のもと、チャレンジドチームは、村松昭子主査、黒岩美喜技術専門職、職場指導員3名、シニアスタッフ1名で運営され、現在、実働部隊のチーム員(知的障害者、発達障害者)は10人である。

2. チャレンジドチームの業務内容
各部署から受注した書類の裁断作業などの事務補助業務や会議室等の清掃など環境整備業務が主な業務である。組織が大きいため、これらの業務もまとまると大変な量となり、現在ではチームの存在は欠かせないものになっている。業務内容の詳細は以下のとおりである。
(1)事務補助業務
①新聞紙でつくるエコバッグの製作(資源ゴミの付加価値化)
②所内連絡便用封筒のリサイクル
③郵便物デリバリー
④シュレッダー作業(廃棄文書回収箱の定期回収、ホッチキス針・付箋の除去、裁断作業)
⑤チューブファイルのリサイクル
⑥職員の名刺製作
⑦各室の名札製作
⑧封筒のゴム印押し、封筒の宛名シール貼り
⑨宅急便の伝票切り離し
⑩宅急便伝票の入力作業
⑪共済組合パンフレット(全国配布用)の仕分け・封入作業
⑫研修資料の印刷・製本・封入作業
⑬コピー用紙の補充
⑭年末調整用個人別封筒と申告書類+付属書類の袋出しと整理
⑮源泉徴収票の個人別封筒への封入作業
(2)環境整備業務
①会議室等の清掃
②共用自転車の清掃・空気入れ等の整備
③執務フロアー内のカウンター・応接セットの清掃
④執務フロアー内のゴミ収集
⑤傘立ての整頓
⑥花壇の整備
⑦体育館の清掃
⑧一時預り保育所の遊具の清掃
⑨歩道・駐車場・排水溝の清掃
⑩屋外の除草・清掃作業
(3)写真で見るチャレンジドチームの業務

郵便物デリバリー

所内便封筒リサイクル

源泉徴収票の封入作業
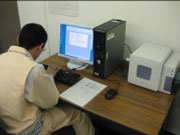
名刺の作成

書類の裁断作業

会議室の清掃作業

体育館の清掃作業

共用自転車の整備

屋外の除草・清掃作業

花壇の整備
3. 取り組みの内容
(1)求人と配属先の決定方法
①身体障害者および精神障害者は、ハローワーク(公共職業安定所)、障害者のための就職・転職求人サイト(平成20年度で終了)、障害者就職面接会を通じて求人している。
②書面審査に合格した人について、面接試験を実施している。この面接試験には産業医も参加し、配属先等について助言をしている。
③面接試験に合格した人は、障害の種類や経歴等を勘案して配属予定先を選定している。その後、配属予定先の管理者と本人との面談を実施し、配属先の決定を行っている。
④知的障害者、発達障害者は、就労移行支援機関(茨城障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターかすみ、茨城障害者職業センター)で職業訓練を受けた人や茨城県発達障害者支援センターで相談経過のある人を紹介してもらい、職場実習を行っている。この職場実習の評価で一定の基準以上の人は面接試験を受け、合格者はバリアフリー推進室チャレンジドチームに配属される。養護学校から現場実習の受け入れを行っているが、今のところ直接雇用の実績はない。
(2)作業するに当たって特に配慮する点
①各部署に配属されている障害者は、他の契約職員と基本的には同じ扱いで、障害部分以外、特別な配慮はしていない。しかし、体調等本人が特に申し出た点については当然であるが、相談にのっている。
②一方、チャレンジドチームに配属になっている障害者は、その障害特性に合わせたグループ編成で業務を行っている。チーム員のフォローアップ(作業中の安全を確保、障害を持つ部分をカバー、等)を行うために職場指導員を新たに雇用し、業務指導を行っている。
(3)設備改善
チャレンジドチームを立ち上げるに当たって新たに執務室を設けたが、特に設備改善は行われていない。その他の部門については、次のような一般的な改善であり、特別変わったことはしていない。
①トイレの改修
②身障者用駐車場の増設
③手すりの設置
④照明スイッチの増設(車いすで手が届く位置にスイッチを増設)
(4)教育はどのようにやっているか?
チャレンジドチームの場合は、基本的には職場指導員によるOJT。OFF-JTでは、マニュアル本(高齢・障害・求職者雇用支援機構発行等)を活用している。その他の部門については、基本的にはOJT。OFF-JTでは各種研修を受講している。
(5)制度の利用
茨城障害者職業センターが実施している職務試行法を活用して発達障害者を雇用した事例は、これまでの職場指導員の対応では困難であったため、同センターのジョブコーチ支援事業を活用した。これらの制度は大いに活用したらよいと考える。
(6)退職者
この2年間の退職者は、民間企業や地方公共団体に就職した身体障害者のほか、症状が悪化した精神障害者、1人では着替えが困難な知的障害者等、職場指導員の対応では困難な事例があるだけで定着率は高い。
4. 取り組みの効果
バリアフリー室と障害者(チャレンジドチーム)の家庭を結ぶ連絡ノートは、定着するまで続けられる。その中のいくつかを以下にご紹介するが、これだけ見ても取り組みの効果がよくわかる。
(1)家族の感想
それぞれのどの言葉の後にも、感謝、喜びの言葉が添えられており、まぶしいくらいに明るい家庭を垣間見た思いがする。
①毎日が幸せそうで、にこにこして報告をしてくれます。
②毎日、「疲れた」という言葉より「お腹がすいた」といっています。仕事に少しずつ慣れてきており、楽しんでいるようです。
③毎朝、「行ってきます」と元気よく出かける後ろ姿を見ながら「無事にお仕事ができますように」と、心で念じています。
④仕事は本当に楽しいようで、毎日はりきっています。今月のお給料でデジカメを買いました。
⑤少しずつ落ち着いてきたのでしょうか、今日はお給料の明細を見せてくれました。貯めて買いたいものがあるそうです。1万円を家に入れてくれるそうです。うれしいです。
⑥あれもできるようになった。これもできるようになったと、毎日報告をしてくれます。これからも可能性が広がると思いますので、何事にもまじめに取り組んでほしいと思います。
⑦パソコンの仕事ができることをとても喜んでいます。
⑧周りの方々とのかかわり方や仕事はちゃんとできているのか、心配をしておりました。課題点等を家族で話し合いました。「僕、がんばるから!!」と、言ってくれました。
⑨バリアフリー通信(所内報)ありがとうございます。自分の名前があったということもあり、よく読んでいました。連絡ノートを見ると、様子がよくわかり、助かります。ありがとうございます。毎日、日誌を見せてもらったり、私の質問に答えてくれたりするのですが、最近は仕事以外のことで、「○○さん風邪ひいている。明日大丈夫かな?」…等よく言っていました
⑩先週からの風邪もだいぶよくなりましたが、インフルエンザの時はプリントに従って休ませます。日曜日でも「産総研に行きたい」と言っていました。きっと毎日楽しく働いているのだと思います。
⑪「学校から先生方や後輩達が来るんだって…」と話を伺ってから、前日まではうれしそうでしたが、当日になると「僕なんだかドキドキしてきた…」と言いながら出かけました。帰ってきてからは「少し緊張したけど、先生やみんなと会えてうれしかった。先生“がんばってね”って言ってくれた」と言っていました。「僕、仕事がんばる!!」と言うので「頑張れ!!」と励ましました。
⑫本日は思いがけないクリスマスクッキーのプレゼントをいただき本当にありがとうございました。とても喜んでおり、その日の内に全部食べると言いましたので、大切に少しずつ食べるようにと話しました。
⑬現在の仕事についても、慣れればスムーズになると思いますが、学習障害というものは何度も繰り返して覚えていくのがタイプですので、様子を見て仕事に対する取り組み方も指導していただきたいと思います。指導する方法ですが、耳から入る言葉では理解することがまず難しいことなので、作業の手順など絵や図に書いて目で見て理解するように説明すれば効率よく能力を発揮できるかと思います。
⑭毎日の仕事の中で至らぬことも多々あるかと思います。仕事中は仕事に集中して、しっかりやるよう話しています。
(2)本人の感想
それぞれのどの言葉の後にも、「これからもがんばります。よろしくお願いいたします」という言葉が添えられていた。みなさんやる気十分!頼もしい! なお、ここに紹介する言葉は後述する「バリアフリー通信」に掲載されたものである。
①草取り、会議室の掃除などを行いました。たまにはつらい時もあるけど、休憩をしながら頑張っています。帰り(天気のよい日)は、荒田駅まで歩くけど、ダイエットになってちょうどよいです。
②まだ少し緊張はあるけど、徐々に慣れています。掃除や草取りをして、きれいになるとうれしい。通勤は苦にならないです。
③エコバッグ作りをしました。むずかしくて大変だったけどがんばりました。また作りたいです。
④宅急便の伝票の練習、名刺作りを行っています。これからは、会報作りなどをやってみたいです。
⑤毎日楽しく仕事をすることが出来、みなさんどうもありがとうございます。みなさんに優しくしてもらって嬉しく思います。ずっと働けるように一生懸命頑張ります。これから、パソコンやいろいろな仕事にも挑戦していきたいです。
⑥今は仕事が楽しいので一つ一つ覚えていき、また、別な仕事にもチャレンジしたいと思います。
⑦僕は、今、エコバッグ作りや書類整理などをがんばっています。これからも、いろいろな仕事を覚えます。
⑧今、私は清掃作業、エコバッグ作り、所内便封筒リサイクル等に、時には真面目に、時には間が抜けたり(笑)と少々面白可笑しい時間を過ごしております。
⑨歩道清掃を行っています。寒いなと思う時もありますが、みなさんが優しくして下さって嬉しいです。
⑩仕事を始めて間もなく1ヶ月になります。最初はどんな仕事をするのかと不安でしたが、仕事に慣れると毎日が楽しく、特にエコバッグ作りが好きです。これからはいろいろな仕事にチャレンジし、ずっとこの仕事を続けたいと思います。
⑪現在、駐車場利用状況の調査とその結果のデータ入力の仕事を行っています。新しい仕事にも挑戦したいと思います。
⑫封筒のリサイクル、エコバッグ作り、草取り、清掃などをしています。清掃や草取りで、他の人ともっと協力して作業したいと思います。
5. 今後の展望と課題
(1)将来展望
チャレンジドチーム員は、1年単位で契約を更新する契約職員となっている。1日6時間(週5日勤務)、月額報酬88,200円(月21日勤務の場合)。労働保険、社会保険、通勤手当あり。
報酬以外は、健常者の契約職員と同じ条件ではあるが、一人ひとりが持っている将来の希望や職業適性に応じたステップアップの仕組みを考えていく必要があると認識している。この点を検討していく上で、障害者就業・生活支援センター等の関係機関との連携は不可欠であり、今後もご支援、ご協力をお願いしていきたいとのことである。
(2)職員に対する受入れ教育
チャレンジドチームの活動状況などを知ってもらい、さらに理解を深めてもらうために「バリアフリー通信」をほぼ1月のペースで発行している。また、雇用管理者や同僚向けに「障害者雇用の基礎知識」を発行している。まだまだ周知不足のところがあるため、これらについては、今後とも継続的に行う必要があると考えている。
(3)労働災害、交通事故
これまでは労働災害、交通事故は発生していない。しかし、災害ポテンシャルはどこに潜んでいるかわからない。今後も教育の徹底、作業方法の見直し等で、無事故・無災害を継続するようにしていきたい。
(4)労働意欲・作業態度の課題
チャレンジドチームの障害者も十人十色でいろいろである。今回は発達障害者について紹介する。
障害部分については、職務遂行に必要なことは全面的にカバーしたいと考えている。しかし、障害と関係のない個人的な事柄だからといって放置していると、これが仕事への取り組みに悪影響を及ぼすことになり、周囲の理解を得ることはできなくなる。結果的に本人が居づらくなって職場定着は困難になってしまう。
このように、どこまでが障害であるのか、どこまでを職場がフォローすべきなのか、を見極めなくてはならない。これまでに、医師・家族・本人たちとしっかりコミュニケーションをとって対策してきたこと、関係機関とのケース会議を開いたことが職場定着の一因と考える。また、仕事が変わった途端、別人のように能力を発揮する人もいる。適材適所が如何に重要であるかということも学んでいる。
| 発達障害者の問題点と対策 |
| 課題:(高機能自閉症)指導員の指示に従わない、注意に対し言い訳をすることが度々あり、やりたくない仕事のときに顕著にこれが表れていた。頭は良くて弁が立つ。まくし立てた後、「いらいらするので言ってみただけ」などということもある。 対策:本人、指導員も、とことん話し合うことにより、お互いを理解し合うようになった。本人の体調の良し悪しもわかってきたので、指導員もゆとりを持って対応ができるようになってきている。最近は素直な態度で指示を聞けるようになってきている。しかし、時折、まだ不満が表情に出ることがある。気長に対応していきたい。 |
| 課題:(広汎性発達障害)次の行動に移ると、その前に指示されたことを忘れることが度々あった。 対策:指示されたことをメモにとるよう指導した結果、最近は落ち着いて仕事ができるようになってきている。しかし、肝腎のメモをなくすこともあり、完全によくなったわけではない。一気に理解させることは困難であり、一つの指示をいくつかにわけて説明するので、普通の人の2、3倍の時間がかかる。明るく、後に引きずらないカラッとした性格であることは長所である。なお、花壇の苗の植え付けを任せたところ、農業関係の学校の卒業者だけに、あっという間に、しかもきれいに行ったので、適材適所の重要性を実感した。 |
| 課題:(広汎性発達障害)仕事中に居眠りをしたり、わからないままになっていたり、ということがあり、指導員が注意すると「障害だから仕方がない」と言い訳することがあった。 対策:家族に状況を話したところ、家族が本人の生活状況(夜、遅くまで起きていて寝不足になっていたことや、不安な時に飲む薬を飲み過ぎていたこと等)を把握していなかったことがわかった。早速、家族が医師に連絡し、薬の服用方法と薬を変えたところ状況が改善された。このことから医師・家族・本人の連携を密にすることが大事であることを学んだ。 |
| 課題:(アスペルガー症候群)学生時代のいやな記憶(いじめ)のフラッシュバックが根本にあり、コミュニケーションをうまくとれない。また、家庭での問題を職場まで引きずってしまい、精神的に不安定な部分がある。 対策:グループ活動がストレスの原因になっていることがわかったので、一人で行う仕事に就けたところ、今ではパソコンを使ってデータ管理をするなど責任感を持って仕事をするようになった。このように仕事面でのサポートは指導員が行うが、私生活の問題は、地域の支援機関にお願いしてサポートしてもらったところ、大分症状改善がはかられた。このような役割分担も重要と考える。 |
(5)チーム員の能力向上
①チーム員に職業人としての意識を如何に持ってもらうか(働くということ、給料をもらうということの厳しさ)、繰り返し指導する。
②従業員用チェックリスト(高齢・障害・求職者雇用支援機構編)を活用しながらチーム員の能力を最もよく引き出すための効果的な指導を行う。
③障害特性別のグループ編成をしながら、その中においても職業適性別のチームを編成し、双方のメリットを活用する。
④チーム員のうち、特に発達障害者の雇用管理の困難さに対応するため、ケース会議(茨城障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターかすみ、ハローワーク、当研究所出席)の定例化を検討する。
⑤チーム員のステップアップを構築していくために、関係機関とより緊密に連携をとる。
(6)バリアフリー推進室の今後
現在の障害者雇用の状況は、大上段に構えず、できるところから「はじめの一歩を踏み出そう」という姿勢でやってきた結果と思っている。また、チャレンジドチームの運営では、特例子会社や就労支援機関等を訪問し、いろいろなことを学んできたことが今に生かされている。今後も先進的な取り組みを行っている事業所の事例等を一層学んでいきたい由。
障害者に働く場を提供していくことは、公的機関としての責務であり、障害者雇用は予算面で「障害者人件費枠」があり組織的な取り組みとなっている。しかし、これに甘えることなく、各部門から安定した業務を確保し、費用対効果の検証を欠かさないようにしなければならない。そのためにもチャレンジドチーム運営のキーマンである職場指導員の体制を一層充実させていくとともに、チャレンジドチームを設けている2つの地域センターとの連携を密にしていく必要がある。
今後も公的機関の義務として、法定雇用率を常に上回っていくように取り組んでいきたいと前向きである。
6. おわりに
わが国最大級の公的研究機関の本部だけあって、近代的な建物が林立しており、未来都市に足を踏み入れたような錯覚を覚えた。
当研究所は、全国に拠点があり、行っている研究内容は日本のトップというより世界のトップともいえるもの。障害者の雇用も教育もさすがに組織的であり、教育マニュアルをはじめ各種資料も充実しており、「さすが!」と唸らざるを得なかった。
短期間に多数の障害者を雇用したにもかかわらず、症状悪化等で退職した人以外は、ほぼ全員が定着しており、安定している。ほかの独立行政法人の雇用は、なかなか進まないと聞いている。当研究所が、障害者の雇用についても先駆者となり、日本の障害者雇用の牽引車として一層の成果を上げることを期待したい。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











