正社員として必要な存在
- 事業所名
- 株式会社カメヤマテック
- 所在地
- 三重県亀山市
- 事業内容
- 液晶、ディスプレイ製造
- 従業員数
- 295名
- うち障害者数
- 4名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 2 梱包作業(2) 肢体不自由 2 事務(1)、軽作業(1) 内部障害 知的障害 精神障害 - 目次

1. はじめに
株式会社カメヤマテック(以下、本事業所)は、平成15年にシャープ株式会社が亀山工場を稼動させたのと同時期に、株式会社ミエテック亀山工場として開設され、平成17年11月に「株式会社カメヤマテック」を設立されている。
主な事業内容は、大型液晶テレビに使用されるTFT液晶ディスプレイの製造となっている。現在(平成21年7月15日現在)の従業員数は、1,215名(正規職員のみでは295名)で、この中に、身体に障害を持つ従業員が4人含まれている。本事業所には、本社工場・シャープ亀山工場構内・矢板工場の3つの工場があり、身体障害をもつ従業員(以下、障害者従業員)は計4名が勤務している。
4名の障害者従業員の従事作業としては、工場内の生産部と呼ばれる部署での軽作業や、製品梱包作業と、経営管理部におけるパソコン入力等のデスクワークとなっている。
2. 採用に至るまでの経過
本事業所では、母体となった株式会社ミエテックにおいて、すでに障害者雇用に取り組んでおり、一定の経験や知識があったことが、本事業所における障害者雇用の推進に大きな影響を与えている。今回訪問して話を伺った担当者の方も、株式会社ミエテックにおいて障害者雇用の担当をしており、そこでの経験からどのように障害者雇用を進めることが効率的なのか、ということについてよく理解をしていた。
当時の経験として、障害者雇用に踏み切る当初は、どのような労働条件の提示が出来るのか、どのように募集をすればエントリーをしてもらえるのか等、様々なことが手探りであった、とのことである。通常の募集の仕方では、障害者からのエントリーが全く無かったために、公共職業安定所(ハローワーク)が主催する障害者向けの就職説明会に参加したところ、これまでエントリーがなかったのが信じられないくらい、説明を聴きに来たり、工場を見学に来る障害者の方が増えた。この時は現在のように身体障害者枠ということで考えずに、様々な障害種別の人の雇用にチャレンジをしたとのことである。しかしながら、事業所の取り扱う製品(精密機器)の特性から、注意力が散漫な人や、集中力を要する作業に向かない人等は作業に不向きであると考えて選考していった結果、現在のような身体障害者を中心とした採用になった。現在雇用している聴覚障害のある方の採用にあたっては、手話通訳者を派遣してもらい、採用面接を行なっている。これは公共職業安定所との連携で行なわれており、本事業所が障害者雇用を展開する要因の一つとなっている。また面接では、日常生活や会社において必要とされる援助や一人で遂行することが困難なことなどを聴いて、その内容から採用や配属を決定した、とのことである。
これらのことから、本事業所における障害者雇用が進展した要因として、事業所としての成功の体験があり、その体験を実際に担った担当者が、本事業所に配属されていることが挙げられる。また事業所全体としても、1.8%の法定雇用率を達成するために、社長以下が積極的に障害者雇用を推進するという意識を持ち、採用に当たっては正社員として扱うことで、障害者従業員の労働意欲を高める努力をしていることも挙げられる。その他として、公共職業安定所を通して採用するため、特定求職者雇用開発助成金を受けることもしておられるが、助成金はあくまで採用をしたときのおまけのようなもの、と担当者は話していた。
3. 障害者雇用における配慮
障害者雇用に踏み切った本事業所において、障害者従業員の職場定着に寄与していると考えられるものは先に挙げた正社員としての扱い、次いで雇用管理、工場長をはじめとする従業員の理解の3点があげられる。このうち雇用管理については日々の管理は所属部署で行なっているが、それ以外について経営管理部がその業務を行なっている。
経営管理部では、障害者雇用における公共職業安定所との窓口業務や勤怠管理、長期休職の書類受付などを行っており、休職が長期にわたる場合には、その従業員の自宅近くで待ち合わせをし、心身の健康状態把握に努めるなど、職場に戻るタイミングを障害者従業員とともに考えるなど、単に書類管理をするのではなく、個別的な対応を丁寧に行っていることが、職場定着の要因として考えられる。下肢障害のある従業員のために、駐車場の位置を一番職場に近いところにしたり、聴覚障害のある従業員が孤立感を募らせないように、同じ聴覚障害のある従業員を同じ工程に配属したり、工程責任者・管理者が積極的に話しかけるようにしていることなどが具体的に挙げられる。
工場の生産部で働く1名の障害者従業員は、クリーンルームでマスク・白衣を着用し、軽作業に従事している。下肢に不安があるために、重い荷物を持たなくて良い作業を割り当て、定着につなげる配慮をしている。また作業で動く距離を短くして身体にかかる負担の軽減も図っている。
もう2名の障害者従業員は、聴覚に障害があり、コミュニケーションを図る際に、口元をみて理解する場面もあることから、マスクを着用しなくてもよい職場環境が必要との配慮で、一般作業の梱包を行っている。その2名は普段は大きな声でゆっくりと話せば理解できることもあるが、細かなことは独自にノートを作っており、業務において不明なことは筆談をして理解しようと努めている。このノートはコミュニケーションの道具であるだけではなく、業務におけるQ&Aになっており、分からないことが出てきた場合には、そのノートを開けると対応できるなど、一種のテキストにもなっている。また勤怠管理を行っている経営管理部の職員とはメールでやり取りをしており、通院や欠勤の連絡等をメールで行っている。
もう1名の障害者従業員がこの経営管理部で働いているのだが、左手でパソコンを使っての入力作業を担当している。主にはスケジュール管理や対外的な書類・内部名簿の作成などである。左手のみなので、作業スピードは若干遅いが、経営管理部においては非常に重要な存在として認識されている、とのことであった。この方は採用当初、以前の業務内容から、生産技術部に所属をしていたが、業務をある程度試行した結果、工場内の移動が多く、体に負担となっていることから、業務変更の必要性が考えられ、現在の業務に変更されている。この変更は本事業所からではなく、本人からの申し入れに基づき、適した職務を考えて行われている。
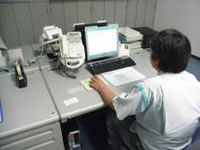
4. さいごに
現在では、それぞれの障害者従業員が仕事を覚えて、それを遂行できるようになっており、それを周囲の従業員も認めるところになっている。仕事が出来るようになってくると、次第に周囲も必要な関わり方で、それぞれの障害者従業員を受け入れるようになってきている。
職場内の配慮では障害に起因するものを除くと、他の正職員と同じ扱いであり、必要以上に干渉していないことも、それぞれの障害者従業員の意欲を高めていると考えられる。本事業所では従業員からの意見に耳を傾けて聴き、その内容を十分に検討するという姿勢が見られる。このことは障害の有無に関わらず同じように対応していることが要因の一つと考えられる。
現在の経済状況では今以上の障害者雇用の展開は望みにくいが、状況が好転すればまだ採用可能な部署があると思われるので、今後の展開を期待したい。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











