地域に優しく、人に温かい ~「障害者の自立と長期間勤続の支援」~
- 事業所名
- JAえひめアイパックス株式会社
- 所在地
- 愛媛県大洲市
- 事業内容
- 食料品製造業(食肉処理加工・販売)
- 従業員数
- 239名
- うち障害者数
- 5名
-
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 1 養豚 肢体不自由 2 事務処理、製造 内部障害 2 養豚、製造 知的障害 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要
(1)事業内容
・ 食肉の処理解体
・ 食肉の製造・販売
・ 副生物・副産物の処理加工・販売
・ 家畜の飼育・販売・生産団地の造成
・ ファーマーズマーケットの経営
(2)従業員数
総数239名 うち雇用障害者数5名 雇用率3.35%
| 身体障害者 | 知 的 障害者 |
精 神 障害者 |
担当業務 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覚 | 聴覚 | 肢体 | 内部 | |||
| 1 | 事務処理 守衛・清掃等 機器及び排水管理 微生物検査 |
|||||
| 1 | 1 | 農場管理事務 養豚 |
||||
| と畜解体 | ||||||
| 1 | 1 | 牛部分肉加工 豚部分肉加工 |
||||
| 事務・配送・営業 工場肉加工作業 店舗作業 |
||||||
(3)沿革
| 1978年 | (株)愛媛クミアイ食肉センター設立。 「1978年・1979年度総合食肉流通体系整備促進事業」により大洲工場の建設に着工。 |
| 1980年 | 大洲工場竣工。 家畜処理・部分肉カット加工業務本稼働。 |
| 1983年 | 「1983年度総合食肉施設整備事業」に基き、伊予工場「牛部分肉処理工場」の建設の着工。 |
| 1984年 | 伊予工場に「牛部分肉処理加工場」竣工、業務開始。 |
| 1994年 | 大洲工場に「串加工施設」を設置。 |
| 1995年 | 安全・安心の食品製造体制の強化のため「食品検査施設」を設置。 |
| 1996年 | 「1995年度食肉等流通体制緊急整備事業」第一期工事が完了。 伊予工場の処理機能を大洲本社工場に集約。処理能力を豚換算960頭に拡大。 社名「株式会社アイパックス」に変更し、社章を決定。 |
| 1999年 | 社名「県農えひめアイパックス株式会社」に変更。 |
| 2002年 | 本社工場内に「愛媛県食肉衛生検査センター」開所。 |
| 2003年 | 実験農場「川上農場」の施設再設備開始。 |
| 2004年 | 社名を「JAえひめアイパックス株式会社」と変更。 ファーマーズマーケット「いよっこら」の建設着工。 |
| 2005年 | ファーマーズマーケット「いよっこら」竣工、営業開始。 「せと風ファーム」竣工。 |
| 2007年 | ISO9001/2000認証取得(本社・いよっこら)。 |
| 2008年 | ISO9001/2000認証取得(農場)。 |
2. 取り組みの経緯、背景
1980年頃、当時の総務部長が障害者の就労支援に理解があったこともあり、当時の養護学校等を通して積極的に障害者雇用に取り組んだ。豚肉の処理業務は、複雑な変化が伴う作業であり、難しい面も多かったが、その時採用となった障害のある社員は、比較的軽易作業を担当することで対応し、現在も勤務している。その後、障害者の新規採用は見送っていたが、2005年に1名の聴覚障害者を採用する運びとなった。この採用は、一般募集で、これは障害の有無に関係なく、事業所の求める人材と希望者の能力とを考慮して雇い入れるという考えからであった。なお、この考えは現在も基本的な方針として維持している。
3. 取り組みの内容及び効果
(1)障害者雇用の取り組み
工場内は常に室温15度を保ち、枝肉やまな板などの細菌数検査をはじめ、施設・搬入車両・ユニホームに至るまで定期的にチェックし、工場全体のクリーンな環境維持に努めている。
消費者へ安全でクリーンな製品の提供するためには、働く人の安全をも確保する必要があるという考えから、障害者も安心して働ける職場環境づくりを目指している。障害の有無によって左右されることなく、障害者も健常者も同じように一従業員として接している。

◎ 雇用体制
募集・採用に関しては、特別に障害枠を設けるなどの取り組みは行わず、健常者、障害者の区別なく、各人の意欲・能力を考慮し、雇用するという意向である。入社後も、『一人前』になれるように丁寧な指導を行うようにしている。一人では危険、または難しい作業の場合は、他の従業員と行うなどして、それぞれの『一人前』について考え、柔軟に対応している。
◎ 定着
障害者の働く環境を整えるために、障害者職業生活相談員を選任し、障害者職業生活相談員を中心にして、周囲が障害を理解し、全従業員で職業生活を支え合うように取り組んでいる。障害のある従業員の適性配置や継続的な教育訓練とともに、必要に応じて医療関係機関と連絡をとりながら、施設・設備等の改善を含む作業環境の整備を行うことにも力を入れている。また、補助者の配置や通院による就業時間の配慮など、一人ひとりの状況に合わせて柔軟に対応するようにしている。
これらの取り組みが、現在の高い定着率につながっている。
(2)雇用の効果
「好きなことを仕事にしたい」「得意な分野を活かしたい」「自分の仕事に誇りをもって働きたい」「生まれ育った場所に貢献をしたい」…。誰でも働くことを考えた時、あるいは働く意義を求めた時、これらの思いを巡らせるだろう。
この事業所で働く障害のある従業員が、このような思いを実現し、非常に真面目かつ前向きに業務に取り組んでいる。また、確実に個人個人の能力も伸びており、定着率もよく、勤続29年の従業員もいるほどである。

「ずっと続けてこれたことが自信となっています」
(3)障害のある従業員の声
養豚場に、男性の中でたくましく働く、一人の女性従業員がいる。今回、彼女とその直属の上司の方のコメントをもらった。
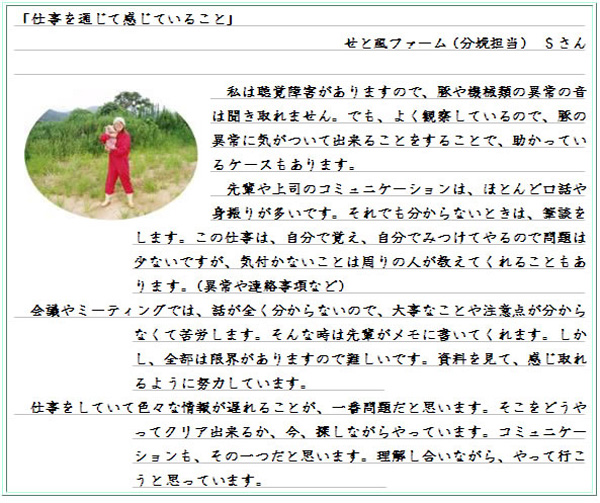
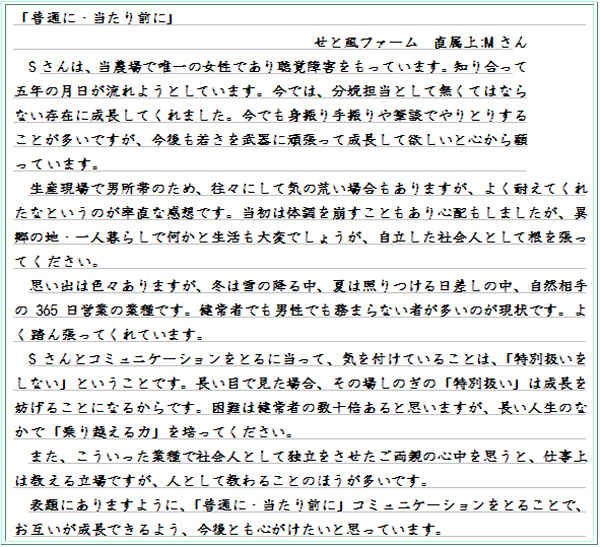
4. 今後の課題と展望
地域に根付いた企業として、さらには社会的責任を果たすという観点からも、多くの障害者を雇用したいとの考えであるが、作業内容が多様な変化を要するものであるため、難しいのが現状である。
しかし、障害特性と作業内容とを照合させ、企業が適切な職場環境を提供できるよう、行政レベルでの保障制度や支援体制が整えば、この事業所でも多くの障害者を雇用できるのではないかと考えている。しかしながら、当面は、現在の雇用率を維持させながら、事業所が求める業務に対応できる人材であれば、今後も障害の有無に関係なく、雇用していく意向である。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











