理想の会社には、障害者が存在する
- 事業所名
- 株式会社坂本製作所
- 所在地
- 茨城県筑西市
- 事業内容
- 通信機器部品製造及び環境関連製品の製造・販売・メンテナンス
- 従業員数
- 66名
- うち障害者数
- 3名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 3 バリ取り、プレス作業 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
昭和14年の創業以来、「良い物を早く、安くご提供する」を会社理念として活動している。富士通株式会社および同グループ会社の通信機器部品製造ならびに環境関連機器の製造および販売、メンテナンスを行っている。
(1) 当社には、現在3名の知的障害者が働いている。そのうち2名は、昭和52年、平成5年入社で、勤続はそれぞれ32年、16年と大ベテラン。残る1名は平成19年入社、勤続2年。大ベテランの2名は、今から9年前の平成12年に、退職を余儀なくされるような危機があった。代表取締役社長市村智明氏が最も苦悩したITバブルがはじけた時である。
(2) 当時、当社の取扱い製品のほとんどはIT関連であり、売上げは半減に次ぐ半減と、大変厳しい状況となっていた。役員報酬のカット、徹底したムダの排除、ワークシェアリング等、ありとあらゆる努力をしたが、どうにもならない。最後の決断として、2つの工場を1つに減らし、130名の従業員を半数以下の60名に削減せざるを得ず、障害者もその対象となった。
(3) そのころ、スマップの「世界に一つだけの花」(作詞・作曲 槇原敬之)がヒットしていた。社長はこの歌を初めて耳にした時、特に2番の次の歌詞に心を打たれ、この歌が大好きになった。
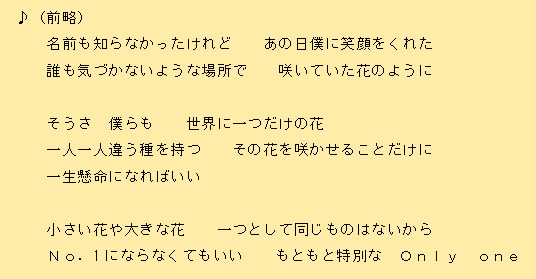
この歌から社長は、次のことを教えられた。
「世の中は、強い人ばかりで成立するものではない。弱い立場の人を含めてこそ、理想とする世の中が存在し、会社も存在できる」と。
社長が、弱い立場にある障害者を、“欠いてはならない存在”と認識した瞬間である。そして2名の知的障害者の存在価値と彼らの将来を合わせ考えて解雇の対象から外した。
(4) 「なぜ、私たちより仕事のできない障害者を解雇しないで、私たちを解雇するのか?」と言い寄る従業員もいた。しかし、社長は、「障害のないみなさんは、この厳しい不況の中でも雇用される可能性は十分にある。しかし、2名の障害者はここでしか雇ってくれるところはない。当社でがんばる他はない」と、説得した。
この時が、それまで何となく当社に存在していた障害者に光が当たった瞬間であり、真の意味で障害者が当社に雇用された瞬間であったかもしれない。
(5) 当社の障害者は、3名全員が知的障害者である。しかし、あえて知的障害者ばかりを選んで雇用しているわけではない。これは社長の“市村流自然体”で、たまたま近隣の高等養護学校や障害者就業・生活支援センター等から実習依頼があり、これをきっかけに採用しただけとのことである。
その高等養護学校から実習を経て平成19年に入社したのはAさん。2年生の時に2週間の現場実習を行い、その数ヶ月後、続けて3年生前期の現場実習の申込みがあった。社長は、本人のことを考えて、「世の中にはいろいろな仕事、会社がある。折角の実習機会なので、いろいろとチャレンジして、視野を広げてみては」と、他社の実習を薦めた。しかし、本人はどうしても当社で実習したいとのことで、3年生前期の実習を行った上、さらに3年生後期の実習申込みもあり、結局3期続けて実習を行った。3期続けて1社で実習することは、この高等養護学校でも例がないとのこと。Aさんは、よほど当社が気に入ったのであろう。
(6) 実習受け入れに当たっての社長の考えを聞くと、Aさんが当社に惚れ込み、実習したくなった気持ちがよくわかる。実習を始めるにあたり、社長は、「人にはいろいろな適性があるので、失敗をしてもよいから、できるだけ多くの作業体験をしてほしい。そして仕事そのものを楽しんでもらいたい」と、日替わり的にいろいろと仕事をしてもらった。そして実習終了時には、これまで操作した機械を写真に撮って、それを見ながら「この機械はうまくできるようになったね。これはうまくいかなかったが、なぜだろう?」と、実習生と一緒に語り合った。社長がAさんと“肩を並べて”実習を振り返ったということは、Aさんに大きな感動を与えたことだろう。そして極めつけは、実習終了時に社長が直筆でAさんに渡したA4、2枚の手紙。
(7) Aさんは、当時実習日誌に「ああすればよかった。こうすればよかった」等、失敗したことばかり書いていた。そこで社長は、手紙にこう書いた。「反省は人間を成長させるには欠かせない大切なもの。しかし、失敗のことばかり考えていては、なかなか前向きにならない。眠る直前でいいから、今日一番よかったことを思い浮かべながら眠ろう!」。
また、アメリカのケネディ大統領の就任の挨拶、「国が自分たちのために何をしてくれるのかを問うのではなく、自分たちが国のために何ができるかを考えよう」を例に引いて、国の代わりに「お母さん、お父さん」、「友人、知人」を入れて、いろいろな人の役に立つことを考えてほしいとも書いた。
Aさんは、よほど感動したのであろう、社長からの手紙を“生涯の宝物”として、大切に持っている。
2. 取り組み内容と効果
(1) 社長は、あくまでも自然流である。教育もOJT主体で、一緒に仕事をしているオペレーターに任せている。もちろん、その前提として、“任せて安心”の信頼関係があることは言うまでもない。当社は、従業員に対して障害者受入れのための特別な教育を行っているわけではない。しかし、障害者は、ごく自然体、空気のように会社に溶け込んでおり、しかも欠かせない存在となっている。
これは、前述したとおり、従業員の半数以上を解雇した時も、「世の中は、強い人ばかりで成立するものではない。会社にとって、障害者は欠いてはならない存在である。どんなに会社が苦しくても、ハンディキャップを持つ障害者を助けたい」と、1人として障害者を解雇しなかった。この時の社長の決断、発信されたメッセージが、以来当社の全従業員の目線となり、会社の伝統になったと考える。
(2) Aさんは、当社に惚れ込み3度も実習しただけのことがあって、勤続は2年と少ないが、バリ取り、プレス作業と多能化しており、一人で自主的に仕事をこなすこともできる。車の免許も持ち、挨拶もしっかりしている。また、社長に書いてもらったケネディ大統領の就任の挨拶にならって、「僕にもお母さんのためにできることがある」と、初給料でお母さんにプレゼントを贈ったという、うれしい話もある。
(3) Bさんは、勤続32年。バリ取り、プレスオペレーターと多能化しており、任せて安心である。挨拶もしっかりしている。
(4) Cさんは、勤続13年で、現在バリ取り担当であり、バリ取り作業をしながら目視検査もしっかり行い、「おかしい」と思ったらすぐに一緒に作業をしている責任者に製品に問題がないかどうか確認する注意深さも持っている。
Cさんは、会社行事の忘年会には残念ながら参加していないが、社長は、「そのうち出席したくなったら参加すればよい。無理をしてまで参加することはない」と言う。ここでも自然体である。

Aから品物を取り出しBで包装する

包装する時も目視検査は欠かさない

慎重さを要するプレス作業

手を挟まれないようA、B両ボタンを同時に押さないと機械は作動しない
(5) 当社は、鋼材を扱ったり、大型機械が稼働したり、一見すると危険を感じるところもある。しかし、社長は、「ケガ(事故を含む)は、基本を守らず、ルールを破った時に発生するものがほとんどである。ルールどおりの仕事をしていれば絶対安全である」と言う。
知的障害者は、「言われたとおりのことしかしない。余計なことはしない。決められたとおりのことしかしない。応用はない」。これらの事柄は、一般的に考えると、困ったことのように見えるが、安全面ではとても大切なことである。それを証明するように、障害者を雇用するようになってからすでに30年以上が経つが、これまで障害者のケガや事故はゼロである。
(6) 一人ひとりの作業スピードは速くないが、会社には、ウサギに向いた「速さを求められる仕事」は多いものの、そればかりではない。カメに向いた「スピードよりもコツコツと持続力を求められる仕事」もある。
3名の障害者は、ゆっくりしたペースのものであれば、1日中、同じ仕事をしていてもあきない驚異的な持続力がある。「障害のない人では、これらの作業を1日中、1年間続けるのは厳しいかもしれない」と社長は言う。制限された厳しい時間内の仕事は不得手であっても、同じペースでできる仕事は障害のない人以上にこなせる。高望みしないで、その人の適性に合った仕事であれば、会社としてしっかり計算できる能力を発揮してくれる。
障害のない人も障害者も同じで、その人の適性に合った仕事をしてもらうことが一番である。「障害者に合わせて仕事を探すと、障害者のできる仕事は、ほとんどの会社にかならず存在する」と、社長は確信している。
3. 障害者が退職したケース
(1) 障害者雇用がすべて順調であったわけではない。読者の参考になるのであればと、あえて社長は、退職した知的障害者のDさんのケースをご紹介してくれた。Dさんは、障害者就業・支援センターの紹介で平成16年、31歳の時に入社したが、3年で退職した。対人関係が苦手で、自分から話をすることはなかった。また、返事も小さな声で、挨拶もしっかりできなかった。しかし、仕事は順調に覚えていったので期待していた。
その後、自立したいということで、福祉施設を出て一人でアパート住まいをするようになったが、これも成長の一つと喜んでいた。しかし、それから数ヵ月後、それまで無遅刻・無欠勤であったDさんが初めて無断欠勤をした。
(2) 実はDさん、内臓疾患を抱えていた。本来常用すべき薬を飲んでいなかったため体調不良になったのである。福祉施設で生活していた時は、施設の人がしっかり健康管理をしてくれたが、一人住まいになってからは病院通いもおろそかになって、体調を崩してしまったようである。
原因がはっきりしたので、病院、障害者就業・生活支援センター、と連携をとり、朝の出勤がきついのであれば、午後からの出勤にしてもよいと、本人の希望を聞いて短時間労働を取り入れる等、工場長・部長・課長が1枚岩になって応援した。その甲斐あって、体力も回復しフルタイム勤務もできるようになった。しかし、しばらくすると体調不良を理由に何日か休んでしまう。5月、8月の長期の連休が入ると、2週間以上休むことも多く、結局本人が出勤しづらくなったのであろうか退職した。
ここからの教訓は、一人住まいの危うさである。知的障害者は疑うことを知らない人が多い、これに付け込む訪問販売も後を絶たない。今回のケースは、訪問販売絡みではなかったが、飲むべき薬を飲まなかったり、食事も不規則になって体調不良を招いてしまったようである。毎日の食事の準備は、障害のない人でも大変なことで、特に独身者は、インスタント食品や外食に偏りがちであり、食生活は十分留意しないと、健康面で心配がある。
4. 障害者の声
・Aさん(勤続2年)
「機械を使用して製品を加工することや、バリ取り、面取りなど、どの仕事も楽しい。困った時は、上司や同僚が親切に教えてくれる。これからは、製品を加工、整備、修理するなど、幅広く仕事ができるようにがんばりたい。」
・Bさん(勤続16年)
「みなさん親切で、困った時は何でも相談にのってくれるので、一緒に働けることが本当にうれしい。今まで以上によい製品を作れるよう、健康に気をつけながら一生懸命がんばっていきたい。」
・Cさん(勤続32年)
「何の変哲もない金属が形になっていく過程が楽しい。上司や同僚が何でも丁寧に教えてくれるので、一緒に働けることに感謝している。今後も品質を考え、よい製品を作り、みなさんと協力して仕事をしていきたい。また、長く元気に勤められるよう健康に気をつけていきたい。」
5. 今後の展望
(1) これも市村自然流であるが、「雇用率には特にはこだわらないで、障害者ができる仕事があれば何人でも雇用する」と言う。しかし、時間に規制の少ない作業、注意点の少ない作業となると、かならずしも多く存在しているわけではない。従来の通信機器部品の製造だけでは、障害者雇用にも限界がある。そこで新しくチャレンジを始めたのが、時代の要求に応える数々の環境、エコ、食品、健康関連機器の製造、販売業務である。これらの製品の売上げが伸びると、障害者雇用の機会が限りなく広がっていく。いつの日かこれらの製品が当社のもう一つの柱となるよう心から期待したい。
(2) まず、食品資源リサイクル機器(生ごみ処理機)は、ある病院で現在デモ機が稼動中であるが、静音(ほとんど音を出さない)、無臭で、1トンの生ゴミを13kgの肥料に変身させて関係者をびっくりさせている。これは病院、スーパー、ホテル、学校等に販路拡大が期待されており、これが現実のものとなれば障害者雇用拡大の夢が生まれてくる。生ゴミが変身した肥料の回収には、障害者ばかりでなくシルバー人材センターの高年齢者の活用も考えられ、夢は限りなく広がる。
(3) また、スーパーやコンビニエンスストアなどで排出される「包装されたままの食品廃棄物」を、風の力で瞬時に「食品資源」と「包装材」に分別する包装食品資源分別機、食中毒や院内感染対策等の味方である電解水衛生環境システムも、売上げが伸びてくれば、障害者雇用につながる可能性が出てくる。
6. 今後の課題
(1) 障害者もいずれは一人で生活するようになる。自立したものの体調不良となって退職したDさんの轍を踏まないようにしなければならない。賃金ばかりでなく、しっかり自立した生活ができるようになってほしい。幸い当社は、高年齢者の継続雇用についても大変進んでおり、全員が65歳まで継続して雇用されるようになっている。
とりあえず65歳までは、健康であれば雇用される。しかし、知的障害者の健康は、障害のない人に比べて心配があると言われている。その理由は、自宅と会社の往復だけで、外出することが少ないため運動不足となり、メタボリックシンドロームになりやすいことによる。当社の障害者は、目下のところまったく問題はないが、今後はその予防も課題となってくるであろう。また、年金や少子化の問題もあり、70歳までの雇用が現実のものとなってくる日も近い。これらの対応についても早めに行っていくことが重要と考える。
(2) 市村社長の信念
「会社は税金を納め、雇用を通じて社会貢献することが責務であるが、そのためには利益を上げなければならない。しかし、そればかりではない。世の中も会社も強い人ばかりで成立するものではない。弱者を思いやる経営者、従業員、これに応えようとする障害者がいて、会社としての団結力も生まれ、理想の会社となる。これからも理想の会社をめざして、障害者と共生していきたい。
また、障害者雇用の限界に挑戦するため、今後も当社の柱である通信機器部品製造の一層の充実はもとより、時代の要求に応えながら障害者雇用の輪を広げていく環境、エコ、食品、健康関連機器の製造、販売業務に力を入れていきたい」。

アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











