個々の特性を生かした職場配置と創意工夫による職業指導、支援機関との綿密な連携により継続就業を実現
- 事業所名
- 株式会社 コバヤシ
- 所在地
- 東京都台東区
- 事業内容
- 合成樹脂の原料及び材料の販売。食品、農業、工業用プラス製品の製造販売
- 従業員数
- 405名
- うち障害者数
- 7名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 1 原材料計量、運搬等段取り作業 肢体不自由 2 ドラム缶清掃、製造ライン 内部障害 1 原材料等運搬作業 知的障害 3 段ボール組み立て、製造工程ライン 精神障害 - 目次
1. 事業内容
(1)会社設立 昭和27年5月
| 資本金 | 8,000万円 | ||
| 所在地 | 本社 | : | 東京都台東区浅草橋3丁目26番5号 |
| 事業所 | : | 葛飾事業所・大阪・長野・仙台・弘前 | |
| 工場 | : | 葛飾・石岡・滋賀・弘前・伊那・松戸 | |
| 事業概要 | プラスチックの総合企業 | ||
| 従業員数 | 常用雇用者405名(うち 障害者7名 平成21年11月現在) | ||
(2)経営理念
株式会社コバヤシは
人間性尊重の経営を行い、社員にとって魅力ある会社になります
社会的責任を果たし、お客様に信頼される会社になります
これらを実現するために、正しい利益を追求する会社になります
(3)事業
① コバゾール事業部
おもちゃ、マネキン、フィギュア、食品サンプル、文具、自動車部品、家電部品、建材部品などに用いられる「コバゾール」という液体のプラスチック素材の製造。
② 容器事業部
主な商品は、納豆・豆腐容器、インスタント食品の容器(カップ麺の丼など)冷菓・ヨーグルト・プリンの容器などの製造。
③ 農業資材事業部
主に果実や野菜運搬用の包装資材と生産資材、菓子、パン、惣菜の袋の製造。「地球にやさしい」をテーマに、生分解性プラスチックの採用、リサイクル事業。CO2削減を目的とした新製品の開発。
④ 産業機材事業部
汎用素材から高機能性素材まで、さまざまなプラスチックシート・フィルム・ペレットを扱っている。また、シート・フィルムのマイクロスリッティングを行っている。
⑤ 技術研究所・新規開発事業部
技術研究所は既存事業の枠に収まらない領域に対応し、新しいオリジナル商品を研究・開発するR&D部門。新規開発事業部は技術研究所が開発した新製品のための市場を開拓し、販売を行う部門。
2. 障害者雇用の取り組み
(1)経営理念と障害者雇用
当社の経営理念は、「人間性尊重」「社会的責任」というキーワードがある。会社は障害のない社員、障害のある社員、そして様々な特質をもった人々の集団であることが当たり前(ノーマライゼーション)と考え、障害者の雇用と定着活動を行っている。
(2)障害者雇用の経緯
① 障害者雇用のきっかけ
障害者雇用が進んでいなかったため、ハローワークから参加を呼びかけられていた「新規大学等卒業予定障害者就職面接会(平成18年4月)」に参加し、数名の学生と面接を行った。この時には、応募はなかったが、このことを契機に障害者雇用への意識が高まった。
② 雇用に向けた取り組み
*障害者雇用支援セミナーへの参加、特例子会社見学など
東京労働局・ハローワーク(公共職業安定所)主催の「障害者雇用支援セミナー」に参加、その後もこのようなセミナーに数多く参加し「障害のある方の働く場を創ること」に本格的に取組むこととなった。
事務作業での雇用を想定したが、調整が困難となった折、セミナー講師である特例子会社の方から「障害者雇用は企業、出身学校、就労支援機関等、家庭との連携が重要である、ただし企業は、障害者就労では軸とならなければならない。だからといって担当者がひとりで悩まないこと」という貴重なアドバイスを得た。
このことを機に、障害者就業・生活支援センター、特例子会社などに相談・見学を行い、社外とのネットワークを構築した。
*雇用の決断~人事担当者と工場トップ(受け入れ側)との連携~
障害者就労・生活支援センター等への相談を行っていた同時期にある工場から受け入れを考えているという連絡を受け、事業部長から「社会の役に立とうよ」その一言で雇用に向けた「GOサイン」が出た。
*作業の切り出し
作業の切り出しは、支援機関、工場長、担当者で「量があり、納期的に余裕のある業務」を主眼に、「製品梱包用段ボールの組立て・印字作業」の二つの作業の切り出しを行った。
*受け入れ職場への事前説明
受け入れ予定の職場の雰囲気・男女構成・年齢構成などを把握し、時には配属予定者の障害特性、配慮事項、CSRなどついて、各部門の方針に沿った形で支援機関の協力を得て事前説明会を行った。

朝礼(業務報告等)
③ 適正実施勧告と経営トップの決断
平成19年12月、最初の障害者を採用した同月、雇入れ計画2年目の終わる時期、計画通りに雇用が進んでいないということでハローワークから「障害者雇い入れ計画適正実施勧告」を受けた。経営トップから「法定雇用率必達」の社内指示があり、急速に雇用が進み、3年計画最終年に法定雇用率を達成した。現在の実雇用率は2.24%である。
(3)障害者雇用の推移
平成18年以前:1名 平成19年:1名 平成20年:4名 平成21年:1名
(4)障害者の受け入れ態勢
① 作業指導の工夫
障害種別により作業部署を選定し、作業の状況(習熟度や安全性)を見極めながら次のステップへ進むようにしており、特に障害者だからという特別な方法は講じていない。しかし、必要に応じて就労支援機関から作業指導の支援をお願いしている。
② 職域開拓
障害者雇用を初めて取り組んだ時と同様に「手の空いた時に誰かが、必ずやらなければならない、熟練を要さない作業」を採用担当、現場担当、支援機関等で工夫している。将来は、事務部門での職域について検討していく。
③ 教育訓練
基本的にOJT(特徴として「リハビリ」的な要素を盛り込んでいる)により行い、手順が定着するまで反復指導している。

作業打合わせ
*製造課の課長と主任の指導法の一例
「遅刻してもいい」:「遅刻するときは、会社に連絡しましょう」の意
「手がかかってもいい」:「自分のことは、自分でできるようにしましょう」の意
「すぐに仕事を覚えられなくてもいい」:「ゆっくりだけど着実に仕事を覚えましょう」の意
作業の自立を促すために“なんでもやってあげるのではなく、できるためのきっかけ作りをする”“なぜできないではなく、どうしたら出来るか・わかりやすいか”という視点での指導をしている。
④ 障害のない社員への啓発
実習の受け入れ時、採用時に障害程度・接し方等の説明を支援機関の協力を得て該当職場に対し行っている。
(5)支援について(定着支援)
① 社内支援
問題発生時(配慮や要望)の迅速な対応を支援機関の協力を得て行っている。
*事例:Aさんは、身体障害者で、記憶・注意に課題があるが、液体のプラスチックのドラム缶内壁の清掃を1日約30本処理している。
・出退勤時:
入社当時は支援機関に立ち寄ってから出勤(第3者による出勤確認)
支援機関から会社までの地図(曲がり角には、電柱・店の看板などをデジカメで撮影し、地図上に張り付)を行きと帰りの風景の見え方が異なるために往復分作成。
・工場内移動時:
工場内は入り組んでいて迷いやすいので、入社当時は、同僚がトイレに行きだけ付添、しかし戻れないことがあり、場内のAさんの持ち場とトイレのある方向を矢印で表示。


作業風景

工場内行き先表示

工場内行き先表示(拡大)
・家族、支援機関との交換日記
Aさん専用の連絡帳を活用し、職場での本人の就労状況、支援機関への課題相談、家族からは生活状況・心配事、職場からの回答などを記入し情報を共有している。又、本人がリハビリの意味で毎日の昼食メニュー、服薬について記入している。

交換日誌
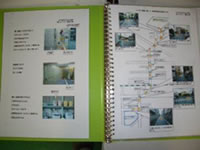
作業指示書と出勤・帰宅時の地図
② 障害者就業・生活支援センター
入社した障害のある従業員のほとんどが、障害者就業・生活支援センターに登録し、その支援を受けている。
支援の内容は、下記の通り
・雇用前の作業の切り出し、実習支援、雇用後の定着支援
・作業指導、作業評価などジョブコーチとしての支援
・家族との連絡調整、金銭管理、身だしなみなどの生活支援
(6)障害者雇用のノウハウ
地域就労・生活支援センター等からの支援の実績と雇用している職場の個々障害者の特性・適正に合わせた指導法と環境作りの経験がノウハウとして日常業務に活かされている。
(7)助成金の活用
障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置助成金、特定求職者雇用開発助金)を活用している。
(8)実習・採用について
採用に向けた実習は、本人の特性と当社の業務への適正、働く意欲の確認のために必ず行っている。
これまでの採用基準は、「何々できる人、何々を満たしている人」ではなく、面接・実習を通じ当社で働く強い意思と意欲のある人で、しかも当社が、「この人ならやっていける」と判断し、可能性を信じて行っている。
3. 障害者雇用についての今後の課題
(1)全ての事業所及び工場に障害者の配属を検討する。
人事が中心となり、既に雇用している職場の管理職・一般職の職員の協力を得て、管理職クラスを始めとして職場全体への啓発活動を行う。
(2)精神障害者の雇用を検討する。
人事担当者が先ずセミナーへの参加や既に雇用している企業の好事例を学び(出来れば見学を含め)、経営トップへのアプローチと社内全体に啓発活動を行い、徐々に受け入れ体制作りを行うこととしている。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











