医療業での雇用の取り組み
~支援により成就感や自己有用感を達成できる職場~
- 事業所名
- 社会福祉法人恩賜財団済生会 山口県済生会山口総合病院
- 所在地
- 山口県山口市
- 事業内容
- 医療業(総合病院)
- 従業員数
- 513名
- うち障害者数
- 3名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 2 内部障害 知的障害 1 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)概要
済生会は国内41都道府県に支部を持ち、病院、介護老人保健施設、訪問看護ステーション等を中心に、計377施設を有する社会福祉法人である(平成22年1月現在)。
その病院の一つである山口県済生会山口総合病院は、山口市のほぼ中心部に位置する病床数310床の病院である。
(2)障害者雇用の経緯
・得意な分野を任せる
当院で障害者雇用とその支援にあたっている事務局人材開発室課長補佐の遠山純氏と、同室主任の中村文子氏に話を伺った。
「当院ではこれまで、障害のある方の積極的な雇用を行っていない頃もありました。しかし現在では、公共職業安定所(ハローワーク)などと連携し、トライアル雇用や実習の受け入れを行っています。そして、就労可能な職域を、院内に探しつつあるところです」
現在、山口県済生会山口総合病院では、3名の障害者が院内での業務に日々取り組んでいる。身体障害者2名、知的障害者1名である。
「障害のある職員には、比較的得意な分野を任せるようにしています。そして、お互いのコミュニケーションを保つよう心掛けています」

2. 職場での支援の実際
3名のうち、2名(Aさん、Bさん)を以下紹介しよう。
(1)Aさん(下肢障害;身体障害者手帳1級)
Aさんは、小学生の時の交通事故によって脊椎に損傷を負い、下肢機能に障害が残った。現在、車いすを使用している。山口県内の肢体不自由養護学校(現;特別支援学校)の高等部を卒業後、県内の印刷会社に就職した。その後、公共職業安定所の紹介により、平成19年から済生会山口総合病院に就職した。契約職員として、1年更新をこれまで継続してきている。
①Aさんが取り組む仕事と職場からの支援
Aさんのデスクは、院内2階の人材開発室にある。仕事内容としては、パソコンを使用しての院内・院外広報誌や求人広告のデザイン作成、職員の個人データや履歴の管理(入力や更新)、院内で使用する印刷物の校正・管理、ネームプレートや名刺の製作等がある。車いすに座った状態でパソコンを操作できるよう、デスクは適切な高さに調整され、Aさんはここでかつての印刷会社で習得した知識・技術を十二分に発揮している。当院はAさんが使い易いパソコンソフトを購入し、さらに印刷機やコピー機などは、なるべくAさんに近いところに設置し、職場内でのストレス軽減に配慮した。なお、人材開発室の床には一本の配線も走っておらず、フラットである。それゆえ、車いすでの移動に支障はない。

従業員の基礎データを入力しているAさん

Aさんが製作した院内・院外広報誌

Aさんが製作したネームプレートと名刺
また、病院全体がバリアフリーの造りになっているため、Aさんの就労に際し、例えばトイレやドアについての改修等は必要とされなかった。
②楽しいコミュニケーションつくりへの配慮
職場の忘年会や各種レクリエーションにAさんが楽しく参加できるよう、車いす利用者への配慮がなされている飲食店等を選ぶことを幹事は心掛けている。山口市内にも、身体障害者用トイレを設置するバリアフリー構造のホテルや料理店等が徐々に増えてきており、Aさんにとって楽しいコミュニケーションつくりの場ともなっている。
③駐車場の配慮
Aさんは山口市内にある自宅から自家用車で通勤している。病院裏に患者専用の外来駐車場があり、ここを使用できる配慮がAさんになされている。

Aさんが無料で使用できる外来駐車場(病院裏)
(2)Bさん(知的障害;療育手帳「B」・障害者職業センターの重度知的障害者判定「重度」の判定有)
Bさんは、山口県内の知的障害養護学校(現;特別支援学校)の高等部を卒業後、県内の農園に就職した。その後、公共職業安定所の紹介により、済生会山口総合病院にてトライアル雇用の制度で就労体験をした。またジョブコーチの制度も利用した。そして平成19年より当院にパート職員として就労し、1年更新をこれまで継続してきている。
①Bさんが取り組む仕事と職場からの支援
Bさんのデスクも、Aさんと同じく院内2階の人材開発室にある。仕事内容としては、(a)印刷の請負(印刷から製本、出来上がりの連絡まで)、(b)各種資料の準備、(c)郵便物の重さ厚さの確認・切手貼り・投函、(d)注射液の運搬等がある。
(a)印刷の請負
例えば、医師や看護師が集う院内勉強会で使用する資料等を、Bさんが準備する。Bさんは、手渡された資料をコピー機等で人数分複写し、綴じるという一連の作業に取り組む。この作業で用いるのは「印刷依頼書」である。この依頼書には印刷の種類(白黒・カラー)、印刷の方法(片面・両面)、パンチの種類(穴なし・二つ穴・四つ穴)、ホッチキスを打つ位置、製本・印刷部数等に関する指示内容が簡潔に記されている。また、この依頼書の文面に使用されている単語については、わかりやすい説明が添えられている(例;依頼部署(お願いしたところ)、担当者(出来あがったら連絡する人)等)。Bさんはこの依頼書を受け取り、まず声に出して読む。このようにすることで、支援者はBさんが正しく理解しているかどうかを把握でき、必要に応じて説明することも可能となる。Bさんは、今ではこの一連の作業を確実にこなせるようになった。

印刷依頼書
(b)各種資料の準備
パンフレット等の中に、新たな資料を差し込む作業もBさんの仕事である。Bさんは支援者が用意した「見本」を見ながら、各種資料を決められた順番に組み合わせ、それをパンフレットの中に差し込んでいく。Bさんにとって、見本が用意されることの効果は大きい。特に、初めて体験する作業の場合は、支援者は事前に必ず見本や手本をBさんに示し、Bさんが理解したことを確認した後に作業を開始させるようにしている。また、一つの作業を終了する度に休憩を入れることで(約2時間に1回)、心身両面の疲労が蓄積しないよう配慮している。
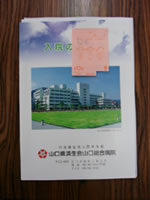
見本

見本を見ながら資料を組み合わせるBさん
(c)郵便物の重さ厚さの確認・切手貼り・投函
当院からは、毎日大量の郵便物が院外に郵送される。Bさんは、デスク上で郵便物の重量を計測した後に、その厚さが1センチを超えるか否かを確認し、必要な郵送金額を封筒左上に記入していく。ここでBさんが使用しているのは、当院自作の「計測器」(木製)である。中央部分に幅1センチの切れ目が入っている。郵便物がこの切れ目を通過するか否かで、1センチを超えるか否かを判別できる。作業道具の工夫と活用が、Bさんの作業活動を円滑にしているといえよう。一連の作業が終了した後、Bさんは郵送金額に応じた切手を選び、貼り付けていく。そして、病院玄関横にある大型ポストに全ての郵便物を投函するまでが、Bさんの仕事である。

当院自作の計測器

計測器を使って郵便物の厚さを確認するBさん
(d)注射液の運搬
院内の製剤室で製造された注射液を外来処置室に運搬するのもBさんの仕事である。製造された注射液はケースに詰められ、戸棚に置かれる。そしてケースの上には決められた番号カードが1枚置かれることになっている。その番号を確認したBさんは、そのケースを戸棚から取り出し、バッグに入れ、外来処置室に運搬する。このバッグは、Bさんのために支援者がホームセンターで購入したものである。
さて、このバッグを肩に掛けたBさんは、院内の廊下を外来処置室まで早足に歩いていく。その途中には、右折あるいは左折の曲がり角があるが、Bさんはその手前で一旦足を止め、左右から歩いて来る人(例;患者や職員)の有無を確認し、接触しないよう注意する習慣が身に付いている。これも、支援者からの指導によって習得した習慣である。最初の頃は、足を止めるべき位置に支援者が色テープを貼り、ここで足を止めて人の有無を確認するという練習が繰り返された。

注射液を取り出し、これから外来処置室に向かうBさん
なお、院内を移動する途上で、Bさんが患者や来院者から質問等を受けることも予測される。こうした時、コミュニケーション上のトラブルが発生しないよう、Bさんはネームプレート裏面の文面を相手に示すことにしている。ここには「私にはわかりませんので、総合案内にお聞き下さい」という意味の文章が記してある。
②全体を通しての支援
安定した就労生活のためには、周囲がBさんの体調不良などを素早く察知する必要がある。それゆえ、Bさんの顔色や仕草などにいつもと違う変化がないか、周囲の職員が気を配っている。以前、Bさんの支援に入ったジョブコーチが、Bさんの性格や特徴、対処法を伝達してくれたことがあった。例えば、Bさんは周囲からの質問や指示内容がうまく理解できない時には緊張し、頭をしきりに掻き始めたり、周囲からの語りかけの言葉をそのまま繰り返したりすることがある。対処法として今も取り入れているのが、Bさんに対してその質問等を繰り返さぬこと、深呼吸をアドバイスすること等である。
また、職場で心配事が生じた時には、連絡帳を使用して家庭へ報告し、アドバイスをもらえるようにしている。家庭からも、急な連絡を職場に届けることもできるため、この連絡帳は職場と家庭をつなぐ架け橋となっている。

職場と家庭をつなぐ連絡帳
3. 今後の障害者雇用の方針
これまでは、公共職業安定所から障害者を紹介された後、「その障害の種別や実態(等級等)に適合した業務内容を院内に探す」という順で検討を進めるきらいがあったと人材開発室課長補佐の遠山純氏は語る。
「しかしこれからは、院内で必要とされる業務内容をまず広く見出し、その後に公共職業安定所に障害者の紹介を依頼する、という積極的な方針に移したいと考えています」
この積極的な方針は、医師、看護師等を含めた院内全局への理解啓発が鍵となる。同時にこの理解啓発は、障害者雇用という社会的責任を前向きに果たそうとする意識を院内に育てることを意味する。
4. 成就感、自己有用感の体得
細やかな支援のもとで、当院に就労している障害者は今日もその持てる力を発揮し、職場の“戦力”となっている。自分自身の働きが、周囲の人(医師、看護師等を含めた職員)から認められ、感謝されたという体験を通すことで、人は成就感や自己有用感を体得することができる。そして、これからも自分自身の責任と役割を職場で前向きに果たしていこうとする姿勢につながっていくと思われる。
障害の有無にかかわらず、人は皆、その持てる力をこの社会で発揮し、社会参加したいと願っている。山口県済生会山口総合病院は、障害者の「働きたい」という熱い願いを叶えることを通し、地域の中核病院としての社会的責任を果たしていく経営を今日も続けている。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











