地域に根ざした障害者雇用に向けて
- 事業所名
- 株式会社西
- 所在地
- 徳島県海部郡海陽町
- 事業内容
- 自動車機器(ワイヤーハーネス)の製造
- 従業員数
- 56名
- うち障害者数
- 3名
障害 人数 従事業務 視覚障害 0 聴覚障害 0 肢体不自由 0 内部障害 0 知的障害 3 ハーネス組み立て 精神障害 0 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
株式会社西は徳島県南部、高知県との県境に近い徳島県海部郡にあり、平成8年創業、平成18年に現在の株式会社西となる。
社員数は56名、比率的に非常に女性の多い職場である。
創業以来、国内大手自動車メーカーにクルマの神経・血管にあたるワイヤーハーネス(自動車用組電線)を供給している。

(2)障害者雇用の経緯
最初の障害者雇用は、高知県内の私立養護学校より知的障害のある生徒の夏季・職場実習を依頼され、その受け入れから始まった。そして実習生の卒業に合わせて雇用について検討、家族が同社に従事していたこともあり雇用することになる。作業配置については本人が重度障害であり、他の従業員と同じラインでは到底無理と判断し、周りに負担をかけない程度の簡単な作業に従事することとし、会社としてはその成果を期待することはなかった。
はじめての障害者雇用で本人の障害特性もよくわからず、支援機関もないという状況であったが、家族である従業員が指導を担当するということで最初の障害者雇用にトライした。
その後、障害者の就労を支援する機関(ハローワーク(公共職業安定所)、障害者職業センター、就業・生活支援センター)や養護学校との関係が深まり、障害者の雇用支援制度(ジョブコーチ支援等)を利用して、二人目以降の障害者雇用へとつながっていった。
2. 障害者の従事業務、職場配置
現在働いている障害者は3名で、障害のない人に混じってワイヤーハーネスの組み立てを行っている。その内の2名はパーツの供給、もう1名はハーネスの組み立てを行っている、彼らの作業内容においては障害のない人と何ら変わるところはない。
労働条件においても契約期間、配置場所、勤務時間は全く同じであり、賃金についても同じ評価方法をとっている。
業務内容と配置については工場長、主任担当者との話し合いにより決めている。支援者のアドバイスを参考に本人の障害特性を考慮して、彼らの持つ特性を生かせるように適性配置に心掛けている。この配置方法は作業効率という点においても、非常に有効な方法であると考えられる。
過去の障害者雇用において配置を考える際、まず社長自身の業務内容の見直しを行った。仕分けしてみると障害がある人たちに任せることのできる作業が多いことが分かった。その中からいくつかの作業を抽出しそれらをひとつの作業配置として確保することができた。更にこのことにより経営者として本来の業務を効率的に行えるようになったとのことである。どこの職場においても障害者が従事できる仕事はあるという社長の考えからできた配置である。

迅速かつ確実な作業が要求される

ラインに供給するパーツの作成

きちんと分類され、保管位置もすべて指定されている。
これは障害者のための工夫ではないが、マニュアル化された品質管理方式は障害者にとっても理解しやすい。
3. 取り組みの内容及び効果
① 障害特性の把握
これまで係わってきた支援者や家族から障害のある従業員の得意・不得意、こだわり、課題等を聞き取り、状況に合わせながら支援を進めた。
最初は社長・工場長・主任担当者だけしか本人の特性を知らないまま支援を進めたが、途中から特別支援学校が作成した【サポートブック】を家族から借り、職場内で全ての従業員に休憩時間や昼休み等を利用して目を通してもらうことで、それまで関心のなかった従業員も気にかけるようになり、障害に対する理解が社内で徐々に深まっていった。
② 職場でのキーマン(主任担当者)の配置
従業員の中から専任の指導者を配置し、本人の状況を見ながら意志疎通を図り、作業内容の伝達等、安全且つ効率よく作業遂行できるよう指導する役割を持ってもらう。
キーマンについては仕事に対して大変責任感が強く、自分の役割に強い使命感と熱意を持った人物である。それ故に、障害のある人に対する指導は、周囲から見ると、「厳し過ぎるのでは?」と思われることもあった。
しかし、会社が扱っている製品が車を動かす上で重要な部位であること、それ故に中途半端な製品を作り出すことは会社の存続に繋がることになる。そこで、障害の有無に係わらず従業員として自分の仕事には責任を持ってもらいたい、という思いから指導についても特別扱いはしないというのがキーマンの信念である。
社長としても、そういうキーマンを信頼し指導を託しているので、ミスをした際に注意をしている場面を見ても、制止したりかばったりは一切しないそうである。そうしないと、注意を受けた本人は誰の指示を聞けばよいのか迷ってしまうからである。
そして、社長は場所を移して休憩時等に本人の気持ちを聞いてあげたり励ましたりしてフオローしているそうである。注意を受けた本人は、その時は泣いたりして落ち込むこともあるが、翌日迄引きずることなく仕事を休むこともないそうである。これは、キーマンとの信頼関係が自ずと築かれている所以であろう。共に働く従業員も彼らの頑張りが刺激となり、職場全体の活性化が図られるようになっている。
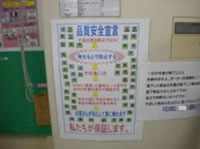
③ 関係機関との連携及び各種制度の活用
障害者雇用の経緯のところでも述べたが、最初の障害者雇用について保護者が従業員として働いていたこともあり、全て作業の段取りや指導については保護者に任せていた。しかし結局離職に至ってしまった。
二人目以降の受け入れについては、ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターとの連携を図り、常に職場と各機関が共通認識を持ち一緒に進めていった。目的は一つであり、それぞれの専門性を生かしながら、同じ方向を向いて支援に当たることが出来たのは、大変有効であった。
職場だけでなく、主体となる障害者本人が様々な支援を受けることで安心して取り組むことができたのである。
ジョブコーチ支援制度、職場適応訓練、トライアル雇用・・・と各制度を有効に活用することで職場の余分な負担を軽減し、且つ困難な問題も協力しながら推し進めることができ、それが雇用に繋がったといえる。

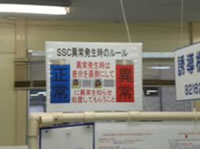
4. 今後の課題、まとめ
(1)今後の課題
障害の特性といえども個々により違いがあり、それを少しでも早い段階で一人ひとりの強みや課題を把握しスキルアップを図る必要がある。そのためにも、会社としては職場の中に訓練用のスペースを確保するのが課題である。そこで障害のある従業員のグループを作り彼らのステップを調整したり、個々の障害特性に応じて作業がしやすいようにプロセスや方法を工夫したりするなどしてから、ライン等に配置すると更に効率アップに繋がるだろうと考えている。
(2)まとめ
「企業就労」は、一人ひとりの障害のある人を成長させ、経済的な安定をもたらせると考える。今後、更に障害者雇用に向け新しい職場を開拓していく中で、一つでも多くの企業が意識を変え、“株式会社 西”のように障害のある人たちと一緒に働く土俵をどう整えていくのかに向き合ってもらえることを切に願う。
そのためにも、我々の役割はどうあるべきか。会社に求めるだけでなく彼らが真に仕事に向き合えるよう、支援者として彼らの「働きたい」という気持ちを大切にし、側に寄り添いながら歩みを進めて行きたいと考えている。
就労支援ワーカー 多富 英昭
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











