ハンディは認めるが特別扱いせず、過不足なく配慮することで、就業による自立生活を実現する事例
- 事業所名
- 医療法人笹本会
- 所在地
- 山梨県甲府市
- 事業内容
- 整形外科診療所及び高齢者居宅サービス事業に加え、甲府市から地域包括支援センター事業を受託
- 従業員数
- 95名
- うち障害者数
- 3名
障害 人数 従事業務 視覚障害 2 マッサージ(リハビリ業務) 聴覚障害 肢体不自由 1 介護サービス(介護福祉士業務) 内部障害 知的障害 精神障害 - 目次


1. 事業所概要
(1)事業内容
生涯にわたって、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは、誰しもの願いであり、医療や介護保険は、看護や介護が必要となっても、自分の持てる力を活用して生活することを支援することであると考えている。
医療法人笹本会は、地域の皆様に必要な医療や介護を提供するとともに、住み慣れた家庭や地域で安心して暮らしていけるよう支援している。
現在、次のとおり甲府市南部に整形外科、通所リハビリセンター、デイサービスセンター、グループホームなど、高齢化社会を支える諸施設を運営している。
それらは、この地域の医療・介護支援の核となる存在として、地域住民が安心して暮らせる街づくりに貢献している。
① 笹本整形外科
整形外科疾患を中心とした診療およびリハビリテーションを行うとともに、介護・介護予防事業所との連携を図り、地域医療の提供とその発展に貢献することを目的としている。
事業内容は、整形外科一般の診療、特に骨折、リウマチ性疾患の治療、救急患者様の診療、居宅療養管理指導の実施(緊急時の往診も対応)、訪問看護、骨密度検査等である。
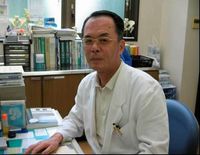
② おおくに在宅ケアセンター(高齢者居宅サービスの拠点)
介護保険法などの関連法令に基づく中で、利用者の立場に立ち自宅での生活を継続していくことを基本に、その人にとって最良の介護支援サービスを提供していくことを目的としている。
事業内容は、居宅サービス計画の策定、訪問サービス・デイサービス等を通じての看護・医療上の処置や精神的ケア、食事・排泄・入浴介護や洗濯・掃除等の生活上の支援、身体機能維持のための機能訓練等である。

③ グループホームおおくにの家
認知症の方が家庭的雰囲気の中で、入居者の皆様が協力し合いながら可能な限り自立した生活を送ることを目的としている。
事業内容は、認知症対応型共同生活介護であり、2ユニット18名の入居者が共同生活を営んでいる。


④ おおくにいきいきプラザ(介護予防事業の拠点)
在宅にお住まいの要支援高齢者(要支援1または要支援2の要介護認定を受けた人)を対象に、介護予防、自立支援のためのデイサービスを提供すること、及び、在宅にお住まいの高齢者のうち、要支援・要介護状態になるおそれや不安のある人(特定高齢者)を対象に、介護予防、健康増進のためのデイサービスを提供することを目的としている。
事業内容は、運動器機能向上(理学療法士、介護予防運動指導員が担当)、口腔機能向上(歯科衛生士が担当)、栄養改善(管理栄養士、保健師が担当)等である。


④ 甲府市南西地域包括支援センター
甲府市の委託を受け、国母・大国・大里地区にお住まいの高齢者のみなさまに安心して地域で暮らしていただけるよう支援することを目的としている。
事業内容は、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師による高齢者及びその家族の皆様への支援である。3職種はそれぞれ専門分野を持っているが、専門分野の仕事だけを行うのではなく、お互いに連携をとりながら総合的に高齢者の皆さんを支えており、主な内容は以下のとおりである。
・特定高齢者や要支援1、2の方の介護予防ケアプランの作成
・地域の高齢者の総合相談の窓口
・権利擁護、高齢者虐待防止への取り組み
・ケアマネジャーの支援
・地域の特定高齢者(虚弱高齢者)の把握
・認知症に関する普及啓発活動
・地域住民、地区組織、様々な職種や機関と連携するためのネットワークづくり
・地域保健に関して、どこに相談して良いのか分からない心配事や悩み事の相談窓口
(2)経営方針
経営方針は次のとおり(原文のまま)である。
「経営理念」
・私たちは、地域の皆様が安心して医療を受けられるよう、医療に携わる者としての誇りをもって努めます。
・私たちは、高齢者の皆様が住みなれた環境の中で安心して暮らせるよう、介護に携わる者としての心をもって努めます。
「基本方針」
・たゆまぬ医療技術の改善、向上を積極的に図り地域の皆様に提供して参ります。
・生活圏域の中で、医療サービスと、通って、泊まって、住めるという介護サービスを一体的、総合的に提供できる拠点を設置して参ります。
・いつの時でも、地域の皆様をよく知り、理解し、意欲を引き出し、自律を促し、潜在的な力を発揮できるように支援して参ります。
(3)組織構成
組織は大きく分けて、次の部門から成り立っている。
◇笹本整形外科(放射線科、看護科、リハビリ科、医療事務科)
◇介護・介護予防事業部
おおくに在宅ケアセンター(居宅介護支援、訪問看護、訪問介護、デイサービス)
グループホームおおくにの家
おおくにいきいきプラザ(介護予防、訪問リハ、デイサービス、居宅介護支援)
◇地域支援科(甲府市から甲府市南西地域包括支援センターを受託)
◇事務部

(4)障害者雇用の理念
医療法人笹本会は、理事長である医師笹本憲男氏が、北里大学や北里研究所メディカルセンター病院等で身に付けた知識と技術を故郷の方々に還元したいという熱い気持ちを抱いて整形外科診療所を開設したのが出発点である。その後、高齢社会では医療に連動するものとして介護・介護予防が不可欠との思いから介護事業所を開設し、いつか地域の方に「ここがあるから安心して住める」と言っていただけるような存在を目指してきたのである。
障害者雇用も理事長の思いである、「生涯にわたって、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰しもの願いであり、医療や介護保険は、看護や介護が必要となっても、自分の持てる力を活用して生活することを支援することである」という自立支援の精神の延長線上に位置づけられるものである。多職種との連携の中で、障害者も能力を発揮することが可能であり、特に機能訓練の分野は、活躍の場として考えられる。
当法人が、地域の皆様に必要な医療や介護を提供し、高齢者や要看護者、要介護者、障害者等を含めたすべての人が、住み慣れた家庭や地域で安心して暮らしていけるよう支援するなかに、自然と障害者雇用も含まれることとなり、これこそまさしくノーマライゼーションの実現に他ならないと考えられる。
障害者雇用の取り組みのきっかけは、理事長が山梨障害者職業センターの相談員を委嘱されていたことであり、相談員としての役割を通じて障害者雇用に取り組むこととなった。
実際に求人をする場合には、ハローワークと同時に山梨県立盲学校へも連絡しており、盲学校経由での採用もある。
2. 取り組みの具体的な内容
(1)労働条件
労働条件は障害のない職員と全く同じである。また、平成7年の診療所開設当初から短時間正社員制度を導入し、障害者も活用している。特に賃金については、所定労働時間に応じて按分される仕組みであり、過不足なく支給されている。
① 期間
職員全員が期間の定めのない契約を締結しており、定年制が適用になる。
② 場所
笹本整形外科のリハビリ科内、おおくに在宅ケアセンター内である。
③ 時間
原則として障害のない他の職員と同じであり、短時間ではなくフルタイムである。なお、短時間正社員制度を活用することも可能であり、その場合は短時間勤務となる。
④ 賃金
障害のある、ないの違いは全くなく、賞与や退職金も支給されている。
(2)仕事の内容
視覚障害者は整形外科のリハビリ科で、マッサージ及び運動機器を用い主に機能回復を担当している。
肢体不自由者はユニットケア(※注1)を採り入れたデイサービス事業所で、食事やトイレ支援など介護業務に係わっている。職員がチームとして編成され、その一員として仕事に従事する中で、利用者の安全確保のため、入浴支援や送迎等の本人が担当できない部分は、チーム全体でカバーしている。


※注1 ユニットケア
ユニットケアは、在宅での生活の質が確保されるよう利用者の心身の特性を踏まえ、具体的な日常生活動作の維持・回復を図り自立支援につなげるため導入しているものである。
そのため、①サービス利用にあたり、利用者自身が主体的に参加できるよう目的を引き出す。②心身の機能別に小グループでの活動支援を行う。③利用中に喜び、悲しみ、苦しみが表出でき、心の安定が図れるよう支援する。④自立支援を重視して心身の残存能力を強化するため、デイサービス利用中の全ての場面(入浴、排泄、食事、移動など)をリハビリテーションとして利用者自身で行えるよう支援する。⑤常に職員が家族の役割を担うことにより、効果として①上下肢筋力増強による要介護度の改善。②ユニットごとの会話を増やし利用者の表情を豊かにする。③友達づくりによる楽しみの増加。④様々な体験の中から思考能力が活発となり心豊かに活動的になることを目的とするものである。


(3)助成金の活用
助成金等については、活用実績はない。
(4)労務管理の工夫
当法人では、法人全体としてワークライフバランスの実現に取り組んでおり、障害のある職員も含めての取り組みであることは言うまでもない。具体的には次のとおりである。
「ワークライフバランス宣言 — 平成19年11月21日 —(原文のまま)」
職員が仕事上の責任を果たしつつ、結婚や育児をはじめとする家族形成のほか、介護やキャリア形成、地域活動への参加等、仕事と生活がバランスのとれた働き方を安心、納得して生活していけるようにすることがワークライフバランスと考えられている。
ワークライフバランスは、個人にとっては、仕事と家庭の両立、自己啓発や地域活動への参加、健康維持・確保につながり、法人にとっては、多様で優秀な人材の確保や職員の満足度、仕事への意欲の向上に表われ、社会全体にとっては、生産性経済活力の向上、少子化への対応などが効用として指摘されている。
我が法人においては、育児・介護休暇制度やボランティア活動規約、職員提案規程などを整備して職員の自己実現のサポートをしており、もっとも基本的な就業規則でも年次有給休暇や福利厚生、安全衛生などの条項を定め、職員の労働条件の維持向上や人格の尊重をうたっているが、なかなか活かされていないというのが現状である。
この度、21世紀職業財団の職場風土改革推進事業実施事業主としての指定を受けた。
医療法人笹本会は、育児・介護に関する両立支援の更なる充実ひいては、ワークライフバランス宣言の実行のため、職場風土改革に取り組んでまいります。
この取組みによって、仕事の進め方や働き方の見直しを進め、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、仕事と個人生活のバランスをとり、ゆとりある生活を営み、働きがいを高め、働きやすい、風通しのよさが職員に活力を与え、能力を高めていく職場風土を築いて行くものと考えております。
具体的には、
・勤務時間の柔軟性(勤務時間選択制・短時間勤務制度等)
・ゆとりの確保(ノー残業デイの設定、仕事の分担や意志決定権限の見直し、業務体制や会議の効率化)
・休業中や復職への対応(職務分担、勤務体制の見直し、アルバイト等の代替確保、休業者とのコミュニケーション)
・職員のキャリア設計支援(管理者の職員面接による意見・要望の把握、各種制度の周知、経験者からのアドバイス)
といった観点から、ワークライフバランス施策を積極的に推進することによって、仕事と家庭の両立や、法人職員ということだけでなく、地域や社会の一員という意識を持った職員になります。
一.具体的な取り組み
障害のない職員と区別しないのが原則であり、ハンディは認めるが、チーム全体でカバーして働いてもらっている。具体的には、次のような点に心がけている。
・管理者に障害の状態を詳しく伝え、安全が確保できるようにしている。
・メモをとる。
・足がもつれないように注意する。
・本人が焦らないように、よく声をかけ、気持ちを和らげる。
・声をかけたときに体調を把握する。
・ユニットメンバーだけではなく、職場全体で見守るようにしている。
・同時に複数の指示は出さない。
仕組みとしての取り組みは、次のようなものがある


・入社一年未満の頃は安全第一という観点から、毎日の打ち合わせを活用して、いろいろな課題にすぐに対応できるように日々改善を行う。
・新規採用者を対象としてプリセプター(指導者)を配置する。成長して中堅になると、本人が新規採用者のプリセプターとなる。なお、指導される側をプリセプティと呼ぶ。
また、二年前からは法人全体で毎年MVP賞を選び表彰し、職場の活性化を図っている。これは、業務以外の活躍を対象としたもので、職員間の推薦により決定する。過去には、盲人野球の功績を認められ、障害者が受賞したこともある


なお、当法人は、デンマークの在宅ケア制度を開発され、各国へ発信されたレーナ・ホレンナー先生(コペンハーゲンケアアカデミー教授)を平成17年よりお招きし、実地指導をいただいており、そのことも障害者雇用に有形無形のプラスの影響を与えている。
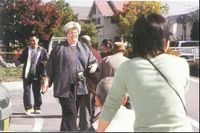
二.上司としての接し方
上司として、業務上の技術的な部分だけではなく、理念も含めて指導することが大切である。それは障害者に限ったことではなく、よく話をすることが基本となる。
3. 取り組みの効果
障害のある職員がチームに加入することにより、相手に対する配慮が生まれ、それは高齢者等に対する配慮に通ずるものである。
即ち、利用者・職員皆一律ではなく、個人として尊重する気持ちが生まれ、尊厳を大切にすることが自然とできるようになるなど、非常に大きな効果が認められる。
実際に、障害のある職員が朝一番に出社して解錠や洗濯物の整理など、率先していろいろな準備を行っているため、皆の仕事に対する意識も高まらざるを得ず、相乗効果を上げている。また、毎日の朝の体操の時に、「今日は何々があった日」と自発的に調べてきて発表するなど、職場の雰囲気を明るくして、大いに盛り上げてくれている。

4. 今後の課題と対策・展望
(1)課題
介護現場で、今後、障害のある職員にどのような仕事や役割を担ってもらうかがポイントとなるであろう。介護の現場では人が相手であり、画一的な労務提供はあり得ないので、障害の内容や程度に応じて、配置が異なることが予想される。
(2)対策・展望
短期間での離職者があると、新規採用に躊躇することも感覚的にはあるが、今後も、障害者雇用を前向きに捉え、取り組みたいと考えている。
(3)総括
最後に、今後障害者雇用に取り組む企業に対してアドバイスするとすれば、次のような点が挙げられる。
① 職場が障害を理解することが重要
② ハンディがあることを認識して過不足なく配慮することが必要
③ 「なぜ、あの人だけが」というような感情が、職場の中に芽生えないような労務管理が必要
④ 特に、通勤手段の確保(確認)を考え、出勤、退勤時間の配慮が必要
以上であるが、障害者雇用の当法人における原則は、ハンディは認めるが、必要以上に配慮(特別扱い)はしないというものであり、言い換えると、過不足なく配慮することこそ肝要ということになる。
これは、先に取り上げた理事長先生の思いである、「生涯にわたって、個人として尊重され、その人らしく暮らしていくことは誰しもの願いであり、医療や介護保険は、看護や介護が必要となっても、自分の持てる力を活用して生活することを支援することである」を、まさに障害者雇用の分野で実践しているものと認められる。
トップの思いが経営理念となり、それが、地域の医療・介護支援の核となる存在として、障害者雇用も含めて、地域住民に安心して暮らせる街づくりの役に立っていることが非常によく理解できる事例である。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











