“障害者雇用から学んできた新たなコンセンサス”
そして 知的障害者雇用に取り組む際の新たな気づき

1. 事業所の概要
(1)事業内容
当社は電子部品メーカー“村田製作所グループ”の中核拠点として、「積層セラミックコンデンサ」の開発・生産を行なっている。
(2)社是
技術を練磨し
科学的管理を実践し
独自の製品を供給をして文化の発展に貢献し
信用の蓄積につとめ
会社の発展と協力者の共栄をはかり
これをよろこび感謝する人びととともに運営する
(3)沿革
| 1983年 | 8月 | 会社設立 |
| 1984年 | 2月 | 生産棟(A1棟)竣工 |
| 4月 | 操業開始 | |
| 1984年 | 6月 | 生産棟(B1棟)・生産棟(BP棟)竣工 |
| 1985年 | 5月 | 生産棟(C1棟)・エネルギーセンター棟竣工 |
| 1988年 | 8月 | 生産棟(B2棟)竣工 |
| 1992年 | 3月 | 管理・福利厚生棟(F棟)竣工 |
| 1993年 | 8月 | ISO9002(品質システム)認定取得 |
| 1995年 | 5月 | ISO9001(品質マネジメントシステム)認定取得 |
| 11月 | TPM優秀賞第1類受賞 | |
| 1996年 | 6月 | 生産棟(A2棟)竣工 |
| 1997年 | 7月 | QS9000(品質管理システム)認定取得 |
| 1998年 | 2月 | 生産棟(S棟)竣工 |
| 12月 | ISO14001(環境マネジメントシステム)認定取得 | |
| 1999年 | 3月 | 生産棟(D棟)竣工 |
| 2000年 | 8月 | 生産棟(C2棟)竣工 |
| 2006年 | 1月 | エネルギー管理優良工場(中国経済産業局長官表彰) |
| 2007年 | 11月 | ISO/TS16949認定取得 |
| 2008年 | 1月 | 生産棟(E棟)竣工 |
| 2008年 | 1月 | エネルギー管理優良工場(資源エネルギー長官表彰) |
| 2009年 | 10月 | 平成21年度「緑化優良工場等 経済産業大臣表彰」受賞 |
2. 障害者雇用の経緯
1983年に会社設立し、同年に既存従業員の障害者認定はあったが、初めての障害者雇用は1984年4月からであった。4月に身体障害者を1名採用、その年には後に2名の採用があり、その後徐々に人数を増やしてきているが、これまでは身体障害者の雇用が主であった。当社としては、障害者だからといってそれほど特別な対応はしておらず、同じ社員として十分な戦力となり、継続的な雇用を考えている。2008年に特別支援学校の実習の受け入れで知的障害者と出会ったことがきっかけとなり、知的障害者の雇用を検討するようになった。その際、ハローワーク(公共職業安定所)に採用に向けてのコンセンサス等を相談。その中で出雲障害者就業・生活支援センター リーフ(以後、リーフとする。)からの情報提供・協力があり、2008年、2009年に知的障害者1名ずつを採用するに至った。
3. 取り組み内容
(1)募集・採用
ある時、ハローワークの協力で、ハローワーク内にて障害者雇用のための就職説明会を行った。障害者雇用における新たな可能性を模索していた折のことで、非常に有効な施策の後押しをして頂いたと思っている。説明会には身体障害や精神障害をもつ方のほか、リーフ同行のもと知的障害者「Aさん」などの訪問もあった。ここでは、本人から当社への質問等を上手く伝えることが出来ないことに対して、リーフの力添えを貰った。また、ちょうど同じころに、特別支援学校学生のインターンシップ実施や、リーフの各種制度及び「知的障害」に関する様々な情報提供も重なり、当社で初めての「知的障害者雇用」が現実味を帯びてきた。
前述の説明会の後、参加者Aさんより当社採用選考への応募があった。リーフのアドバイスを受け、Aさんについては実習終了後に、当社での就業がお互いに適しているかどうかを見極めた上で、採用の可否を判断するのが最善であろうという結論に達した。当社の場合は交替勤務制をとっており、仕事の内容がAさんに適しているかということに加えて、交替勤務の生活リズムに順応してもらえるかどうかという点も重要なポイントである。本人とリーフ、当社担当者とでじっくりと相談し、まずは2週間、日勤・準夜勤の2サイクルの体験をしてもらった後で、問題がなければ、次は深夜勤務も組み入れた実習を行ってみるという計画を立てた。前半は特に大きなトラブルもなく、次に深夜勤務も組み入れた実習を行ったが、全ての勤務に対応できることがわかり、実習後すぐにAさんの採用を決定した。
特別支援学校の学生については、学習カリキュラムへの協力という形で、複数回受入れた。ただし2009年に受入れを行ったBさんについては、当社の採用ニーズと重なっていたこともあり、新卒採用の可能性を模索するため、2度の実習を行った。高校生のため日勤のみの時間帯で実習を組み、採用にあたっては、勤務時間や業務内容が習時とほぼ同じ体制がとれるよう社内で検討した。実習中には、特別支援学校はもちろん、ハローワーク、リーフからも支援と協力を受けることとなった。
(2)障害者の業務・職場配置
【Aさん】

前述のとおり、2段階の実習を経て採用に至った。
まず第1段階であった、日勤・準夜勤のみの実習における業務の遂行状況については、前半よりも後半で確実に成長が見られた。前半の準夜勤では23時頃より集中力に欠け、ミスも多かったが、後半はミスも少なくなった。このような事から、継続して従事すれば、より正確な作業が行ってもらえるだろうと判断した。その後更に2週間、深夜勤を含む実習も行なった。全ての実習を振り返ると、2つのことを同時に指示するとミスが出たり、一人分の作業をするにはまだ難しいということが分かったが、時間をかければ確実に業務をこなしていけると感じた。日勤・準夜勤・深夜勤の全てを体験してもらったことで、継続した業務遂行の可能性を見出すことが出来た。その間には通勤支援等を関係機関に協力してもらったり、採用を決定するまでに関係機関と何度も話し合いを行なった。
上記のような過程を経て、2008年12月5日に採用し、実習先であった第2製造部製造1課に配属とした。勤務時間は1勤(日勤)8:30~17:15 2勤(準夜勤)17:00~1:15 3勤(深夜勤)1:00~8:45の3交替勤務である。業務内容はブロック熱処理(積層のハガレ防止)といい、カットする前の板状の製品(製品は非常に小さいチップ形をしたものだが、板状の半完成品をカットして作成している)をオーブンで熱処理をする作業である。Aさんの他に社員1名が同じ作業を行っているが、シフトが異なるため、通常業務は1人で任されている。
業務に慣れるまでは、半年ほどかかり、習熟も時間を要した。習熟するまでは、伝票記入ミス、炉に入れるときの組み合わせミス【ロット(製品・部品等をひとかたまりにしてライン等に流すこと)により枚数が違うため、計算が必要である】など、大小さまざまな失敗があった。慣れてからはミスも減り、障害のない社員と同じように、十分な働きをしてもらっている。Aさん自身も仕事に対する自信もつき、やりがいを持って取り組んでいる。業務は一人で行なうため、他の従業員との関わりは少ないが、休憩時間等に上手くコミュニケーションも図れている。3勤の勤務体制に慣れるまでは辛かったようであるが、本人の努力と周りの社員の理解・協力のもと、すぐに慣れることが出来たようである。
【Bさん】
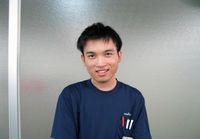
特別支援学校高等部3年生時に2回の実習の受け入れを行う。1回目は10日間、2回目は3週間で、実習内容は1回目、2回目とも同じ作業を行なった。
実習中には「メモを取ること」「大きな声で挨拶すること」「返事をすること」などを大切にするよう指導し、休憩時間のコミュニケーションに配慮しながら作業の様子をみてきた。学校の先生より、「疲れやすく、長時間集中して取り組めないときがあるため、長時間勤務が難しい」と言われていたが、2回目の実習では、前半は6時間、後半8時間での実習を行ったところ、長時間勤務でも集中して取り組むことができた。現場の担当者にも仕事が丁寧で集中して取り組めることや作業態度等に好感がもたれ、採用の可能性が十分見込めるとして、新卒採用選考のフローにのっとり面接試験等を実施した。その結果、2009年4月1日付けで採用を決定した。
入社後は第1製造部製造1課に配属。勤務時間は通勤に関する事情を考慮し、1勤 8:30~17:15の固定とした。業務内容は実習で経験した作業と同じ内容で、焼成工程サヤ詰め/サヤ空け作業。製品を窯で焼き上げる前後、「サヤ」と呼ばれる器に製品を充填したり、回収したりする作業である。一緒に作業するのは3名程のメンバーだが、他メンバーは交替勤務のため4チームあり、Bさんの場合は実質、12名程のメンバーと関わりながら働いている。初めのうちは、体力的にも辛そうであったが、今は8時間勤務に慣れ、集中して仕事に取り組めている。とても慎重に作業を行なうため、大きな失敗はほとんどない。逆に作業・確認の慎重さから、メンバーのミスを見つけてくれることもしばしばある。
4. 今後の課題と展望
(1)知的障害者を雇用して感じたこと
受け入れ前は、「対応が大変ではないか」「仕事はどのくらいできるのだろうか」「どのように話しかければよいのだろうか」など不安や心配なことはたくさんあった。ハローワーク、リーフからの情報提供から事前に実習を行うことで、本人との関わりができ、得意なことや苦手なことなどを理解することができた。その結果、実習受け入れ前の不安が解消され、採用を決定することが出来た。一口に「知的障害」と言っても障害の状況は人により様々であり、人材の幅広さを感じた。特に軽度の方については、当社でも想定していた「障害」とは違っており、こちらからの伝え方さえ工夫すれば、きちんと仕事ができることを実感した。また、思いもよらないことが「苦手」であったり、ある事については障害のない者よりも「得意」であったりするなど、個々人の個性について、本人や支援者の方からきちんと聞き取りを行い、職場のメンバーの理解を得ることが、就業の上で非常に重要であると感じた。
(2)今後の課題
現在、当社で就業中の者について大きな課題を感じているわけではないが、やはり周囲のメンバーの理解を得ること、指示のしかた・伝え方が重要である。また当社の場合は交替勤務を組んでいるため、「運転免許の取得が困難→公共交通機関で通勤→深夜勤務ができない」「長時間勤務ができない」など、勤務形態に制約が出てくる場合の対応が難しい。そのようなケースへの対応も、今後の課題と言える。
(3)展望
当社の2件の事例は、どちらも本人の持ち前の長所や、事前の綿密な話し合い等が功を奏し、採用・定着に結び付いたものと考える。そうした意味で、この一連の経験をとおし、当社自体も多くのことを学んだ。当社としては、各人の個性を十分理解したうえでマッチングを行い、それぞれの方に合った会社・職場で働けるような状態が理想と考える。それぞれが自分の力を最大限に発揮できるようになればと思う。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











