通常の人事制度に基づき普通に雇用することで不可欠な人材として育成する事例
- 事業所名
- 株式会社コニカミノルタサプライズ
- 所在地
- 山梨県甲府市
- 事業内容
- 複写機・プリンター用消耗品の製造
- 従業員数
- 265名
- うち障害者数
- 3名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 2 品質保証、生産管理 肢体不自由 内部障害 1 生産管理 知的障害 精神障害 - 目次

1.事業所概要
(1)事業内容
当社は、1981年(昭和56年)2月に設立され、沿革は下記のとおりである。主な事業内容は、電子写真複写機用資材及びレーザープリンタ用資材(感光体ドラム・現像剤)の製造販売であり、主な取り扱い製品は現像剤、感光体ドラムである。
「企業沿革」
|
1981年2月
|
コニカ株式会社の電子写真複写機用サプライ生産部門として、資本金5千万円にて現在地に「株式会社甲府ユービックス」設立 |
|---|---|
|
1981年6月
|
セレンドラム工場稼働 |
|
1982年1月
|
デベロッパー工場稼働 |
|
1982年12月
|
トナー工場稼働 |
|
1984年9月
|
OPCドラム工場稼働 |
|
1987年10月
|
社名を「株式会社コニカサプライズ」に変更 |
|
1989年9月
|
新OPC工場稼働 |
|
1990年
|
厚生棟の新設 |
|
1991年
|
資本金:2億円に増資 |
|
1993年
|
IS09002 認証取得 |
|
1995年
|
TPM優秀賞第2類を受賞 |
|
1997年
|
TPM優秀継続賞第2類を受賞、IS014001認証取得 |
|
1998年
|
3月 キット工場、物流倉庫を建設 |
|
1999年
|
TPM優秀賞第1類を受賞 |
|
2000年12月
|
ミノルタ株式会社の出資により、合弁会社化。 社名を「株式会社コニカミノルタサプライズ」に変更。重合トナー工場稼働 |
|
2001年8月
|
OPC工場増産ライン稼働 |
|
2002年9月
|
資本金15億円に増資 |
|
2002年11月
|
TPM優秀継続賞第1類を受賞 |
|
2003年5月
|
重合トナー第2工場稼働 |
|
2003年8月
|
コニカ株式会社、ミノルタ株式会社の経営統合により コニカミノルタ株式会社の100%出資会社化 |
|
2005年12月
|
重合トナー第2工場増設ライン稼働 |
|
2006年12月
|
TPM特別賞を受賞 |
|
2007年1月
|
辰野工場稼働 |
|
2009年11月
|
辰野工場にてTPM優秀賞カテゴリーB受賞 |
|
2010年1月
|
OPC工場増産ライン稼働 |
|
2011年1月
|
コニカミノルタグループグリーンファクトリー一次認証取得 |
|
2011年1月
|
OSHMS認証取得 |

(2)経営方針
「経営理念」は次のとおり(原文のまま)である。
コニカミノルタサプライズの全社員が顧客の要求を理解し、提供する製品によって顧客の満足度、信頼度を高めていくことが継続的発展の上で最重要であることを自覚し、これを実現するために全員参加の生産革新活動をたゆまず実践してゆく。
(3)組織構成
組織は大きく分けて、次の部門から成り立っている。
・生産部門
・管理部門(障害者在職)
・総務部門


2.障害者雇用の理念、経緯
(1)障害者雇用の理念
コニカミノルタグループが考えるコンプライアンスは、国内外の法令遵守にとどまらず、企業倫理や社内規則類までを広く含んでいる。この認識に基づき、コニカミノルタグループが発足した2003年の10月に、コニカミノルタホールディングス株式会社の代表執行役社長が「コンプライアンス推進宣言」を行うとともに、「コニカミノルタグループコンプライアンス行動指針(※注1)」を制定した。
この行動指針は、日本国内のグループガバナンスを貫くものとして、企業活動におけるすべての行動において最優先すべきものと位置づけられている。
また、コンプライアンスの徹底に向けて、グループ従業員に対する教育を実施している。教育にあたっては、コンプライアンスとは何かといった単なる知識の習得にとどまらず、日々の行動として表れることを目指している。その実現に向けて、「コンプライアンスは企業に対する社会的要請である」というグループ共通の価値観、文化の醸成に努めるとともに、具体的な仕組みづくりを進めている。
また、コニカミノルタグループは経営理念として「新しい価値の創造」を掲げている。ここには、製品の便利な機能や使い勝手の良さといった価値だけではなく、経済、環境、社会の3つの側面から、その時代に必要な価値とは何かを追求し、実現していく、という意味が込められている。
この経営理念に基づいて、コニカミノルタが社会との関わりの中で自らを変革し、より社会に貢献できる企業となるための指針として定めたのが、「コニカミノルタグループ行動憲章(※注2)」である。コニカミノルタで働く一人ひとりが、この行動憲章に基づいて、事業活動のあらゆる面においてCSR(企業の社会的責任)活動を展開している。
障害者雇用に関しても、上記のコンプライアンスとCSR活動の実践の一つとして取り組んでおり、それはノーマライゼーションの実現に他ならない。
また、ダイバーシティとしての取り組みにおいても、あらゆる選択肢の一つとして障害者雇用を考えることも可能であり、多面的な意義を有している。
※注1:コニカミノルタグループ コンプライアンス行動指針(要約、原文のまま)
基本姿勢
1.私たちは、国内外の適用ある法令及び社内規則類を遵守します。
2.私たちは、社会的規範を尊重し、企業倫理を十分に認識して良識と責任をもって行動します。
3.私たちは、この「行動指針」の内容を深く理解し、常に行動の拠りどころとします。
4.私たちは、「利益のため」、「会社のため」、「上司の指示」、「以前からやっている」、「他社がやっている」とか、「この業界、この国では、あたり前」であっても、この「行動指針」に反する行為をしません。
※注2:コニカミノルタグループ 行動憲章(原文のまま)
企業は、公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体であると同時に、広く社会にとって有用な存在であることが求められています。コニカミノルタグループは、全社員が本憲章の精神を深く認識し、社会的良識をもって行動します。
経営トップは本憲章の精神の実現が自らの役割と責任であることを認識し、率先垂範の上、全社員に周知徹底します。また、グループ内外の声を常時把握し、実効あるグループ内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図ります。
(2)障害者雇用の経緯、背景
上記障害者雇用理念にあるとおり、コンプライアンスの一つとして、法定障害者雇用率の達成はもとより、社会的責任を果たし、地域に貢献する取り組みを行うことを目的として、障害者雇用を行っている。
また、最初から障害を持っている方だけではなく、交通事故や傷病などにより、中途で障害を持つに至った方の雇用を確保することも非常に重要と捉えている。
3.取り組みの具体的な内容
(1)労働条件
労働条件は障害のない従業員と全く同じである。特に、「障害者だから」という考え方はなく、同じ人事・賃金制度に基づき処遇している。 したがって、パートから準社員に転換するケースもある。
①期間
無期契約、有期(0.5年)契約
②場所
事業場内
③時間
障害のない従業員と同じであり、原則としてフルタイムである。
④賃金
月給制又は時給制であり、当社の人事・賃金制度に基づき処遇している。
(2)仕事の内容
・ケース1
生産管理業務を担当し、伝票処理や事務作業、パソコン業務を行っている。
・ケース2
品質保証業務を担当し、原材料の受入検査(品質検査)や製品の出荷検査(評価)を行っている。


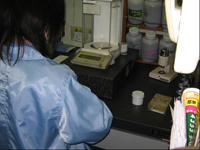

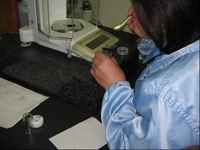


(3)助成金の活用
助成金等については、活用実績はない。
(4)労務管理の工夫
①採用について
採用に関する労務管理の工夫がよく分かるように、採用を検討する段階から受け入れ準備までを、次のとおり時系列的に紹介する。
●採用の検討
これまで、知的障害者と心臓機能障害者が在籍していたが、新たに障害者を採用することとし、検討を行った。その際の検討事項は次のとおりであり、事前にハローワークに相談に伺った。
・どんな障害を持った方を採用していくのか
・どんな業務をしてもらうのか
相談の結果として、障害者就職面接会に参加することとし、応募者に対して面接を実施した。
●就職面接会後
社長の方針 (1.永く勤めて会社の戦力になってほしい。2.独立して集中できる仕事があれば、聴覚障害者が適当ではないか。3.一人の採用では孤独になってしまう可能性もあり、二人採用してはどうか。)を踏まえ、採用の前提条件である「当社は化学装置産業であり、生産工程で働いていただくのは難しい(事故の危険性)」を受けて、採用者を決定することとなった。
●採用決定(内定)
社長方針を受け、聴覚障害者を2名(生産管理部門 1名、品質環境部門 1名)採用することを決め、採用面接実施後、内定者を決定した。
●受け入れ準備(内定後)
当社はこれまで聴覚障害者を採用した実績がなく、従業員も普段接する機会のない者がほとんどであり、「声をかけるにはどうしたらよいか」等の不安を抱いていた。そこで、次のような取り組みを実施した。
・高齢・障害・求職者雇用支援機構よりパンフレットを入手し、職場にて自主学習を実施した。
・障害者情報センターにお願いして「職場の対応」について講習会を実施した。
②業務について
業務内容を標準化し、専門用語は手話にないため、作業標準書を作成し、パソコンの画面上で業務指示ができるように改善した。また、グループ内のメンバーの顔と名前が一致するように机の配置一覧表を作成した。
なお、連絡等も最初は紙ベースであったものが、ホワイトボードになり、現在はメールを活用して、伝達効率を高めており、会議内容や社内の様子等については、上司が確実に状況を伝えるようにしている。
③緊急時対応について
火災報知器が鳴った時に分かるように、天井にパトライトを設置した。

④コミュニケーションについて
コミュニケーションの手段としては、次のようなものがある。
「口話」:職場内で多く使われる。
「筆談」:口話では分かりにくい内容や専門的な単語等の説明に多く使われる。
「手話」:最近では言語として認識が広まってきたが、習得までに訓練を必要とする。
上記のとおりであるが、当社でもなかなか手話へのアプローチが少なく、どうして手話が使われないかを当社の様子から考えてみたところ、「間違えたら恥ずかしい」、「手話が覚えられない」、「業務内容により専門用語が多い」などを理由として挙げることができた。
そこで、当社では次のような取り組みを実施した。
a.手話の本を購入し、毎日新しい手話を1~2つ覚え、会話の中で実際に使う。
b.お互いにメモを用意し、筆談でやり取りをする。
c.100円ショップよりホワイトボードを購入し、筆談を行う。
上記のaの取り組みでは、手話の参考書を購入し、最初に挨拶、そして指文字を勉強した。その結果、初めは筆談で会話していたものが、今では、手話による日常会話は問題ないレベルになっている。すなわち、試行錯誤した結果、aの方法が最も適していることが実感できたのである。
また、声のかけ方に関しても、「本人の視界に入ってから」が鉄則であり、手話等を勉強する中で身に付けることができたもので、現在では、その認識を職場全体で共有している。
ちなみに、手話の勉強には次のようなエピソードがあり、当事者(上司等)の意欲的な取り組みが認められる。
「エピソード」
・職場の15,6人で手話サークルを立ち上げ、二年間、手話の勉強に取り組んだが、そのサークルの流れが現在も続いており、一緒に昼食を楽しむなど良好な職場作りに役立っている。
・最初は、筆談用のメモを携帯するなど、専ら筆談からスタートしたのだが、字が読みづらいという感想もあり、一念発起して手話を徹底的にマスターすることを決意し、自主的に手話の勉強会等に参加した。また、障害者本人から手話を教えてもらうこともあり、コミュニケーションの促進にも一層役立つ結果となった。また、笑い話のような手話での失敗もあり、例えば、「宮原」という名前を伝えようとして、「三の腹」と表現したところ、「子供が3人お腹にいる」と伝わり、二人で笑ってしまうこともあった。




⑤その他について
障害者本人にお話しを伺うことができ、次のようなコメントをいただいたので紹介する。このコメントの中にも、労務管理のヒントが詰まっているものと思われる。すなわち、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)やディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)が求められていることが認められ、当事例においては、それが実現されていることが分かる。
「データがしっかり取れた時などは達成感を感じる。お昼に職場の仲間と話をするのが楽しみ。家庭と仕事の両立で大変な時もあるが、仕事は楽しく、長く勤めたい。」
「育児と仕事の両立で忙しいが、仕事はおもしろく、やりがいを感じている。お昼の会話が楽しみ。長く勤めたい。」
4.取り組みの効果
当社の理念でもある人材育成は、障害の有無は全く関係ないものであり、全従業員を戦力として育てることを目指している。そして現在では、会社として不可欠の存在として活躍している。
職場全体としては、次のような効果が認められる。
・人間的な視野が広がった。
・ものを伝える能力、教える能力などを始めとするコミュニケーション能力が向上した。
・ごく自然に気遣いができる職場となった。
・自己啓発意欲が高まった。
また、余談ではあるが、職場見学に訪れた山梨県立ろう学校の生徒が、就職先として高く評価してくれている実績もあり、一つのメルクマールとして捉えることができる。
上記のような効果を生んでいることは、職場全体の取り組みの賜物であることは間違いないが、障害者本人の意欲や努力なくしては、あり得ないものと思われる。
すなわち、障害者本人が明るく意欲的に仕事に取り組む姿勢は高く評価でき、その姿勢と職場の取り組みが相乗効果を生んでいると言っても過言ではない。
5.今後の課題と対策・展望
(1)課題
今後は、通常の人事制度に基づき、職域の拡大や不測の事態が起きた時の対応などが課題と考えられる。また、現状を維持する中で、モチベーションを高め、長く働いてもらう仕組み作りなども検討の余地はあると思われる。
(2)対策・展望
現状維持をベースに、必要なタイミングに応じて障害者採用を図ることになると考えられる。
(3)総括
最後に、今後障害者雇用に取り組む企業に対してアドバイスするとすれば、次のような点が挙げられる。
・必要以上に心配しないこと
・普通に接すること
・コミュニケーションを確立すること
・やってみれば何とかなる
・何の障害を持っているかではなく、意欲があるかどうかがポイント
・企業、職場、仕事内容に合うかどうかがポイント
以上であるが、当社における障害者雇用の原則は、「普通」の一言に尽きる。障害による制約は認めるが、必要以上に特別扱いはしないというものであり、通常の人事制度により対応している。
すなわち、「普通」に対応することが、結果として円滑な障害者雇用を実現していると考えられる。上記の障害者本人のコメントからも、「普通」の大切さを実感することができるであろう。特に、ワーク・ライフ・バランスの取り組みなどは、障害のある者・ない者の区別なく、労務管理にとって極めて重要であることが理解できる。
当事例からは、企業が持続的に成長していくためには、CSRの展開の一部として、ダイバーシティやワーク・ライフ・バランスの取り組みが求められ、その実現が、人材の高度化・グローバル化を促進し、少子高齢化問題への対策、障害者雇用につながることが分かる。すなわち、CSRの取り組みの重要性及びメリットが非常によく理解できる事例と思われる。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











