はじめての障害者雇用、1年間で2名を採用
- 事業所名
- 株式会社 ロハス余呉
- 所在地
- 滋賀県長浜市
- 事業内容
- 宿泊サービス業
- 従業員数
- 21名(常用雇用労働者)
- うち障害者数
- 2名
-
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 1 草刈り、清掃 精神障害 1 施設管理・送迎 - 目次
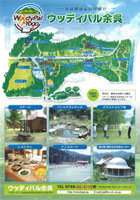
1.事業所の概要
株式会社ロハス余呉は2009(平成21)年3月に設立され、長浜市の公共施設であるウッディパル余呉(宿泊レジャー施設)の指定管理を事業としている。経営理念のテーマは「人と自然の共生・心と体の調和・地産地消によるロハスな生活の推進による生活文化の創造」であり、自然資源や農林資源、人文資源といった余呉町の豊かな地域資源をいかしたロハスな余呉文化の創造と発信を目指している。
2.障害者雇用の経緯
(1)ある講演を聞いて思ったこと
「誰もが働ける職場」を目指すこと。それが同社の障害者雇用の理念である。「『日本でいちばん大切にしたい会社』という本にも取り上げられている日本理化学工業株式会社という存在を知ったことや、滋賀県中小企業家同友会主催の講演会で同社の話を聞いたことがきっかけになった」とウッディパル余呉の支配人である辻川氏は言う。「自分たちのような小さな会社でも、できることはやっていこう。そこで、いろいろな仕事を見直してみたら、障害のある人でもできる仕事があるんじゃないか」ということになり、そこから障害者雇用の取り組みが始まった。
その取り組みは、会社の設立(=株式会社への変更)が2009年3月18日と比較的最近のことでもあることから、まったくのゼロからのスタートとして始まった。
(2)経験がなく分からないことばかりで始めたこと
はじめての障害者雇用。支配人としての自分の思いをどう伝えればいいのか?まずは職員会議に図り、障害者を雇用することについての考えを職員に尋ねる。その時点で、雇用することに後ろ向きというか、反対の意見はなかった。次は経営会議。「会社は社会の公器であって、儲けているだけではアカン。障害者の雇用を含めてみんなが働ける職場をつくっていくことも大事じゃないか」という結論となった。
しかし、これまで間接的に作業所等の障害者を見ることはあっても、直接的に接したり、ともに働くことは初めてで、まして採用者側になって障害者を雇用するということはまったくと言っていいほど分からないことばかりだった。そこで、ハローワークに相談に行ったところ、障害者の支援機関である「障害者働き・暮らし応援センター」(「湖北地域しょうがい者働き・暮らし応援センター“ほっとステーション”」)を紹介された。そして、同社の仕事の内容も検討の上で、仕事に適するだろうという人を支援機関で選んでもらうこととなった。相談から2か月ほど経って、具体的な人の紹介があり、トライアル雇用での受け入れが始まった。
3.取り組みの内容
(1)とりあえず受け入れてみて、そこから考えていくということ
紹介があって間を置くことなくトライアル雇用が始まった。それは、「受け入れのためにはこちら側(=会社)が経験しないとダメだ」との強い思いがあったが、それ以上に、「ほんとうのことを言えば、とりあえず受け入れたんです」と支配人は言う。精神障害がある男性(精神障害者保健福祉手帳所持)のトライアル雇用は2009年11月末に始まり、その3か月後の2010年2月末に終了となるが、その間の出来事については項を新たに見ていきたい。
(2)受け入れたはいいけれど、本人は休むし、正式雇用への判断なんてできるの?
トライアル雇用が始まって1か月が経ち、問題が起こる。本人が仕事に来ない。このままでは雇用どころの話ではない。それ以上にもっと気がかりなことは、本人は当方の仕事が嫌なのかどうかが分からない。本人あるいは家族に連絡を取ろうとしても、電話もつながらない。障害がある人にどう対応したらいいのか、それも分からない。1か月程いろいろと悩んだ後、本人を紹介した「障害者働き・暮らし応援センター」の支援者に現状を話すことにした。その後、しばらくして本人は支援者と一緒に職場に出てきた。「仕事が嫌なら強制的にしてもらおうとは思っていないけれど、うちの仕事のことをどう思ってるんや?」と支配人が尋ねると、「やらしてもらいたい」という意向で、「それならもういっぺんやってみようか」となった。
トライアル雇用の3か月の終了が近づき、終了後に正式雇用へ移行するかどうかの判断をしなければいけない時期となった。しかし、判断といっても、本人は3か月の間に1か月以上仕事を休み、本来であれば職場として、本人の仕事ぶりや取り組む姿勢等、「見るべきこと」を「見なければいけない時」に、ほとんど見ることができなかった。最終的には「こうした仕事は僕に合っているんです」という本人の気持ちを受け止めて、正式に雇用することとした。
(3)だんだんと分かってきたこと
トライアルを終えて、その後も、トラブルに近いようなことがあった。それは、以前のように休むということではないにしても、人間関係がうまくいかず、「もう、かなわん」と、一時の激した思いのまま短絡的に辞表を出してくる。そのような時はセンターの支援者に来てもらったうえで支配人が話をする。「辞表を出して、辞めてもらうことは簡単だけれども、他に行くところがあるとか、こういう仕事がしたいとか、そういうことがあるならいいけど、単におもしろくないから辞めるというのはどうなんかなあ?」「誰も、あなたのことを悪く言う人はおらんぞ。とんでもない奴だとか、辞めてもらわないといけないとか、そんなことは一切聞かない。みんなで、あんたのことを応援してやっていこう、という話は聞くけど」と話をしていると、次第に落ち着いてきて、「わかりました。辞めません」となる。「はじめのうちはびっくりして、あわてることもあったが、今は、そうした行為にも慣れてきた」と支配人は言う。
(4)雇用して1年を区切りに時給をアップ
本人が担当している仕事は主に施設内外の管理であり、具体的には清掃・除草・修繕等である。本人は仕事に前向きで、自らマイクロバスの運転に必要な免許を取得してきたこともあり、必要に応じ送迎バスの運行も担当している。本人の仕事に対するがんばりに会社としてできる範囲のなかで応えたいとの思いから、雇用してほぼ1年になることを区切りに時給を引き上げることとし、併せて賞与の額も引き上げることにした。こうしたことは本人に対する評価の具体的な結果でもあり、本人にとっては励みになったのではないかと思う。
上記に挙げた仕事以外に野菜作りも担当している。レストランで使う食材を自前でまかなえればいいかなとの気軽な思いから「野菜をつくってみるか」と本人に訊いてみると、本人はやる気を見せたので任せてみることにした。すると、売れるほどの立派な大根が収穫できた。畑仕事が本人に合っているのかどうかは分からないが、他人と競い合うというよりは自分のペースでやることができる仕事なのでプレッシャーは比較的少ないと思われる。
(5)2人目の受け入れ
はじめての障害者雇用の取り組みで精神障害者を1名雇用し数か月が経過した2010年4月、今度は知的障害者をトライアル雇用で受け入れた。その経緯は、すでに雇用している精神障害者のサポートでお世話になっている「障害者働き暮らし・応援センター」から、もう一人推薦したい人がいる、との話があり、「それならいっぺんやってみましょう」ということで受け入れとなった。
しかし、実際に受け入れてみると、精神障害と知的障害では大きな違いがあり、戸惑うことも多かった。加えて、本人は18歳と若く社会人としての経験がなかったこともあり、仕事の上で自主判断するということは全然できなかった。そのため受け入れ当初からつきっきりで仕事を教えるしかなかった。
3か月のトライアルを終えて、さらに1か月トライアル期間を延長したが、従業員からは一緒に働くのは難しいのでは?との声も聞かれ、正式雇用に移行するのはかなり厳しい状況であった。
(6)本人の思いを知り、正式雇用を決定
会社での七夕まつりのイベントを開催した頃、地元の子供たちが集まってきてたんざくに願いごとを書いた。従業員の一人が彼(=上記の知的障害者)にも何か願いごとを書くように勧めると、彼は「ウッディパル余呉の職員になりたい」と書いた。そのことが従業員たちの心をうち、「本人がそこまで一生懸命思っているなら雇ってみたらどうだろう?」と従業員たちから声があがった。一緒に仕事をする仲間が認めたことで、「それなら何とかなるかな」と採用を決定した。
トライアル延長の1か月間。一つに本人の職業能力、そしてもう一つに本人にとって相応しい職場であるかどうか?この2点のことで考え悩んだ、と支配人は言う。最終的には支援者と保護者それぞれに話をした。「ほんまにうちでいいんでしょうか?」「今の職場がいい」との本人の思いを聞けたことで、8月から正式雇用となった。
(7)雇用して1年くらいは細かいことは言わないでおこう
秋が深まるとともに、敷地にある木々の葉が落ち、落ち葉が積もる。毎日毎日、落ち葉を掃いては集め、掃いては集める。本人がしている仕事は単純なものであっても、嫌がらず一所懸命やる。周囲の評価も悪くない。ただ、敷地が広いこともあり、現状では運転免許をもっていないために、誰かが本人を車に乗せて一緒に回る必要がある。今後のことを考えると、本人が成長していくには免許の取得というチャレンジも必要になってくるだろう。ただし、それはこれからのことであり、1年くらいは様子をみようと考えている。
現在、本人が担当している仕事は草刈りや清掃(具体的には拭き掃除や掃除機かけ)といった労務だが、可能性をみていくということもあって、動物(ヤギ)の飼育をしてもらったこともある。「好きか?」と訊くと、「苦手です」ということだった。ヤギを世話する様子から、ヤギが動こうとしなかったり、急に立ちどまったりと、イレギュラーなことが苦手であることが分かった。
(8)人間関係で躓かないためのコミュニケーション
毎朝行なっている全員そろってのミーティング。仕事の予定などを確認して、その後、本人たちに声をかける。また、月に何回か支配人が定期的に、それぞれの就労場所まで一緒に行き、その道中でいろいろと話をする。ただ、知的障害者との会話においては定型的な受け答えが多くなりがちで、たとえば、「仕事はどうや?」という問いかけには、「はい、頑張っています」と返ってくるだけである。しかし無理強いはしない。たとえ良かれと思ってすることでも、本人が嫌がるようなことはしない。付き合っていくなかで、勝手な思い込みはいけないと思えるようになった、と支配人は言う。
4.これまでの経験から考える障害者雇用のメリット
はじめての障害者雇用の取り組みから1年と数か月が経過して、会社として変わったこと、会社としてよかったことを支配人に訊いた。「みんなが働きやすい職場、そうした職場になるにはどうすればいいのか?そう考えるようになったことが一番変わったことだと思います。みんなが互いに気遣いをする、みんなが互いに助け合う。言うのは簡単でも、現実は困難なことが多いなかで、挑戦していこうという雰囲気ができてきていると思います」
2人が頑張っているから、みんなで盛り上げていこうとなる。いい職場とは?そうした実践がこれからの定着を支えていくのだろうと思う。


アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











