得意分野で自分らしく働く

1.事業所の概要
こうぜんかい・はうす生野は、医療法人が運営する住宅型有料老人ホームである。全館バリアフリー設計で30室ある居室はすべて個室。プライベート空間を保ちながら、24時間体制でスタッフが常駐し、入居者の健康・介護への不安を解消している。
また、同法人内の在宅支援診療所、訪問看護ステーション、ヘルパーステーション、ケアプランセンターなどの施設ときめ細やかな連携を行うことで、車いすを利用されている方、寝たきりの方、認知症の方、胃ろう・静脈栄養・インスリン等の処置が必要な方の受け入れも可能にしている。
加齢による心身の不安だけでなく、疾患を抱えている方への支援も積極的に行い、入居者の生活の質にこだわった医療法人ならではのサービスを提供している。
2.仕事内容
Mさんのメインの仕事場は、入居者に食事を提供するための厨房。出勤日には約20名いる入居者の昼食準備を1人で担当している。
<勤務時間> 週3日(シフト制) 11時~14時
<仕事の流れの1例>
11:00~ 勤務スタート
昼食準備(調理・盛り付け)
11:30~ 入居者が食堂に集まり始める。来られた方へ順次配膳。
入居者が食事を終えられると、食器を下げて食洗機へセットしていく。
食器片付け。
13:00~ 調理場の清掃終了。
入居者の居室がある各階の共有スペースの清掃。
14:00 勤務終了
業者からその日の献立に使う調理済みの食材が届くため、マニュアルを見ながら湯せんや機械を使って温め、食器に盛り付けをする。また、ご飯を炊くこともいつもの仕事。軟食が必要な入居者には小さな炊飯器でおかゆを炊く。味噌汁に入れるネギを刻んだり、デザートの果物を切り分けるなど、簡単な調理もこなしている。
上記に挙げた仕事の流れや内容はほんの1例で、仕事に慣れてきたMさんは、自分の判断で柔軟な対応をしている。「最近床の汚れをきれいに落とせていないので、今日は時間を作って床磨きをしよう」、デザートのキウイについて「マニュアルでは半分に切って出すと書いてあるが、食べやすいように一口サイズにカットしよう」など、気遣いや機転を利かせて、意欲的に仕事に取り組んでいる。
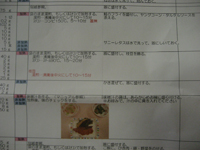

3.就職までの経過
Mさんが就職のための準備を本格的に始めたきっかけは、障害者就業・生活支援センター(以下、支援センター)に相談をしたことだった。その頃のMさんは地域の作業所に通いながら、合同面接会へ参加するなど積極的に就職活動をしていたが、なかなかうまくいかずにいた。相談を受けた当時の精神障害者コーディネーターは、Mさんの「働きたい」という強い思いに寄り添う形で、より就労に近い取り組みをしている小規模授産施設(現在は移行支援事業)のA工房を紹介。お弁当の製造・配達を利用者で分担して取り組んでいるこの施設との出会いがMさんの転機だったと言える。
A工房でMさんは、見違えるように生き生きと作業に取り組むようになる。 A工房で作業に励むうち、Mさんの中に「PCを勉強して事務系の仕事に就きたい」という思いが湧くようになる。そんなMさんに、支援センターの担当者から当センターで実施している『障害者の態様に応じた多様な委託訓練』が紹介され、受講することとなった。
訓練内容は、基礎的なワード・エクセル操作と、体調管理・SST(社会生活技能訓練)など。訓練の中でMさんは、PCスキルを習得するために自宅でも復習して熱心に勉強をしたが、A工房で働いていた頃の生き生きとした表情は見られなかった。それに気づいた支援センターの担当者は、食堂で実施している委託訓練への継続受講をMさんに提案した。もともと体を動かすことが大好きで、以前の職歴の中でも食品製造関係で働いていたころが「一番楽しかった」と話してくれていたMさん。本当はすぐにでも働きたい気持ちだったが、座ってPCに向かうようなオフィスワークが自分に合っているのか?自分に合った働き方はどんなものか?を再確認するため、委託訓練の継続受講を決めた。
次の委託訓練では、洗い物や包丁作業などの調理補助と接客を経験した。お昼時は非常に混み合い、何食出るかは日によって違うため仕事にはスピードが要求され一日の作業量も一定ではなかった。また、忙しい時間帯は情報が一度に入ってきたり、確認したいことがあってもできないことがあったりと、本人の中では戸惑うことが多かった。訓練は無事に修了したMさんだったが、「もう少しゆるやかで、あらかじめその日の作業量が決まっている仕事の方がいいかもしれない」と感じるようになる。
こうぜんかい・はうす生野は、そんな経緯をたどってきたMさんのイメージに合った職場だった。
4.職場での取り組み
Mさんの雇用は2週間の実習期間中に決定した。
受け入れにあたって事業所職員の中には「どんな人が来るのか?」、「決められたシフトをこなしていけるのか?」、「認知症の方との対話、入居者からの要求などに対応できるか?」など高齢者施設ならではの不安もあった。しかし、実習中にMさんの明るい人柄や作業を実際に見たことで解消された部分が大きかったようだ。
事業所側は、Mさんが段階的に仕事に慣れることができるように、最初の2か月間は、
≪職員の仕事のやり方を見学 → 職員と一緒に作業 → 自分一人で作業するところをチェックしてもらう≫
という流れで指導を行った。
以下、職員・Mさんの声を交えながら紹介していきたい。
■Mさんの仕事ぶりは?
職員:「大変真面目です。仕事に対して意欲的で、自分で状況判断し工夫をしながら取り組んでくれています。入居者さんともうまくお話をされていますし、素直にこちらの指示を受け入れて課題をひとつずつクリアされています。今では一人で任せておいても支障はありません。」
Mさん:「慣れるまでは、11時30分までに食事の準備をしなければいけないので、時間のペース配分や段取りの組み方が難しかったです。食材を早く温めすぎて冷めてしまったこともありました。食材を温め始める時間を覚えることや、入居者さんの顔と名前を一致させ、どの方に何が必要かを暗記し、来られたらすぐに配膳することで温かいまま食事が出せるようになりました。」
■職場で配慮されていることはありますか?
職員:「間違ってもいいので失敗を恐れず、自信を持ってほしいと伝えています。失敗はお互い様なので。」「何か疑問や不安があればしっかりと話をするようにしています。また、職員からの指示について、気になることをあれこれと考えすぎないようにとも話しています。家でシミュレーションをして当日に備えてくることは大切なことですし、なかなできることではありませんが、生活リズムを崩してまでする必要はないことを伝えるようにしています。」
Mさん:「“わからないことがあれば何でも質問して”といつも声をかけてくださることが配慮して頂いていると感じています。以前の職場では“この人わかってへんな”と思われることが怖くて本音で質問できないことが辛かったのですが、ここでは安心して質問できます。」 「引き継ぎ事項があれば必ずメモを残しておいて下さるので仕事がしやすいです。」
また、Mさんが入居者の顔と名前を覚えて配膳しやすいように、職員が、入居者の名前が書かれたマグネットプレートを作成するなどの配慮もされている。


5.まとめ
お話を伺って、Mさんがこうぜんかい・はうす生野で一人の職員として必要とされ、認められていることがうかがえた。
作業所通所や訓練を通して自分の得意分野を知り、“自分に合った仕事は何か”を体験しながら絞り込んできたMさんにとって、こうぜんかい・はうす生野での仕事はやりがいを感じられる仕事だ。しかし、勤務し始めた頃は、「自分はちゃんとできているのだろうか」と不安になって落ち込んでしまうことも多かった。そんな時には職員の「しっかりできている」「頼りにしている」という言葉がけで支えられてきた。また、職員は、Mさんが一通りの仕事を覚えてからは仕事の進め方を本人に任せており、それがMさんには「信頼されている」という実感となって自信につながっているようだ。
Mさんの力を信じ、“任せるところは任せる”が、不安なことがあればしっかりと話を聞き声がけを絶やさない事業所側の“見守り”の姿勢が、Mさんが安心して勤務を継続していける環境を作っていると言える。
「今では仕事は生活の一部。長く続けていきたい。」とMさんは感じている。
大阪市職業リハビリテーションセンター 短期委託訓練部門 山本みお
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











