めざすは地域に根ざした障害者雇用

1.事業所の概要
創業は1946年、2011年は65年目を迎える。戦後間もないころ、「物不足の時代に子供たちにキャラメルを」と、創設されたのがカバヤ食品である。甘いものに子供たちが飢えている時代、子供たちに喜んでもらうにはどうしたらよいだろうという発想から、戦前から製造されていた水飴を使用してお菓子を作ろうと考え発売したのが「赤箱」の愛称で知られる「カバヤキャラメル」である。発売と同時に爆発的人気を博した。そのキャラメルのおまけとして1952年に登場した「カバヤ文庫」は物不足の時代に「本」がもらえるという、とても貴重なおまけとして人気を集めた。
「カバヤ食品」という社名は、「子供にアピール → 動物 → 戦後間もない頃の平和を願う気持ち」から「おとなしく平和を愛するというイメージ」の強い「カバ」をマークとした「カバヤ食品」という社名が誕生した。キャラメルの販売全盛の頃には社名のとおり「カバ」を象った「カバ車」でのキャンペーン活動や、檻を備えたトラックに本物のカバを乗せ「移動動物園」として街頭宣伝に回るなどユニークな活動をしていた。
その後1964年の「ジューC」、1975年の「マスカットキャンディ」、1978年の「ビッグワンガム」というように品種を増やしていった。そして1984年に関東工場を建設、本格的なチョコレートメーカーとしての体制をつくり、総合菓子メーカーとなっていった。さらに1991年には商品のより高品質化、均一性、安全性のアップのため、岡山駅南から現在の場所へ「自然と調和し、より環境にやさしい」をコンセプトとした岡山本社工場を建設、移転した。その後2000年には新ブランド「カレーム」を立上げ、焼き菓子ラインを増設して現在に至っている。
2006年には創立60周年ということでカバ車も復刻され、地域のイベントや、キャンペーン活動へ参加している。2011年3月には復刻版カバ車のガールフレンドもデビューする。創業当時より「お菓子を通じて、世の中に夢と文化を、そして健康と味のメルヘンを提供し続けたい」という願いはいつまでも変わることはなく、これからも安全、安心の商品を提供し続けることに取り組んでいきたい。
2.障害者雇用の背景
カバヤ食品は「社会貢献・地域貢献」ということに前向きな考えを持っている。環境問題や安全安心の社会といったことを踏まえ、ISO14001、9001の認証取得(それぞれ2000年、2005年取得)をした。
また地域の方、岡山の皆様に当社の活動を見ていただくこととともに、安心して花見をしていただける場所を提供するために、毎年岡山本社工場で「桜祭り」のイベントを催している。復刻カバ車でのクリスマス時の病院慰問や交通安全パレードへの参加、地域マラソンの先導といったイベントにも積極的に参加している。これら以外にも工場見学の受け入れなども行い、地域に根ざした活動を心がけている。
そして、このような「地域貢献・社会貢献」だけでなく、企業の責任という観点から取り組み始めたのが障害者雇用である。障害者雇用促進法の改正、法定雇用率の引き上げといった社会全体としての取り組み強化もあり、当社としてもできるだけ地域の障害者の雇用を推進しようとしている。
その取り組みの一環として、高等支援学校からの職場体験の受け入れを行っている。高等支援学校からの要請があると、工場のラインで職場体験をしてもらう。体験者の障害の程度によってまちまちではあるが、2週間前後を目処に仕事に従事する。体験する仕事の大体は、梱包積み付けや包装ラインの商品供給である。「とても楽しかった」と言われる方が大半だが、慣れない環境で、慣れない事をする負荷に耐え切れず、予定を切り上げざるをえない人が出てくることもある。現場はそのたびに障害者の受け入れの難しさを感じるが、そのことは受け入れる側の勉強にもなり、よい効果も生んでいる。
また、地域の障害者支援施設などの作業体験の受け入れも行っている。この体験は単純な軽作業で、何種類かの商品を袋に詰め合わせる作業である。この作業でできた袋詰品は工場見学に来られた方の来場記念のお土産となったり、販売商品となったりする。
これらの取り組みは従業員の障害者に対する理解を深め、障害者雇用を行いやすい環境づくりに結びついている。当社としては、今後も『企業は地域貢献を行うことが社会的責任である』という会社の理念として継続して取り組んでいきたい。
3.就労の状況
(事例)キャンディライン従事者 Aさん、Bさん(共に知的障害者)


Aさんは製造されたキャンディ生地を個包装(一粒づつ包装したもの)まで仕上げた個装品(仕掛品)を袋包装のラインへ供給する仕事をしている。写真は、仕掛取りした個装品を、3種類のアソートキャンディを生産するラインへ供給しているところの様子である。3種類が均等に混ぜ合わされるようにすることや、それぞれの個装品が供給切れしないようにすることに注意しながら各供給口へコンテナから個装品を入れていく作業をしている。すでに何年もこの業務に携わっており、作業手順にも習熟し問題なく作業している。
Aさんは、「作業のやり方を主任や、同僚の方が優しく教えてくれるのでうれしいです。仕事は面白い」と笑顔で答えてくれた。他のラインや場所で仕事をすることはないのか聞いたところ、そういうこともあり、新しいところで初めて作業するときは緊張するとのことだった。だが、「現場の主任、同僚がいつも丁寧にしっかり教えてくれるので頑張れる」と話してくれた。目をキラキラさせながら話しているのがとても印象的だった。


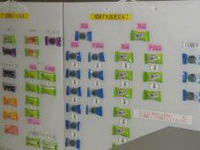
Bさんはキャンディの個装品(仕掛品)の選別作業を行っている。個装品に仕上がったものから不良品として選別したものを再度仕分けをして、良品だけを包装ラインへ戻す作業をしている。個装選別はキャンディ生地を個装品まで仕上げる工程で、包装がずれていたり、規定どおりに密封されていなかったりしたものをより分ける作業である。そこの作業は熟練した作業員が行う。Bさんは選別作業の補助として、選別されたものの中からさらに良品をより分け個装取りラインへ戻す作業を担当している。選別見本を見て、良品と不良品を分けるので高い注意力が必要になる。一つ一つ見本と比べながら作業を行っていては作業効率が悪くなる。そのため目視しただけで良品、不良品を見極めることができるようになる必要がある。Bさんはまだすばやく選別をすることはできないが、現場主任からは、だいぶ慣れてきて選別した結果は合格点、との評価をもらっている。



もうひとつのBさんの仕事は個装取りという作業である。個装品に仕上がったキャンディで個装選別し終わったものがラインから出てくる。それをコンテナに受ける作業をしているところである。かなりの量が絶え間なく出てくるため、コンテナが一杯になった際にすばやく次のコンテナを受けなければならない。コンテナの充填状況を注意しながら、一方で一杯になったコンテナをパレットに積み付け、所定の場所へ移動させる仕事をしている。作業手順や掛る時間を予測しながらの作業となっている。
当日は、検品補助作業と、個装取りを同時に行っていた。入社して4年目だが、一生懸命頑張って取り組んでいる。「仕事は楽しいですか?」の問いかけには、おとなしい素直な方なせいか、はにかみながら小さくうなずいた。現場の主任からは、「真剣に仕事をしていることが伝わってくる。そのせいか、作業をしているときには障害者ということを忘れるようなときがある」との話だった。Bさんが補助に就いた検品作業をしている同僚がよく声を掛けている様子が見え、よい雰囲気を感じた。
<現場での指導、担当主任より>
障害の有無にかかわらず、現場で最も注意することは事故である。そのため、新しい作業を行う場合は必ず危険な箇所、危険な所作についてまず説明をすることから始める。その後ベテラン従業員が必ずマンツーマンでつき、作業を教える。慣れないことでの事故防止だけが目的ではなく、熟練者からの細かい指導によってより早く仕事を覚えることができる。また慣れてきても障害者が従事している職場では、同僚が目配りをすることを指示している。誰でも経験があるように、慣れた頃の気の緩み、注意力が下がることで事故が起きやすくなる。障害者は、注意力が散漫になりやすいこともあるため、声掛けをすることを意識している。
2005年に採用された重度知的障害者であるCさんの雇用継続にあたって、2009年までは「障害者介助等助成金」の中の「業務遂行援助者配置助成金」の支給を受けていた。しかし今では援助者(当社従業員)の助けを借りる必要もなくなり、同僚と一緒に元気に仕事をしている。これも、本人の努力はもちろん、援助者の地道な指導もさることながら、周りの同僚の声掛け・アドバイスなどの力も大きかったと思われる。
またAさん、Bさんともに、一度やり方を覚え、作業に慣れてくるとほとんど問題なく仕事を行うことができる。ただ、みんなのペースに合わせながら行わなければならないライン作業では、かなりストレスを感じ、ついてゆけなくなることがあるため、自分のペースでできる仕事を中心に従事してもらっている。特別な配慮というものではないが、現場では以上のような点に気をつけて障害者を指導している。
カバヤ食品としては障害者を特別扱いせず、できるだけ他の従業員と同様に扱うように心がけている。これは厳しい指導をするということではなく、むしろそのことで本人の自立心・やる気を育て、より前向きに仕事ができるようにしたいと考えているからである。
4.今後の課題
障害者雇用はカバヤ食品が行っている社会貢献、地域貢献の中のひとつという位置づけであるということは前述のとおりであるが、その取り組みはまだまだ胸を張るところまでは達しておらず、道半ばといった状況である。これはただ障害者の雇用者数を増やせばよいというものではなく、受け入れる社内の土壌作りや長く勤められるような就労体制作りの取り組みがすぐに結果が出てくるものではないことを表している。
その中で、前述のとおり地域貢献をより促進する中で徐々に結果を出していくことができればと考えている。まずは障害者に対して援助になることは何か?といったことを改めて考える必要がある。雇用だけでなくほかの方法(職場体験や作業体験などは良い例)での取り組みも長い目で見た障害者雇用につながるのではないかとも考え、そういったことに許される限り門戸を広げていきたい。また企業としてコンプライアンスは当然のことで、法定雇用率を必ず上回ることは絶対条件としていかにそこに上乗せしていくかを念頭において、今後とも障害者の雇用を継続発展させていこうと考えている。当面の対応として今春の障害者採用を予定している。
会社として目指す「グッドカンパニー」はお客様にはもちろんのこと、会社にも、従業員にも、そして地域の方にも「いい会社ですね」と言われることであり、そうなっていくことを目指していきたい。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











