チームワークで障害を乗り越え、
訪問療養マッサージで在宅ケアのプロを目指す
- 事業所名
- 株式会社パーソングロー
- 所在地
- 広島県広島市
- 事業内容
- 在宅療養者に対する訪問療養マッサージ
- 従業員数
- 8名
- うち障害者数
- 3名
障害 人数 従事業務 視覚障害 2 マッサージ師 聴覚障害 肢体不自由 1 マッサージ師 内部障害 知的障害 精神障害 - 目次

1.会社の概要
(1)会社理念(会社ホームページより抜粋)
『人間の無限の能力を信じ、共に成長を目指す』
社名は、『人(パーソン=Person)は、成長する(グロー=Grow)』という意で命名。
「利用者の隠れている生活能力を発見し、訓練により能力を再び呼び覚ますことに尽力します。一人ひとりと真剣に向き合い、本人や見守る人達の要望が何かを理解し、主治医・介護者の人達と密な連携を取りながら、心と身体のケアを目指して取り組んで参ります。そして、「自分らしく生きることを楽しんで頂く」ということを目的とし、そのお手伝いをするのが私たちの仕事です。医療に携わる者として、プロの自覚と責任を持ち、さらなる医学的知識・技術の習得に日々努力し、利用者や私たち自身の無限の能力への挑戦を続けます。
(2)沿革
平成21年 1月 広島市東区戸坂千足にて株式会社パーソングローを設立
平成21年 2月 利用者宅・施設へ訪問を開始
平成22年 6月 会社を広島市西区打越町へ移転
(3)事業内容
転倒の危険性が高く外出が困難な高齢者や、脳卒中や骨折などで長期的な療養が必要な人達に医療保険適用の訪問療養マッサージを提供している。
具体的内容としては、
①マッサージ(筋肉の凝りの解消や除痛、ストレス発散を目的とする)
②関節可動域訓練やストレッチなどの機能訓練(健康の維持、介助量の軽減などを目的とする)
③筋力強化訓練(健康の維持、介助量の軽減などを目的とする)
④在宅での運動プログラムの作成(日常動作訓練など)
⑤環境調整への助言、介護指導 などが挙げられる。
2.会社設立の経緯
株式会社パーソングローは、「障害者であってもやればできる。」という想いからはじまった訪問療養マッサージを提供する会社である。ここでは会社設立の経緯を紹介する。
① 訪問療養マッサージとの出会い
平成18年、私は同業種の会社で相談員として訪問療養マッサージに携わることとなった。そして全くの素人だった私に訪問療養マッサージのノウハウを指導してくれたのが、マッサージの国家資格をもつ障害者の施術スタッフ(以下、施術スタッフ)である。
② 利用者と接して感じたこと
私は、まず訪問療養マッサージの制度や施術内容、障害者に関することから勉強を開始した。そして、いろいろな施術スタッフに同行する中で、在宅で困っている人達がたくさんいること、そして私は「利用者に対して何ができるのか?」ということを考えるようになっていった。
③ 施術スタッフの苦悩
施術スタッフと接していく中で、障害のない人が当たり前に行なえることが、簡単にできないことを知った。例えば医学書を読むことであったり、目的地への移動であったり。そして正社員雇用の促進も然りである。
④ 施術スタッフの可能性
何らかの障害をもっている施術スタッフであっても、相談員とチームを組むことで利用者の生活に、より適したアプローチができるのではないか、そして相談員である私は、利用者の声を丁寧に聞くことで、何かお手伝いができるのではないかという可能性を感じていた。
⑤ より良いサービスを提供するために
訪問療養マッサージに関わりはじめて2年、利用者に喜ばれるサービスを提供するためには、在宅医療(在宅リハビリ)に関する知識を高め、施術スタッフが能力を十分に発揮できる環境を会社が整えることが必要だと感じていた。そしてこの頃から、私自身が理想とする訪問療養マッサージの会社を一から作りたいと考えるようになっていった。
⑥ 会社設立、これからの目標
平成21年1月、私の思いに賛同してくれたスタッフ数名と株式会社パーソングローを設立。現在は8名のスタッフでがんばっている。これから施術スタッフも増えていく中で、それぞれの個性(障害)を理解し、のびのびと仕事に専念できるようにサポート体制を整えていきたいと思っている。
3.具体的な業務内容「施術スタッフの1日」
9:00~12:00 スケジュールにより現場へ直行または事務所へ出勤(約3~4名訪問)
◇訪問スケジュールは週単位で固定されているので、計画的に利用者様の経過を見ていくことができる。

12:00~13:00 休憩(事務所にて昼食&インターネットで情報収集など自由)

◇休憩中や利用者が休みの時は事務所で待機している。
13:00~18:00 午後のスケジュール(約5~6名訪問)

◇普段生活しているベッドや手すりを使って練習できるので、即実践が可能である
18:00 業務(訪問)終了後 自宅へ直帰または事務所へ帰社

社内勉強会では様々なことに取り組んでいる。
◇中枢神経疾患について
・脳卒中、パーキンソン病など
◇整形外科疾患について
・変形性関節症、脊椎疾患など
◇廃用症候群について
・寝たきりの方へのアプローチ
◇利用者様のカンファレンス
4.心に残った症例「利用者Sさん」
(紹介)
利用者名:Sさん(女性:83歳)
診断名:多発性脳梗塞(H20年発症)
施設入所のSさんは、多発性脳梗塞による運動麻痺および長期臥床による筋力低下により歩行困難な状態で、評価をもとに非麻痺側の筋力増強を目的に施術を進めていった。しかしコミュニケーション面では、表情は乏しく、問いかけにもやっと答える程度で、自分がどうなりたいという希望もない、いわゆるモチベーションの低下が訓練を阻害している状態が推測された。そこで私は、訪問時には受身の訓練から利用者が主体となるようにと思い、できるだけ日常会話や冗談、昔の話などしながら楽しい雰囲気をつくるように心掛け、施術を行なっていった。
訪問開始1ヶ月、Sさんに変化が表れ始めた。少しずつ笑顔も増え、コミュニケーションも徐々にとれるようになった。そして、これまで車いすでしか出来なかった移動が、押し車を押しながらでも自分の足でできるようになっていった。この頃から、Sさんは、自主訓練に対して積極的に取り組み、訓練に対しても「今度は杖に挑戦したい。」などの発声が見られるようになっていった。
あれから数ヶ月が経過し、現在では杖を使って歩くことへ挑戦している。Sさんの頑張る姿は、家族や施設のみんなだけでなく、私自身にも勇気と感動を与えてくれた。施術者は、ひとつひとつの機能を改善していくことが大切である。しかし病気を発症して数年、十数年も経っている利用者も多く、長い闘病生活の末に精神的にも落ち込んでいることも多いため、メンタルケアにも十分配慮し、生きる意欲を持ってもらうことが重要だと改めて考えさせられた症例であった。
5.会社の取り組み「仕事に専念できるように」
① パソコンソフト機能を使って業務遂行
視覚障害者にとって、文章の読み書きの業務はかなりの負担となる。そこで独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の就労支援機器の貸し出し制度を利用し、パソコンの音声対応ソフトを導入している。また、パソコン操作の音声ガイドやインターネットの文章を読み上げる音声ソフト、文章を作成する音声ガイド付きワープロソフトを導入することにより、日報や報告書などの書類作成、インターネットを利用して疾病や治療方法などの情報を検索して勉強することが可能である。
② 視覚障害者対応の寮を完備
遠方からの視覚障害者の就職に際して、重度障害者等通勤対策助成金(住宅の賃借)を利用した寮を完備している。

③ 専属の運転手
車の運転ができない視覚障害者のスタッフには、専属の運転手がついていく。よく複数のスタッフを車1台で巡回しながら訪問している会社があるが、精神的負担が大きいため、当社では専属の運転手で送迎を行っている。
④ 職場環境の安全対策
事務所の出入口周辺で照明の暗い部分にセンサーライトを設置している。また外階段も雨の日に滑りやすいので、滑り止めを施し、転倒事故防止に努めている。
⑤ チームワーク
訪問事業は個々で行なうため、仕事での悩みなど一人で抱え込まないようにチームワークが大変重要となってくる。社内旅行(昨年は宮崎)、ビアガーデン、バーベキュー、野球観戦など社内イベントも盛んに行いながら、従業員同士のコミュニケーションも深めるように心がけている。



6.障害者のスキルアップ改革「東洋医学と西洋医学の融合」
① 在宅マッサージでは、整形外科疾患・脳卒中など専門的な医学的知識を必要とするため、国家資格保持者であっても日々の勉強は欠かせない。週1回の社内勉強会で、それぞれの担当利用者の経過報告を行い、問題点や施術方法などを、スタッフみんなで意見を出し合いながら、最善の施術プランを検討している。それらを重ねる事により、より実践的な臨床研究、スキルアップができると考えている。またより深く専門性を追求するために、月に1度、理学療法士を招いて現場への個別同行や勉強会を行っており、視覚障害者のためのリハビリについて実績を積みながら、確立していきたいと考えている。

② 視覚障害者にとっては、インターネットだけでは得られない情報をいかに習得していくかが課題となってくる。社内研修としての新人教育プログラムも整備し、視覚障害者向けの独自のスキルアップシステムも構築していきたいと考えている。また今後は、特別支援学校在学中の生徒へ職場体験や在宅リハビリに関する勉強会などを行い、訪問療養マッサージへ興味を持ってもらうことで、卒業後の進路を決める際に役立ててもらう企画を計画している。
7.施術スタッフからの一言「これから在宅リハをめざす方へ」
施術スタッフのリーダーである視覚障害1級のAさん(資格:あん摩・マッサージ・指圧師)からのコメントを紹介する。
私はこの会社に勤めるまでは、多くの資格者と同じ治療院・マッサージセンター・病院などに勤めていた。その中で現在の社長の思いに共感し、「社会貢献としてマッサージ師の自分にどこまでできるのか?」と考え、初めてこの世界に飛び込んでから早2年が経過した。当時は、障害を持っていることと、初めての在宅リハということもあり、正直どこまでやっていけるか不安でいっぱいだったと思う。
在宅でリハビリを必要とされている方の内容は幅広く、いわゆる寝たきりの人の機能維持から、歩行などの動作改善を目的とする人まで様々である。そして対象者も脳梗塞・脳出血後遺症、廃用症候群、加齢による運動器障害など多岐にわたる。当然、新しく学習することも多く(笑)、音声学習が主体である私は、どうしても深く勉強しようと思うと制限されるのが現実である。しかしコツコツと努力することと、会社のみんなの助けも借りて、「成せばなる」という思いでがんばっている。
業務内容や症例紹介などを見て、この仕事が大変と思うか、やりがいがあると思うかはわからないが、「笑顔で迎えていただき」「笑顔で見送ってくれる」。施術スタッフの訪問を心待ちにして待っていてくれる人がいる、こんな風に感じることは治療院で勤めていたときにはなかった感情である。今後いっそう高齢社会が進む中、マッサージ師ができる一つの社会貢献として、がんばっていくつもりである。 みなさん、興味があればまず見学に来てください。
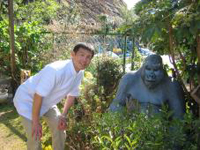
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











