それぞれの個性を理解し、自立を促す

1.事業所の概要
医療法人高信会辰元病院は、宮崎市中心地から北西に約20キロメートルの所に位置する。昭和48年に宮崎市内に辰元クリニックを開設し、昭和53年より現在の場所に高岡クリニックとして開設した。そして、昭和58年には特例許可老人病院となり、平成6年に辰元病院に名称変更し、現在に至る。
現在、辰元病院には、看護・介護とリハビリテーションに重点をおいた医療療養病棟38床、長期療養患者で医学的管理が必要な要介護者の入院施設として介護療養型医療施設145床がある。辰元グループとしての関連施設には、この他に介護老人保健施設信愛ホーム(定員80名)、特別養護老人ホーム裕生園(定員74名)、ケアハウス シャトル(定員50名)、グループホームたちばな(定員26名)、介護付有料老人ホーム宮崎信愛園(定員40名)、セントラルキッチンたつもと、養護老人ホーム長寿園(定員50名)、介護付有料老人ホーム アルテンハイムグジブランド(定員65名)などあり、高齢者医療・保健・福祉複合施設となっている。
お年寄りのターミナルケアを中心とした病院で、身体の不自由な方がほとんどの介護力強化病院である。あらゆる患者の手となり足となって食事、入浴、排泄介助、洗濯、また処置、医療などが行われている。理念には「今日の一日を奉仕と感謝の心で過ごし、職員として職務と技術の向上に努めます」とあり、寝たきり患者担当の看護師の介護十則の中には、「自分の親と思い、人間愛に燃え、豊かな心で看護する事」が強調されている。身体の不自由な患者に対して、「人の心」を大切にした職員一体となった取り組みがなされている。
障害者雇用の基本的な考え方、「生活全般に関しては、なんら障害を持たぬ者と変わらぬ“心の働き”を大切にして、共に喜びも悲しみも、分かち合えるようになりたい」とし、障害者雇用でも「人の心」を大切にした、共に分かち合えるための支援が行われている。
2.障害者雇用の経緯
障害者雇用に取り組むようになったのは、知的障害者総合福祉施設向陽の里より、体験学習として2名の知的障害者を住み込みで受け入れたことによる。
病院には、特別養護老人ホーム同様洗濯場があり、昼夜兼行で洗濯、特にオムツや肌着、衣類を洗濯機・乾燥機を使って、洗い、乾かして、たたむという作業がある。短期に受け入れた彼らの体験学習での仕事ぶりは、驚くほど忍耐力があり、一度覚えたことに忠実で、しかも真面目であった。
そのため、当初2名を職員として採用することになり、その後も同様に職員として採用し、現在では5名(一時6名のときもあった)の知的障害者が勤務している。平成4年から採用され、ほとんどが現在まで継続して勤務し、勤続年数は16年から18年になる。各業務内容を熟知しており、今では他の職員に頼られる存在になっている。
なお、看護師の採用については、一般の採用試験と同様に行い、採用されたものである。
3.取り組み内容
給与は日給制で社会保険に加入し、ほぼ全て障害のない職員と同じ取り扱いである。勤務時間は、①7時~16時、②10時~19時、③12時~21時の交代制であり、週3日~4日の勤務日数である。業務内容には、清掃業務と洗濯業務がある。障害の有無に区別はなく、勤務時間は基本的にローテーションとなっている。
ただし、業務内容、勤務時間について、日々の個々の状況に応じた対応がされている。担当職員は障害者と話し合いの場を持ち、その時々の状況を把握して、適切な業務内容、勤務時間に変更するなど配慮している。これまでの長年の付き合いの中で一人一人の個性を理解しているため、個々に合った適切な判断が可能となっている。実際に使用されている介護勤務表を図1に示す。

作業は、チームを作って行われる。障害者の状況にあった取り組みは、このチーム内でも行われ、チームリーダーが障害者の状況にあった受け持ちを指示する。
清掃業務は、玄関、廊下、トイレ、病室のゴミ等を片づけることが主である。写真1に清掃用具を示すが、障害者によってはモップのメーカーやストック数などにこだわる人もいる。そのため、その障害者に対応した用具を揃えるよう配慮している。
清掃作業は責任感を持って、非常に丁寧に、確実に行っている。病院内のお年寄りの障害者(患者)と接する機会もあり、しっかりと挨拶することが徹底され、患者へ優しく接する姿も見られる。

洗濯業務は、ヘルパーの持ってくる衣類、布おむつなどの便をすすぎ、熱湯消毒し、洗濯機械を用いて洗濯、乾燥、たたみを行う。おむつは、夜用、昼用でそれぞれ異なるたたみ方をする必要があり、熱湯消毒、乾燥等を行うために夏は暑い中での作業になる。写真2に洗濯機、写真3におむつをたたむ様子を示す。


また、辰元病院では職員アパートが用意されてあり、障害者のうち3名は、現在職員アパートに住み込みで働いている。部屋はそれぞれの希望を聞き、部屋割りされている。職員アパートと職場は隣接しており、普段の生活から声かけされ、見守りが行われている。休日は、それぞれ自由な活動時間になっており、バス等を用いて宮崎市街地のデパートへ買い物に行くことが楽しみの一つとなっている。
このような自立した生活ができるために、辰元病院ではいくつかの決まりごとを作って実施している。その一つは無駄使いをしないようにお小遣いの管理、そしてもう一つは外出の際の報告である。写真4に外出記録簿を示すとおり、行き先と帰りの時間を必ずノートに記入するようになっている。当初は必ず2人以上での外出しか認めていなかったが、現在では一人でも行けるようになった。自立を目指したこのような取り組みは、それぞれが責任を持った行動ができることに繋がっており、評価できる。
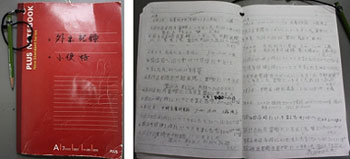
4.取り組みの効果
障害者を雇用しているからといった特別な取り組みをしている意識は職員のほとんどがなく、職員の一人として自然に対応されているということであった。障害者にも当然、その意識はない。職員間の友好を深めるためにこれまでに様々な催し(例えば誕生会、慰安旅行、カラオケ大会、大忘年会など)が企画され、職場以外での職員との繋がりもあって、みんなと打ち解け合っている。現在も年に2~3回行われる職員が患者に行う「お楽しみ会」では、職員と一緒に参加し、練習に励んでいる。
病院にはたくさんの職種がある中で、最も地味な仕事を大事に行っている障害者の姿は、職員みんなの信頼を得、みんなの模範にもなっている。遅刻、欠勤はほとんどなく、体調が悪い人がいれば交替し、優しく思いやりのある、ボランティア精神旺盛なその態度は見習うべきものがある。ひたむきに黙々と働くその姿は、多くの職員に愛されているということである。
自立に向けての取り組みでは、職員アパートを出て、自宅通勤をしている障害者もいる。自宅で炊事、洗濯、掃除をするなど、正に独り立ちしていると言ってよい。また、仕事の幅も広がり、ヘルパーの助手ができる障害者もおり、ヘルパーも特別視せず、同僚として一緒に作業ができている。
5.今後の展望と課題
辰元病院は、周りが田んぼに囲まれた田園地帯で、病室からは天ケ城というお城が見える眺めの素晴らしいところにある。患者にとっても気の休まる静かなところであろう。
そうした辰元病院の創始者である前理事長の辰元忠氏は、障害者の雇用に関して非常に関心を持った人で、その精神が現在の辰元病院に生きている。冒頭に書いた障害者雇用の基本的な考え方がそれで、「人の心」を大切にした共に分かち合えるための支援となっている。
職員の方への障害者雇用に関しての取材で、「何か取り組みをしていますか?」という問いに対して、「別に何もしていない。」という返答がほとんどであった。障害者の方々に話を聞くと、自分の考えや意見など思ったことを素直に伸び伸びと発言し、職員の方と親しく話されている様子が伺えた。辰元病院の障害者雇用の基本的な考え方にある「人の心」を大切にするということを前提に、それが職員の方の答えとなり、両者のなんら変わらぬ会話を生んでいたのだろう。
福祉の専門家集団である辰元病院は、職場定着するための能力に応じた適性配慮、そして職員と融合した充分な障害特性へのサポート、さらに障害者の相談及び組織の充分なフォローを念頭に障害者雇用がしっかりと実践されていることがわかった。
今後の課題には、やはり高齢化である。現在雇用している従業員の退職後の対応について身元引受人との連絡と協力が必要になってくる。また、長年勤務している職員が多いため、新規の障害者雇用がここ数年は行われていない。これからも「人の心」を大切にした共に分かち合えるための支援に向けた取り組みが継続して行われることを期待する。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











