活躍の場が少ない知的障害者の働く場の創出に向けた取り組み
- 事業所名
- 明電ユニバーサルサービス株式会社
- 所在地
- 群馬県太田市
- 事業内容
- a)工場敷地等の緑化維持管理受託
b)リサイクル品改修業務委託
c)清掃業務受託 - 従業員数
- 43名
- うち障害者数
- 21名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 21 緑化、リサイクル、清掃 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用への取り組みの背景
(1)事業所の概要
| ① | 2006年1月設立(特例子会社認定 2006年5月) |
| ② | 資本金 1,500万円{ 株式会社明電舎の特例子会社 } |
| ③ | 理念:障害というハンデキャップよりも才能を重視し、属性(障害、年齢等)に関係なくやる気や能力のある人に活躍してもらえる企業を目指す=ユニバーサルスピリット |
(2)障害者雇用への取り組みの背景
| ① | 障害者雇用の考え方 |
親会社明電舎と特例子会社明電ユニバーサルサービスとが連携して法定雇用率の達成を目指す。
親会社では、雇用対象を身体障害者とし、新規・中途採用も含め今後も継続して身体障害者を雇用する。
特例子会社では、活躍の場が少ない知的障害者を雇用対象とし、各地の製造拠点への支店展開等の拡大・拡充を進めて雇用の拡大を図る。
2010年度(6月1日時点)には、障害者雇用率が1.95%となり、法定雇用率を達成した。
| ② | CSR経営の推進 |
明電グループは中期経営計画「POWER5」の中で、「CSR経営の推進」を基本方針のひとつとして定めている。CSRを経営戦略として推進し、社員一人ひとりの行動に根差している状態を目指している。社会的責任を果たそうということが、きちんと明文化して掲げられているため、障害者雇用担当者は社内で障害者雇用に向けた取り組みを展開しやすいことも大きなポイントである。
2. 取り組みの内容
(1)募集・採用
長期安定就労を目標とし、地域の支援機関と連携しながら、丁寧な募集・採用活動を展開している。具体的には、管轄ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等と連携し、事業所見学、1~2週間の職場実習、面接、採用、ジョブコーチ支援の活用等を通じて、長期安定就労につながるよう努めている。
(2)障害者の業務・職場配置
明電舎では、重量物の取り扱い等危険を伴う作業があるため、障害者雇用のしづらさを感じていた。そこで着目したのが、群馬県太田市にある太田事業所の17ヘクタールに及ぶ広大な敷地である。敷地面積の32%に当たる5.5ヘクタールを緑地、屋外運動場、広場等が占めている。それら工場敷地内の緑化維持管理業務の社員として知的障害者を雇用することとし、5名の採用を皮切りに障害者雇用の拡大を図ることとなった。
障害者の雇用にあたっては、障害者を仕事に適合させようとするのではなく、一人ひとりの長所や興味に応じた業務・職場配置の工夫をしているのが、当企業の大きな特色と言える。これは、米国で1990年代前半に生まれたIPS(Individual Placement and Support)と呼ばれる、就労支援に焦点を当て開発された科学的根拠に基づく援助プログラムに通じるものである。IPSでは、本人の「働きたい」という希望に基づいて、本人の好みや長所に注目した支援を展開する。「知的障害者一人ひとりの特性に配慮しながら、よく観察して、長期的視野で係わっていくことが何より大切なこと。さもなければ、彼らのことを理解し始める前に、破綻してしまう」という現場責任者の言葉が印象的である。
2011年6月1日時点では、全4事業所(太田、沼津、名古屋、東京)に展開し、緑化の他に、清掃、リサイクルといった業務を手掛けるようになった。
なお、2010年度には、太田事業所が緑化優良工場等表彰制度に基づく「財団法人日本緑化センター会長賞」を受賞した。この受賞により、知的障害のある社員の間に、「私たちの仕事が会社や地域の役に立っている」「きれいにすると、みんなが喜んでくれる」という実感が生まれ、働く上でのモチベーションの向上につながっている。


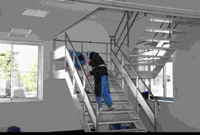

(3)職場適応を支援するための取り組み
明電ユニバーサルサービスでは、知的障害者の職場適応を支援するために、60歳以上のOB社員等が「指導員」として共に働いている。20代、30代を中心とする知的障害のある社員とは親子ほどの歳の差があり、まさしく親子同士のような温かい関係が形成されることを期待しての取り組みであったが、相性は予想以上に良好とのこと。
知的障害のある社員一人ひとりの特性や、前日の様子なども踏まえた対応ができるよう、毎朝ミーティングを行い、指導員間の情報共有に努めている。
また、指導員の目が届く環境で作業を遂行しているため、何らかの問題が発生した際には、すぐに対応することができるようになっている。
(4)支援機関との連携
地域障害者職業センターや、障害者就業・生活支援センターといった支援機関を活用している。また、設立当初は知的障害者への対応方法が分からないことから、地域の知的障害者福祉工場や、障害者雇用事業所などを訪問視察して、理解を深めていった。初めは、障害のある社員へ「お客様対応」をしていたが、共に働く中で、だんだんと「障害のない人と何ら変わりはない」と感じるようになった。障害のある社員の欠勤の少なさには本当に感心しているとのこと。
(5)障害者雇用が成功した秘訣
①徹底した障害者中心主義
明電舎では、特例子会社設立にあたって「誰のためにある会社なのか」「どこに軸を置くべきなのか」を熟考したという。その結果、明電ユニバーサルサービスは、障害者を中心にした事業展開を目指すことになった。
「仕事ありき」でなく、「障害者ありき」という考えが根底にあり、例えば親会社の本業(発電機の製造等)と直接的には関連のない業務を、特例子会社の事業としたこともその一端を示すものである。親会社の本業と関連のある業務を担うことになると、ノルマやクオリティーを要求される。緑化や清掃といった、親会社の本業とは一線を画す業務を担うことにより、障害者の雇用や処遇を最優先にした指導・配慮が可能となっている。
障害者への配慮の一例として、就業時間の設定をあげることができる。所定の就業時間について、同じ敷地内にある親会社は7時間45分であるが、特例子会社では7時間15分と定めている。これには、特例子会社の社員が出社する時間帯を、親会社の社員が数多く出勤する時間帯と重ならないようにする狙いがある。太田事業所にはマイカーを運転して通勤する社員もいることから、親会社の社員が運転する車で混み合う時間帯をずらすことで、事故などのトラブルや、それによるパニックなどのリスク軽減を図っている。
事業の収支についても、黒字を達成することは最初から考えていなかったという。短期的には赤字であっても、障害のある社員の技術や仕事量が向上し、長期的にプラスマイナスゼロになれば良いと考えている。
②親会社社員の特例子会社への出向
現場責任者および総務・人事担当については、親会社明電舎からの出向社員を配置している。このことにより、現場責任者や総務・人事を担当する社員が、親会社と特例子会社について、どちらか一方ではなく、両方のことを理解し、バランスよく配慮・関与することができている。
③設立初期から支援機関を活用
特例子会社設立当初から地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター等の支援機関を活用した。群馬障害者職業センターと連携して、雇用開始と同時にジョブコーチ支援を活用して職場定着の促進を図っている。また、障害者支援センターわーくさぽーとと連携して、求職中の知的障害者やその家族を対象とした事業所見学や職場実習を実施した。生活面の悩み等についても、障害者支援センターわーくさぽーとの就労支援ワーカーに相談し、支援を要請している。
3. 今後の展望と課題、障害者就業・生活支援センターの係わり
(1)今後の展望と課題
①障害者雇用の促進
中期経営計画「POWER5」に沿って2013年までに障害者雇用率2.0をクリアする!(親会社との協働)
※2011年6月時点で達成(2.09%)
②雇用拡大のための新規業務取り込み
- 受託業務開拓の取り組み
- 職業能力開発、訓練の充実
③長期安定就労への取り組み
- 安全・衛生教育の充実
- 福利厚生、社内イベントへの参加
このほか、障害のある社員の高齢化や、地域社会への貢献を進めることについても、今後検討・対応していきたいとのこと。
(2)障害者就業・生活支援センターの係わり
平成17年、「太田に特例子会社ができるらしい」という話を耳にして、明電舎太田事業所を訪問したのが、明電ユニバーサルサービスとの最初の係わりだった。「知的障害者を雇用して、緑化作業員として活躍してもらいたい」「特例子会社を設立して障害者雇用の拡大を図りたい」との意向を受け、明電舎と障害者支援センターわーくさぽーとは、知的障害者の雇用、そして特例子会社の設立という最初の目標に向かって、タイアップして取り組んでいくことになった。
特例子会社の設立期から係われたことは、障害者の就労を支援する者として、大変勉強になり、知的障害者5名の雇用を同時に開始するダイナミズムを感じることができた。
まず、当事業所に対して行ったことは、事業所見学そして1~2週間程度の職場実習の提案であった。面接だけで採否を決めることは、本人・事業所双方にとってリスクがあることを伝え、この提案を実施することになった。最初に、障害者支援センターわーくさぽーとの登録者から見学希望者を募り、事業所見学を実施。構内の見学や、従事する仕事の内容等について説明を受けることで、見学後応募に至らなかったとしても、知的障害者にとっては実際の企業・仕事に触れることのできる数少ない貴重な機会となり、企業にとっても、様々な知的障害者の態様を知る機会となることを期待した。
見学後、入社を希望した人を対象に職場実習を実施。職場実習においては、面接だけでは見えてこない、希望者の様々な面が見えてきた。緑化作業の実習を行って、初めて草花へのアレルギーがあることが判明して入社を辞退したケースもあった。実習後、当事業所の仕事に対応可能と判断されながら、これまで在籍してきた通所授産施設を退所して企業に入社することに対して、本人・家族がためらったケースもあった。リスクを軽減し、本人と企業双方が納得した上での雇用となるよう、個別の事情に合わせて、実習期間を延長したり、家族に実習に取り組む本人の様子を見学に来てもらったりしたこともあった。
会社が設立された平成18年には、職場実習を経て5名の知的障害者が採用されることとなったが、当企業にとっては初めての採用であり、なおかつ知的障害者を複数名雇用することから、雇用管理、作業指導、人間関係の調整などで少なからぬ苦労が予想された。そこで、職場適応援助者(以下、ジョブコーチ)の活用を提案した。群馬障害者職業センターから派遣されたジョブコーチは、支援体制の構築に向けて、個別の状況に応じた作業方法や手順に関する助言、人間関係の調整、知的障害・自閉症・てんかんなどの障害特性や対応方法に関する説明等を実施。以来、当事業所では、新たに障害者を雇用する際には、ジョブコーチ支援を活用している。
また、職場以外の生活場面における問題が、就業に大きな影響を与えてしまうことがある。こうした場合には、障害者支援センターわーくさぽーとが状況把握や家庭との連絡調整等を行っている。健康管理、身だしなみ、交友関係、通勤途上でのトラブル、福祉サービスの利用等問題は様々。
今後、太田市内の福祉施設に通所する障害者10数名の職場見学を受け入れることも決まった。これは、当事業所への就職を目的としたものではなく、福祉施設を出て一般企業へ就職を目指す障害者を対象とした社会訓練の一環である。働く意欲のある障害者が、実際に企業で働く障害者を見る機会は大変貴重であり、明電グループが目指す地域社会への貢献の一つの形と言えるだろう。
障害者支援センターわーくさぽーと 就業支援ワーカー 三浦 裕幸
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











