精神障害・知的障害者を雇用して~支援機関との協働で障害者をサポート~
- 事業所名
- 医療法人見松会 あきやま病院
- 所在地
- 長崎県諫早市
- 事業内容
- 精神科病院
- 従業員数
- 228名
- うち障害者数
- 4名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 3 看護助手 精神障害 1 看護助手 - 目次

- ホームページアドレス
- http://www16.ocn.ne.jp/~a_hp/
1. 事業所の概要と障害者雇用の経緯、背景
(1)事業所の概要
昭和34年7月「諫早精神科病院」として90床としてスタートした。その後数回の増床を行った。施設等の老朽が進行したため、平成14年4月、現在地(目代町)に移転新築し「あきやま病院」と改称し、同時に増床(354床)を行い新たにスタートした。
諫早市の郊外の美しい自然に囲まれた高台に位置して、南フランスのホテルをイメージした設計で、これから直面する高齢化社会・ストレス社会に向けて、十分対応すべく、認知症病棟、アルコールストレスケア病棟など、機能分化した病棟構造になっている。
「人にやさしく、自然にやさしく、地域に根ざした病院」を基本理念にしている。平成15年には、旧病院跡地に診療所を開設して、アルコール専門外来やもの忘れ専門外来など専門外来を開設している。
(2)障害者雇用の経緯、背景
元来当該施設は、当院へ入院している患者の退院支援を行っていて、退院後の社会復帰を考え企業への就職先の開拓又当該医院へ雇用ができないものか理事長以下、全職員スタッフの検討事項であった。
当該法人の関連施設(社会福祉法人・特別養護老人ホームしろみ)が障害者雇用をハローワーク等の活用にて積極的に行なっており、トライアル雇用後、常用移行して他職員の対応もスムーズにできている現状を担当施設長より各種情報を入手した。また雇用後の職務の創出として現在スタッフが担っている仕事を障害者に一部担当してもらうことで、現スタッフがさらに患者への充実したケアが提供できるのではないかとの考えがあった。このような事例を参考に当院でも積極的に障害者雇用に力を入れる結論となった。全職員へ雇用受入れに関して意識が浸透していき職場環境体制づくりへつながっていった。
まずは、各セクションに障害者を雇用した場合、職務の創出先として、又特性を配慮してどのような仕事があるのか検討を行った。各セクション担当者が持ち寄った意見を検討した結果、看護助手が担っていた院内の清掃・リネン(洗濯)業務がベストではないかとの結論に至った。
その後、ハローワークの障害者担当官へ相談を行い又、障害者就業・生活支援センターからの紹介や福祉施設からの職場実習、見学等の受入れを行った。ハローワーク担当官からの参加要請があり諫早地区で開催さる「障害者合同面接会」に参加し、障害者と直接面談を行った。障害者就業・生活支援センター等の勧めもあり、面接の結果6名(知的5名・精神1名)の障害者をまずは職場実習として受け入れを行った。
職場実習の受入れ先として院内の清掃及びリネン(洗濯)の各業務に就かせた。1名は1日でリタイアしたが、5名は約1か月の実習を無事終了し、その後トライアル雇用制度を導入した。3ヶ月のトライアル雇用終了近くにハローワーク障害者担当官、障害者本人(親権者も同席)、当院担当者を交えてケース会議を開催した結果、4名が常用移行の結論となり雇用の継続に至った。
2. 障害者の従事業務、職場配置
常用移行後の4名の障害者は、看護部に所属し病棟内各施設の清掃業務及びリネン(洗濯)の各業務に従事している。当該施設は郊外に位置しており通勤に関しては公共交通機関の便が悪く通院者等の送迎バスを利用している。
Aさん 精神障害者手帳3級 統合失調症
[雇用条件]
- 配置先は認知症病棟に所属。主に洗濯場の責任者を担当している。
- 勤務形態は月~金、9:45~15:45、土曜は、10:45~16:45までの勤務。
- 発病前は就労歴もあり、当院雇用前にも、社会適応訓練事業や就労継続A型で就労トレーニングを行っていたので担当業務はスムーズに対応できると思っていたが、今まで経験した事のない業務(清掃業務)だったためか、実習初期では「続けきれない」との本人の弱気な発言が聞かれたため、配置転換(洗濯場)を行った。配置転換がよかったのか、その後は本人の弱気な発言もきかれず、勤務態度も真面目であり又担当業務も丁寧に行い他職員からのクレーム等も発生せず良好な職場環境を維持している。

Bさん 療育手帳B2 知的障害
[雇用条件]
- 配置先は認知症病棟に所属。病棟内の清掃や洗濯、患者様の食事の配膳下膳などを担当している。
- 勤務形態月~金は、9:45~15:45、土曜は、10:45~16:45までの勤務。
- 当院雇用前は、一般就労経験はないものの、通所授産施設を利用していた。勤務態度、就労態度等に問題はなく積極的に仕事に従事する姿勢がみられる。施設利用者及び他職員の好感を得ている。
Cさん 療育手帳A2 知的障害
[雇用条件]
- 配置先は認知症病棟に所属。病棟内の清掃や洗濯、患者様の食事の配膳下膳などを担当している。
- 勤務形態月~金、9:45~15:45まで勤務。
- 当院雇用前は、一般就労経験はないものの、通所授産施設を利用していた。重度の知的障害ということもあり、継続して就労できるか心配だったが、任された仕事はキチンとこなしている。実習当初はあまり発語もなかったが、最近では自ら他のスタッフに話しかけたり、敬語もつかえるようになった。業務内容も慣れつつあり本人の努力が第一であるが他職員の理解、協力等が下支えとなっている。
Dさん 療育手帳B2 知的障害(障害者職業センターで重度判定)
[雇用条件]
- 配置先は精神科老人病棟の清掃業務を担当している。
- 勤務形態月~金、9:45~15:45までの勤務。
- 当院雇用前は、一般就労経験はないものの、就労支援事業所を利用していた。いつもにこやかな笑顔でスタッフ及び患者からの評価もよい。担当業務に関しては毎日指導スタッフからの指示のもと行われているが目が離せない日々の連続である。

3. 取組内容
障害者雇用に至るまでを時系列的に紹介する。
*障害者の導入前(平成22年1月~2月)
| ・平成22年1月 | ハローワーク障害者雇用担当官の専用窓口へ相談。 障害者就業・生活支援センターへの相談。 福祉施設より職場見学の受入れ(諫早市の就労継続B型)。 職域開発の検討。 |
| ・平成22年2月 | 諫早地区障害者合同面接会への参加。 職域選定の検討。 院内カンファレンス(実習生に関する情報共有)。 |
職域開発を検討し、関係機関への訪問・見学や福祉施設等から見学の受入れをし、障害者合同面接会への参加等を行った。まずは職場実習の形態で受入れを開始し、各人のストレングスポイント、ウィークポイントを現在利用している施設のスタッフから情報を得て、各情報を整理し、直接かかわるスタッフとの情報共有を図った。その時に「ストレングスポイントを活かし、ウィークポイントには適切なサポートをし、継続して実習ができるよう支援していく事」を確認した。
*職場実習の受入れ(平成22年3月)
| ・平成22年3月 | 職場実習を開始した(就労前訓練など)。 トライアル雇用の制度説明及び導入会議を行った。 |
受入れ予定者個々の職場実習プログラムを作成した。各病棟の指導、教育担当者をきめた。職場実習障害者に対しては、日誌を記載してもらい、何ができたのか、何が難しかったのかを振り返ってもらった。その日誌を元に、翌日の教育、指導にあたる判断資料とした。
各病棟の担当者には、数回に分けて実習生の評価(職業意識・生活習慣など)、報告を指示した。
- 参考資料

*トライアル雇用の導入(平成22年4月~6月)
| ・平成22年4月 | トライアル雇用の開始。 カンファレンス実施。 |
| ・平成22年6月 | トライアル雇用終了会議の開催。 |
トライアル雇用期間中は、個別カンファレンスを実施。作業スケジュールや作業手順がわかりやすいように目に訴えるために掲示して対応した。
トライアル雇用がスタートしてから障害者職業センターの職場適応援助者の支援計画の活用を行い、支援計画書に基づきジョブコーチが各人につくようになった。障害者本人だけでなく、指導する病棟スタッフにも、指導方法を助言してもらうことができた。
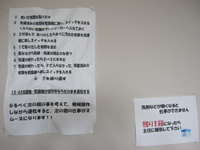
*正式採用後(平成22年7月~)
トライアル雇用期間中からジョブコーチ支援の活用を行い、支援事項及び支援計画の経過に関する会議を以下のように開催した。
| ・平成22年9月 | 第1回ジョブ会議 |
| ・平成22年12月 | 第2回ジョブ会議 |
| ・平成23年3月 | 第3回ジョブ会議 |
| ・平成23年7月 | 第4回ジョブ会議 |
会議内容及び検討事項として
各対象者も配置先の職場環境、人間関係等にも慣れ業務に関してミス等なく推移してきたが、時間の経過とともに緊張の糸がきれた事が原因なのか、担当業務が今までできていた事が雑になったり、ミスが発生して通常業務から逸脱する事が多くなった為、対象者各人の業務不備内容等に関するデータを参考に、3ヶ月に1度本人及び配置先担当スタッフが集まり、業務内容の振り返りなどを行ない、再度作業手順の見直し及び業務内容に見られる雑な部分、ミスの発生箇所の確認を行い指導、教育を行った。
- 参考資料

4. 取組の効果と今後の課題
(1)取組の効果
障害者の雇用に際して、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター等の関係機関の支援をうけ、職場実習、トライアル雇用を経て4名が就労している。各対象者の配置先における担当スタッフとの業務遂行内容等に関してのトラブルが多々あったが、ジョブコーチ等との定期的なカンファレンスを実施することで問題点の解決に対応が出来た。
対象者の配置先で直接指導、教育する病棟スタッフは、「どう指導したらいいのかわからない」「指導したことで辞めたらどうしよう」との葛藤もあり、対応の方法等の経験がない職員が殆どであり障害者にどのように接したらいいのかわからないとの声も多くきかれたが、定期的なジョブコーチ等の訪問により、障害者及び事業主の担当指導スタッフや他職員対しても助言をしてもらうことができた。
- 職場実習の効果として
各障害者の選定された職域での職場環境、特に人間関係づくり又担当業務の手順をある程度習得できた。 - ハローワーク(トライアル雇用の活用)の効果として
障害者雇用担当官の制度等の説明、障害者への対応方法の助言をいただいた。 - 障害者合同面接会への参加の効果として
会場で多数の応募者に面接が即座にでき対応ができた。 - ジョブコーチ支援の効果として
対象者支援に関しては支援事項、支援計画に沿って行われ、本人の業務手順の確認が出来た。各人の特性を考慮した支援内容であり受入れ側として大変感謝している。
事業主支援に関しては配置先担当スタッフの行動がより明確になり、指導・教育等に関しての助言を頂き、他職員又対象者へ対するコミュニケーションがスムーズに行われる職場環境を構築できた。
(2)今後の課題
本格的に障害者雇用に向けた取組みはスタートしたばかりであり、又事業所全職員の障害者の特性の理解、雇用受入れに関しての理解が得られる職場環境作りもスタートしたばかりである。現在就労している障害者の受入れ経過を基本にして、又現在就労している障害者の問題点等を集約して、今後の障害者雇用の参考にしたい。
現状では、障害者を雇用する計画は未定である。当面の課題として、現在就労している4名の職場定着が最優先課題である。その為にも、障害者雇用受入れに際しての働きやすい職場環境づくりに全職員の理解、努力が求められる。また、従来まで問題点の発生時はジョブコーチ等の他関係機関に助言等を求めていたが、将来的には事業所全職員の総力で対処していく。
リハビリテーション部 医療福祉相談課 御堂 和貴
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











