障害に配慮した雇用で地域に貢献
~関連機関との連携で企業の社会的責任を継続~
- 事業所名
- 株式会社秋田新電元
- 所在地
- 秋田県由利本荘市
- 事業内容
- 半導体素子製造(ダイオード、サイリスタ等の製造)
- 従業員数
- 763名(2011年12月1日現在)
- うち障害者数
- 18名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 2 金属プレス作業、社内清掃 肢体不自由 4 一般事務、製品外観、部材運搬 内部障害 1 構内清掃 知的障害 11 部材運搬 精神障害 - 目次


1. 事業所の概要
当社は新電元工業グループ半導体製品の製造拠点として1970年(昭和45年)に秋田県本荘市(現由利本荘市)に設立以来40年余り、「独創技術を活かした新しい価値創造」を基本理念に、お客様のニーズにあった多くの半導体製品を世の中に送り出してきた。工場規模も本社大浦工場に加え飛鳥工場をラインアップするに至ったことは一重にお客様の信頼とご愛顧の賜物と深く感謝申し上げる次第である。
21世紀が到来し、世の中は急速にマルチメディア社会へと進行している。また「環境」が重視され環境対応車や省エネ機器、さらに新エネルギー分野での開発・商品化が活発に行われている。これらに使用される電子機器の需要は更に拡大の一途をたどるものと思われる。
この電力変換、電力制御を行うパワーエレクトロニクスの心臓部とも言える基幹部品が「パワー半導体」である。私たちはこれまで培って来た独自の製造技術・品質管理技術・要素技術を更に磨き、高効率・高速化・高破壊耐量化・複合化・小型化などの半導体製品として、シリコン整流素子、サイリスタ、トランジスタ、ハイブリッドIC、チップ等の半導体素子の製造及び新製品の研究開発や生産設備の自社設計を行っている。
そういった中、2008年にはISO/TS16949の認証取得により高いレベルの品質管理体制の充実を図り、また環境面においては1997年にISO14001の認証を取得し、「地球温暖化防止」、「廃棄物の削減」、「環境負荷の低減」、「環境に良い製品開発」、「グリーン調達」等を設定し、全社をあげて積極的に取り組んでいる。
当社は柔軟な発想と情熱を持って、産業の米「半導体」の限りない可能性をどこまでも追求し新しい道を切り開らき、社会と共に、お客様と共に、そして従業員と共に成長を図ると共に、これからもお客様のエレクトロニクスビジネスに貢献していく。
- <社是>
人は品質及び生産性向上の源泉であり最も大切な資産である
成功への鍵は品質と納期を守ることにより
顧客の信頼をかち取ることである - <品質方針>
私達は、社会や環境との調和を図りながら
お客様の要求する品質を提供し続けることにより
お客様の満足と信頼の確保を追求する
2. 障害者雇用の経緯、背景
障害者を雇用した当初は身体障害者の採用であったが、これは新卒者や即戦力となる中途採用者がたまたま障害者であったということであり意図的に採用した訳では無かった。
しかしながら、当時、障害者法定雇用率について達成出来ていない状況にあり、また、「社会と環境との調和を図る」当社の方針もふまえて改善していく必要があった。
そういった中、特別支援学校から求人の依頼があり、1997年4月に初めて知的障害者1名を採用した。この知的障害者の採用により、作業遂行力をふくめ身体・知的両障害者への社内全体の理解も深まり、同年に更に2名(知的障害者1名、身体障害者1名)を中途採用した。
その後も地域及び社会貢献の一環として、地元で求職活動をしている障害者をハローワークと連携し、協力を得ながら定期的に採用し、2004年には当面の目標としていた法定雇用率を上回る事が出来、それは現在も継続している。
また、採用にあたっては、障害の種類は特に問うてはおらず、作業遂行能力を基本的な判断基準としている。
今後も引き続き障害者の雇用および働き易い職場環境づくりを継続していくものである。
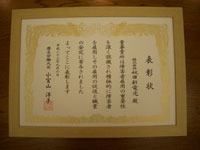
厚生労働大臣賞受賞
3. 取り組み内容
(1)障害者の従事業務、職場配置
障害の種類に応じて、障害者が作業上負担とならないような障害に適した作業配置を考慮し決定している。(一部の作業者除く)
| (例) | 聴覚障害: | 手話や筆談・口話で十分意思疎通ができるため、場内作業の中では比較的音量が高くなる金属加工作業に従事している。 |
| 肢体障害: | 障害程度に応じて一般事務、製品外観といったデスクワーク中心の作業に従事している。 | |
| 知的障害: | 職場の責任者が援助者となり、作業指導を行いながら、製造工程への部材(樹脂・フレーム・薬品・梱包材等)の供給および廃棄物回収(運搬)といった比較的身体を使った作業に従事している。 |
※ 雇用比率の最も多い知的障害者においては、
- ① 一つの部署に同じ障害のある従業員同士を配置させる事により、お互いに様々な情報を共有し合ったり、私生活を含め気軽に話し合える環境にあり、いつでもコミュニケーションが取れる職場環境となっている。
- ② バーコード管理等の環境整備を図り、作業負担の軽減や効率化等を推進している。
障害者の具体的作業内容(事例)
| ① | 部材運搬・回収作業(知的障害者) 製造工程で使用するリードフレーム、接続子、モールド樹脂、フレーム巻き用リール、各種薬品、梱包材等といった各種部材について、定期的に資材倉庫より出庫し製造工程内へ供給している。 また、各工程から排出されたフレーム切断屑、樹脂スクラップ屑、使用済薬品廃液、プラスチック、スポンジ、ビニール類等のRDF向け廃棄物の回収・廃棄作業も行っている。 尚、出庫については、バーコード管理する事により各部材に付けられているバーコード表示を読み取り、また各自に割り振ってある個人バーコードを読み取る事により、数量を数えたり出庫者の名前を記入しなくても自動的に処理される為、数量の数え間違いや記入(入力)ミスという事がなく、作業者の負担軽減に役立てている。 |
| ② | 製品収納マガジンのストッパー取付作業(知的障害者) 製造工程で使用する製品を収納するマガジンの片側に、収納した製品が落下しないようにストッパーを取り付け製造工程に供給している。 |
| ③ | 製品収納ケース組立・バラシ作業(知的障害者) 工程から出荷されるウエーハやチップを収納する為のケースを組み立て、製造工程に出庫したり、使用済みケースを素材ごとに分別し廃棄を行っている。 |
| ④ | 金属加工作業(聴覚障害者) 製造工程や生産設備内製等に使う金属部品を、機械を使い切断、面取り、研磨等を行い、依頼部署へ出荷している。 |
| ⑤ | 製品外観作業(下肢障害者) 製造工程で生産された製品を、机上にて顕微鏡を使い目視外観した後、良品判定された製品を次工程に供給している。 |


(2)障害者職業生活相談員資格の取得
知的障害者の所属する職場の管理監督者や人事担当者に対し「障害者職業生活相談員」の資格を取得させる事により、障害者のスキルアップや公私にわたる相談にも対応出来るようになり、障害者が安心して仕事や生活が出来る環境にもなっている。
(3)特別支援学校生の工場見学及び実習生の受け入れ
ここ数年来、地元の特別支援学校に対し学生の工場見学や1~2週間程度の期間にて職場実習の受け入れを行なっている。
また過去の実績として、職場実習受け入れした学生を新規採用もしており、地元地域社会にも貢献している。
(4)障害者支援会議への参画
地元地域の行政、社会福祉団体、学校、企業で構成する障害者支援会議に積極的に参加し、障害者への理解を深めると共に意見交換を行い、障害者が働きやすい職場環境整備や作業改善に努めている。
4. 取り組みの効果、障害者雇用のメリット
障害者の雇用に力を入れ10年近く経過したが、当時採用した従業員は殆ど現在も勤務中である。
これは、配属された職場の上司や先輩が、当時は障害者に対しどのような対応を取るべきなのか、どのような配慮が必要なのか分からないままとにかく親身になって指導し、配慮ある対応をした結果、信頼関係が形成され不安も解消され、仕事がしやすい、居心地がいい、長く勤めたいという意識が芽生えた事によるものではないかと思われる。
また、長く勤務している事により、新たに障害者が入ってきた場合も、今までの経験を生かし同じ障害を持った者が実務作業を教える事により、障害のない従業員が指導するよりも更に分かりやすく説明してくれる為、習熟も早いように感じている。
作業においても、知的障害者が多い部材供給作業を例に取れば、部材の出庫・運搬・回収等、一見単純な作業に感じられるが、その日の出庫数や種類によって必要な部材の数、種類が異なる事から、各自で必要な部材を判断し出庫しなければならず神経を使う作業であるが、熟練者ともなれば殆ど間違える事はなく、生産に支障をきたすこともなく貴重な戦力となっている。
こういった事からも、仕事に対しやる気や責任を持って取り組んでいる様子が覗え、「責任感の醸成」と「コミュニケーション」が障害者が生き生きと働ける職場づくりの基本と考えている。
その他の業務についても、殆どの作業が内容的には障害のない従業員と区別なく行っている事からも、障害者の一人ひとりが当社の従業員である自覚と仕事に対する責任感を持って取り組んでいると感じている。
その為、仕事を与える職場の上司も極度に負担の掛からない作業を与える事により、やる気と緊張感を常に持たせ、就業意欲を高める工夫をしている。
更に、障害者の特性をしっかりと理解し配属することで、質の高い正確な仕事が集中力を切らすことなく行われ、それは企業、障害者の両者にとって付加価値が増すものと思われ、またこの事が障害のない従業員の意識向上や自覚にも波及されているものと思われる。
また、障害者を雇用したことにより、雇用当初は一時的には障害のない従業員とのコミュニケーションに課題もみられたが、部門内や他部門をふくめて報告・連絡・相談の励行や責任感の醸成に向けて総務部門の担当者や所属部門の責任者による適切な指導していった結果、現在は全社的にコミュニケーション意識が高まり、障害者の業務への意欲的な取組は全従業員の励みにもなっているものと理解している。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











