最高の販売体制を支えるひとつのチームとしてのダイバーシティ戦略
2011年度作成
- 事業所名
- 株式会社髙島屋横浜店
- 所在地
- 神奈川県横浜市
- 事業内容
- 百貨店業
- 従業員数
- 1,665名
- うち障害者数
- 24名
障害 人数 従事業務 視覚障害 2 スタッフ・販売 聴覚障害 肢体不自由 3 洗場・販売・スタッフ 内部障害 6 売場支援・スタッフ・販売 知的障害 13 洗場・作業(売場)・作業(後方支援) 精神障害 - 目次

事業所外観
1. 事業所の概要
株式会社髙島屋は、1831年(天保二年)創業で、現在181周年を迎えた。
- 経営理念
髙島屋グループの経営理念「いつも、人から。」に込められた「人の心を大切にする」という精神は、企業活動を通じて、社会に貢献していくことこそが、企業のあるべき姿であるという考えが基本にある。髙島屋グループが目指すべき方向性は、次の5つである。① こころに残るおもてなし
② 未来を切り拓く新たな生活・文化の創造
③ いきいきとした地域社会づくりへの貢献
④ 地球環境を守るためのたゆまぬ努力
⑤ 社会から信頼される行動 - グループ全体での障害者雇用
各店舗ごとの取り組みとなっている。髙島屋グループにおける障害者雇用の取り組みは、2011年社団法人大阪雇用開発協会から「障害者雇用優良事業所」表彰を受賞した。今回は、横浜店の取り組みを取り上げて紹介する。 - 横浜店は、1959年(昭和34年)に横浜市西区に開店した。
- 障害者雇用の経緯
30年以上前からそれぞれの売場・部門に所属させ、販売や後方スタッフとして業務に配属していたが、仕事とのマッチングに注目した場合、適切な仕事を提供できていないケースがあった。そこで業務を見直すとともに新しい雇用スタイルとして2007年3月から新たに、知的障害者の雇用促進・職務開発を目的として、総務部人事グループ内に「ワーキングチーム」を設置した。 ワーキングチーム作業場の様子
ワーキングチーム作業場の様子
2. 障害者雇用の形態と業務内容
- 総務部ワーキングチームとは
総務部人事グループ内にあり、知的障害者と企業内ジョブコーチ(第2号職場適応援助者)とのユニットのチームで横浜店独自の取り組みである。ここは、売場の後方支援業務を請け負うことで少しでも売場の販売時間を創出し、お客様へのサービス向上へ繋げることを目的としている。また、売場・部門が残業で行っていた業務や外部に委託していた業務を請け負うことで経費節約の目的も果たしている。 - 主な業務内容

リボンシールカット作業
りぼん作業 印刷作業
印刷作業 米の品だし
米の品だし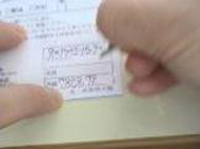 伝票書き作業
伝票書き作業
パン袋作業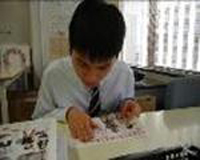 媒体折り作業
媒体折り作業
ハンコ押し作業全員が同じスキルを身につけている訳ではない。得手不得手は日ごろのアセスメントでジョブコーチが把握しており、その評価は日々、本人にフィードバックしている。(詳細は3の③で紹介) お中元カード仕分け作業
お中元カード仕分け作業 - 表彰
平成21年には、障害のある人を雇用し、障害のある人が働きやすい職場環境を作るための努力や独自の工夫を行っている企業(事業所)を表彰するハマライゼーション企業グランプリを横浜市より受賞した。 横浜市長と記念撮影
横浜市長と記念撮影
3. 取り組みの内容と効果
- いきいきと働くための心得
『仕事を通じて人生を楽しむ!』これは働く上で最も大切なことだ。職場でいきいきと末永く働き続けるために、当社では以下の5つの項目を重視した環境作りを行っている。
① 職業人として自立する。
自分で考え、自分で選択し、決定することを習慣化している。業務の組み立ては、各自が行うことが前提であり、スケジュール管理を任せている。② 新しいことに挑戦する。
毎日夕刻には、スケジュールボードにある500枚以上のスケジュール札の中から、「最優先」→「優先」の順に並べておく。翌日の業務を前日に組み立てて見通しを持って一日を終わるようにしていると、翌朝、出勤した時からスムーズに作業に入れるメリットがある。
自分が自信を持ってできる業務について責任をしっかりと果たすことが大事であることを常日頃から意識させているので、できない業務は選択しない。また、同じ業務が重なったり、取り合いになったりすることはなく、「チームにとって、どの業務をすることを優先しなければならないか」をそれぞれが考えて業務を組み立てることができるようになった。選択をする習慣が少なかった人達だが、選択をする機会を作っただけでできるようになった。
また、飛び込みの業務があった場合は、日頃からの「優先順位を考える」習慣が生き、突然の変更にも柔軟に対応できるようになっている。
スケジュール管理
スケジュール札現状に満足せず、常に少し高めのハードル(目標)を設定する。これは、モチベーションを上げる効果がある。③ 作業の基本
同じ業務を繰り返し行うことが十分できる人達だが、その業務だけしかできないのでは可能性の幅が広がらない。常に新しい業務の可能性を試し、可能性がある場合には、確実にできるようになるまで練習を積み、本人が「できるようになった」と実感できれば、スケジュールを作成する際にその業務を選べるようになる。できることが増えると多様な依頼にも応えることができる。依頼主から喜ばれたり、感謝されたりのフィードバックを受けるとモチベーションが上がる。
中には、変化を怖がったり、嫌がったりする人もいるが、それぞれのスキルに合わせて進めていけば何ら問題はない。「できるようになりたい」「認めてもらいたい」という気持ちは持っている人達なので、その向上心の芽をつぶさないように関わっている。1.正確に 2.丁寧に 3.効率よく の3拍子で行う。そのために、品質管理チェックシートやタイマーを使って、作業の成果が上がる工夫をしている。④ 閉鎖的な空間に留まらない。
業務は、自分が責任を持ってできる作業を担当しているが、たまにエラーが起こることがある。そのエラーの再発を防止するために「品質管理チェックシート」を使用している。この「品質管理チェックシート」は、担当業務の際、作業を始める時に、正確にできているかどうか、丁寧にできているかをジョブコーチが確認し、OKサインをする。そのOKが作業のスタートを意味する。シートを有効活用している人は、かかった時間を記入したり、総数を書いたりして、品質保持の努力をしている。
また、タイマーは、効率よく作業するための必須アイテムである。例えば、伝票1束(50枚)を何分で書けるか自分のスキルを試してみることや、今日は5束やったので、自分の平均タイムは何分であると認識することにも使用できる。ただ、効率ばかり意識して、作業が雑になってしまうタイプの人にはタイマーは不要なアイテムである。
作業の基本は3拍子、より高い品質を保持し、心のこもった作業をすることを意識しながらより生産性を上げることを日々心がけて業務に当たっている。 品質管理チェックシートとタイマー人事グループ内の作業場に留まらず、本館へ移動して行う作業、お客様を迎えてする作業など、閉鎖的な空間に留まることなく、社会性を広げる工夫をしている。作業場は、人事グループ内の一角にある。障害者だけの空間ではなく、様々な部署の人が行き交う事務所にあるので、自然と視野が広がる。また、総務部の総合事務所はさらに大きなフロアであり、見られている・見ている適度な緊張感が生む当たり前の感覚が、社会人としての幅を広げる大事な要素になっている。閉鎖的な空間が生む当たり前の感覚に慣れてしまうのではなく、広く社会に目を向け柔軟に対応できる社会人として育てている。⑤ 余暇活動を応援
品質管理チェックシートとタイマー人事グループ内の作業場に留まらず、本館へ移動して行う作業、お客様を迎えてする作業など、閉鎖的な空間に留まることなく、社会性を広げる工夫をしている。作業場は、人事グループ内の一角にある。障害者だけの空間ではなく、様々な部署の人が行き交う事務所にあるので、自然と視野が広がる。また、総務部の総合事務所はさらに大きなフロアであり、見られている・見ている適度な緊張感が生む当たり前の感覚が、社会人としての幅を広げる大事な要素になっている。閉鎖的な空間が生む当たり前の感覚に慣れてしまうのではなく、広く社会に目を向け柔軟に対応できる社会人として育てている。⑤ 余暇活動を応援 総務部総合事務所での作業休日は、ガス抜きを十分に行い、仕事に臨むオンとオフを明確にし、仕事に集中する生活のリズムを応援している。遊びが充実していると、仕事にも集中できる人が多いことから、『遊びは豊かな人生のエッセンス』をモットーとし、社員の余暇を応援している。
総務部総合事務所での作業休日は、ガス抜きを十分に行い、仕事に臨むオンとオフを明確にし、仕事に集中する生活のリズムを応援している。遊びが充実していると、仕事にも集中できる人が多いことから、『遊びは豊かな人生のエッセンス』をモットーとし、社員の余暇を応援している。
社会福祉法人運営の余暇グループに所属している人は、社外の仲間と旅行や食事会を楽しんでいる。また、一日15キロジョギングをする人、書道教室に通う人、プロ野球やJリーグ観戦を楽しむ人などそれぞれが余暇を楽しんでいる。しっかりガス抜きをしていると、多少の職場でのストレスにも耐えることができる。
休日にはテニス
休日には料理教室 - 企業内ジョブコーチの関わり
ジョブコーチは、売場や社内のニーズをくまなく調査し、作業を受注し、障害のある社員に仕事を結びつけたり、社員のスキルアップを支援したり、課題を分析し、作業環境を整えたり、精神的なケアを行う。また、他の部署への出張作業を通して人と結びつけたり、社内での活動(食事・休憩・厚生面)もフォローする。ジョブコーチはいわゆる「通訳」「橋渡し」「影武者」であり、日々、一人ひとりのスキルを見極め、「できること」「できないこと」と業務を結びつけることによって少しずつスキルアップを図っている。【社員食堂利用のサポート】
数千人の社員が利用する社員食堂を重度自閉症の社員が1人で利用できるようになるためには、約30項目の課題をクリアする必要があった。スキルに合わせ段階を追って支援し、できるようになってからはフェイディングしていった。環境を整備する工夫として、混んでいる時間帯を避けた。また、メニュープレートにはルビを振るよう食堂担当者に要望した。昼食は憩いの時間、豊かな休憩が午後の仕事の能率UPに繋がっている。【福袋封入作業】 昼食サポートの様子
昼食サポートの様子
売場や部門が残業でやっている業務について、生産性を向上するためにはどうすれば良いかと常に課題分析を行っている。その中で「ワーキングチームに仕事を頼めないか」という相談が増えている。年末には、福袋封入作業の依頼が初めてあった。「人を貸してほしい」というのだ。 福袋封入作業
福袋封入作業 - 特徴ある取り組み
① 就業体験
横浜の老舗企業として、地域貢献は企業の使命であり、これから障害者雇用を考える企業や事業所の人々・地域の特別支援学校の生徒や先生、保護者・行政職員、福祉関係者、大学生の見学を受け入れている。見学といっても、ただ、障害者が働く様子を見てもらうだけでなく、彼らに教わりながら一緒に仕事を経験するという就業体験を実施している。平成21年~23年の3年間に約1500人の就業体験を受け入れた。② 大阪研修
就業体験は、社員のコミュニケーションスキルを上げる効果もある。作業説明は、自分だけがわかっていても相手に伝わらない。作業の結果を見て、自分の指導が正しかったのか、言葉が足りなかったのかを毎回痛感できるのである。例えば、利き手が違う人に、自分のやり方を教えても作業はうまく進まない。相手の状態に合わせて指導をしていくということは非常に難しいことではあるが、就業体験の指導を積極的に希望する社員は、毎回の反省を嫌がらないで、次はもっとがんばろうという前向きな気持ちで就業体験指導に向かえるよう指導している。
アジアの国々から研修
特別支援学校の教員研修
当社の自己研修プログラムを利用して、半年に一度大阪研修(大阪店視察と大阪の企業での就業体験)を実施している。日頃から閉鎖的な空間に留まらない自立した職業人を目指しているので培ったスキルが他社で通用するかどうかそれぞれが目標を持って研修を行う。宿泊は、ビジネスホテルのシングルを利用して、生活自立のトレーニングも兼ねている。また、他社での企業実習は、社員の伸び具合を確認でき、本人が次の目標設定をする貴重な機会になる。例えば、ミスがなかった社員は、次に効率を意識することが課題だという認識を持てるように振り返る。また、就業体験で指導する側に回る機会が多い社員は、他社の社員さんたちの一挙手一投足が目標になる。閉鎖的な空間で、これで良しとはせず、刺激を次のステップに生かすための研修になっている。③ 検定 企業実習
企業実習 タカシマヤ大阪店前にてより生産性を向上し、会社の利益に繋がる仕事を行うためにスキルUPを目的とした「検定」を行っている。食パンの保存袋作業の「パン袋検定」では、15分間にいくつできたかを競争し、生産性向上を意識させている。マイペースを保つタイプも、前回の自分の記録よりも多くできるよう努力を示すようになってきた。一人ひとりが努力することが生産性を上げていくことに繋がることをこの検定を通して教えている。
タカシマヤ大阪店前にてより生産性を向上し、会社の利益に繋がる仕事を行うためにスキルUPを目的とした「検定」を行っている。食パンの保存袋作業の「パン袋検定」では、15分間にいくつできたかを競争し、生産性向上を意識させている。マイペースを保つタイプも、前回の自分の記録よりも多くできるよう努力を示すようになってきた。一人ひとりが努力することが生産性を上げていくことに繋がることをこの検定を通して教えている。 パン袋検定の様子
パン袋検定の様子
4. ワークライフバランス、今後の課題と展望
(1)ワークライフバランス
仕事と生活の調和(ワークライフバランス)は、人材の確保・定着、仕事の意欲維持・向上などのために必要不可欠である。当社では「いい仕事しよう。いい人生しよう」をスローガンにワークライフバランスを大切にしている。
入社4年目の内田さんは、入社1年目にグループホームに入居し、生活の自立を果たした。休日には、地域の余暇支援グループに所属し、カラオケ・テニス・料理教室などに参加し、充実した生活を送っている。グループホームに入居して約3年、実家には時々帰る程度でグループホームの入居者とカラオケに行ったり、ディズニーランドへ行ったりして、親元を離れた生活を楽しんでいる。

内田さんの余暇【テニス】
(2)今後の課題と展望
- 今後の課題① 法定雇用率維持と安定した雇用
② 雇用拡大に向けて、新たな業務の切り出し
③ 新規分野の雇用、新スタイルの障害者雇用
④ 店内の知名度の向上
⑤ 経費節約
⑥ 助成金制度の活用
⑦ さらなる社会貢献
⑧ 充実した就業体験の提供 - 今後の展望
当社もこの雇用スタイルにするまでは、どのように障害者雇用を進めていけばよいのか戸惑っていた。「ジョブコーチを入れてみてはどうか?」という地域就労支援センターからのご提案がなければ、現在のようなスタイルを構築することは難しかった。障害者にどのような業務が可能だろうか?コミュニケーションを円滑にとっていけるだろうか?様々な不安を抱え、長い期間適切な業務を模索していた。発足から約5年経過した今、やっと軌道に乗ってきた。
当社のような雇用は、どちらかと言うと中小企業向けの雇用スタイルである。障害者とジョブコーチのユニットでひとつのチームを作り、当社のように社内の雑用を一手に引き受けるスタイルは、特別な会社を興す必要もなく、特別な部屋を用意することなく、手軽に雇用を進められる方法である。今後もさらに当社の取り組みを外部に発信していきたい。
執筆者:株式会社髙島屋横浜店 総務部人事グループ 大橋 恵子
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











