障害の特性を活かし企業の戦力に
- 事業所名
- 木村メタル産業株式会社 関エコテクノロジーセンター
- 所在地
- 岐阜県岐阜市
- 事業内容
- 非鉄金属の回収、加工、販売、OA機器の解体処理及びリサイクル
- 従業員数
- 68名
- うち障害者数
- 34名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 5 機械オペレーター、選別検査、データ処理 内部障害 1 OA機器解体作業 知的障害 28 OA機器解体作業 精神障害 - 目次
1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
当社は、昭和57年4月に会社を設立し、産業廃棄物を適正に処理し、それを有効に資源として活用している企業である。
平成18年には、関エコテクノロジーセンターの操業を開始した。非鉄貴金属の回収、加工、販売などOA機器等のリユース、リサイクルを一貫した業態で再使用、再生利用、素材還元を行うマテリアルリサイクル工場として立ち上げた。システム管理も充実しており、データを一元管理することでトレーサビリティーを実現している。
(2)障害者雇用の経緯
循環型社会形成推進基本法を契機に、「地域との繋がりを大切に」を社風として社会貢献、地域社会との共存共栄を図るため、ハート雇用(障害者雇用)がスタートした。
まず、関エコテクノロジーセンターの新設に伴って13名の障害者を新規に雇用し、施設出身の指導者をジョブコーチおよび責任者に配置するなど障害者の働きやすい環境を整えた。
さらに、工場内はバリアフリー設計を施し、車いすでの移動をスムーズにするためエレベータや手すりを設置した。他にも、工場内のドアはカームドアを使用し、全フロアに身障者トイレを完備するなど障害者の精神的不安を和らげる受け入れ体制を整えた。
現在、当社では40人の障害者を雇用し、障害者雇用率は51%と多くの障害者に働いて頂いている。
企業内授産として施設利用者の体験の場、岐阜県の「働きたい ! 応援団 ぎふ」(企業内学習)岐阜版デュアルシステム8校に登録するなど、特別支援学校生徒の企業内・就業体験学習の受け入れも積極的に実施している。
<これまでの見学者受け入れ実績>
| 2007年 | |
| 特別支援学校生徒 | 107名 |
| 生徒父母 | 35名 |
| 学校・施設職員 | 33名 |
| 行政 | 1名 |
| 2008年 | |
| 特別支援学校生徒 | 44名 |
| 生徒父母 | 32名 |
| 学校・施設職員 | 35名 |
| 行政 | 42名 |
| 2009年 | |
| 特別支援学校生徒 | 7名 |
| 学校・施設職員 | 79名 |
| 行政 | 43名 |
| 民間企業 | 1名 |
| 2010年 | |
| 特別支援学校生徒 | 110名 |
| 生徒父母 | 45名 |
| 学校・施設職員 | 68名 |
| 行政 | 29名 |
| 民間企業 | 7名 |
| 2011年 | |
| 特別支援学校生徒 | 169名 |
| 生徒父母 | 67名 |
| 学校・施設職員 | 31名 |
| 行政 | 3名 |
| 民間企業 | 10名 |
| 高齢・障害者雇用支援センター | 35名 |
| 2012年 | |
| 特別支援学校生徒 | 80名 |
| 学校・施設職員 | 1名 |
| 行政 | 6名 |
| 民間企業 | 1名 |
| (2012年1月5日~3月16日現在) | |
2. 取り組み内容
(1)特別支援学校生徒の企業内学習のモデル事業に参画
平成21年岐阜県特別支援学校生徒の就労移行に関する企業内学習の開発・導入など社会的自立支援のモデル事業(中濃版デュアルシステム)を実施するため、中濃特別支援学校と企業側として弊社担当者が会議を先導して行った。1年目は協力企業の募集、学校内の準備、ネットワーク会議の開催、2年目は実践期間として、企業内学習の実施、取り組みの検証、中濃版デュアルシステムの構築を行い、このモデル事業が23年度4月より岐阜県版デュアルシステム事業として稼動を始めた。
この成果は協力企業を含め弊社の職場内において、知的障害を持った人への理解を深め、社内の職域や職種の拡大へとつながった。学校側も企業がどのような要望を持ち合わせているのかを知ることができ、先生の職場訪問・指導技術を獲得する良い機会となった。
当社では特別支援学校の卒業生を昨年度4名、この春には1名を内定とした。
(2)障害のある社員を応援する体制
当社では、障害者支援の知識を持った人を「ジョブコーチ」として配置している。
ジョブコーチの支援は、作業指導や生活面のサポート、障害者のバックアップ、関係行政機関との連携など多岐にわたる。
作業指導では、日々の作業に対する指導だけでなく、年に4回勉強会を実施している。そこでは挨拶の仕方や正しい言葉の使い方など基本的な社会人としての心構えから、工具の正しい使い方や整理整頓の方法といった、安全作業の為に必要な知識など様々な内容について学んでもらうこととしている。その他にも、写真を付けることで視覚化された作業マニュアルを作成するなど障害者に働きやすい職場作りを心がけている。

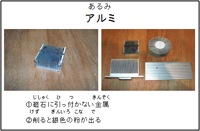
さらに、ジョブコーチの中には施設で障害者の一般就労を長く支えてきた人もおり、生活面におけるサポートも進めている。生活面でのサポートでは、障害に対する知識の少ない一般社員への障害者理解の推進活動や障害者社員同士のトラブルの調整を行うこともある。
この他にも、障害年金や療育手帳、職能判定の申請方法を知らない障害者やその家族も多くいるため、これらの申請などの支援も行っている。
関係行政機関との連携は、ジョブコーチでは踏み込むことのできない領域の問題や、会社と障害者社員とのトラブルに第三者として介入していただくことで問題の早期解決を図るなど、障害者雇用を進める上で非常に大切な部分であるので、地域の障害者就業・生活支援センター、各市町村の窓口と常に情報交換を行っている。
これまでジョブコーチの支援内容の説明をしたが、実際に企業で働く障害者を応援するためにはジョブコーチの力だけでは足りない部分が多くある。その中で社長など上司の理解はとても大きく、会社全体で障害者を応援していく体制づくりが重要であると実感している。
(3)4つのポイントで支援
| ① | 社会人としての教育 社会人としての基本は挨拶や言葉遣い、マナーである。基本的な部分からの教育を行い障害者にも社会人としての自覚を持ってもらえるよう配慮している。 |
| ② | レベルアップを目指した作業指導 ジョブコーチの指導のもと、作業に関する知識を身につけてもらうとともに、個々の特性を活かすため、作業内容・作業方法を提案し、自信を持って作業に取り組む環境を整えている。 具体的な事例として、障害者社員A君とハードディスクドライブ(以下「HDD」という。)の解体作業がある。A君は療育手帳B1、自閉症と診断され、職能判定は重度判定を受けている。A君は入社当初はパソコンやサーバーなどの解体を行っていたが、解体品は製造メーカーによって構造が違い、作業の変化に戸惑うことが多く、作業についていけない状態であった。 そこでジョブコーチの提案で、作業内容をパソコンやサーバーなど構造に違いのある解体作業からHDDを専門に解体してもらうように作業内容の変更が行われた。HDDはパソコンや様々なコンピュータに利用されている記録装置で、製造メーカーによって構造の違いがほとんどない。 A君がHDDの解体作業を行うようになってからは、作業変化の戸惑いはほとんどなくなり、長所である作業への集中力を発揮して現在ではジョブコーチよりも早くHDDの解体を行えるようにまでなった。 この事例はほんの一部で、時には提案した作業に適合できなかった失敗事例もあるが、失敗を次の成功に繋げられるように、より本人に合った作業内容・作業方法の提案を行っている。 
HDDの解体作業

HDD
|
| ③ | 雇用の安定(職場環境の充実) 工場内はバリアフリー設計で、身障者用トイレやカームドアなどを完備している。 また、静養室を設け体調不良を訴えた時や、精神的に不安定になった人のために心身を落ち着けることのできる場を提供している。また、出退社には専用バスにて送迎も行っている。 年間行事を企画・提案し、余暇の面でも充実を図っている。5月に実施する日帰り旅行はご家族にも参加して頂き、関係作りを積極的に進めている。8月に会社敷地内で行なわれる納涼祭は、障害者と一般社員との交流を深める場として計画をしている。また、広報誌として「クローバー通信」を発行し、障害者の仕事ぶりや会社内での様子などをご家族にお知らせしている。 |
| ④ | 就労生活に必要な援助 ジョブコーチは、作業指導のほか、対人関係(仲間同士、一般社員)の調整を図ったり、作業環境の改善に努めている。また、年金の申請や療育手帳の判定など様々なサービス利用の援助も進めている。 さらには、障害者の社会的自立を支え地域生活を守るため、様々な相談にも応じている。 |
(4)実習の機会をつくりだす期間が大切
特別支援学校の生徒・施設利用者の実習・就労希望者、求人募集で応募する人は、実際の仕事内容を知らずに就労希望する場合が多く見られる。そこで当社では説明会を開催し、工場見学や仕事の内容・会社のシステムを知ってもらった上で、2週間の実習を行っている。実習中は家族の付き添い、バックアップする職員の見守りなど、本人の心細い心境を少しでも和らげ、作業に集中できるよう配慮し、家族・本人・職員とジョブコーチとの関係作り、情報交換を行うことで、就労後の安定継続に努めている。
岐阜県では、障害者チャレンジトレーニング事業という実習期間、本人と会社に謝金や労災にかわる保険に対応する制度があり、本人も企業もこの制度を活用して実習に取り組んでいる。
障害のある社員は、集中力があったり責任を持って確実に作業をこなしたりと、さまざまな力を秘めている。障害の特性をうまく活用し、会社が少しアイデアを持ち合わせ、環境を整えることができれば障害のある者が活躍できる場はかなりあると思う。


3. 今後の課題
「雇用の拡大に必要なことは、本人の応援をすること」
もっとも重要なことは、地域で働く本人を応援するシステムをつくることである。本人の状態、家族の状態を見守り、本人を応援し続けるシステムを地域につくっていくことが、企業での就労を広げていくために必要である。
市町村は障害者の現状を把握しておらず、障害者や家族はサービスが充実していても利用方法を知らないのが現状である。障害者が自立した生活を開始し、いろいろな分野へ積極的に社会参加できるような現実をめざしていくためには、関係機関や地域社会が連携を密にして、一体となった広域的な福祉ネットワークが必要であると感じている。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











