農業分野で知的障害者の雇用に取り組んでいる事例
- 事業所名
- ハートランド株式会社
- 所在地
- 大阪府泉南市
- 事業内容
- 軟弱野菜の水耕栽培
- 従業員数
- 13名
- うち障害者数
- 8名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 7 サラダほうれん草の栽培 精神障害 1 サラダほうれん草の栽培 - 目次

1. 事業所の概要、企業グループとしての『障害者』雇用の歴史
(1)事業所の概要
大阪府南部、泉南市の丘陵地帯に大阪府が開発した農業団地「かるがもの里」の一角にハートランド株式会社がある。ガラス張りの約3000㎡のハウスを含む、4000㎡の敷地をもつ農業生産法人である。
ハートランド株式会社は、事務用品メーカーのコクヨグループの特例子会社として、知的障害のある従業員8名(うち重度障害者4名)を雇用している。事業内容は、ハウス内でのサラダほうれん草の水耕栽培を主としている。
(2)企業グループとしての『障害者』雇用の歴史
コクヨグループでは、障害があることは「害」ではないという考えのもと、グループ内では『障害者』を『障碍者』と表記することで統一している。本稿においては、一般的に使用されている『障害者』と表記することを、最初にお断りをしておく。
コクヨ株式会社での障害者雇用の取り組みは、戦前からの歴史がある。創業者の黒田善太郎により、昭和15年から当時の本社工場において、聴覚障害者の雇用に取り組んでいた。
昭和24年、現在の社団法人大阪府雇用開発協会の前身、大阪府身体障害者雇用促進協議会には、発足当初より理事として参画している。昭和36年、大阪の八尾工場が稼働し、工場内設備が整えられた。あわせて障害者にとっての働きやすい職場環境の整備にも取り組んでいった。
そのため、コクヨ株式会社では、障害者雇用が義務化された当初から、法定雇用率を大きく上回っている。
コクヨ株式会社での障害者雇用の転機となったのは、聴覚障害者が多数働いていた八尾工場の滋賀工場との統合である。八尾工場で勤務していた社員は全員、滋賀工場へと異動せざるをえない状況となったのだが、障害のある社員にとっての転勤は容易でない。障害のある人の雇用継続をはかることも目的に、通勤圏で事業所を設けることとした。
それが大阪市内でカタログ印刷等を行うコクヨKハート株式会社である。コクヨKハート株式会社は、後に特例子会社の認定を受けている。グループ適用を受けることで企業グループとしても法定雇用率を十分に上回る取り組みとなっている。
本稿で取り上げているハートランド株式会社は、既にグループ内で操業している特例子会社、コクヨKハート株式会社の子会社として位置付けられる。コクヨグループの企業が増える等により、グループ全体での常用雇用者数の増加にともない、新たな障害者雇用を検討すべき状況となった際に、印刷業務であれば就労が難しい知的障害者の職域を拡げることを目的に創業された。平成19年10月のことであった。
ハートランド株式会社の取り組みが始まったこともあり、現在(平成23年度時点)ではグループ適用実施会社内での雇用率2.35%、コクヨグループ全体での雇用率2.19%を達成している。
2. 障害者の適性に配慮した職務の設定、障害者のモチベーションを高めるための関わりの工夫
(1)障害者の適性に配慮した職務の設定
ハートランド株式会社は、これまでのコクヨグループでは雇用が難しいとされていた知的障害者に就労の場を提供する目的として作られた。
播種、定植、収穫、計量、出荷と、サラダほうれん草を栽培する作業工程には、「わかりやすい作業」「同じ内容の作業の繰り返し」の要素が多い。重量物を繰り返し運ぶ等の力仕事の要素も少ない。さらには、農作物を育てる達成感や喜びなど、仕事の成果、働きがいがわかりやすいという点でも、知的障害者の職域として野菜栽培が適していると考えられた理由である。
ハートランド株式会社が育てるサラダほうれん草は、ハウス内で栽培をしている。
温度や水やり等の管理が自動制御でできるハウス内での水耕栽培にすることで、季節や天候に左右されることなく、一定の収穫量を確保することにつながっている。
とはいえ、従業員数の過半数が障害者であるハートランド株式会社にとっては、設備を整えるとともに、障害のある従業員に能力を発揮してもらえるような職場環境作りが不可欠となる。農作物を取り扱うがゆえに、収穫から出荷までの工程における効率を高めなければ、収益につながっていかないからである。
そのため、ハートランド株式会社には、障害のある人が効率よく仕事ができるための工夫が随所にみられている。
例えば、写真①は、出荷用の箱詰め作業で使われる道具である。作業をする人が詰めるべき個数を間違えないように仕切りをつける工夫である。現場での作業は、パックされた商品が次から次へと機械から流れてくるので、限られた時間内で素早く箱詰めしなければならない。忙しい状況であっても、数量のミスを少なくするだけでなく、自信をもって取り組めることにつながっている。
また、障害のある従業員の適性を踏まえた職務配置も大切である。
サラダほうれん草を栽培するという一連の業務の中には、同じ場所で留まったままの作業があれば、一輪車を押して動きまわる作業もある。また、他の人と一緒に流れ作業の一端を担う工程もあれば、黙々と単独作業を行う工程もある。そのため、障害のある従業員の個々の得意な部分が発揮できるよう、職務配置にも工夫をしているとのことである。
取材で訪問した際に、作業服を着て仕事をしている障害のある従業員の皆さんが、きびきびと動き、元気よく挨拶の言葉をかけてくれたのが印象的であった。細かな播種作業を集中して繰り返し行う人、収穫物やゴミを運搬する人、機械の前で計量や包装の作業をする人、最終検品を行いつつダンボール箱に商品を詰めて梱包をする人など様々である。
それぞれが自分の役割に自信をもち、主体的、積極的に仕事に取り組む明るい職場環境となっているのも、個々の障害を踏まえて職務を設定する等の配慮があるからこそといえる。
知的障害のある人の中には、得意な作業と苦手な作業の差が顕著な場合も少なくない。また、「『得意な仕事』が『好きな仕事』になっていく」ということも、よく言われている。障害のある従業員一人ひとりが仕事に対して一生懸命に向き合い、力を発揮できるようにするためには、個々の障害者の障害特性や得意な部分を踏まえた上での職務の配置、物理面での作業環境の工夫が重要であることを、ハートランド株式会社での取り組みを通して、改めて気付かされる。
(2)障害者のモチベーションを高めるための関わりの工夫
これまでに述べてきたように、写真②のハウス内での野菜栽培は、一年を通して同じ業務内容である。知的障害者にとっては「いつも同じで分かりやすい」職場というメリットではあるのだが、一方では変化が少ないことからマンネリに陥りやすいというリスクもある。そのため、ハートランド株式会社では、障害のある従業員のモチベーションを高めるために、普段の関わりに工夫がみられる。
例えば、毎日の終礼で翌日の作業を確認するとともに、誰かに指示等をされることなく率先して仕事の準備をした人や、出荷量をこなすために頑張った人、お客様に大きな声であいさつできた人に対して現場監督者から『写真③がんばるシール』がもらえることになっている。そして、月ごとにシールを最もたくさんもらうことができた従業員には、『月間MVP』として表彰されるようにしているのである。表彰される従業員にとって励みになるのはもちろん、周囲の従業員にとっても、相乗効果を生み、会社全体の士気の向上につながっているようである。
出荷量を増やすためには、業務の効率を追求していかなければならないため、現場の監督者は、時には障害のある従業員に改善点を示すべく注意せざるをえない場面も出てくる。注意されるばかりでは士気が下がってしまうので、普段の仕事の些細な頑張りにも焦点を当てて、積極的に認める機会、褒める機会を設けるための取り組みなのである。
ところで、わが国の知的障害者雇用の取り組みにおいて有名な日本理化学工業株式会社(川崎市)の大山会長の著書の中に、次の言葉がある。
人間の究極の幸せは、
- 人に愛されること
- 人に褒められること
- 人の役に立つこと
- 人から必要とされること
ハートランド株式会社の中でも、共感をもって受け止められている言葉である。上述のような社内表彰制度等で従業員を積極的に評価、賞賛し、会社の中での役割を常に確認できる取り組みは、大山会長のいう従業員の「究極の幸せ」にも通じるといえる。
事業を開始してから、まだ4年あまりの取り組みであるが、「ゆくゆくは障害のある従業員からリーダーとなって指導できる人材を輩出していくことが目標」と力強く語っておられたのが印象的だった。障害のある従業員一人ひとりに対して、人間としての成長を期待しながら、日々の業務に向き合っている様子がよくわかる言葉でもある。





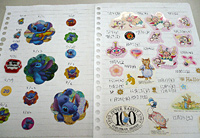
3. 農業分野での取り組みゆえの苦労、おわりに
(1)農業分野での取り組みゆえの苦労
農業分野での障害者雇用の取り組みは、前例がほとんどないモデルである。そのため、ハートランド株式会社の取り組みに対する各方面からの関心はとても高く、年間500~600名の視察者がやってくるのだそうだ。
とはいえ、前例がほとんどないゆえに、一連の取り組みを軌道に乗せるまでには、相当な苦労があったと思われる。現在では大手スーパー、飲食店、地元のJA等に栽培したサラダほうれん草の販路が確保されているが、これらは、長い期間をかけてお客様に信頼を得てきたゆえの成果であると聞いている。
また、事業の流れが確立されてきた今でも、日々の業務には苦労が絶えないそうである。
例えば、ハウス栽培であっても、収穫までの日数は、日照時間等の天候の些細な変化に影響してしまうため、お客様から注文を受けた全ての数量を出荷できない場合もあり、出荷量を細かく見込むことに限界があるのだ。工業製品を計画的に製造していく事業にはない悩みともいえる。
また、ハウス内の設備や作物の育成状況を確認する等、休日も交替で出勤して何らかの業務を行わなければならないようである。取材を通して聞き取ることができた苦労話は、ほんの一部であって、ハートランド株式会社が抱える農業分野での事業ゆえの苦労は、枚挙にいとまがないと思われる。
(2)おわりに
ハートランド株式会社では、企業グループとしての障害者の法定雇用をすすめるだけにとどまらず、地域の福祉施設と連携し、利用者の就労体験の場として位置付けた取り組みも行っている。企業での就労を目指す施設利用者にとっては、実践的な就労体験ができるために意義は大きいのはもちろんであるが、ハートランド株式会社の障害のある従業員にとっても、施設の利用者に対して指導的な立場も担うことを将来の目標として目指すことにつながっているようである。
なお、本稿は、農業分野での障害者雇用のモデル的な事例として紹介をしているが、障害適性に配慮した職務を設定したり、物理的な作業環境の工夫をしたり、頑張りに対して賞賛する風土づくりは、あらゆる業種においても参考としていただけるものでもあると考えている。
今回の取材を通して一貫して感じたことは、障害者雇用を慈善事業的に捉えるのではなく、企業としての収益性を目指そうとする高い理念である。数多の困難を抱える農業分野での障害者雇用に取り組むハートランド株式会社の進化に向けた挑戦は、まだまだ続いていく。
執筆者:財団法人箕面市障害者事業団
箕面市障害者雇用支援センター 所長 下司 良一
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











