障害者と共に地域社会に愛され、信頼される企業を目指して日々是前進
- 事業所名
- あなぶきパートナー株式会社
- 所在地
- 香川県高松市
- 事業内容
- 障害者自立支援
- 従業員数
- 11名
- うち障害者数
- 8名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 2 事業所清掃・名刺作成 内部障害 知的障害 6 事務所清掃・書類ファイリング等事務作業 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用と特例子会社設立の経緯
(1)事業所の概要
あなぶきパートナー株式会社は、不動産業・分譲マンション事業を中心に総合不動産業を営む穴吹興産株式会社を中核とする、あなぶきグループの障害者雇用の一層の促進を図り、障害者雇用の枠にとらわれない障害者の自立支援を目的に、グループ内4社の共同出資により平成20年5月2日に設立された。
翌平成21年2月3日に香川県では2例目となる穴吹興産株式会社の特例子会社として認定され、主にグループ各社から委託される事務所清掃、名刺作成、ダイレクトメール印刷及び封入発送業務などを行っている。
障害者の社会人としての自立を支援し、生産性の向上を図り、できる限りグループ会社に依存しないという企業姿勢を基本スタンスにして、社員が持っている能力を最大限に発揮し、あらゆる可能性にチャレンジして日々成長しながら、障害者の職業を通じた社会参加を実現し、個人の幸福や社会の発展にあなぶきグループと共に貢献していくことを目指している。
(2)障害者雇用と特例子会社設立の経緯
親会社である穴吹興産株式会社やグループ各社が障害者雇用の積極的な展開を始めたきっかけは、地域に生かされ生きる地域密着型企業として、働く意志と能力を有する多くの障害者に対して、職業生活の場や働くチャンスを作ることが社会的使命であるとの考えが社内に広まってきたところからであった。
しかしながら、当時(平成19年度)の穴吹興産株式会社の障害者雇用率は0%であり、グループ全体で見ても0.8%であったことから、特例子会社設立を目指した障害者雇用の取組みがスタートした。もちろん、特例子会社設立に当たっては、社内でも「障害者雇用は大切なことではあるが、何も子会社まで設立する必要はない」という反対意見もあったが、社長の障害者雇用に対する理解と英断により取組みは加速した。
子会社設立の目的は、障害者(特に知的障害者)の雇用の促進と確保、障害者の社会進出及び自立の支援、雇用率の達成、障害者に配慮した職場環境の整備、障害者の特性に応じた業務内容の選択が可能であること、特例子会社制度の活用が可能であること等にある。しかしながら、障害者雇用の経験もなく、実際の監督や指導をどのようにするのか、具体的に障害者にやってもらう業務をどのようにするのかなど、設立準備期間となった約一年間は、数多くの不安やさまざまな問題と対峙しながら解決していかなければならない時期ともなった。
まず、第一歩として、社員向けのアンケートを実施して障害者支援等ボランティア活動に興味があると答えた社員32名の中から、子会社へ出向して専任で業務にあたる現場責任者と事業規模の拡大にも対応できるように現場責任者とともに業務にあたる社員の人選を行った。選ばれた2人は、ハローワークや関係機関との協議、支援機関や特別支援学校等との連携及びネットワークの構築、先行企業や特例子会社への見学の実施、障害者雇用の情報の収集及び講習会等への参加等々中心になって熱心に取り組んでいった。この努力により、平成20年5月にはあなぶきパートナー設立後第1号となる身体障害者を採用すると、その後も雇用を進めていき、翌年2月3日に特例子会社として認定されている。
2. 取り組みの内容
① 障害者の雇用状況
現在雇用している障害者は、重度2名を含む6名の知的障害者と重度1名を含む2名の身体障害者の計8名(男女各4名)である。全員が20歳代と若く、特別支援学校や授産施設の出身者が多い。全員がハローワークのトライアル雇用を経て採用されている。この8名以外にもグループ会社から重度2名を含む3名の知的障害者が出向してきている。定着率は良好であるが、残念ながら退職者もおり、特に今年10月に退職した知的障害者は、平成20年7月の採用者(子会社設立後第2号)であり真面目に業務に取り組んでいたが、発作による体調の悪化により止むを得ず退職することになった。会社の努力ではどうしようもない事項であるが、以降、社員の健康維持については特に注意している。
障害者の雇用については、障害者合同就職面接会には毎回参加しており、特別支援学校と連携して職場実習なども行っている。採用にあたっては、①家族の理解があること、②明るく笑顔で挨拶できること、③他人に迷惑をかけないこと、④勤務先まで自分で通勤できることを重視している。
② 障害者の業務内容
基本的な業務は、朝礼後事務所を出発して全員がグループ各社の清掃を行い、午後は事務所内で名刺・DMの作成、シュレッダー、給与明細・社内報の発送、パンフレットスキャニング、伝票などのファイリング、ギフトカード発送・発注・梱包等の軽作業を行う。終了後は、業務日誌を作成してパソコンのデータ入力練習もする。また、電話の応対も積極的に行っている。

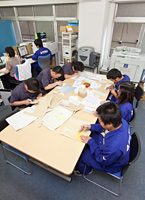
③ 雇用管理
週初めに朝礼を実施し、各人の体調の確認や意欲・態度面の変化の把握を行うとともに障害者自身が朝礼の司会を順番に務め、一週間の目標を発表する(コミュニケーションや挨拶の練習にもなっている)。また、毎日の業務終了後に日々の目標と業務内容、反省点等を業務日誌に記入し、その内容についてサポートスタッフが良かった点、悪かった点、注意点などを文書や口頭でコメントしている。業務日誌は大変有効であるが、業務日誌に書けない内容もあるため、そのフォローをどうするかという課題もある。更には、家族との情報交換を行うために、「連絡帳」を作成し、職場で何か気になる点があればその内容を記入して家族へ連絡し、逆に家族からの情報を得るようにしている。
また、特に力を入れているのは、「個人目標の設定とキャリア資産の棚卸シート」の作成である。年度始めに各人の職場での目標、プライベートでの目標などの年間目標を設定してもらい、6月頃に中間面談をし、達成状況の把握・指導等を実施している。年度末には、経験した仕事、期間、その仕事を通じて発見したこと・気付いたこと、この一年でできるようになったこと、自分らしさを発揮できたことや思い出に残ること、この一年でできなかったことや来年できるようになりたいこと等を記入してもらい、これにより個々人の能力等の「見える化」を図るよう心がけている。
④ 人間関係と教育
出向の障害者3名を含めると11名の障害者がおり、性格はおっとりしているが遅刻や異性関係に問題のある者、報告や整理が苦手な者、黙々と真面目に仕事をするが不器用な者、話が苦手で対人関係に問題はあるが器用でメモを取って次に活かすことができる者、協調性があり挨拶もでき特に問題のない者など、障害者の性格や能力・資質は様々である。年齢も若く、日常生活において喧嘩や異性問題等のトラブルがどうしても発生する。注意すると自虐的になったり、精神的に不安定になったりすることがある。問題がおきれば、全員で話し合いをすることで解決していくが、それでも難しい場合は家族や支援機関と協力して対処する。時には医療機関と相談することもある。とりわけジョブコーチとの連携や協力は欠かせない。トライアル雇用中から本人の情報収集や指導の仕方、仕事の進め方について相談を行うことは、本人や家族の安心感にもつながっている。仕事については、基本的にサポートスタッフが指導するが、各業務の各人の状況及び能力を理解し、十分にその能力を生かせるように業務担当を決定するなど各人がスムーズに作業できるようにできる限り配慮している。「嘘を言わない」「仕事は厳しく」「職場は明るく」を障害者と共に目指している。一方で、現状はサポートスタッフ3名体制となっているが、その業務は多岐にわたり仕事量も多い。サポートスタッフ自身のスキルアップを含め、よりきめ細やかなサポート体制の構築に鑑み、組織上難しいところではあろうが、増員などの問題についても考えていかなければならないところである。
⑤ 助成金の活用
障害者雇用を円滑に進めていくうえで、助成金の活用は重要なファクターの一つである。雇用面においては、ハローワークの「トライアル雇用奨励金」や「特定就職困難者雇用開発助成金」の活用、障害者の業務遂行支援のために独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用納付金制度に基づく助成金として「第一種作業施設設置等助成金」、「業務遂行援助者の配置助成金」を活用している。また、香川県から「平成20年度障害者自立支援臨時特別負担金」を受給している。
3. 取組みの効果、今後の展望と課題
(1)取組みの効果
同社の存在は、親会社やグループ企業にとっての障害者雇用率適用に留まらず、様々な効果をもたらしている。親会社では社内報「あなぶきパートナーNEWS」を発行してパートナーでの業務内容、メンバー情報、その他イベント等の情報と同時に障害者雇用についての考え方や障害者雇用を通じて学んだことなどをグループ社員及びその家族に定期的に発信している。また、新入社員の職場研修の場となり、普段は接することが少ない障害者達とふれあうことで、みんな明るく、元気よく、挨拶もきちんとでき、熱心に仕事をする姿から仕事をする喜びと他人を思いやることの大切さを再確認させている。更には、親会社の全社員イベントなどにも積極的に参加し、あなぶきパートナー社員が中心となって進めるイベントもあり、親会社やグループ各企業の社員との交流を深めている。これらの活動は、障害者の自立と主体性を育てることにもつながっている。また、障害者のこのような活動や仕事に対する真摯な姿勢を直接目の当たりにすることによって、人に誉められたり、必要とされたり、役に立つといったいわゆる存在価値をあらためて学ぶことにもなり、会社に自信と誇りを感じることができるといった社員満足効果を生み出しており、グループ企業の障害者雇用に対する考え方に大きな変化をもたらしているといえる。
更に対外的な活動にも積極的に参加しており、とりわけ全国障害者技能競技大会(アビリンピック)には、会社を挙げて毎年様々な種目にチャレンジし優秀な成績を修め、全国大会にも出場している。全国障害者スポーツ大会にも参加し活躍している。
その他、職場見学を随時受入れており、県内外の民間企業や特別支援学校などが見学に訪れ、障害者の業務内容や雇用上の配慮など様々な問題に関する意見交換を行い、就労支援の参考企業にもなっている。
(2)今後の展望と課題
同社が特例子会社と認定されて3年近くになるが、まだまだ発展途上であり、いろいろな課題がある。最重要課題は仕事の確保である。仕事の確保は雇用の確保に直結する。現状では親会社やグループ企業からの受注が大半であり、今後外部からの売上をいかにして伸ばしていくことができるかが鍵になる。そのためには新しい分野の仕事を創出していく必要があり、現在、畑を借りて耕すなど農業への進出に取り組んでいるところである。グループ企業は、ホテルを保有しており、食材の提供などが可能となることから、新しい職域として期待できる。現状のままでは、これ以上の障害者の雇用が難しい状況にあるため、新しい仕事の確保が新規雇用にもつながることから大いに期待される。
障害者の中からリーダーとなる人材の育成や成長に応じた人事処遇の課題もある。リーダー該当者は育ってきていることから、障害者達のスキルアップに応じた給与等処遇面を考慮していかなければならない。また、現在は知的障害者が主体となっており、バリアフリー等オフィス環境の問題から、身体障害者(車いす利用者)や視覚障害者の雇用、雇用管理上の不安から、精神障害者の雇用は難しい状況にあるという。この課題に前向きに対峙して、一歩一歩改善していくことにより更なる発展をしていかなければならない。これにより単なるグループ一企業にとどまらず、地域を代表する障害者雇用のモデル企業として、社会から愛され信頼されるあなぶきパートナーとして、前進していくことが望まれる。
木曽 潤二
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











