障害者の長期就労実現の原動力は社員の力
- 事業所名
- 共立寝具株式会社
- 所在地
- 青森県弘前市
- 事業内容
- 一般用貸布団、病院・医療患者用病衣、基準寝具
医療・福祉関連施設寝具、おむつ等 - 従業員数
- 119名
- うち障害者数
- 17名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 1 営業 内部障害 知的障害 16 仕分け、洗い、仕上げ、検品 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要
(1)沿革
| S38.9 | 病院の基準寝具関係の業務を行うために創立。 |
| S63.5 | 新工場を重度障害者多数雇用事業所施設として弘前市神田5丁目に神田工場を建設。障害者13名就労する。 |
| H 3.5 | 神田工場の業務拡張にともない、第3工場を別棟にて新築。障害者就労が18名となる。 |
| H15.1 | ISO9001:2000取得 |
| H16.4 | 広野より門外に工場移転。バックモノレールシステム採用のほか、国内でもトップクラスの最新鋭設備を導入。 |
| H18.9 | 障害者雇用優良事業所として青森県知事表彰を受ける。 |
| H24.9 | 障害者雇用優良事業所として厚生労働大臣表彰を受ける。 |
(2)組織、事業概要
有限会社(当時)弘前ドライクリーニング工場において、病院・医療患者用病衣、基準寝具の業務をおこなっていたが、一般の家庭や事業所のクリーニングとは分けて行うよう指導があり、それに対応するために昭和38年9月に創設。現在では、病院・医療患者用病衣、基準寝具に加え老人福祉施設・老人保健施設等の老人用オムツのレンタル(クリーニング含み)等医療機関、福祉施設のリネン関連サービスを展開している。
営業区域は、青森県津軽地方を網羅するとともに、下北地方では地元同業者と連携し、営業を展開している。また、営業区域にある同業他社との共存、共栄を図るために、技術提供、指導も行っており、地域の信頼を得る努力を重ねている。
当社は昭和23年9月に設立した株式会社弘前ドライクリーニング工場及び昭和39年9月に設立した有限会社コスモス商会とで、グループを構成しており、全体の従業員数は、320名であり、うち障害者は33名となっている。
2. 障害者雇用の経緯と雇用状況
(1)障害者雇用の経緯
先代社長久保栄三(創業者・故人)は社会福祉活動、社会貢献については人一倍強い思いがあり、障害者の就労、生活についても強い関心を持って経営にあたっていた。障害者雇用のきっかけは、日本が高度成長時代に入り、所得倍増、東京オリンピックと沸き立ち、多くの若者が金の卵ともてはやされ集団就職で関東方面に出ていき、地方では極端な人手不足に陥り、人集めに苦労していた頃に遡る。そのような時期に、知人から重度聴覚障害者を紹介され、昭和38年2月に採用したのが最初であり、その人が一生懸命に働いてくれたことから、引き続き障害者を採用するようになった。
また、これ以来、障害者の採用に関わり、公共職業安定所や養護学校(特別支援校)などに障害者の就労等の実情を聴き歩くうちに、肢体不自由児者親の会役員はじめ、障害者の関係者との交流を持つようになっていた。
そんな折の昭和53年に協力関係にあった社会福祉法人七峰会が知的障害者通勤寮拓心館を開設し、養護学校卒業生、知的障害児・者施設、在宅から利用者を迎え、寮において生活支援をしながら、公共職業安定所や事業所の協力を得て就労支援を行う事業を開始し、加えて通勤寮職員が障害者の業務支援(現在のジョブコーチにあたる)を行ったことにより、当グループの知的障害者の雇用が増えていった。
このことを通じて、先代社長は障害者の就労の場をさらに拡大してゆく必要性を痛感していたが、コスト、生産性など経営面のリスクが壁となっていた。そのような時に、障害者雇用についての助成制度を知り、公共職業安定所の支援と、(社)七峰会の協力を得て、障害者雇用の施設を作る決意を固めた。途中様々な問題を乗り越え、昭和56年1月に青森県で最初の重度障害者多数雇用事業所を始めることができた。
当グループの業務拡大にともない、昭和63年には共立寝具の新工場を重度障害者多数雇用事業所として建設し、障害者を13名新規に雇用した。
障害者の担当する業務は当初、簡単な仕分け、運搬等の労務に限られていたが、最新鋭設備の導入や、業務の工程を分化し、機械、器具の工夫、改善を繰り返してきたことにより、障害者の適応できる工程が大幅に増加してゆき、職域拡大が図られると同時に、品質の向上と生産性の向上が図られた。
それまでの障害者雇用への取り組みが評価され、平成18年に青森県知事表彰、平成24年に厚生労働大臣表彰を受けた。
(2)障害者の状況と業務内容
平成24年2月1日現在、在籍する障害者の状況と業務内容は次の通りである。
(年齢構成)
| 年齢区分 | 人数 | 構成比 | 身体重度 | 身体重度外 | 知的重度 | 知的重度外 |
| 60歳以上 | 0 | 0.0% | ||||
| 50歳以上60歳未満 | 4 | 23.5% | 4 | |||
| 40歳以上50歳未満 | 8 | 47.1% | 1 | 5 | 2 | |
| 30歳以上40歳未満 | 4 | 23.5% | 2 | 2 | ||
| 20歳以上30歳未満 | 1 | 5.9% | 1 | |||
| 20歳未満 | 0 | 0.0% | ||||
| 合計 | 17 | 100.0% | 1 | 11 | 5 | |
| 最年長(歳) | 59 | 構成比 | 0.0% | 5.9% | 64.7% | 29.4% |
| 最年少(歳) | 23 | |||||
| 平均 | 44.2 |
(勤続年数構成)
| 勤続年数区分 | 人数 | 構成比 | 身体重度 | 身体重度外 | 知的重度 | 知的重度外 |
| 30年以上 | 0 | 0.0% | ||||
| 20年以上30年未満 | 10 | 58.8% | 1 | 8 | 1 | |
| 10年以上20年未満 | 6 | 35.3% | 3 | 3 | ||
| 5年以上10年未満 | 0 | 0.0% | ||||
| 5年未満 | 1 | 5.9% | 1 | |||
| 合計 | 17 | 100.0% | 1 | 11 | 5 | |
| 最長(年) | 25 | |||||
| 最短(年) | 0.1 | |||||
| 平均 | 18.6 |
上表からも分かるように、知的障害者が94.1%、内重度者が68.8%とその割合は高い。また、勤続年数10年以上の人が94.1%を占め、平均勤続年数は18.6年になっており、極めて定着率が高く、知的障害者が業務内容によく適応し、周囲でも就労継続のための配慮がなされていることがうかがわれる。
(業務内容)
① 営業部 営業 身体重度外1名
② 生産部
- 仕分作業…搬入された寝具、リネン品を種類毎に仕分けし、洗いに回す。
知的重度1名 仕分け作業
仕分け作業 - 洗場…仕分された品物を洗濯機、乾燥機への出し入れをして、仕上げ又は干場に回す。
寝具:知的重度1名 乾燥機の出し入れ作業
乾燥機の出し入れ作業 - 下着干し作業…洗濯後の品物(乾燥機に入れられない品物)をハンガー掛けして、乾燥室への出し入れをする。
知的重度1名 - 仕上げ作業
○寝具、病衣、枕カバー、シーツ
仕上げロール機へ、シミ、ヤブレを確認しながら機械がけをする。
知的重度4名、知的重度外2名○タオル・オムツ ロール投入作業
ロール投入作業
自動たたみ機へ、シミ、ヤブレを確認しながら機械がけをする。又、結束し、袋詰めをする。
知的重度、知的重度外各2名 タオルフォルダ
タオルフォルダ
3. 取り組みの内容
(1)社員教育と福利厚生事業
毎朝、作業前に社員一同が会し、社是である「健全なる生活、健全なる工場、健全なる人生」に関連する小講話や、説話等の朗読、連絡事項を行い、気持ちを引き締めるとともに、社員の和合、志気の高揚に気を遣っている。
また、終礼において、各班での一日の作業状況を報告し合い、障害者の心や身体の変化があった場合はその対応について話し合っている。最近、作業中の様子が少し不自然になっていた状況の報告があった。そのため、就業・生活支援センターと相談をし、医師の診察の結果、てんかん発作が起きていることが判明したため、投薬を受けながら、勤務を継続させた事例が発生している。
社員教育と福利厚生を兼ね、一年に1回、障害者含めた全社員に希望を募り、グループ内の他の工場見学を企画している。見学の後で、障害の無い社員を中心に小グループを作り、見学で感じたこと、考えたこと等をまとめ、自分たちの業務に向かう姿勢を改めて見つめ直す機会としている。見学には外食の設定があり一日を楽しく過ごせるよう工夫している。
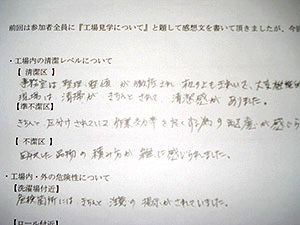
また、夏場には、暑気払いと、慰労、意欲喚起のために、納涼祭を実施し、カラオケや、ゲーム等に興じながら、全社員心を一つにして楽しい時間を過ごしている。

(2)知的障害者の就労継続への働きかけ(事例の紹介)
| ① | YM君は仕事の継続に問題があり、欠勤しがちになってきていた。その一因が担当している業務の回転が速く、それについていくことが、難しくなってきていたことにあるとの判断から、工場を替え、業務内容も周りのスピードに惑わされることの少ないものとした。最初は、尻込みし、新しい工場へもやっとのことで入れることができた。新しく就いた業務を身に付けるまでは、欠勤しがちでもあったが、自宅まで迎えに行ったり、周囲の社員が皆で励まし、また家族からの後押しでどうにか辞める(辞めさせる)ことなく、勤務に就いた。どちらかと云うと単独での仕事である今の業務がYM君には合っていたようで、嬉々として作業に取り組み、欠勤することがあまりなくなってきている。(知的重度、勤続21年) |
| ② | SMさんは、普段は明るく、素直でいい返事をしているのだが、時折、作業中に奇声を発し、周りを驚かせることがあり、社員が抱擁し落ち着かせる場面もあった。また、帰宅後も家で奇声を発したり、軽い自傷行為をすることがあり、お母さんを驚かせ、仕事場で何があったのかと心配して、工場に電話を掛けてくることもしばしばであった。奇声を発する要因に、彼女の心と身体のペースと周囲から課せられる仕事のペースが調和しておらず、そこからくるストレスを発散することができないまま、溜めに溜め、結果一気に噴出してしまっているのではと考え、一人で黙々と自分のペースで進められる業務への配置換えを行った。その甲斐があってか、奇声を発することが少なくなり、最近では安定している。(知的重度、勤続18年) |
| ③ | MMさんは、普段は明るく仕事をしているが、どうかすると、腰の痛みを訴え、仕事から離れようとしたり、心の元気を全く失うことが多い状態が続いていた。周りでは、励ましの言葉を多くかけ、心の元気回復に気を配っていた。その後、腰に負担が係る業務から、負担が少ない業務に配置換えし、元気回復のための声掛けを繰り返しているうちに、落ち着き、あいさつも良くするようになり、休むこともなくなってきた。平成19年には同じグループホームで生活している○○さんと結婚し、楽しく生活している。(知的重度外、勤続19年) |
| ④ | NKさんは、はずかしがりやで、気分にむらがあり、安定して仕事を継続することが難しく、周囲の社員がおだてたり、叱咤激励を繰り返すことが、仕事を継続させる条件となっている。(知的重度外、勤続19年) |
この他の人たちも、一人ひとりが、それぞれの持ち場で、業務に就いており、時折、離職の危機を迎えている。その都度、係わり方の相談や場合によってはジョブコーチ支援を津軽障害者就業・生活支援センターに依頼したり、それぞれの家族の協力を求めたり、さらには、生活(支援)の場であるグループホームやケアホームの担当者との連携を図りながら、その危機を乗り越えてきている。
また、工場においては、殆どの社員が、障害者の社員と共に作業を続けてきていることで、それぞれの作業状況や態度の変化を把握しながら、声掛けを行うことで励まし、指導を繰り返している。このことによって障害のある社員一人一人を理解し、障害を理解し、ともに働く仲間として受入れることで支えている。そのことで、お互いの信頼関係も構築され、不安や緊張の緩和に役立っている。
このような、日々の実践と、周りの係わりのある人々の理解と協力があってこそ就労の継続が図られている。
4. まとめ
当グループは障害者の雇用が柱となりそれぞれの事業の発展を続けてきているが、それを支え、進める原動力になっているのは、障害のある人と共に働き、声掛け、指導の配慮を日々、実践している社員に他ならない。
障害のある人と共に業務を遂行し、事業目標を実現することは、決して容易なことではないが、障害のある人の生活を支えている家族、グループホーム、ケアホームの職員の皆さん、また地域に生活し、商品や、サービスを利用している皆さんなど、多くの皆さんの力添えや、それとは知らず力添えをしてくれている人がたくさんいるということを常に思い、感謝しながら、仕事を進めているという。
このことは、株式会社弘前ドライクリーニング工場を取材したときのテーマである「障害者雇用を前提として経営の合理化と作業効率の向上をめざす」姿勢と対をなすものであり、当グループの発展を支え、事業目標を実現してゆく原動力であると思った。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











