知的障害者の新たな職域開発
~本人の個性を活かし介護の現場で働く~
- 事業所名
- 有限会社アズ デイサービスセンター杏
- 所在地
- 群馬県高崎市
- 事業内容
- 高齢者福祉業
- 従業員数
- 49名
- うち障害者数
- 1名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 1 高齢者介護業務補助 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要と障害者が従事する業務
(1)事業所の概要
| ① | 沿革 | 平成11年12月 | 有限会社アズ設立 | |
| 平成12年 4月 | 高崎市片岡町にアズケアスタッフ開所 高齢者訪問介護事業を開始 以後、高崎市新町にてグループホーム事業・居宅介護支援事業を開始 |
|||
| 平成23年 | 高崎市新町に本社を移転 通所介護事業を開始 |
|||
| ② | 事業構成 | (通所介護) | デイサービスセンター杏 | |
| (訪問介護) | アズケアスタッフ アズケアスタッフ新町 |
|||
| (グループホーム) | グループホームあんず グループホームなずな |
|||
| (居宅介護支援) | あず居宅介護支援事業所 | |||
③ 事業所周辺の環境
今回取り上げるデイサービスセンター杏のある新町は、平成18年の合併により現在は高崎市の一部となっているが、かつては中山道の宿場町として栄えた歴史を持つ。合併以前は、東西2.8km、面積3.7平方kmと関東で最も小さい町であった。現在でも下町の雰囲気が残り、人とのふれあい、隣近所とのつながりを大切にする地域である。地域イベントも多く、事業所と近隣の人との交流も盛んである。
④ デイサービスセンター杏の特徴
ゆったりとした時間を過ごせるよう、小規模で家庭的なサービスを目指している。一日の利用者数は8人から10人程で、「安全」「安心」「安楽」をモットーにしている。
特徴は、以下のとおり。
| ○ | 洗濯サービス 入浴時に、希望により着替えを洗濯・乾燥し、当日又は次回利用時に持ち帰っていただく。 |
| ○ | ゆったり入浴 一人の職員による個別対応なので、一人ずつゆっくり入浴できプライバシーも保てる。一般浴槽と特殊浴槽があり、特殊浴槽では体の不自由な人も安心して利用できる。 |
| ○ | 夕食の持ち帰り 利用日の夕食弁当が持ち帰り可能。 |
| ○ | 少人数 利用者数は最大でも15人、少人数ならではの和やかでゆったりとした時間が過ごせる。 |
| ○ | 日曜日も営業 日曜・祝日も営業(年末年始休業)。 |
(2)障害者が従事する業務
① 高齢者介護の現場で働くAさんについて
Aさんは、中学時代は特別支援学級に在籍していたが、本人の意思と家族の支えもあって普通高校(私立明和高等学校)に進学、障害のない生徒と共に学び卒業した。卒業後は、藤岡市地域活動支援センターさくらの家に通所。さくらの家では、請負作業や花の栽培に積極的に取り組んでいた。高校を卒業してから7年間、デイサービスセンター杏に勤務するまで、一般就労の経験はなかった。
なお、Aさんは障害者雇用促進法における重度知的障害者の判定を受けている。
② 障害者の業務内容
<デイサービスの内容とスケジュール>
| 時間帯 | 状況 | サービス内容 |
| 8:30 | 送迎 | |
| 9:00 | 施設到着 入浴 |
①配茶 ②バイタルチェック ③入浴 |
| 11:00 | 体操 | ①嚥下体操 ②舌体操 |
| 12:00 | 昼食 | 食事休憩 |
| 13:30 | 体操 | ①顔面体操 ②発声訓練 |
| 14:00 | レクリエーション | 頭と体を使うゲーム、苑外活動等 |
| 15:00 | おやつ | お茶とおやつ |
| 16:15 | 帰宅準備 | |
| 16:30 | 送迎 |
<Aさんの業務とスケジュール>
| 時間帯 | 状況 | 業務内容 |
| 8:30 | 出勤 受入準備 |
①カーテンを開ける ②お湯を沸かす ③お茶のカップを準備 ※利用者の人数を確認 |
| 9:00 | 利用者 来所 |
①お茶入れ ②入浴準備 ※ドライヤー・くし・鏡・マットの準備 ③洗濯物を干す ④花の水やり |
| 入浴時 | 見守り ※入浴の済んだ方へ水分補給 |
|
| 12:00 | 昼食時 | ①おしぼり配り ②お茶入れ ③布団を敷く ④歯ブラシ・コップの準備 |
| 食後 | 見守り | |
| 14:00 | レクリエーション | ①一緒に参加 ②洗濯物を取り込み・畳み ※利用者の帰宅に間に合うように |
| 16:00 | 利用者帰宅 | ①フロア掃除(掃除機・モップ) ②雑巾掛け (テーブル) ③トイレ掃除(床・便器) |
| 17:30 | 退勤 |

2. 障害者雇用の経緯、取り組みの内容
(1)障害者雇用の経緯
① 障害者雇用に対する考え
アズを創業した現社長は、創業当時に障害者と関わる機会があった。それは、ある知的障害者通所施設を訪ねた際に、障害者が作業に取り組んでいる姿を見て、その作業のスピードときれいな仕上がりに驚き、障害があっても可能性はたくさんあるということを感じたものだった。
当時は、ヘルパーが利用者宅で介護サービスを行う訪問介護のみの事業構成だったので、障害者を受け入れるには難しい状況であったが、いずれグループホームやデイサービス等の入所や通所の事業を立ち上げる目算もあり、その際には障害者を雇用したいとの考えを持っていた。
② 雇用のきっかけ
平成23年、社長はAさんの母親へデイサービスセンターの職員として働かないかと話をした。数年前に出会って以来、社長はAさんの母親から、わが子に知的障害があることや子供の将来について話を聴くこともあったという。
この申し出に対しAさんの母親は、娘の地域活動支援センターへの送迎があるため、勤務は難しいと社長へ伝えたところ、「じゃあ、Aさんも一緒にチャレンジしてみれば」と思ってもいなかった言葉を聞くことになる。
Aさんの母親は、Aさんの将来や自立について考えてはいたが、親子が同じ事業所で働くとなると、迷いも生じた。母親の立場からすると注意したくなるような場面も想定される。また、事業所や一緒に働く同僚へ迷惑を掛けたくはない。しかし、この時、Aさん本人の強い希望で普通高校への進学を決めたことを振り返る。
躾の厳しい学校であったが、家政科を子供と一緒に勉強するつもりで前向きに頑張って来た。お裁縫の宿題も一緒にやった。そして、今まで一緒に乗り越えて来たのだから、チャレンジしてみようと決め、社長に親子で働く意思を伝えた。
こうして、アズの、そしてAさんの、障害者雇用へのチャレンジが始まることとなった。
③ 障害者就業・生活支援センターを活用して採用へ
採用にあたり、Aさんが利用していたさくらの家に相談したところ、新町を含む多野藤岡地域の障害者就業・生活支援センターであるトータスを紹介された。トータスでは、会社訪問する一方で、Aさんと母親から今までの経過や就労に向けて不安なことを聴き取りした。アズとして障害者雇用は初めてだったので、どんな制度の利用が可能なのかについても説明を受けた。トータスの生活支援ワーカーは、障害特性と必要な配慮事項を確認し、Aさん親子と事業所に相互の情報を提供しながら、雇用へ向けて準備を進めた。そして、障害者就業・生活支援センターの職場実習制度を活用して、アズはAさんを受け入れることとなった。
(2)取り組みの内容~職場実習から現在まで
① 障害者就業・生活支援センターによる職場実習への支援
生活支援ワーカーは、Aさんにできる作業を創出していく支援からスタートした。実習初日から、デイサービスで行われる1日のすべての作業を書き出し、他の職員の動きや作業をするタイミングなどもすべてチェックしていった。ポイントとしては、Aさんに「できること」「やってもらえたら現場が助かること」を意識し、作業スケジュールを組み立てていった。こうして、先に挙げた<Aさんの業務とスケジュール>ができあがった。
② 実習から雇用へ
実習を通して意欲も確認でき、担当する作業のスケジュール化も整った。そこでまずは、3ヶ月間のトライアル雇用制度を利用した。その間にも、Aさんが環境や徐々に増える利用者にも慣れてくる様子が窺えた。スケジュール化された作業の流れもつかめ、自発的に行動が取れるようにもなっていった。本人の頑張りや周囲の理解もあり、トライアル雇用満了後に常用雇用となった。
③ 本人の課題に合わせた支援
生活支援ワーカーは、定期的な職場定着支援の中で新たな課題が出た際には、どのような方法をとれば、更なる本人の理解につながっていくかを考えて支援を行う。
今回の例では、入浴後の利用者に対してヘアドライヤーを掛ける際に、Aさんには頭とドライヤーの距離を把握することが難しいようだったので、1人でも作業できるよう、入浴時準備品リストと併せてまとめた視覚的な作業支援ツールの作成を行った。

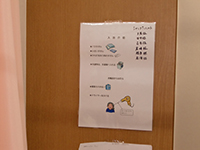
④ 現在の状況
時間の経過とともに作業の効率も良くなり、Aさんの動きもスムーズになってきた。仕事に対する意欲や責任感も生まれ順調に進んでいた。ちょうどその頃、本人は善意で行った行動が、そう受け止めてもらえずに厳しい言葉を受けたことがあった。それは、デイサービスはさまざまな高齢者が利用しており、なかには配慮が必要な人もいるということであった。Aさんは無事に立ち直れるだろうか、仕事に復帰できないのではないかと周りが心配する出来事であったが、Aさんは気持ちを切り替え、「色々な人がいる。仕方がない」と割り切ることができて、直ぐに仕事に復帰することができた。
このようにAさんは、作業遂行面の向上だけでなく精神的にも大きな成長を見せ、定着支援として訪問する度に、生活支援ワーカーはその変化を感じることとなった。相手のことを考えた行動や立ち振る舞いを周りも評価し、何よりも自信がついてきたことが表情の変化として見てとれるようになった。
3. 障害者雇用の効果、今後の展望と課題
(1)障害者雇用の効果~個性を活かす
① 障害者雇用に対する経営者の思い
誰だって人間は、苦手な事と得意な事があって当然である。障害があるから、障害がないからということではなく、ひとり一人が活躍できる場所は必ずある、と社長は語る。高齢者福祉の分野でも各人の「できないこと」を見るのではなく「できること」を見て評価する流れに変わって来ているのだから、障害者雇用についても同じ視点を持つべきだ、と専務も熱い思いを口にした。
Aさんがこの職場に定着できたのは、このような経営陣の理解の下で、障害者として扱われるのではなく、一人の個性ある仲間として受け入られてきたからであろう。
② 障害者雇用の効果
実際にAさんの個性が、デイサービスに活かされている様子が窺える。
共に働く職員からは、Aさんは利用者の小さな変化に気付き、一度覚えたことは次から必ず行動に移していること、その素直さが利用者にもしっかり伝わり、良い関係が築けていることが評価されている。Aさんは現場のムードメーカーであり、Aさんが休みの時には日々やってくれていることへのありがたみを感じている、という声も上がっている。
利用者からは、「Aさんがいないなら、デイサービスに行きたくない」という声まで出ている。Aさんは、いつでも誰にでも同じ態度で接し、裏表のない純粋な気持ちで応対してくれるから、というのが介護職員としてのAさんに対する評価である。今では、Aさんは杏になくてはならない存在になっており、利用者や職員に必要とされる存在になっていると言えるだろう。なお、杏では、利用者に対してAさんが障害者であることを積極的には開示していない。
また、Aさんの母親は、母としてではなくひとりの介護職員としてAさんに接し、適度な距離で本人の成長を見守っている。職員も利用者も親子という捉え方ではなく個々の職員として見ており、そのこともAさんの成長につながっている。
今回は、デイサービスセンターのオープニングスタッフとして、Aさんと職員が一緒にスタートした。職員のほとんどが、知的障害者と共に働くことは初めてのことで、出来ること苦手なことや接し方をAさんと直接関わることで初めて知った。日々の業務の中で「何事にも素直な気持ちで取り組む」ことがAさんの個性であることに、職員全員が気付いていった。
「素直な気持ちで取り組む」ことが、結果として利用者へのきめ細かいサービスへとつながる。Aさんが示したことがデイサービスセンター事業に貢献し、Aさんの成長が周囲にも良い影響となって、杏の現在の形があるとも言えるのではないか。


(2)今後の展望と課題
Aさんには現状の業務を継続しながら、人と人とのふれあいを大切にしてもらいたいと杏の責任者は話す。介護者として直接的なスキルアップを求めるだけではなく、Aさんだからできる関わり方を大切にしたいと考えている。
今後の障害者の受け入れについては、認知症の人への関わり方が課題になるのではないか、とアズでは考えている。認知症の特徴や状況の把握には、障害者だからということではなく、一般的にも難しい問題がある。しかし、高齢者介護の現場で障害者自身の個性を活かしながら働けるチャンスはたくさんある。高齢者の地域ケアの分野で、障害者の活躍が進んでいくことを期待させるものである。
生活支援ワーカー 亀井 あゆみ
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











