みんなの笑顔とともに…共生・共働のあるべき姿
- 事業所名
- 青山商事株式会社 井原商品センター
- 所在地
- 岡山県井原市
- 事業内容
- 全国の洋服の青山、TSC、キャラジャへの商品発送
- 従業員数
- 86名
- うち障害者数
- 21名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 7 入出荷・ピッキング 内部障害 知的障害 8 値札付け・ピッキング 精神障害 6 値札付け・入出荷 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
全国の洋服の青山デリバリーセンターとして平成6年から稼動し、全国の洋服の青山やTSC(ザ・スーツカンパニー)キャラジャへ商品発送を行い、オンラインストアの運営も行っている。
(2)障害者雇用の経緯
平成11年より障害者雇用を始め、平成18年より知的障害者の雇用を始めた。
全てが手探り状態での雇用であったが、関連機関への相談などを繰り返し、社内で障害特性の勉強会を行うなど従業員の理解も徐々に深まり、現在は身体障害者7名、知的障害者8名、精神障害者6名の合計21名の雇用に繋がっている。
配置については障害特性を考慮して決定しており、指導方法にも注意をして業務を行っている。
障害のない者、障害者に限らず、誰しも長所があれば短所があり、欠点については容易に見つけることが出来るが、「まずはその人の良いところを見つけ、その人がどのような作業に向いているか?」、「どんな作業ならやりがい、達成感を感じながら継続雇用が出来るのか。」ということを話し合いながら、作業場所や担当業務を決定している。また入社するとグループでの作業を行うが、慣れてくると部署を変えて少しずつ責任のある業務に変更をしていくことがある。
それは本人のモチベーションを上げることももちろんのこと、今まで一緒に作業していた人への刺激にもなった。しかしながら、雇用拡大については順風満帆であったわけでなく、人数が増えるとそれに比例して起きる問題も増えていった。問題が起きた際に話をしてみると、ほとんどの場合が「作業の説明不足」「中途半端な指示」「それぐらい分かるだろう」という自分本位の進め方であるときに起きていた。
そんな時に助けてくれたのが同僚や関連機関の人達であり、個々の問題に対して根気強い対応を続け、障害者側はもちろん従業員側も改善を行いながら、現在雇用継続に向けて邁進している。


2. 職場の体制と作業の流れ、従業員から一言
(1)職場の体制と作業の流れ
センター内の作業は加工物流と呼ばれる値札付け作業や、商品を色やサイズで分けてセットアソートを組んだり、入荷出荷などの運搬作業、また出来る人には無線端末を使用した作業も経験してもらいながら、スキルアップに繋げている。
現在の入社時には全体朝礼で本人の自己紹介と共に障害特性を説明して、全従業員に理解をしてもらったうえで接してもらうようにしている。その方法を採用してから誤解から生じる問題も減り、お互いがよりよい関係を構築していけるようになってきている。
以前は一部の従業員しか知らなかったため、
「なぜ返事が出来ないの?」
「あんなこともわからないの?」
「何回同じことを教えたら出来るようになるの?」
といった不満が出されることもあり、当事者は作業をそれまで明るく楽しそうにしていたが、そのようなことがたびたび起これば沈みがちになり、作業中の笑顔は消えてしまうこととなった。しかし、それは障害特性を説明していないことで起きることであり、事前に情報を提供すればそれに対する準備も出来て、起こるであろう問題を想定することが出来るため、このようなトラブルを回避することが出来る。
作業を行ううえで問題が発生すると業務の流れが悪くなり効率も落ちるわけだが、前もって起きることが想定できていればそのようなことも少くなり、センターのモットーとしている明るい職場作りが出来る。
最初のころは当事者の欠点をさらすような気がしていて消極的だった障害特性の説明は、今では非常に大事なことであると認識を改め、情報共有することで従業員皆がフォローし、調子の悪いときにも早い対応が出来るようになった。
日々の作業については従業員も含めた班単位で行っているが、障害特性上、口頭での指示だけでは作業が難しい場合も多くあり、どのような伝達方法で指導するかを模索しながら、表や画像を使用した作業マニュアルを作成するなどの方法をとっている。その事が結果的には従業員全員の作業理解を深めることに繋がり効率も上がっている。
井原センターから全国の店舗へ商品を送るには何十万点、何百万点の商品を扱っているがその作業進捗率も一目瞭然で分かるようになり、以前は経験と感に頼っていた部分が「見える化」されてきた。それにより「だいたい、適当に、ちょっと」などのあいまいな表現も少なくなってきたように思う。
その他では近隣の支援学校や各関連機関より見学を受け入れたり、インターンシップの受け入れなども積極的に行っており、障害等級、障害特性を理解したうえでの雇用となることが継続雇用出来る基になっている。倉敷障がい者就業・生活支援センターで行われる、障害者を雇用する企業の集まり(チームプラス)にも参加させていただきながら、雇用を通じての問題や対応を話し合い各種勉強会にも参加して、そこで得た知識を井原センターへ持ち帰りセンター内の各班毎のミーティングで話し合う事にしている。
また洋服の青山ではスーツの販売を行っている上で、各高校への着こなし講座を開いているが、それを一部の高等支援学校でも開催しており、お店には障害がある人ない人を問わずご来店いただいている。あらゆるお客様に満足してもらえるようなサービスを提供するためには、通常ではなかなか訪問することの無い支援学校を店長が訪問して、自分の目で生徒を見て何が出来るかを感じることも非常に大切なことであると思う。もちろん着こなし講座ということで訪問するが、そこで当方もとても重要な勉強をさせていただいている。
雇用といえば会社だけのようであるが、障害者雇用については当事者はもちろんのこと家庭とも話をする機会が増えてくる。家庭ではきちんと仕事が出来ているかなど、会社の様子を心配されており、会社で起きたことを場合によってはお伝えすることも必要であると考える。お互いが安心して雇用を継続する上では非常に重要なことであり、障害にもよるが必要に応じて家庭と会社がパイプで繋がり情報を共有することで非常に大きな安心感が生まれてくる。会社外での生活についても知ることで、社内での変化に敏感に対応することが出来るようになるわけである。
平成22年8月には岡山県手をつなぐ育成会から知的障害者の長期雇用に関して表彰を受けた。周りのフォローがあって始めて成り立つ継続雇用である。センター内で働く従業員には本当に感謝している。

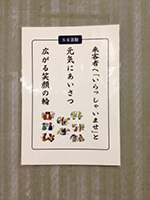


(2)従業員から一言
【身体障害者Aさん】
彼は7~8人のグループで指導を行い、率先して作業に取り組んでくれている。経験も豊富で10年以上勤務のベテランである。
| Q. | 楽しいですか? |
| A. | 毎日皆と明るく仕事が出来るのでとても楽しいです。 |
| Q. | 困ったときにはどうしている? |
| A. | 困ったときにもグループなので周りの人(社員)にすぐ聞くことが出来るので大丈夫です。 |
| Q. | 大変なことは? |
| A. | 重たい荷物を皆が自発的に持ってくれないことかな。 |
| Q. | そんなときはどうする? |
| A. | 自分が頑張りますが、声を掛けると皆も手伝ってくれます。 |
| Q. | 今からどうしたい? |
| A. | 毎日楽しいので継続して行きたいです。給料を上げてほしいな… |
| Q. | 給料は何に使っているの? |
| A. | 服やDVDを買ったり、食事に行ったりしています。 |
【知的障害者Bさん】
彼は入社2年目で支援学校在学中にインターンシップを経験して入社。
| Q. | 会社に入ってどうですか? |
| A. | 仕事が楽しいと思います。 |
| Q. | 困ったときにはどうしている? |
| A. | 周りの先輩に聞いて教えてもらっています。 |
| Q. | 休憩時間は何してる? |
| A. | 自分の好きな本を読んだり、ジュースを飲んだりしています。休みの日には家族と買い物に行ったりしています。 |
| Q. | 井原センターに入社してよかった? |
| A. | はい!よかったです。これからも続けていきたいです。 |
【現場責任者より一言】
障害を持った各人が職場規律を守りながら毎日笑顔で作業をしている。
「できる人ができる事をやる」という使命のもと、各々が助け合い、補完しながら作業を進めている。
共通の仕事を通して、身体障害者、知的障害者共に自分に出来ることで時間を共有している。


3. グループ就労について、取り組みの効果と今後の課題
(1)グループの就労について
この仕組みは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金制度によるもので、1ユニット5名の障害者に対して1名の支援員が企業内において請負契約に基づき行う取り組みである。
多機能事業所における利用者工賃倍増に努める中、担当者との思いが通じ、めでたくグループ就労が開始された。
多機能事業所内では出来ることも限られており、就労機会、就労経験を積むことも困難な中、本事業を行うことにより「職場実習!工賃確保!障害者雇用につながる!」といいことばかりである。
利用者からは「青山に行きたい!」「青山がえ~!!」という人ばかりとのこと。
「休むことなく出来ることを支援員が責任を持って出勤時間内に支援させて頂き、ご迷惑の無いように仕事をさせていただいています。」とは、社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会岡田氏からの声である。
この仕組みはインターンシップと比較して、長期にわたり作業の様子を見ることが出来る事と、支援員が居る事で企業への負担が掛からないということである。一年間に一人の雇用をすることについては、長期間見ることで判断もしやすくなり、何より全従業員が障害者雇用の重要性を理解しやすくなるということである。作業については慣れるまでに多少の時間は掛かるものの、最近ではスピードも上がり十分な戦力として作業に取り組んでいただいている。
しかしながら良いことばかりではなく、1年間という期限で行うため企業に仕事があるということが前提となり、そのことがこの仕組みが広がらない一つの原因ではないだろうかと考える。
この仕組みがもっと広がるように企業側が業務の見直しをすることも必要ではないだろうか。


(2)取り組みの効果と今後の課題
井原商品センターでは、従業員86名中21名が手帳を持っており雇用率は24.4%になった。
雇用率が増加するにつれ支援が必要な人も増えるため、安定した雇用を継続させていく為に第2号ジョブコーチ(企業内ジョブコーチ)の資格を取得し、今まで見よう見真似で行っていた対応も、専門的知識を取り入れた対応ができるようになった。障害者への支援や面談を行い、個々にマッチングした作業マニュアルを作成し、従業員には障害特性についての勉強会を開催している。
障害者雇用を進めていくと、さまざまな壁にあたる。
一つの壁を越えるとまた次の壁といったことにもなるわけであるが、決して一人ではうまくいくものではない。従業員または行政や福祉機関の人の協力も頂きながら一つずつ乗り越えていっている。しかし、いつしか今まで壁だと思っていたことは、壁に感じなくなってきた。
『いつ自分や家族が障害をもつことになるか分からない。
言えるのは、皆なりたくて障害者になった訳でないということ。
「できる事をできる人がする」ということである。』ということを思い、
弱い立場の人へどのような支援の手を出せるのか、自分の家族だと思えば出来ることではないかと思う。
今後は従業員に有資格者を増やすことで知識を深め、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害がある人もやりがいを感じ、お互いが楽しく、笑顔で働くことが出来る職場を構築して、共に生き、共に働く喜びを感じ、全ての人が達成感を味わえる事が出来れば素晴らしいと思っている。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











