繊細で義務感の強い精神障害者の雇用が進んだ事例
- 事業所名
- 社会福祉法人徳島県心身障害者福祉会
指定障害者支援施設 あおばの杜 - 所在地
- 徳島県徳島市
- 事業内容
- 障害者支援施設
- 従業員数
- 58名
- うち障害者数
- 2名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 1 生活支援員 内部障害 知的障害 精神障害 1 洗濯及び清掃業務 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
昭和52年、社会福祉法人「徳島県心身障害者福祉会」を設立。翌年、定員30名の精神薄弱者更生施設(通所)「おおぎ青葉学園」が認可される。平成14年5月、知的障害者更生施設(入所)「ジョイフル若葉」(定員35名)開設。平成19年10月1日には、「おおぎ青葉学園」「ジョイフル若葉」が障害者自立支援法による新体系へ移行、施設名を「あおばの杜」に改称し、下記サービスを開始する。
サービス概要
| ●生活介護 | 定員 | 65名 |
| ●就労移行支援 | 定員 | 10名 |
| ●就労継続支援B型 | 定員 | 20名 |
| ●施設入所支援 | 定員 | 35名 |
| ●放課後等デイサービス | 定員 | 10名 |
| ●短期入所事業(1日) | 定員 | 5名 |
| ●日中一時支援事業(1日) | 定員 | 10名 |
| ●相談支援事業 | 相談受付 |
なお、「あおばの杜」の経営理念として次のように掲げている。
<私たちの願い>
私たちの施設は心身にハンディーを持つ子らの幸せを守るために、親や社会の人々が心をこめて創ったものです。
この人たちの幸せは、親や職員はもとより、行政や地域のすべての人々の心がこの人たちの心と一つになったとき生まれます。
心が一つになること、それは愛です。愛こそ喜びのみなもと、幸せのもと、平和のいしずえです。私たち職員は親や周りの人々と協力し、愛をこめてこの人たちの人権を守り、ともに喜び生きがいを見いだしていきましょう。
この人たちが不幸でいるかぎり、世界に平和は訪れません。
この人たちが幸せになるとき、世界に平和が生まれるのです。
(2)障害者雇用の経緯
当事業所は障害者雇用について日頃から念頭に置いており、利用者・その家族・地域社会が交流できる、福祉システム作りの核となるような機能を持った職場づくりを目標としている事業所である。しかし、障害者の雇用継続には至っていなかった。
今回、ハローワークや障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携を図ることにより、障害者雇用に繋げることができた。
雇用したのは精神障害者保健福祉手帳を持つ男性Mさんである。
Mさんのこれまでの職場では、障害に対する理解不足や、障害をオープンにしたことにより、人間関係の構築に悩むなど、就労継続が困難な状況であった。
障害者職業センターでの相談・検査や、ハローワークにおいて自分に合った労働条件や職場環境を探して、長期間求職活動を行っていた。
当事業所の面接時に、本人のマナーを大切にした発言や、就労への強い意欲を感じ、受け入れを決定した。
受け入れについては、まず障害者就業・生活支援センターによる職場実習を設定するとともに、ジョブコーチ支援事業を利用し、ジョブコーチとの連携を図りながら、業務の構造化や支援体制の整備などを実施した。
現場のスタッフにおいては、これまで精神障害者を雇用したことがない職場であったため、一緒に働くことへの不安を感じていたようだった。
業務を進めるうえで、本人との接し方や、業務の指示の出し方など、就労移行支援や就労継続B型の利用者の人たちとは、また違った存在に戸惑うこともあったようである。
そのため、障害者就業・生活支援センターの協力や、ジョブコーチと密に連携を図り、その都度、Mさんについての相談や情報交換をしながら、一緒に仕事の役割を決定し、改善が必要だと思われるところは、その都度改善していき、より働きやすい環境作りに努めてきた。
また、スタッフ間においても、食事や休憩時間を利用して、Mさんとのコミュニケーションを積極的に図ることにより、お互いの理解が進んだ結果、実習終了後の雇用へと繋がった。
2. 取り組みの内容
(1)業務と職場配置
障害者Mさんの作業内容は主として洗濯業務である。利用者のパジャマや衣類、尿や便失禁により汚れた衣類を回収し洗濯する。入浴時のタオル、マット類の洗濯も行い、その後、利用者個人の衣類等については、各居室へ運び返却する。また、洗濯機や乾燥機作動中の手が空いた時間には、施設入所支援施設の各フロアのトイレの掃除も担当している。
(2)業務遂行の工夫
まず、本人の職務内容に応じた業務マニュアルを作成し、タイムスケジュールに沿って詳細な業務の流れを把握できるようにした。洗濯業務では、フロア別の洗濯カートや男女別の洗濯ネットを準備し、スタッフ間でもその使用を徹底することで、Mさんの業務遂行をスムーズにした。また、突発的な洗濯物等については、スタッフとの引き継ぎを確実にするため伝言カードを利用した。それに加えて、2度の洗濯が必要な汚れものについてはマグネットを利用し、1回目、2回目の洗濯であることが解りやすいように視覚的な工夫を行い業務の効率化を図った。
特に、Mさんは対人業務での緊張が高いことに加え、真面目で責任感の強い人であるため、昼休憩の時でも早々に切り上げて仕事に取りかかる等、一生懸命さはあるものの、一日の仕事の中で適切なワークバランスを考えて取り組むことが難しい状況にあった。改善策として洗濯室の環境を整備することとし、洗濯室での休憩が出来るように作業空間の確保や空調設備の充実など、オフィスアメニティーの向上を図ることで精神面での余裕が生まれ業務の向上に繋げることができた。



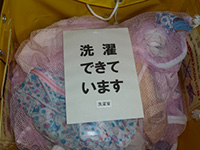



(3)障害特性への対応
洗濯業務の遂行については、業務時間内で全ての洗濯物が片付くわけではなく、定時になると、夜勤スタッフに引き継ぐことになっていた。「スタッフのために、少しでも業務を進めて、引き継ぎたい。」との本人の思いや、中途半端なまま業務を終えたくないという気持ちから、定時を超えても退勤せず徐々に勤務時間が長くなる傾向があった。
そのため、これらのことがストレスに繋がらないように、洗濯室にはアラーム機能がついた時計を準備し、業務時間の意識付けを行った。
加えて、スタッフが業務中や終業時近くに業務遂行の様子を見に行き、声かけを行ったり、引き継ぎ時間にはスタッフが洗濯室へ出向き本人との引き継ぎを行うなど、精神面に配慮したスムーズな引き継ぎ・退社ができるよう支援した。
(4)支援機関との連携
ジョブコーチによる専門的な支援を受けることにより業務の構造化を図り、現場の職員やジョブコーチ、障害者就業・生活支援センターが協力し、その都度、相談・情報交換しながら、Mさんと一緒に仕事の役割を決定し、改善が必要なところは、その都度改善していき、より働きやすい職場環境作りに努めた。
3. 取り組みの効果、今後の展開と課題
(1)取り組みの効果
障害者Mさんにとっては、業務遂行においてマニュアルの整備や視覚的効果を利用するなど各種の工夫を行うことにより、業務の理解や把握が容易となり、スキルアップが図れた。
また、業務の流れが理解できたことから、Mさんの仕事に対する不安も軽減され、精神的に余裕をもって業務に取り組めるようになった。そのことから、不眠や体調不良など健康面や情緒面での安定が図れ、雇用の継続が図られている。
Mさん自身も「雇用に繋がったことから、経済的に安定し、自立に向けてスタートラインに立てた。また、今まで障害をオープンにすることにより、周りとの壁を感じる場面も多くありましたが、現在の職場は理解があり、安心して働くことができます。」と話している。
企業にとっては、今までスタッフが利用者の支援の合間を縫って行っていた洗濯やトイレ掃除の業務を、Mさんのスキルアップや雇用の安定が図れたことにより安心して任せることができるようになったので、現在はスタッフも利用者への直接支援に力を注ぐことができる状況になっている。


(2)今後の展開と課題
障害者の雇用については、働く環境を整備することが重要であると考えている。その上で、業務プログラムを構築し、本人の能力を最大限に活かせる職場環境づくりに職員一同で取り組んでいる。
また、長期計画で本人のスキルアップを図るとともに、雇用の継続を目標としている。
Mさんについては、真面目で上手く力を抜くことができなかったり業務がスケジュール通り進まない等が本人のストレスになるなど支援を必要とする場面もあったが援助により解決し、今後も支援機関との連携を図っていくことにより継続雇用に繋げていきたいと考えている。
最後に、この事例が広く周知され、障害者雇用が促進されることを望んでいる。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











