自社の業務に合う者だけを採用し、徹底した教育・研修で障害者雇用を実現している例
- 事業所名
- 株式会社日の丸交通
- 所在地
- 鹿児島県鹿児島市
- 事業内容
- タクシー業(一般乗用旅客自動車運送業)
- 従業員数
- 101名
- うち障害者数
- 10名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 1 乗務員 肢体不自由 3 配車係1名、乗務員2名 内部障害 6 運行管理者1名、乗務員5名 知的障害 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
昭和59年(1974年)、ある地元企業の関連会社の一つであったタクシー会社を、その企業から引き継いだ株式会社町田建設が、自社のタクシー部門として新たな屋号で営業を開始したのが始まりである。
平成5年(1993年)、株式会社町田建設から分離し、株式会社日の丸交通として独立、現在に至る。
この事業では必要不可欠である無線設備を業界内でもいち早くデジタル化し、鹿児島では他同業者に先駆けて全営業車に防犯ボード(運転席後方の透明な仕切り板)を設置しドライブレコーダーの導入を進めるなど、常に業界をリードする会社である。
自らを叩き上げと称する荒田榮男社長は、現在、タクシー協会の理事も務める。自身がタクシードライバーや運行管理者としての経験を持つ、現場に精通した経営者でもある。この社長のキャリアが、同社独自の研修制度、引いては障害者の多数雇用につながっている。
(2)障害者雇用の経緯
障害者を雇用していたり、障害者雇用に深い理解を示すもしくは積極的な考えを持つ経営者等に話を伺うと、多くの場合、障害者に目を向けることとなった、あるいは雇用することとなったきっかけや動機につながる「何か」を持っている。
それは人それぞれ違うのだが、例えば
① 経営者自身が障害者である
② 身近(多くの場合は身内)に障害者がいる
③ 小中学校に在籍中、学校内で養護学級の児童生徒と触れ合った経験を持っている
④ 従前の勤務先で、障害者である同僚と一緒に働いていた
⑤ 取引先等の障害者とかかわりを持った
⑥ 他者(知己、親戚、学校や施設関係者など)に頼まれた
といったようなことである。
こうした状況や経験が、ある時は障害者を雇用するのは企業の社会的責任であるといった考え方を持つことにつながり、またある時はこれまで持っていた障害者に対するある種の偏見「障害者は障害のない者より仕事遂行の面において劣っている」を打ち破ることにつながる。そしてこれが障害者雇用の動機やきっかけとなるのではないだろうか。
しかし、本事業所が、会社として最初に障害者を雇った経緯について詳細ははっきりしない。
現在在職中の10名の障害者は、在職中に障害者となったいわゆる中途障害者もいれば、ハローワークを通じてトライアル雇用を活用して入社した者もいれば、入社の際には障害者とわからず、所得税の年末調整の際に自己申告がなされて初めて障害者だったことが判明した者等々、様々である。
「年末調整事務の際に判明」などというのはいったいどういうわけなのだろうか、入社の際に障害者がそうであることを隠していたということではないのかといささかいぶかしく思いながら、そのあたりのことについて意地悪い質問であることを承知で尋ねると、同社の荒田社長はにこやかに笑いながら答えてくれた。
「年末調整では、少しでも税負担を軽くし、還付を受けたかったんでしょうな。そういう者が1名や2名じゃなかったので、私もびっくりしました。ですから、会社としては、障害者を積極的に採用してきたつもりはなくて、いつの間にか障害者が増えていたという感じなんですよ。でも、皆、まじめで、一生懸命で、障害のない者とも全く遜色なく業務をこなしてくれているから、まあ問題はないんです。障害があろうとなかろうと、そんなことは関係ありませんよ。」
2. 障害者の職場配置と職務内容、障害者雇用の理念、障害者採用のポリシー
(1)障害者の職場配置と職務内容
タクシー業は、障害者雇用率算出の際の除外率が高い業種であり、障害者を雇用することの困難度が高い業種であるということであるが、同社においては10人に1人に近い割合で障害者を雇用している。
これは驚異的な数値である。こんなことを可能にした、その秘密を明らかにするためにも、同社では障害者がどのような職務についているのか、一部の障害者について障害の態様と担当する業務内容を具体的に紹介することとする。
Aさん (心臓の機能障害(3級)/勤続24年)
運行管理者を務めている。ドライバーの運行管理だけでなく、営業活動もこなしている。
Bさん (左腕が上腕部から切断(2級)/勤続15年)
無線配車係を務めている。顧客からの電話を受け、待機中のタクシーや現場に近い空車を見つけて配車する。
電話もデジタル配車システムも、右腕一本で器用に扱っている。
Cさん (左手の親指の欠損(4級)/勤続1年)
職業安定所からの紹介。トライアル雇用を利用した。
タクシー利用者の中には、指が一部欠けていることにクレームをつけたり不快感を抱く者がいないとも限らないため、指の欠損を目立たせないよう、乗務中のドライバー手袋着用を義務付けている。
また、営業車の清掃作業で使用するタオルを洗って(特に)絞ることに不自由することもあるので、洗車場に洗濯機を設置したり、また近くにいる者がサポートするなどしている。
その他、人工透析を受ける必要がある者については、勤務スケジュールに配慮している。同社における障害者雇用体制の特徴の一つとして、障害者向けの機器類、補助具等は一切使用していなこと、肢体不自由者のために改造を施すといったようなハード面における特別な配慮は一切していないことがある。もちろん、タクシーも全てノーマル仕様である。
(2)障害者雇用の理念
同社の障害者雇用の理念はいたってシンプルである。
一言で言えば「障害者も障害のない者もみな同じ」ということだ。
障害者に対して必要な配慮はするが特別扱いすることはないし、もちろん贔屓もしない。研修や教育は、障害の有無にかかわらず全員全く同じ内容で行う。
業務遂行に支障がなければ、一生懸命働き稼いでもらえばよいわけで、そこに障害の有無など入り込む余地はない。裏を返せば、業務遂行に支障が出てくるようであれば、障害の有無にかかわらず、それは自分で判断してもらいたいということのようである。
(3)障害者採用のポリシー
求人は基本的にハローワークへ求人票を出している。就職情報誌や新聞等に求人広告を出すことはない。
障害者、障害のない者、どちらの応募も受け付けることにしており、他方、一律に経験者優遇というわけではなく、同業者間を渡り歩いているような求職者は必要とせず、むしろ未経験者を歓迎するとのことである。また、障害の有無については採用面接時にきちんと確認するが、これは採用するかどうかの直接の判断材料としてではなく、障害者であっても業務に支障さえなければ採用するという意思を応募者に明確に伝えるためである。そして応募者が障害者である場合には、自社での障害者の勤務状況について、きちんと説明をするとも荒田社長は語る。
もう一つ重要なポイントがある。障害者であることを全面に出して、障害者だから特別扱いして欲しいと要求する者や特別扱いされるのが当たり前だと考えている者、あるいは障害のない者と一緒に仕事を行っていく上でわがままが出る者、いわば障害者であることに甘えている者は絶対に採用しないことである。
3. 障害者雇用に躊躇しない秘密・・・それは徹底した研修制度、最後に
(1)障害者雇用に躊躇しない秘密・・・それは徹底した研修制度
同社では、ドライバーに対する法定の安全研修、新入社員研修は、原則全て荒田社長自身が行っている。
社長には社長本来の業務があるわけで、これとの両立は、時間的にも心身的にも非常にハードだと思うのだが、これはどうしても外すわけにはいかないとのことである。
「ドライバーはうちの宝です。」と言ってはばからない荒田社長は、また「ドライバーは、一人ひとりが営業マンでもありますから。」と続ける。
会社が利益を上げそこに働く者が潤うためには、同社のドライバー全員が高い質を保っていくことが不可欠である。そのためにはドライバーに対する徹底した教育・研修こそ一番大切なことであり、ムラのない一貫した同質の研修を施すためにはこの方法しかないのだとも言う。




研修カリキュラムは、障害者も障害のない者も全くの同一内容である。それは車の清掃に始まり、マンツーマンでの路上走行研修にまで及んでいる。
社長自身もドライバーであった経験がここで生きてくるわけで、未経験者の場合なら、快適な乗り心地につながる運転方法、客の拾い方から、どこを流せばよいのか等々まで、みっちりと叩き込まれることになる。それもこれも、歩合制の高い給料であるがゆえに、大いに稼いでほしいといういわば親心からである。
研修において力を入れているのは、顧客及び自身の安全確保に関すること、顧客満足度の高位維持のために必要なこと、観光案内に関すること等である。
まず、何よりも、利用客の生命を預かる仕事であることは最重要、最優先事項であることを徹底している。また、タクシー業は究極のサービス業だと位置づけている同社において、CS(顧客満足)を非常に重要視することもまた当然である。
その他、観光案内についても研修を行っている。日に何件もある仕事ではないが、通常の営業よりも非常に歩留りがよいという特長を持っており、また、鹿児島を訪れる観光客には、歴史等に詳しい場合が多く、誤った知識で案内することはクレームにつながる恐れもあり、何より利用客の思い出に汚点を残してしまうことになるので、基本事項についてはきちんと研修を行っている。
また、地元商工会議所が主催する「ご当地検定」の受験も推奨しており、公式テキスト代や受験料を会社が負担する制度もある。

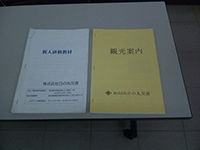
このように徹底した教育・研修を行うことで、障害があろうとなかろうと、経験者だろうと初心者だろうと、一人前のドライバーに育て上げるシステムが確立されている。だからこそ、障害者であっても業務に支障さえなければ採用できるし、長期雇用も可能なのであろう。
(2)最後に
タクシードライバーは、一旦、会社の車庫を出てしまえば、基本的には誰の助けも借りず、自分自身で判断し、行動しなければならない職業である。
そのため業務を遂行する上でヘルプを必要とする障害者は雇い入れることができないし、逆にこうした職務内容をこなすことに支障がないのであれば、障害者であろうと全く問題ないわけである。
誤解を恐れずに言えば、入口(採用)に厳しい関所を設け、徹底したふるいにかけて残った者のみを採用し、育て上げているのが同社の障害者雇用のカタチであろう。つまり、障害者雇用を成功させるために、採用時に最も力を入れているということである。
一見すると障害者に厳しい職場に見られそうだが、そうではない。自身がドライバーでもあった荒田社長は、ドライバーの安全、安心のための投資は惜しまない。安全や安心が確保されて、それが土台であってそこから全てが始まることを熟知しているのである。
障害者に厳しいわけではなく、障害者にも障害のない者にもみんなに分け隔てなく優しい職場なのである。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











