個人の特性、特徴に合わせて活躍できる職場
- 事業所名
- 電気化学工業株式会社 渋川工場
- 所在地
- 群馬県渋川市
- 事業内容
- 電子回路基板、放熱部材、エミッター、構造用接着剤、半導体プロセス関連部品の製造・研究開発
- 従業員数
- 229名(渋川工場)
- うち障害者数
- 7名(渋川工場)
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 3 研究、製品デリバリー、物流事務 内部障害 2 研究、電気保全 知的障害 1 構内整備、清掃 精神障害 1 構内整備、清掃 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯と現状、障害者が従事する業務
(1)事業所の概要
電気化学工業株式会社は、1915(大正4)年に設立された総合化学品製造会社で、本社を東京に置く。従業員数は、グループ連結で4,900名を数える。国内に6工場があり、渋川工場は1951(昭和26)年に塩化ビニル樹脂の製造工場としてスタートし、以降は同社の塩化ビニル系樹脂の製造拠点として発展してきた。1976(昭和51)年に、構造用接着剤ハードロックの製造を開始し、さらに1984(昭和59)年に電子材料事業に本格的に参入してから、事業領域の転換を進めてきた。現在では、電子回路基板、放熱部材、エミッター、構造用接着剤や半導体プロセス関連製品など、エレクトロニクス関連製品の生産に特化し、有機系電子材料の中核拠点として同社の成長の一翼を担っている。
(2)障害者雇用の経緯と現状
2003(平成15)年の全社労務担当者会議で「障害者法定雇用率の達成・向上を図る」がテーマに上がり、各工場で障害者雇用に積極的な取り組みが開始された。
渋川工場では、当時は4組3交替勤務となっており、また危険物を取り扱っていたので、障害者雇用は難しいと考えていたが、「障害者の働ける環境とは…」を考えながら管轄ハローワークの障害者担当雇用指導官と相談をし、障害者雇用に向けて活動を始めることにした。
また、当時は群馬県単独事業「障害者のための職場開拓事業」が行われており、この事業において障害者支援事業を行う社会福祉法人に配置された障害者雇用サポーターと連携することで、渋川工場では職場実習の受入れなどを実施し、障害者の職場へのマッチングを図っていった。
職場へのマッチングにあたり、「どこの職場でどんな作業があるか」を洗い出した。その際に、1.安全に作業できる場所、2.作業効率が落ちないこと、3.環境が整っていること、をポイントにした。同時に、ハローワーク主催の障害者就職面接会に参加し20名と面接し、この中から1名を内定したが、本人の都合でこの時は採用に至らなかった。
実際に採用となったのは、2005(平成17)年の知的障害者1名だったが、翌年になって前職の職場が忙しくなったとのことで、その誘いを受けて退職してしまった。2006(平成18)年に知的障害者1名と聴覚障害者1名を採用し、このうちの知的障害者1名が現在まで継続雇用となっている。
その後、2009(平成21)年、2010(平成22)年、2011(平成23)年にそれぞれ1名の身体障害者(肢体不自由)を、2010年に1名の精神障害者を雇い入れ、中途障害者(内部障害)2名を含めて、現在は総勢7名の障害者がそれぞれの担当業務で働いている。
2012(平成24)年6月現在の障害者雇用率は、渋川工場で4%超、全社で2%超となっている。
(3)障害者が従事する業務
障害者の担当業務は、内部障害者(2名)は研究(60歳代)、電気保全(60歳代)を、肢体不自由者(3名)は研究(20歳代)、製品デリバリー(40歳代)、物流事務(20歳代)を、知的障害者(1名、40歳代)と精神障害者(1名、30歳代)の2名は構内環境整備・清掃である。


2. 今までの取り組み
(1)職場への配慮
障害者の法定雇用率の達成には、人事部門が推進するだけでなく障害者が働く職場の従業員の理解が重要である。
渋川工場では、障害者を採用する前に職場実習を実施しているが、受け入れの際には、一番接する時間の長い職場の従業員の不安に配慮し、人事担当者は実習生の障害特性を把握して、適性にあう実習作業の選定や受け入れるタイミングについて現場の従業員と相談しながら進めている。場合によっては、ハローワーク渋川や障害者就業・生活支援センター「みずさわ」の就労支援ワーカーを交えて情報交換や職場対応を検討している。
(2)作業内容のマッチング
雇用の経緯でも紹介している通り、渋川工場では「障害者の働ける環境とは…」を常に考えて雇用の準備・継続につなげている。当初は、独身寮管理人の負担にもなっていた独身寮内の清掃作業を、比較的取り組み易いだろうからと2名(聴覚1名、知的1名)の障害者に任せる予定で採用した。しかし、雇い入れから数か月で、管理人との関係作りが上手くいかず、目が届かないところでの作業ミスなどが目立ち、配置転換や退職となった。
現在では、事前に作業内容をハローワークや障害者就業・生活支援センター、特別支援学校へ伝え、それぞれの支援機関で、ある程度のマッチングを行ったうえで面接・見学を行って本人の特性等の情報を収集し、その後に実習を行っている。この取り組みにより事前に見えてくるものも多く、採用後の負担が軽減されている。
(3)課題・問題への対応
マッチングにより課題・問題は減少するが100%は有り得ず、課題・問題を解決するための取り組みも行っている。当初の独身寮での取り組みでは、作業遂行に問題が発生した際は、ハローワークや障害者雇用サポーターと相談し職場訪問やケース会議などを行っていたが、改善があまりみられなかった。その後、雇用サポーターの提案で、障害者職業センターのジョブコーチ支援を利用した。ジョブコーチは、作業手順書の作成や社会人としてのマナーなどの指導・支援を行った。しかし、スキル部分の向上は見られたもののメンタル部分でのミスマッチは補えず、最終的に1名は配置転換、1名は退職となった。
現在は、マッチングの時点で時間をかけているため大きな問題はないが、ハローワーク・支援機関との連携で勤務時間の調整や本人のメンタル状況などを把握し、未然に問題を防ぐ取り組みとなっている。また、会社外の部分は基本的には支援機関に任せているが、本人自身の問題や会社へ言いにくいことなどを支援機関から情報収集して、会社としても関知を怠らないようにしている。
支援機関がかかわっていない障害者へは、人事担当者が適材適所を見極め、作業内容を調整し配置転換を行っている。
(4)障害者との関係作り
構内環境整備・清掃の2名(知的、精神)に関しては、率先して人事担当者が作業指示を行っている。暑い時季の休憩の取り方や、ミスをしてしまった時の注意の払い方などを教える際にも、両名の障害特性に合わせて、冗談を交えながら関係作りを行っている。また、部内での歓送迎会など福利厚生でも他従業員同様に声掛けを行い、参加を促している。
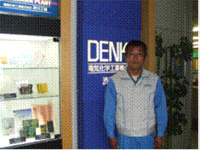
(人事担当者)

(除草作業)
(5)障害者就業支援に関わる制度の利用
当社では、障害者雇用に有効な3つの制度利用を行ってきた。
まずは、「トライアル雇用」である。障害者就業・生活支援センターの実習は一週間程度であるが、この制度を併用することでさらに3ヶ月間の見極めが可能になった。そのこともあって、現在「トライアル雇用」の利用者は、すべて継続雇用されている。また、本人や企業としても金銭的なメリットもあり非常に有効な手段と感じている。
次に「ジョブコーチ支援」である。障害者職業センターによるこの支援制度は、作業遂行については有効であったが、会社として集中支援後のフォローが行えなかったことは反省点である。もともとのミスマッチもあったが、継続的な支援があればメンタル的なフォローにもなるため、非常に有効と感じる点もあった。現在は、障害者就業・生活支援センターのワーカーやハローワーク担当者が、会社から離れた場面でコミュニケーションを取り、メンタル的なフォローをしている。
最後に、「特定求職者雇用開発助成金」である。この制度については、障害者の作業効率や生産力の低さを補うことができた。現在では、作業効率や生産力も伸びたが、当初の企業負担を考えると非常に有効だった。
各支援制度は、状況に応じて活用することで企業負担を軽減するものも少なくない。制度利用は障害者雇用に役立ったと考えている。
3. 社会的責任と今後の展望、課題
(1)地域社会、障害者就労支援機関や特別支援学校との繋がり
障害者雇用率達成や向上のほかに「地域社会と共生した工場を目指して」をスローガンに、環境維持と安全確保を基本として継続的な環境負荷の低減を進めるとともに、地域社会と共生した『いつまでも信頼されるものづくり企業』を目指し、省資源化と省エネルギー化およびCO2排出量の削減、化学物質の環境への排出量の低減と管理、廃棄物発生の抑制と最終処分量の低減、原材料および作品の含有化学物質管理の推進に取り組むとともに、環境関連法令などの厳守に努めている。
また、地域の催しへの積極的な参加や小中学校などの生徒や地元住民の方々を対象とした工場見学会や理科実験教室の開催などを通して地域とのコミュニケーションを図り、渋川工場に対する理解促進に努めている。特に地元自治会が委託管理されている国道17号中央分離帯のアジサイの植栽管理には『企業の地域貢献』の一環として全面的に協力している。
また、障害福祉との繋がりとしては特別支援学校からの見学や実習受け入れ、障害者就労支援機関の見学会、障害者福祉関係部会の見学(勉強)会などの受け入れを行っている。さらに、障害者就労支援機関に対しフィルムの汚れ落とし作業等の内職や当社内清掃などの施設外就労、施設外支援の場を提供している。


「ふれあいマーケット」

工場トイレの清掃

障害者施設内での洗浄作業
(2)今後の展望、課題
今までも、精神障害者、知的障害者の雇用を推進するために製造現場に実習を受け入れ、職場の従業員の理解、状態などを確認してきた。しかし、十分な理解を得られたのはまだ一部の職場であり、今後は、より多くの職場で受け入れの展開を図り、理解を深めたい。
また、障害者雇用率などの基準が上がるなか、雇用率達成ができていない子会社などでも促進を図っていきたいと考え、子会社でも2012(平成24)年4月に精神障害者1名を採用した。現在の就労時間は週15時間のため、短時間労働者としてカウントできないが、1年かけて徐々にステップアップさせていく予定である。また、子会社では、特別支援学校から新卒での知的障害者の雇用を目指して職場実習も受け入れており、2013(平成25)年4月には2名の採用を内定している。
このような課題や展望を考えるなかで、企業での障害者雇用に重要なことは「雇用のための準備、マッチング」「障害者、本人の特性を知る支援者との連携」「支援制度の活用」であると感じている。この点を踏まえ障害者が定着できる職場環境づくりに努め、雇用の拡大を目指したいという。

実習生の受け入れ

適性に合わせる
就業支援ワーカー 金子 孝史
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











