風通しの良い自由でオープンな社風で、障害者雇用に取り組む。
誰でもスキルアップ・キャリアアップのチャンスあり。
- 事業所名
- 株式会社トリニティアーツ 物流センター(現 株式会社ポジック高崎ディストリビューションセンター)
株式会社トリニティアーツ 事務センター - 所在地
- 群馬県佐波郡
- 事業内容
- 婦人服、紳士服、雑貨の企画・製造・販売
- 従業員数
- 物流センター 165名/事務センター15名 (2013年1月現在)
- うち障害者数
- 物流センター 20名/事務センター11名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 事務1 伝票、レシートチェック 肢体不自由 物流6/事務6 返品仕分け、段ボール解体・組立、清掃/伝票・レシートチェック、電話・メール応対 内部障害 物流3/事務2 荷受け作業・返品仕分け、清掃、ピッキング/電話・メール応対 知的障害 物流4 清掃、ピッキング、段ボール解体・組立、清掃 精神障害 物流7/事務2 清掃、ピッキング、段ボール解体・組立、清掃/伝票・レシートチェック、電話・メール応対 - 目次

(物流センター)
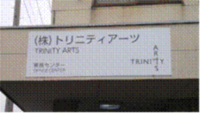
(事務センター)
1. 事業所概要
株式会社トリニティアーツは、前身の株式会社スタジオクリップとして、1982(昭和57)年5月に設立。本社は東京都千代田区、福岡(2007(平成19)年8月)と香港(2012(平成24)年7月)にオフィスを構える。資本金は3000万円、店舗数は207店舗である。
従業員数は社員669名、パート・アルバイト1,338名 計2,007名で、従業員の平均年齢は約30歳(2013(平成25)年1月)になっている。
事業内容は婦人服、紳士服、子供服及び雑貨の企画、製造、販売並びにアクセサリー及び皮製品の製造、販売で、現在、「ニコアンド(niko and...)、スタジオクリップ(STUDIO CLIP)、バンヤードストーム(BARNYARDSTORM)、リーブルメゾン(LIBRE MAISON)、アンデミュウ(Andemiu)」の5ブランドを展開している。
《トリニティアーツはモノやコトを通してライフタイルを提案し、世界をより豊かでハッピーなものにすることを目的とした企業である》
トリニティアーツは、ブランドが提案するスタイルに共感する人が、どんな小物を持ち家具や雑貨も含めてどういう生活をしているかをトータルで追及するライフスタイル提案型のブランドを展開している。デザイン性、価格、お客様の目線に立った販売体制、現場のニーズをいち早く商品化する企画〜製造〜販売までのスピード力などを武器にしている。今後も国内でさらに基盤を固め、アジアを皮切りに全世界に進出し、世界に通用する「グローバルブランド」を目指している。
企業の特徴は、徹底した「現場主義」で、スタッフには基本的に「任せる」ということで新しい力を引き出していく。そして、一人ひとりがスキルアップ、キャリアアップできる仕組みをつくっている。
また、風通しの良さや、言いたいことが言い合える自由でオープンな社風を大切にしており、こうした企業風土が障害者が働く上でも良い環境を生み出している。
2. 障害者雇用の経緯と障害者が従事する業務
(1)障害者雇用の経緯
当社は、2006(平成18)年12月の第二創業から5年余りで急成長し、株式会社スタジオクリップとの合併や新ブランド立ち上げで事業を拡大してきた。それに伴い従業員数も増え、障害者雇用の必要性が生じた。
そこで、障害のある方にできる業務を本部で検討し、群馬県佐波郡の同社物流センターで雇用をすることを決定した。それから、物流センター管轄内のハローワークに相談し、雇用制度や雇用までの流れの指導を受けて求人を出すことになった。その際、複数の障害者就業・生活支援センターも関わり、1次選考としての見学会⇒2次選考としての職場実習⇒最終面接を行った。そして、2010(平成22)年8月より物流センターで3名の身体障害者の雇用が始まった。また、1次選考の際、事務作業が適していると思われた2名は、同年10月から前橋市から同佐波郡に移転した事務センターで採用することになった。
それから、徐々に障害者雇用が進み、2013(平成25)年1月現在では物流センターで20名、事務センターで11名が、個々に合った作業内容で戦力となって活躍するまでになった。
採用する際には、時間管理ができることをポイントにしている。2010(平成22)年に初めて雇用された物流センターの3名のうちの1名は、フォークリフトの免許があることで、返品仕分け業務から荷受け業務に変更となった。また、1名が2012(平成24)年6月より、パートから正社員へ昇格している。
(2)障害者が従事する業務
物流センターの広い倉庫には、大量の段ボール箱が積まれ、たくさんの従業員が協力し合い手際よく商品がピッキングされている。ここから多数の商品が全国の店舗に発送されて行く。壁際を空調ダクトが走り、スポットクーラーも配備されて、労働環境の整備にも配慮が行き届いている。
ここでの従事業務と配置は次のとおり。
①段ボール箱の解体・組立と清掃業務:5名
身体障害者3名(肢体不自由2名・内部障害1名)、知的障害者2名
②フォークリフトを使った荷受け業務:1名
身体障害者(内部障害)
③全国の店舗から返送された商品の仕分け等を行う返品業務:2名
身体障害者(肢体不自由・内部障害)
④全国の店舗へ発送する商品のピッキングと清掃業務:12名
身体障害者3名(肢体不自由2名・内部障害1名)、知的障害者2名、精神障害者7名が2グループに分かれて配置され、身体障害者2名がグループリーダーになっている。
障害者各々の従事業務・勤務時間は採用3カ月後の面談で、物流センター責任者と障害者本人とが話し合って決めている。現在では、段ボール箱の解体・組立と清掃業務に従事する5名が週20時間勤務、他15名は週30時間以上の勤務をしており、当社にとって貴重な戦力となっている。
一方、事務センターでは、身体障害者9名(聴覚障害1名・肢体不自由6名・内部障害2名)と精神障害者2名(てんかん・発達障害)が、全国の店舗から集められたレシートや各種の伝票類を処理したり、電話やEメールに応対する業務に就いている。
オフィス内の雰囲気がとても明るい。事務センターという名前から想像した黙々と業務を進めるイメージとは裏腹に、活発に声を掛け合って賑やかなほどだ。精神障害者のひとり(発達障害)は、入社当時からは想像できないほど自分から話をするようになり、今では笑顔や冗談も見られるようになったとのことで、訪問した際にもその明るい笑顔を見ることができた。


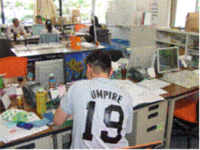
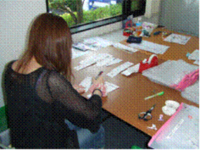
3. 障害者雇用への取り組みと障害者雇用の効果、今後の課題と展望・関係機関との連携
(1)障害者雇用への取り組みと障害者雇用の効果
① 物流センターの取り組み内容
【物流センター責任者に聞く】
『障害者雇用を始めた当初は、障害者とどう向き合っていったら良いか困惑していました。ですが、彼らに関わるごとに個々の障害特性や人柄を理解でき、接し方も解ってきました。今では、現場で一緒に働く障害のないスタッフにも理解をしてもらえるような指導をして、障害がある方の作業部署を決め、新入社員や派遣社員の方でも統一した接し方ができるように配慮しています。また、ピッキング作業では2グループに分けたことで、作業の能率も上がってきたと思います。
仕事に支障のでるような問題が起きた時は、「本人、家族、責任者、直接本人に関わるスタッフ、障害者職業センター、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域で支援する関係者など」でケース会議を開いています。また、様々な障害のあるたくさんの方が働いており、わが社のスタッフだけでは雇用管理が難しくなってきた為に、ジョブコーチ支援をしていただくようになりました。職場定着の為に、問題を整理し課題を見つけ、みんなで改善策を考えています。
障害のないスタッフともお互いに意見を言い合える環境作りを心がけ、障害がある方個々に合った作業内容・雇用条件で活躍していただいています。私自身も、彼らから得るものが多く勉強になっています。
物流センターの採用の流れは、職場見学→職場実習→採用決定です。今後も同じ流れで雇用を増やしていく予定です。』
② 事務センターの取り組み内容
【事務センター責任者に聞く】
『物流センターの責任者と同じように、最初は私も障害者と向き合うことに困惑していました。全くわからなかった障害のことを自分で調べたり、障害者就業・生活支援センターに相談しながら障害についての理解をしてきました。今は個々のできることとできないことが分かるようになりました。1つの仕事を進める時、できることをできる人がやり、できないところを他の人が補い、まだ完成しなければ他の人が補う。みんなが信頼し協力し合って事務センターの仕事をつくり上げています。
発達障害のある人は、初めのうちは過激な言葉も出たりしましたが、その言葉にこちらが過敏に反応するのではなく穏やかに理解を示していくうちに、その人の言葉も穏やかになっていきました。その人の障害を理解した上で、特別扱いするのではなく他の人たちと同じに接して来ました。
また、障害がある人の内から2名の方をリーダーに抜擢し、2つのグループをつくりました。常にリーダーを中心に仕事を進める方法を採り入れ、新規採用の方の指導もリーダーが行うようにしました。仕事上で問題が発生したときは、リーダーを中心に随時ミーティングを行っています。このことによって、責任者の負担が軽減し、効率の良い仕事ができるようになりました。また、小さなグループを作ったことによって、個々の意見が自由に言えるようになり、仕事に取り組む意識も高まりました。事務センター全体としても一人ひとりとしても、着実に成長できていると感じます。
今後の採用は、出店が増えることや事務所の移転、定年退職者などで欠員が出たときなどに必要に応じ考えていくつもりです。』
【事務センターのリーダーに聞く】
Aさん:『今まで働いてきた事業所との違いを感じています。以前の会社では、自分の意見は聞いてもらえなかったり取り上げてもらえませんでしたが、トリニティアーツでは聞いてもらえます。障害があっても、キャリアアップできる会社だと確信できました。』
Bさん:『体調を配慮していただけたり、勤務時間についての工夫をしていただきました。今まで任されなかった責任ある仕事もさせてもらっています。更に、スキルアップ・キャリアアップの希望も持てました。』
*トリニティアーツで働くことを二人の家族も喜んでおり、感謝しているとのことだった。
(2)今後の課題と展望、関係機関との連携
直近の事業計画では店舗数を300店舗に、国内はもちろん、海外展開で事業の拡大を目指しており、こうした中では、出店に伴う人員増に対応しつつ障害者雇用率をアップさせることが今後の課題である。
当社での障害者雇用は3年を経過するが、まだ試行錯誤をしている状況であり、今後、更に多くの障害者を雇用することになると、障害の種別の多様化への対応・業務内容の拡大や見直し・勤務条件の検討・環境の整備を図ることによる長期雇用や定着などについて、意識していかなければならないと考えている。
また、企業の社会的責任を自覚し、地域への社会貢献も視野に入れた上で、障害者雇用を進めていきたいとも考えている。そのために、事業所近隣からの障害者雇用を進め、地域の各障害者就業・生活支援センターや特別支援学校などと連携を更に深めていきたいと考えている。
障害者雇用に関する専門的な知識も必要になるため、ハローワークや関係機関(群馬障害者職業センター、群馬高齢・障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターなど)と連携し、一緒に課題を克服していきたいと考えている。また、国の助成金を活用し、障害者職業生活相談員を配置し、更には第2号ジョブコーチを配置することも含めて障害者雇用を進めるための方法を検討しており、将来的には特例子会社設立も視野に入れている。
これから、当社がどんなに大きくなったとしても、風通しの良い自由でオープンな社風は変わらないだろう。この良き風土は自然に生まれたものではなく、統合された会社の間にある壁を壊し、全社が一体となるために苦労を重ねて創り上げてきたものだから。そして、このような社風に共感して集まった社員のアイデンテティでもあるのだから。
障害のあるなしに関係なく、すべての従業員が同じ目線で、お互いの価値を尊重し合い、一緒に会社を創り上げていく努力をしていく。短期間に多くの障害者を雇い入れ、定着させた秘訣がここにあり、当社の急成長の原点もきっとここにあるのだろう。
主任就業支援ワーカー 岩﨑 美恵子
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











