視覚障害の方、および言語機能・聴覚障害の方の雇用事例
- 事業所名
- 株式会社PHP研究所
- 所在地
- 京都府京都市
- 事業内容
- 出版・研究・啓発活動
- 従業員数
- 348名(平成24年11月1日現在)
- うち障害者数
- 4名
障害 人数 従事業務 視覚障害 1 一般業務 聴覚障害 1 一般業務 肢体不自由 2 一般業務 内部障害 知的障害 精神障害 - 目次

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
株式会社PHP研究所は昭和21(1946)年11月3日、松下幸之助により創設された。PHPとは「Peace and Happiness through Prosperity」という英語の頭文字をとったもので、"繁栄によって平和と幸福を"という意味のことばである。
当時の日本社会は第二次世界大戦直後の混乱のなかで、人々は困窮した状態にあった。その光景を目の当たりにした松下幸之助は「これがこれまでの歴史において大きな進歩を遂げてきた人間本来の姿なのだろうか」と悩み考え抜いた末、「人間は物心とも豊かな繁栄によって、平和で幸福に生きることができるはずだ。その繁栄の道を衆知を集めて探求し、人々に訴え、呼びかけてよりよい社会の実現をめざしたい」と決意したのが始まりである。
そのための方策を幾多の先人や今日の有識者に学びつつ研究活動を続けるとともに、その成果を一人でも多くの人々に広めるため、月刊誌「PHP」をはじめとする各種雑誌や書籍、また、PHPゼミナールやPHP友の会など様々な媒体を通じPHP理念の実現を目指している。
(2)障害者雇用の経緯
当社は、企業は個人のものではなく社会の公器であるという創設者の松下幸之助の考え方に基づき、積極的に社会的責任を果たしていくべく、ハローワークと連携を取りながら障害者を雇用してきた。
最初に採用した社員(以下、A社員)は昭和58(1983)年から今日までずっと勤めてこられ、昨年60歳の定年を迎えた。その後も継続雇用という形で引き続きお力添えをいただいている。現在はA社員を含めて4名の障害者(平成24(2012)年11月時点)がそれぞれ異なる部署で勤務している。
2.取り組みの内容・効果
松下幸之助は「人間というものは、本来だれでも非常にすぐれた素質を与えられている、いわばダイヤモンドの原石のようなもので、磨けばすばらしい輝きを発するものである」と考えていた。
当社もその考えのもと、障害の有無にかかわらず、その原石を磨くためのOFF-JT、OJTでの教育訓練はもちろん、仕事の評価、処遇においても適性、能力、勤務態度、成果、人間向上、職場向上等の評価点により同等に実施している。
障害者を雇用する際はまずこういった当社の基本的な考え方を伝える。「社員の一員として今後、障害のない人と同じ土俵で仕事をしていくのだ」ということを自覚していただくためである。また同時に伝えているのが、今後実際に仕事をしていくにあたり、目の前の業務をただ単にこなしていくのではなく、会社全体が目指す大きな方向性や存在意義を理解したうえで、自分の仕事はその会社の目的を達成するための重要な役割の一部であるという使命感を持って取り組んでほしいということである。
仕事の配置にあたっては、もちろん障害のない人と同じ基準で適性、能力をもとに考えていくが、その結果、最初のうちは今の段階で持っている能力と適性に沿った仕事からお願いしていくことが多くなりがちになる。ただし、個々の仕事に優劣はなく、どの仕事も必要で大切な仕事であるので、大きなやりがいを持って行ってもらいたい。そのためにも自分の仕事がどのような形で会社の理念を実現するために貢献しているのかということを常に意識し、自分の仕事に誇りを持ち、全社的な視点で勤務してほしいということを伝えている。以下、現場の声を聞きながら、実際の勤務状況について報告する。
(1)B社員
平成22(2010)年入社の新卒社員(以下、B社員)は当社で初めて採用した強度の弱視という視覚障害のある人で、ハローワークから紹介された人である。音声読み上げソフトを活用し、ワード、エクセル、インターネットなどパソコンを使用した仕事が可能ということで、当社研究事業の基幹業務である松下幸之助が行った講演、講話といった音声記録を、書籍、論文、ホームページ掲載などのベースとなる文字データに起こす仕事をしている。起こした文字は音声読み上げソフトが読み上げるので、ただ入力するだけでなく、その後の校正も自ら行い、完成度の高い仕上がりとなっている。最初の数ヶ月は会社が用意した音声読み上げソフトとパソコンがうまく適合せず、音声の読み上げ方に誤りが多かったり、度々動作を停止してしまったりするなどで試行錯誤しながら最適なソフトを検討し、現在は不便なく使用できている。

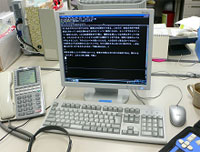
また、B社員は仕事に慣れ始めると、自ら進んで「他になにかお手伝いできることはありませんか」と周りの方や上司に聞いていた。その結果、郵便物の受取や、セミナー等で使用する会場の準備など、当初現場が想定していた以上に様々なことをお願いできるようになった。特に視覚障害者は当社も初めて採用したこともあり、どこまでの仕事ができるのか手探りの状態であった。現場としてもどこかでこの仕事は無理ではないかという限界を設定していたところもあった。そのような状況でB社員本人から、もっといろいろなことをさせてほしいという要望があったことは本人にとっても現場にとっても非常に良いことであったと思う。
平成24(2012)年の春ごろからは、同じフロアの編集部門が取材してきたテープ起こしの仕事も加わり、より仕事の幅を広げている。今後は現在のデータ入力の仕事をより早く、より正確に行っていくことを目指している。
(2)A社員
冒頭に紹介したA社員は、聴覚・言語機能の障害を持つ、当社商品の梱包発送作業の仕事を担当することで職業訓練を受講後採用した人である。
仕事ぶりは誠実で、社員からの緊急の依頼であっても快く引き受けてくれるので誰からも信頼されている。また、A社員自身も、終業後に社内で自身が講師を務める手話教室を開催し、多くの社員が参加するなど職場の人間関係の良化に積極的であった。こうしたことが本人の仕事も円滑にし、結果として定年を迎えられてもまだ引き続き勤めていただいている理由の1つとなっている。
A社員の現在の仕事は採用当時の仕事から変わっている。梱包発送作業中心の仕事から現在の仕事に変わったのは10年以上も前のことである。平成11(1999)年当社ビル移転に伴いこれまで自社で保有していた倉庫を廃止し、その業務を外注化することになり、梱包、発送の仕事が激減したため、新たな業務として通信教育業務のレポート発送作業や集計業務をお願いした。環境が変わり、さらにはこれまでの仕事とは違いコンピューターで照合するといった全く新しいことも覚えていくということで大変であったが、周りのサポートや、なにより本人が環境の変化にも適合するよう努力しようという気持ちで頑張っていただいたおかげで新たな業務も習得し、現在に至っている。
聴覚・言語機能障害ということで、障害のない人に比べればお互い頻繁にコミュニケーションを取りながら仕事をしていくということは難しいという事実はある。だからこそ、現場で作業を教える際は、他の人以上に、最初になぜこの仕事をする必要があるのかというその仕事の意義を力を入れて説明をし、そのうえで、本人が実際の作業方法などを十分に納得したうえで仕事に取り掛かって貰うということを意識している。
なお、朝会においては全体連絡や社員が日替わりで行う所感が発表されるが、どのようなことが言われているのかを同じ部署の人が隣でノートに筆記しながらお伝えをするといったことも毎日行っている。
また、日常のコミュニケーションは身振り手振りや簡単な手話、筆記等により特別な補助なしで行っているが、当社創設記念式典や、人事制度改定の説明等、とりわけ重要なものについては外部の手話通訳士をお呼びして正確に伝えている。
3.今後の展望と課題
平成25(2013)年4月1日から障害者の法定雇用率が2.0%に引き上げとなるが、まだまだ日本全体の人口に占める実際の障害がある人の割合に比べればこの数字は低く、今後ますます積極的に障害者雇用を促進していく必要がある。
しかし、実際の雇用となると、どういった仕事がどこまでのレベルでできるのかが不安な面はたしかに存在する。当社もそのような状態でどこまでお願いしてよいのかの見極めが当初はできずにいたというケースもあったが、障害者自身が現状に留まることなく、より多くの仕事を要望してくれるなどのおかげもあり、想定以上の幅広い仕事を任せることができている。そういったことからも現場は障害者の可能性を限定することなく、まずはフォローしつつも積極的にいろいろな仕事を任せていく姿勢が大切になると考える。
また、事前に職場実習の場を設けるなど、障害者と企業側が採用前段階でお互いの情報を可能な限り多く共有できるような工夫も必要ではないか。今後も多くの事例を参考にしつつ障害者雇用に前向きに取り組んでいきたい。
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











