障害者の適性分析と本人の希望により作業工程へのマッチングを図り、チームとしてリース品の再製化に励む
- 事業所名
- リベラル株式会社
- 所在地
- 東京都江戸川区
- 事業内容
- 中古ビジネスフォン及び中古複合機の清掃・販売、WEBサイト「OAリサイクルショップマウス」の運営
- 従業員数
- 20名(平成25(2013)年6月30日現在)
- うち障害者数
- 15名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 14 ビジネスフォン及び複合機の清掃・整備、商品の仕分け、出荷、データ入力及びシュレッダー業務等 精神障害 1 ビジネスフォン及び複合機の清掃・整備、商品の仕分け、出荷、データ入力及びシュレッダー業務等 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
- 会社設立等
会社設立:平成20(2008)年4月1日(営業開始:同年5月1日、同年10月21日ラディックス株式会社の特例子会社として認定)
親会社のラディックス株式会社は、法人向け情報化支援事業(電話機・複合機・パソコン等のハードウェアの販売、保守/業務パッケージソフトの開発、販売/レンタルサーバーサービス・プロバイダーサービス・IP電話サービス/ホームページの企画、制作)を事業内容としている。また、「ラディックス(RADIX)」は、ラテン語で根・根源を意味し、「常に未来に目を向け、関係する人々及び社会の中でしっかりと『根』をはれる企業」を目指している。
- 企業理念等
リベラル株式会社(以下「リベラル」という。)の企業理念は「障害のない人、障害のある人が共に歩み、働く喜び、やりがいを共有し、それぞれの能力を発揮しながら社会・地域に貢献できる会社」を目指すことである。社名「リベラル」(RIBERAL Co.,Ltd)には、障害者雇用において臨機応変(自由=Liberal)に対応することが大切であるということを認識し、障害のない人、障害のある人を問わず誰でも楽しく働ける、自由な環境を持ったラディックス(根)を作り上げようという「Liberal of RADIX」の思いが込められている。
- 事業の内容
・通信機器、複合機、コンピューター、その他の事務用品機器並びにこれらの周辺機器及び消耗品の販売
・中古通信機器及び中古複合機の販売、レンタル、リファイニング
・インターネットを利用した通信販売、電子取引決済事業、各種情報処理、情報提供サービス、マーケティング調査
(2)障害者雇用の経緯
- 障害者雇用の沿革
平成19
(2007)年6月 親会社ラディックス株式会社が雇入れ計画の適正実施勧告を受け、親会社の企画部門にて障害者の業務等調査 10月 ラディックス株式会社として特例子会社の設立を決定、特例子会社に関する調査を実施 平成20
(2008)年1月 「リベラル」設立準備開始、障害者の採用準備(作業場の内装等の企画、指導者の募集、特別支援学校の見学、障害者職業生活相談員資格認定講習の受講) 4月 リベラル株式会社設立、事業開始の環境整備(作業場の内装等の工事実施、取引先の新規開拓、障害者採用面接) 6月 トライアル雇用開始、複合機再生事業開始、障害者の作業テスト実施、作業マニュアルの作成 9月 知的障害者5名本採用、特別支援学校からの職場実習生受入れ開始 11月 特例子会社の認定、ビジネスフォン再生事業開始、他の特例子会社の知的障害者の業務調査 12月 江戸川区産業賞「心身障害者雇用優良事業所表彰」受賞 平成21
(2009)年3月 コピー機整備事業開始、積極的な外販開始 4月 東京都立白鷺特別支援学校の作業学習支援開始 8月 ビジネスフォンの外販開始 平成22
(2010)年4月 東京都立白鷺特別支援学校の作業学習支援拡大 平成23
(2011)年4月 WEBサイト「OAリサイクルショップマウス」本格稼働 平成24
(2012)年1月 平成23年度東京都教育委員会事業貢献企業等に対する表彰受賞 7月 障害者の業務拡大(コピー機整備、発送、梱包、仕分け、写真撮影、シュレッダー、洗濯、PC入力等) 12月 PC解体事業開始 平成25
(2013)年3月 事業所移転(事業拡大に伴い、小岩から西葛西へ移転) - 障害者雇用の推移
グループ全体(各年6月1日現在)
*( )内はダブルカウントを含む数平成19
(2007)年平成20
(2008)年平成21
(2009)年平成22
(2010)年平成23
(2011)年平成24
(2012)年平成25
(2013)年障害者数 2
(3)6
(7)11
(14)11
(14)16
(21)17
(23)17
(24)雇用率 0.5% 1.12% 2.16% 2.2% 2.6% 2.96% 2.93%
リベラル株式会社 単体(各年6月1日現在)
*( )内はダブルカウントを含む数平成20
(2008)年平成21
(2009)年平成22
(2010)年平成23
(2011)年平成24
(2012)年平成25
(2013)年障害者数 0
(0)5
(7)8
(11)14
(18)15
(20)15
(21)
2. 取り組みの内容
(1)採用
平成20(2008)年4月の会社設立時に採用した5名の知的障害者は年齢も特性も様々であり、なかには字の読み書き、計算が全くできない障害者もいた。作業の習得についても一度で覚えられる者、覚えるのに3か月かかる者等様々であったが、全員が一生懸命努力していた。こうした障害者の就労に対する直向きな態度に接した経験から、採用に当たっては以下の事項を重視している。
- 努力できるか
- 素直さがあるか
- 一緒に働きたいと思えるか
また、継続雇用のために保護者(または監督する方/機関)の対応(姿勢)を重視している。これは、障害者の成長をサポートするためには企業・家庭・就労支援機関の連携が重要であるという考えによる。
会社設立時以後の採用は、特別支援学校からの新卒採用と福祉作業所からの中途採用としている。
当社では、特別支援学校の作業学習に使う「実習」にリベラルの業務を提供(学校では当該業務の作業班を作っている。)し、毎週障害のない社員1名、障害のある社員2名を派遣し作業指導を行うといった支援を実施している。
そのようなことから、新卒採用に当たっては当該特別支援学校の卒業生を社員として受け入れている。また、中途採用は、リベラルの業務を委託している福祉作業所から行っている。委託先福祉作業所から委託業務にあたっている各個人の作業の理解度・習熟度を把握しつつ採用を行っているため、適切な人材の確保が可能となっている。
(2)障害者の従事業務
障害者が従事する業務は以下の6業務である。
- 中古ビジネスフォンの清掃・整備
- 中古複合機の清掃・整備
- 商品の仕分け
- 商品梱包作業
- パソコンデータ入力
- シュレッダー業務等
会社設立から1年間は主に中古複合機のリファイニング作業を障害者は行っていたが、2年目からは中古ビジネスフォンのリファイニング作業を開始し、現在はパソコンデータ入力作業、商品の仕分け/梱包/発送補助作業、複合機パーツのリペア作業等を行っている。これらは作業能力と障害特性を考慮し、徐々に職域拡大を図った結果である。
(3)業務(中古複合機の清掃・整備)の作業工程と作業担当者
- 受入検査・分解作業・整備作業・組立作業・外観検査・機能検査
【作業担当者】障害のない社員 - 清掃作業(分解部品の清掃)
【作業担当者】知的障害者 - 梱包・発送
【作業担当者】障害のない社員及び知的障害者
※下記は各種作業の状況

中古複合機の清掃作業
|

中古複合機の整備作業
|

中古ビジネスフォンの清掃・整備作業
|

商品の仕分け作業
|

商品梱包作業
|
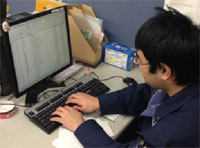
パソコンへのデータ入力作業
|
(4)指導
指導は、まず作業の核となる基本技能を障害者全員に時間をかけて覚えてもらい、その後障害特性や向き不向きを考慮し指導を行う。
- 基本技能の習得
- 方法: マンツーマンによる指導を徹底的に行い、簡単な作業から徐々に難しい作業に移行させる。
- 手順: 以下の作業手順で指導している
| 最初は簡単な作業を行う ↓ やり直しがないように作業を行う ↓ 目標時間を設定し作業を行う ↓ 時間を徐々に短くし作業を行う |
- 時間/日数: 基本技能の習得にかかる日数は平均して3か月である。
- 指導の基本とステップアップ
a.正面から向き合う
企業就労において基本的に必要な「努力」や「忍耐」といったことについても、障害者に合わせていくのではなく、正面から向き合えるように指導している。
会社設立から2年経過したころ、2名が退職した。最も大きな原因は、障害者に対する遠慮や障害者への踏み込みが甘かったことである。当時は『障害者だから・・・』という考えで対処する事象も多く、正面から向き合うことを避けていた。退職者が出た後、それまでの取り組みが本当に正しかったのかについて検討を行い、その結果これまでの取り組みを改め、問題が起きたときはその場で本人が理解するまで徹底的に話し合うなど、彼らと本気で向き合うことにした。もちろん、このことは障害者も同様で、「できない」、「わからない」、「むずかしい」からと逃げずに工夫と努力をするように指導している。
b.ステップアップ
リベラルでは、障害者の人財育成の一つとして、障害者が『教えられる立場から教える立場』として「リーダー」にステップアップするための取り組みを行っている。
仕事を通じリーダーとなる障害者に求めていること(分解部品の清掃担当リーダーの場合)は、以下の事項である。
・働く仲間に信頼されることを意識する
・リーダーはチームをまとめるべく指示/命令をしっかり出す、強い責任感を持ちチーム作業でのミスやトラブルに全力で対応する
・チ-ムのメンバーに対し謙虚さと尊敬の念で接する
・チームメンバーの作業確認については、本来100%であるべき合格ラインを90%~100%の範囲で合格とし、メンバーに自信を持たせるように配慮する
(5)地域との連携
- 特別支援学校の「作業学習」への支援
前述の(1)のとおり、特別支援学校での作業学習にリファイニング作業(コピー機再生班、電話機再生班)を取り入れてもらい、講師として障害のない社員及び障害のある社員2名を週1回派遣し、企業就労を目指す生徒に企業の作業に取り組む心構え、安全、5S、作業手順等について直に伝えるとともに、卒業後社会人となることを見据えた言葉遣い、コミュニケ—ションの取り方等の指導を行っている。
- 実習生の受け入れ
特別支援学校/就労支援センター/福祉作業所から実習生を受け入れ、短期間で作業習得ができるように指導を行っている。特に実習生が抱えている以下の課題について作業を通じて改善し、実習生の成長を企業全体でサポートしている。
- 挨拶・返事ができない
- 集中力が無い
- 友達口調でしか会話ができない
- ハキハキとした受け答えができない
- 時間にルーズである
- わからないことでもわかったとすぐ言ってしまう
- すぐに『できません』と言ってしまう
- 気に食わないことがあると何もしたがらない
- 地域の社会福祉法人の事業への協力
前述の(1)のとおり、リベラルで行っているビジネスフォン及び複合機の清掃業務については、利用者の工賃アップのため地域の社会福祉法人に一部業務委託を行っている。中途採用時の即戦力人材の確保のためにも有効に働いている。
(6)余暇活動
毎年日頃の体の疲れを癒す社員旅行を実施しているが、大変重要な役割を果たしている普段言えないことや考えていることを会社とは違う環境で上司・部下の垣根を越えて話すことで、社員同士の融和と結束が深まり会社の発展に繋がっている。
3. 取り組みの効果、今後の展望
(1)作業指導を通した障害者感の変化
リベラルでは障害者への過度な配慮は、逆に彼らの能力の開花を妨げると感じている。
『かわいそう』、『きっと無理』や『これはむずかしい』といった考えは設立当初にはもちろんあったが、日々彼らと向き合い、彼らを知ることで、コツコツ努力を重ねる頑張り屋という見方に変わっていった。もちろん何かを習得するには障害のない者とは比較にならないくらい時間も掛かるし、理解させるにも色々と工夫が必要である。しかし、そのことがわかれば、戦力として障害のない者と共に企業を支えていける人財になる。『やってみる』、『やらせてみる』と彼らを信じたことで、ひと皮もふた皮も剥け大きく成長している。
(2)社会性、一般常識等についての障害者指導の基本と今後の展望
障害者の成長過程で守られてきたことを考えると、以前は仲間に迷惑をかけたり、嘘を言ったり、ごまかしたりということについて、時には厳しく叱ることもあったが、障害者だから仕方がないと片づけてしまうことが多かった。しかし、今は問題が起きたときはその場で本人が理解するまで徹底的に話し合い、課題解決に取り組んでいる。
そのことにより彼らは見違えるような変化を遂げている。「君と一緒にがんばりたい」、「君が必要である」、「でも今のままではダメである」と真剣に向き合い、話し合ったことが彼らの行動を変える結果に繋がった。
リベラルは、このように障害者が一人の社会人として成長していける環境の創造に努めており、今後もこれを継続していきたいと考えている。
副理事長 小林 幸夫
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











