小さな精肉店から拡充し、地域の発展に貢献、障害者にも優しい企業になった事例
- 事業所名
- キドフーズ株式会社
- 所在地
- 愛媛県喜多郡
- 事業内容
- 食肉販売業、惣菜製造業、食品の冷凍又は冷蔵業
- 従業員数
- 72名(うち正社員15名、パート57名)
- うち障害者数
- 4名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 2 惣菜加工と工場内衛生管理(主に清掃) 精神障害 2 冷凍前の食材加工、惣菜加工 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

本社(原点の精肉店)
|

工場外観
|
1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
- 会社沿革
- 昭和53(1978)年9月 内子町(現本社)で精肉店を創業
- 平成元(1989)年11月 有限会社城戸畜産設立
- 平成16(2004)年10月 キドフーズ株式会社 設立
- 経営理念
『いかに仕事を増やして皆様を幸福にできるか』(経営理念の意味:多くのいろいろな仕事を通じて従業員や取引先、そして購入していただいたお客様まで、事業にかかわるすべての皆様に幸福を。また従業員の皆さんが仕事を通じて達成感を味わい、利益を還元することで幸福になるよう願っている。)
(2)障害者雇用の経緯
地域の障害者支援団体に協賛している商工会メンバーからの申し出により、平成20(2008)年に初めて特別支援学校の体験実習を受け入れた。その時の実習生の就労意欲の高さや真摯に技能習得を目指す姿が、人事担当者が持っていた障害のある人の就労に関する既成概念を払拭したことから始まり、一気に障害者雇用の気運が高まった。
その後当時、授産所と呼ばれていた施設や役場の障害福祉課からの推薦で障害者雇用が実際に始まった。
2. 障害者雇用の取組
(1)障害者雇用の取組
障害者雇用に向けて、障害者職業センターや雇用した障害者が利用していた福祉サービス事業所に相談をしてアドバイスを頂いた。アドバイスは会社だけでなく、仕事上日々接する社員にも指導方法やコミュニケーションのとり方などについてレクチャーを受けながら、会社全体で本格的に取り組み始めた。
当時、外国人研修生の受け入れをしていた経験、実績があることから、社員の間では比較的容易に違和感も少なく、障害者を受け入れることができた。
・当社に在籍する障害者の障害種別と従事作業
| Aさん | 統合失調症 | 冷凍前の食材加工 |
| Bさん | 統合失調症 | 惣菜加工 |
| Cさん | 知的障害 | 惣菜加工と工場内衛生管理(主に清掃) |
| Dさん | 知的障害 | 惣菜加工 |
・在籍者の仕事と余暇
| 障害者Aさんの一日(仕事の内容と流れ) | 障害者Cさんの一日(仕事の内容と流れ) | |
| 食品の冷凍前に行う食材の加工をする。 主にメンチカツの生地を作り規定値にカットする。 |
ル|ティングワ|ク | 加熱前の惣菜加工をする。 惣菜加工は数十種類あるが直属の上司に確認して製造する。 |
| 近々に定年を迎える人がいてその後任として、肉のカット作業を少しずつ覚えているところである。施設から来る研修生(障害のある人)の指導もしている。 | 不定期なその他の仕事 | 揚げ物ラインの換気扇の油分を掃除したり工場内の衛生管理活動をする(清掃作業が主である)。 |
| 休日は、地域のソフトバレーチームに所属し活動している。チームを牽引するリーダー的存在(メンバーは地域の障害のある人)。 対人関係のトラブルがあると昼食時等に落ち込んでいる時もあるが、上司や社内の友人に相談し解決を模索している。 |
昼休み・休日について | 休日は実家の農業、園芸のお手伝いをしている。 昼食はラインのメンバーと談笑しながらとっている。人懐っこい性格で多くの社員から受け入れられている。 |
(2)直属上司や人事責任者の想い
- 直属上司
- ①入社直後
(気をつけていること・フォローしたこと)
食品加工業のため障害者とはいえ、工場内へ自助具となるような個人のメモやマニュアル類の持ち込みができない為、技能が定着し身体が覚えるまで丹念に根気強く指示、指導することが必要であった。障害者本人の心の負担は大きかったと思われるが、受入担当部門全体で一致協力し、声かけフォローすることで障害者も比較的速く仕事にも人間関係にも慣れることができた。
相乗効果として一人の障害者を何とかメンバーの一員に育てようと、一つの目標に向かって一丸となって取り組んだことで、障害のない社員も含め、部門メンバー相互の信頼関係も生まれ大変良かった。
- ②現在
(気をつけていること・フォローしていること)
仕事にも慣れ自信がついてきた反面、自己判断で動くことが多くなり、ヒューマンエラーが目立つようになってきた。そのため解っていることでも再確認のため報・連・相の徹底をしている。また当社には季節商品も多く、時季によっては、全員でセクション間の応援体制を取らざるを得ない時がある。よって、障害者にも自分の仕事、自分の部門の仕事だけでなく他の部門の仕事も覚えてもらう必要があり、新たなストレスになる可能性もある。特にそういう時期には体調を聞いたり出社時の顔色等を注視するなど、今まで以上に多く関わるよう心がけている。
- ①入社直後
- 人事責任者
障害をオープンにできる人とクローズにしたい人が同時に入社した時のことであるが、当然のことながら社員間の情報に偏りが生まれた。そのためクローズにしている人に対しては担当部門全体が対応に萎縮し、ギクシャクしてしまう事態となり、そのことでクローズにしている人はさらに不安になるという悪循環に陥った。
オープンにしている人の気持ちや職場での状況を充分に確認、把握した上で、クローズにしている人に対し『オープンにすることで就労環境が改善される』ことを入念に説明した上でオープンにしてもらうこととした。このことを契機に本人も気持ちが楽になり、目に見えて安定してきた。職場全体が安定したことは言うまでもない。
また、当社の事業はワークシェアリング事業体系であり、季節商品を扱うことも相俟って配置転換や応援作業も多くある。その都度、周知理解を求めるようになれば個人情報の流出が懸念されることから、障害のオープンではなく性格のオープンと定義を変えて伝えるようにしている。クローズでありながら、この人の性格特性として関係者に周知することで、充分な理解を得られるようになった。本人に対して事前の説明を行なうことは勿論、必要不可欠なことである。
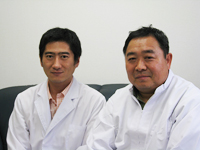 人事責任者(塩崎さん:左)と城戸社長:右
人事責任者(塩崎さん:左)と城戸社長:右
3. 現状の問題点と今後の課題、執筆者所感
(1)現状の問題点と今後の課題
- 障害者に求めたいこと
城戸社長と人事責任者の塩崎さんの思いを伺った。
「細かいことはさておき、1つだけ『障害があるから・・・』と、ネガティブになってしまうことはないだろうか?あくまでも『私は、税金を収めている社会人である』と、ポジティブに社会人としてのプライドを持って欲しい。」
「何事も障害があるからと言い訳にしないでほしい、一人の立派な社会人としての自覚をもってほしい。社員が困っている時、会社はできるだけのことをしたいと考えている。会社が困っている時は助けてほしい。そういう意識を少しだけ持ってほしい。」
- 会社として考えること
製造業は直接的にお客様とのやりとりがなく障害のある人に限らず、一般社員も達成感や満足感を得ることが難しい仕事ではないかと思われる。
そんな就業場所において、多様性のある創造力や問題解決への柔軟性を持ち、仕事と生活の調和の中で達成感を築き上げていってほしいと願っている。
キドフーズ株式会社はファミリーフレンドリーを今後のテーマとしていくつもりである。この考えを障害者にも障害のない人にも是非とも理解していただき、全員が長く定着できる企業になりたいと願っている。
特別支援学校の生徒の体験実習受け入れの経験や、5名の障害のある人の雇用経験から、『障害者が長く安定して働き続けるには、仕事の技術技能の習得もさることながら、段階的な就業支援により様々な環境への耐性づくりが必要なのでは?』と考え、平成22(2010)年3月より就労移行支援及び就労継続支援A型、B型の事業所を別法人にて設立した。
別法人にしたのは、障害特性や技能、その人の住居地域によっては当社だけでなく異業種、他業種への進路にも移行することができる公益性を保ちたいためである。
そういった環境の中で当社を選択していただけるなら、今後も積極的に受け入れ増員して行く考えである。
(2)執筆者所感
取材に当たって、Aさんへのインタビューも行った。次のような質問をしたところ、Aさんからは笑顔を絶やさずはきはきと答えが返ってきた。
- 仕事はどうですか?楽しいですか?
5年目を迎えました。バンドソーの仕事(冷凍ミンチカツの原料肉のカット)を任されています。ある程度、自分の判断できるようになり、時間内に目標ができたり、出来高が多く褒められたりすると嬉しく満足感があり楽しいです。今では関係施設から来る実習生の指導もするようになりました。とても充実しています。」
- 夢、希望について
「近々誕生日を迎え、36歳になるので、ここでの仕事で生活基盤をしっかりとして、結婚したいと思っています。生活基盤をしっかりしないと来てくれる人もいない、だから頑張りたいですね。仕事が大切だから日頃から体力づくりやストレスをためない様に気をつけています。悩みごとができたら、友人や会社のスタッフにも相談したりしています。最近では社長の奥さんにもメールで相談し、悩みを聞いてもらいアドバイスをもらいました。悩みが解決したり、癒されたりして、皆さんのおかげでストレスがたまらない良い状態が続いています。」
 インタビューを受けてくれたAさん
インタビューを受けてくれたAさん 生産終了後の機械清掃作業中のBさん
生産終了後の機械清掃作業中のBさんAさんの上司に伺うと「いつもどおりに仕事をしている」らしいのだが、インタビューの後のせいか、自信に満ちた堂々とした仕事ぶりで頼もしく見えた。工場の中は、入り組んでおり、一目見ただけでは物の流れや人の動き等が良く見えない。しかし、私語などはなく、食品工場らしく皆さん、清潔な制服・制帽・マスク着用で整然と仕事をしていた。
見学の際、この人がBさんです、と紹介された。黙々と作業終了後の機械の洗浄作業に精を出していた。落ち着いた作業振りであった。AさんもBさんも職場に溶け込み一人前の作業者として頑張っているのであろう。
当社の工場と隣接して就労移行支援及び就労継続支援A型、B型の事業所がある。このA型事業所内で最近、利用者同士が結婚したという。会社としては子供ができるまでに何とかご夫婦のどちらかでも、一般就労に移行し、キドフーズで働いてもらえたらと考えておられるようだが本人達にあまり欲がなく、やきもきされているようだ。いずれにせよ、社長や人事責任者のファミリーフレンドリー企業を目指す暖かい気持ちがひしひしと伝わってきた。これからも地域ニーズに呼応した障害者雇用に充分期待が持てる、と確信した取材であった。
雇用支援業務担当 遠山 悦郎
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











