飲食店の店舗数を増やしながら、障害者雇用を安定させている事業所~障害者への周囲の環境を変える想いで出発~
- 事業所名
- 社会福祉法人シンフォニー
- 所在地
- 大分県大分市
- 事業内容
- 障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)に基づく就労移行支援、就労継続支援B型、就労継続支援A型、地域活動支援センター事業
- 従業員数
- 法人全体 143名
- うち障害者数
- 法人全体 46名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 40 喫茶・レストランの接客・厨房業務、メンテナンス業務 精神障害 6 喫茶・レストランの接客・厨房業務、メンテナンス業務 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観
|
1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
社会福祉法人シンフォニーは、平成3(1991)年に障害者の小規模作業所から事業を開始し、現在では大分市を中心に16の事業所を展開している法人である。事業開始から、主に知的障害のある方への関わりを「まちで働く・まちで暮らす」を原点に活動を展開し、平成10(1998)年には大分市が中核都市となって初めての社会福祉法人として認可を受けた。
翌年(平成11(1999)年)4月にデイサービスセンターと通所授産施設の合築施設を開所し、以来、様々な障害者の地域生活支援に取り組み、平成18(2006)年には障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)による新事業体系にも早くから移行し、さらに活動の範囲を柔軟に拡大させ続けている。
平成8(1996)年に小規模作業所として開業した喫茶店「ネバーランド」(現在は就労継続支援A型事業所)は、大分市の中心街にある「コンパルホール」という大分中央公民館や大分市民図書館が入る複合施設の2階にある。
ネバーランドのオープンから17年経った現在(平成25(2013)年)では、就労継続支援A型事業としての当法人の雇用の場としては、このコンパルホールだけではなく、県庁や市役所、大学の中など、7ヶ所で飲食店事業を展開している。また、喫茶店運営だけでなくビルメンテナンス事業、リサイクル事業にも拡大している。障害者本人の得意分野を活かすためにも、業種を選べるように工夫している。その概要は次のようである。
- 飲食店事業
○「ネバーランド」7事業所(コンパル店・大津町店・わさだ店・県庁店・大洲店・芸文短大店・看護科学大学店)
○客席数 40~52席
○1店舗あたりの従業員数 約8名(内、障害者約4名)
- ビルメンテナンス事業
○「コンチェルトメンテナンス」1事業所
○スタッフ12名(内、障害者10名)
○病院、介護施設、マンション等の清掃 他
- リサイクル事業
○「コンチェルトリサイクル」1事業所
○スタッフ7名(内、障害者6名)
○清掃工場での缶・ビン・ペットボトル選別作業
コンチェルト(メンテナンス、リサイクル)は、全16名の従業員(利用者)と4名の職員がその日の勤務に応じて、分かれて勤務している。
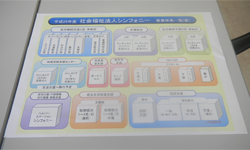
シンフォニーの事業を図で整理されている資料
|
(2)障害者雇用の経緯
創設者である村上和子理事長は、障害者の小規模作業所を立ち上げるために他の施設を見学していくと何かが違うと感じていた。見学した施設では職員と障害者だけで作業をこなしており、地域に出ることもなければ地域の人との関わりもない。障害者が世間から隔離しているように感じた。この状況であれば、障害者が町にでることを億劫に感じ、自立の感覚が養えないのではないだろうか。そうであれば、障害者が地域で普通に活躍できる場所を作らなくてはとの強い想いにより、障害者の就労に関わる方向性を見出していくことになる。そして、障害者は施設の中で基礎的な作業能力を身につけることだけではなく、就労訓練の場自体を町の中で行うことが大切であると考えるようになる。
19年程前、あるうどん屋の店主から障害者の皆さんでうどん店を開業してみないかと勧められた。ところがそれを聞いたある母親が「障害者が作ったうどん屋なんて、だれが食べに来るもんね」と言った。身近にこういった偏見や誤解があるのなら、このことを解消しなければと考え、人が行き交う場所で障害者が活躍できる飲食店を運営したいと考えるようになる。それから数年後、市報の中に市営コンパルホール内での喫茶店経営の募集をみつけ、早速、説明会に参加した。
業者選考の説明会には40社以上の競合相手がおり、出席者のほとんどが実際に飲食店を運営している業者であった。しかし、経験のない当法人が事業計画の審査やヒヤリングの結果で選ばれることになった。この時に選考者から言われたことを当法人の書籍の中に「『今回の決定に当たり一言申し添えます。福祉だから選んだのではありません。そこを間違えないで下さい』と念を押され、それを聞いてむしろ嬉しくなった」と書かれている。


2. 取組について
当法人の障害者雇用の場(就労継続支援A型事業所)として、ネバーランド(喫茶業務)とコンチェルト(清掃・リサイクル業務)の二つがある。それぞれがさらに小さなユニットに分かれて就労に取組んでいる。ネバーランドの喫茶・レストラン業務は、市内7カ所の公共施設や大学内にあり、事務所を置いている店舗にサービス管理責任者を配置し、各店舗には生活支援員や職業指導員が直接の支援に当たっている。
毎週1回朝の1時間、県庁店に各店舗の責任者7名(サブリーダー)とサービス管理責任者が集まり、利用者支援やメニュー、仕入れの相談、ヒヤリ・ハットの報告などの業務連携を図っている。
コンチェルトのリサイクル部門の従業員は、職員と一緒に大分市の清掃工場に隣接している「リサイクルプラザ」において缶・ビン・ペットボトルの手選別作業を、清掃部門の従業員は契約先の病院やマンションなどへの清掃作業を行う。清掃作業は4つのユニットで実施する。請け負った業務内容や天候により通常の体制では対応できない場合には、2つのユニットが連携して共同で業務を分担して実施することもある。リサイクルプラザにおける取組は、自法人だけでなく他法人との協働で行われている。
(1)ネバーランド(喫茶・レストラン業務)における取組
- 徹底した衛生面管理
店内に入った印象は、全体的に明るく清潔、よく整理整頓がなされていると感じる。ネバーランドでは5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を意識して、日常の業務にあたっている。テーブルや食器に汚れがないだけではなく、埃も見当たらず、床もピカピカに磨かれている。日々、この状態を維持しながらサービスを提供している。
- お客様の状況に応じた商品の提供
ネバーランド県庁店のお客様は、県庁職員が大半であり、お客様の昼休みの時間内での商品の提供となる。そのため、短時間でも食事が提供できるようにフードコート形式を採用し、さらに時間短縮のために、昼時のみ各テーブルにお茶やポットとグラスを置くなど、お客様の状況に応じて柔軟にサービスを提供している。
- 失敗を繰り返さないミーティング
ネバーランドでは、失敗を繰り返さないように「ヒヤリ・ハット」を徹底している。従業員が火傷などの事故に遭わないように防止することを始め、ミスにつながり易いことなどを確認し合い、その都度、速やかに対策を練っている。その中からいくつものルールができているが、そのポイントはわかり易く、こういうことかと気づかされる内容である。
今後は、失敗を前向きに工夫して改善につなげた内容を冊子にすることも検討されている。
- チームワークを重視する小規模、少人数の店舗
ネバーランドでは各店舗従業員7名~11名のチームの中に障害者4名~6名を配置し、ユニット支援を行う。小人数であると、分からないことがあれば職員や先輩の利用者に聞きやすく、支援者もよりきめ細かい支援が可能になり、個々の利用者の強みや課題を把握しやすくなる。また、人間関係等でその店舗で働くことが現状で困難な時も、他の店舗であれば人間関係を含む環境を新たにして働くこともメリットである。
- ミニ研修会の実施
ネバーランドでは、月に2回は衛生面や職場のルールを確認し、他の飲食店を視察する等の研修会を実施している。障害者が研修会で真剣に聞く態度には感心させられると理事長は話す。
  商品との引き換えの番号札と商品(写真はとり天定食)
|
(2)コンチェルトメンテナンスによる取組
コンチェルトメンテナンスでは、事業を始める前にメンテナンス会社に相談することから始め、窓拭きなどのできそうな技術を習いはじめた。
まずは障害があっても使いやすいプロ用道具の購入、取り扱い方法を学び、実際の清掃作業を経験した。さらにメンテナンス会社の社長は、コンチェルトで受託できそうな清掃作業を紹介し、見積もりや契約の方法なども助言してくれた。一方で、コンチェルトでは技術が足りない作業や高所のガラス窓の清掃を受注した時は、メンテナンス会社に再委託して協同することで、できないことを乗り越えてきた。
その後、支援員が草刈機を使えるようになると、除草作業の仕事が入ってくるようになる。除草作業はガラス清掃と異なり機械の使用から危険が伴うため、ゴーグルを必ず着用し、草刈り機の付近には絶対に近寄らないなどの安全対策に留意している。
最近では、個人住宅の庭の草取りの仕事も増え、手で根っ子から抜くため「草が生えにくい」と喜ばれリピーターも増えてきている。これらは、障害を持つ従業員の真面目な作業態度や手作業による丁寧な仕事が信用を築いたと言える。
(3)コンチェルトリサイクルによる取組
平成19(2007)年、大分市と由布市の缶・ビン・ペットボトルのリサイクル工場「リサイクルプラザ」が建設されるにあたり、大分市内にある社会福祉法人が連携して多人数を必要とする作業に協働しようと結成された「障害者就労支援協議会」がリサイクル業務を受注することにより生まれた事業である。
この「リサイクルプラザ」は早朝から夜間まで稼動するセンターのため、一つの事業所では仕事量が多すぎて委託をするにも困難な状況であったが、市内5ヶ所の社会福祉法人が組織を作り、協働することで、1事業所では困難な仕事を受注することができた。総勢60人が交代で昼と夜のリサイクル業務に従事できるようになった。
3. 取組の効果、今後の展開
(1)取組の効果
平成8(1996)年にオープンした「ネバーランド」のコンパル店には、オープン当時からの従業員が多く、勤続年数が17年(平成25(2013)年現在)になる。長年、障害者が雇用される環境を維持するには、様々な経営的な工夫があるかと思われるが、その要因のひとつに障害者の優れたところを伸ばし、全力で頑張れる環境や支援があったのではないだろうか。
また、当法人では企業等に働くことについても積極的に支援しており、企業等に就職した後も当法人の行事に参加できる仕組みがある。就職して、またはリタイヤすることになっても、当法人との関わりが継続されるという安心感から、採用試験にチャレンジする人が多い。
(2)今後の展開
事業開始から22年(小規模作業所時代も含む)になる当法人では、数十名の障害者が福祉的な支援を受けながら就労を継続しているが、様々な年代の障害者が働くため、就労についての本人の希望も「いつか企業等で働きたい」、「このままシンフォニーで頑張りたい」あるいは「企業等に働いてみたけれども、いつかシンフォニーに戻りたい」など様々である。
当法人は障害者のそういった「働きたい」という希望を閉鎖的な環境にしまい込むことなく、地域の中において、訓練の場、雇用継続の場を創出および維持し、リタイヤされた方の再出発の場にもなってきた。その過程において、障害者の働きたいという想いを大切にし、その想いが継続することで本人も周囲の人も変わった。特に周囲の人は、障害者本人の適性は様々であり、ほとんどの障害者が得意な分野を活かせれば、手を抜くことがない人ばかりであると認識するようになった。
これからも当法人は、障害者の雇用が継続できるように経営の安定と障害者雇用の推進のバランスを図り、多くの人との出会いをヒントに一人ひとりの障害や特性に応じた就労のスタイルを確立し、さらに障害者が働き易くなる為の住居や余暇、移動に関する支援事業にも取り組まれていくと思われる。
参考文献
社会福祉法人シンフォニー、平成20年度障害者保健福祉推進事業『まちで働く・まちで暮らす』、5-18頁、2009.3
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











