チャレンジド業務での事業所の挑戦
- 事業所名
- 医療法人社団敬愛会(佐賀記念病院・シルバーケア佐賀・シニアケア佐賀)
- 所在地
- 佐賀県佐賀市
- 事業内容
- 医療・介護・福祉事業(病院・介護老人保健施設・有料老人ホーム)「(除外率設定業種)」
- 従業員数
- 464名
- うち障害者数
- 6名
障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 2 介護、看護助手 肢体不自由 内部障害 1 医師 知的障害 2 看護助手(補助) 精神障害 1 看護助手(補助) 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次
 事業所外観 |
1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯
(1)事業所の概要
平成元(1989)年7月、医療法人社団敬愛会を設立、同年8月に前身の内田病院から内田記念病院(院長(当時):内田康文)へ名称変更となる。平成15(2003)年3月佐賀記念病院と名称も新たにして現在地へ移転した。その時のベッド数が158床であった当事業所も平成18(2006)年1月には177床に増床した。
平成21(2009)年5月には有料老人ホームであるシニアケア佐賀を、平成23(2011)年10月には介護老人保健施設であるシルバーケア佐賀を、それぞれ当事業所に隣接して移転・開設した。
(2)事業所の特徴
当事業所では、「佐賀に住んでいてよかった」と思ってもらえるための地域医療を目指している。自分が暮らしている町で治療を受けたいと誰もが願う当たり前のことを実現するために、地域の医療や福祉、保健、病院同士の連携を大切にし、人と環境、医療と地域が調和することで一人ひとりの安心を提供している。
そのために、当事業所は4つの理念(「4C」)を掲げている。
- 【Certain】
「信頼できる」という意味で、患者や他の医療機関からも信頼される病院を目指す。
- 【Clean】
院内の清潔さだけではなく、ここで働く人すべての内面の美しさ(言葉遣いや身だしなみ)もきれいな病院を目指す。
- 【Comfortable】
「快適な」「居心地のよい」という意味で、心身ともに安らげる病院を目指す。
- 【Convenience】
コンビニという言葉のイメージそのままに、誰もが気軽に訪れることができる病院を目指す。
また、診療科目が多いことも当事業所の特徴である。
(3)障害者雇用の経緯と背景
当事業所で最初に雇用した障害者は、今はもう退職しているが20数年前に雇用した身体に障害のある薬剤師であった。その後、平成17(2005)年に身体障害者を2人雇用しているが、いずれも国家資格を持った医師と介護福祉士である。障害者雇用の必要性は理解していたものの、当事業所としては、資格を持っている者や病院内で行っている業務が障害のない者と同程度にこなせる者を希望していたことから、障害者雇用がなかなか進まなかった。
障害者雇用率を達成するためにも、新たに職域開発をして雇用対象となる障害者の範囲を広げなければ障害者雇用は進まないと考え、ハローワークに相談したのが平成26(2014)年2月のことである。看護助手の補助業務を新たに視野に入れて、雇用の取組みを進めていくことにした。
本事例は、その取組みについて紹介するものである。なお、今回の取材では、人事担当である鈴木登統括事務部長、看護部の総責任者である光武弘子看護部長、教育的立場である木塚千春看護師長に聞いた。
2. 障害者雇用の取組み内容
(1)雇用に至るまでの状況
- 事業所見学
当事業所からの新たな方向での障害者雇用の相談を受けて、ハローワークは地域の障害者就業・生活支援センターと就労移行支援事業所等に事業所見学実施の情報提供を行った。その結果、2回実施された事業所見学に3機関の登録者や利用者が10数名参加した。
その際に、光武看護部長と木塚看護師長から、食事の配膳・下膳、お茶出し、エプロン洗い、清拭用のタオルの準備、清拭後の片付け、病室の環境整備、ベッドメーキング、ポータブルトイレ掃除、入院する患者のベッドの準備、患者の案内等の業務のなかで、障害に応じてできることを行って欲しいという説明を行った。
当事業所としては6人程度を雇用し、2階~4階の入院病棟において各階専任で上記の業務を行うことと構想していたが、見学会に参加する障害者の障害種別や程度を予め限定しなかったこともあり、誰がどのようなことができるのかも分からない状況での不安なスタートであった。
- 職場実習から雇用まで
事業所見学後、当事業所で職場実習をしたいと希望したのは4人であった。すぐに当事業所とハローワーク、障害者就業・生活支援センターの3者でケース会議を行った。ケース会議では希望した4人の障害特性を確認し業務の選定を行った。実習の最初の業務は病室の環境整備、患者さんへの清拭後の片付け(タオルを集配場所へ持って行く、洗面器を片付ける)を行わせ、状況を見ながら、清拭用のタオルの準備、ロールシーツ(シーツの下に敷くディスポシーツ)の準備といった業務を増やしていくことにした。
一人が途中で辞退したものの3人(知的障害:2人、精神障害:1人)が予定していた1週間の職場実習を終え、全員から「就職したい」との意向を確認し、3人共にトライアル雇用となった。
(2)業務内容と勤務状況
業務の順番や組み合わせに関しては、職場実習中もトライアル雇用期間中もハローワークや支援を担当した障害者就業・生活支援センターの担当者と相談しながら試行錯誤を繰り返した。現在は2階~4階の入院病棟のうち主に4階の入院病棟で、次のような業務を行っている。
- 業務内容
- 食堂内での作業
エプロン洗い、テーブル拭き等 - 清拭後の片付け、清拭用のタオルの準備
- ロールシーツの準備
- ポータブルトイレ掃除
トライアル雇用期間中に追加したもので、4階に加え2階も行うようになった。 - 病室の環境整備
ベッド柵やドアの取っ手等、よく手が触れる部分(上拭きと呼ばれる)とベッド周囲の柵の下やテレビ台の下等(下拭きと呼ばれる)の拭き掃除、各病室入口の消毒液設置棚や廊下の手すり拭き。この作業は、初めは重症患者の部屋は行っていなかったがトライアル雇用期間中に追加し、4階に加え2階も行うようになった。
- 食堂内での作業
- 勤務状況
雇用された3人が最終的にどの程度までの作業ができるのか、当事業所が望んでいるところまで進むのかも分からなかったため、無理のない範囲から開始することにし、3人と当事業所、支援機関で話し合って、1日4時間・週5日間の勤務から行った。ただ、3人共に長く働くことを希望していたので、状況を見ながら勤務時間を延長していくことにした。勤務時間が延びて1日6時間勤務になったのは今のところ1人である。それ以外の2人は、もっと働きたいとの意欲はあるが、腰痛等体調不良があるため様子を見ている。
(3)働く障害者の様子
- 3人のチームワーク
雇用当初は前述の全ての業務内容を3人一緒に行っていた。3人一緒に行うようにしたのは、看護助手によるシーツ交換等の作業は、効率良くできることから2人一組で行うことが多く、同じようにチームを組んだ方が良いだろうと考えたからである。
例えば、上記の病室の環境整備の業務を実施する際、どの病室が終わったかどうかの確認のためにチェック表を用意した。ケア中や面会中の病室は後に回しているが、このチェック表のおかげで、互いに確認し合い忘れることなく作業を進めていくことができていた。このチームワークはトライアル雇用から常用雇用へ移行するかどうかの話し合いの際に高く評価された。
今では作業にも慣れ、本人たちからの希望もあり、病室の環境整備は効率良く作業を進めるためにペアで行っているが、他の作業は単独で行っている。
- 障害者自身の感想
- ①Aさん:50代女性、精神障害
ひとり暮らしであるため、「生活があるから、頑張らないといけない。体調を見ながら頑張っていきたい」と話している。患者から話しかけられるのが好きで、笑顔で会話をしている。廊下でリハビリをしている患者とすれ違うと、「リハビリ、頑張って下さい」と声をかけている。
- ②Bさん:50代女性、知的障害
「最初は、病院での仕事と聞いて難しい仕事をしないといけないというイメージがあった。事業所見学の時にたくさんの仕事を言われて不安だったが、自分にできることを与えてもらって良かった」と話している。目標は「60歳までは続けること」であり、最後の職業生活だと思って就職活動を行った。3人の中では「一番年上だから」と張り切っており、他の2人からも頼りにされている。
- ③Cさん:40代男性、知的障害
「分からないことがあれば看護師さんや助手さんが優しく教えてくれるので、困ることはない。体も慣れてきたので良かった」と話す。病室が多い為に環境整備では目標を決めて行っているが、常に目標以上の成果を目指して丁寧に意欲的に取り組んでいる。
 環境整備は上拭きと下拭きに分かれてチームプレイ
環境整備は上拭きと下拭きに分かれてチームプレイ - ①Aさん:50代女性、精神障害
- 現場の体制作り
3人それぞれのできるところを評価したり、3人の希望や意見を聞いたりと、当事業所の中で調整役となっているのが木塚看護師長である。3人から体調の相談や通院等でのシフトの相談を受けたり、業務の進捗状況の確認、業務全体の流れを見ながらの業務調整等のほか、鈴木統括事務部長や光武看護部長への相談、現場への指示、支援機関への連絡等、3人が安心して働けるような環境や体制作りにも熱意を持って取り組んでいる。「新しいシステムを作る時は大変なこともある。でも、きっと大丈夫」と言い切る。
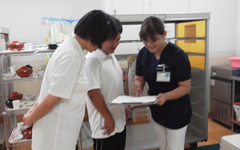 木塚看護師長との業務の確認
木塚看護師長との業務の確認
3. 取組みの効果、課題と今後の展望
(1)取組みの効果
今回雇用した障害者が担当した業務は、当事業所の中で「チャレンジド業務」と呼ばれている。チャレンジド業務を開始するに当たっては、各病棟の看護師長へ周知を図り、3人が気軽に話がしやすいようにと看護助手の中にキーパーソンを置くようにした。
「最初は、どう接して良いか分からないと思っていたが、コミュニケーションを取ることは可能であることが分かった」、「無理をさせないようにと思い、環境整備はやれる所までで良いと言ったことが逆にプレッシャーとなり、ここまでするようにと具体的に指示を出した方が良いことも分かった」、「指示された仕事は最後まで行い、報告できることも分かった」、「3人の働きぶりを目の当たりにして、自然と現場のスタッフの見方が変わっていった」と光武看護部長と木塚看護師長は語る。最初の頃の現場の戸惑いや不安が障害者への理解に変わり、共に働くという意識が芽生えたことの表れである。
また、「専門職が行う本来業務と他に任せられる業務に分けたことで、本来業務に集中できるようになり、患者のベッドサイドに行ける時間が増えた」、「チャレンジド業務の中に病室の環境整備を位置付けたことで、清潔な環境がより維持できるようになった」とも言われる。サービスの向上にもつながっていることが窺える。
(2)課題と今後の展望
- 当面の課題
当事業所としては、今回の取組みから各階病棟病室の環境整備を、主として障害者に担ってもらいたいとより強く考えるようになった。最終的には、雇用を増やしてチャレンジド業務の体制を拡大し、雇用も体制も定着させることが目標である。取材中も聴覚障害者が職場実習を行っており、その後トライアル雇用となった。現在、ハローワーク、障害者就業・生活支援センターに加え、障害者職業センター(ジョブコーチ支援)とも連携しているが、今後は障害者雇用が拡大するにつれて障害種別も多様化することが予想されるため、当事業所の受け入れ体制の強化と、雇用の定着につながる働きやすい環境作りがさらに求められるであろう。
- 今後の展望
佐賀県における障害者雇用の推移を見ると、近年、特に医療・介護分野への就労割合が高くなっている。一方で、医療・介護分野の業務は主に専門職が行うという性格上、障害者雇用のための職域の切り出しが社内的に理解を得られにくいという状況もある。
鈴木統括事務部長は「障害者雇用を拡大できる可能性はあり、障害や作業の内容によって事務業務や厨房での業務も考えられる」とのこと。「看護業務の中で、看護師が測定した血圧等の入力をしてくれる人がいたら助かる」と話すのは光武看護部長。チャレンジド業務と名付けられた今回の障害者雇用への取組みは、確実に当事業所の自信につながっている。今回のチャレンジド業務での取組みが当事業所における障害者雇用の基盤となり、他の部署での職域開発といった次なる挑戦へつながっていくことを期待したい。
障害者就業・生活支援センターワーカーズ・佐賀 生活支援員 船津丸 涼子
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











