「人を活かせないのは、会社の責任です!」
—障害のあるなしにかかわらず平等に成長の機会あり—
- 事業所名
- 株式会社カシマ
- 所在地
- 茨城県かすみがうら市
- 事業内容
- 部品加工メーカー(精密プレス板金・金型設計製作・溶接加工全般)
- 従業員数
- 58名(平成26(2014)年12月末現在)
- うち障害者数
- 9名(うち重度障害者1名、平成26(2014)年12月末現在)
※人数のカッコ内は重度障害者で内数障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 3(1) プレス・洗浄・検査 精神障害 6 プレス・梱包・スポット溶接・ピッキング・パイプ加工 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次
 事業所外観 |
1. 事業所の概要、障害者雇用の理念と経緯
(1)事業所の概要
株式会社カシマ(以下「当社」)は、株式会社ノーリツのグループ会社である株式会社アールビーの100%出資会社である。部品加工メーカーであり、電気部品、編機部品、自動車部品、カメラ部品、建築金物のプレス加工、ボイラー部品の製造組み立て、電気溶接、ベンダー加工、NCタレットパンチングプレス加工を行っている。
(2)障害者雇用の理念
親会社の株式会社アールビーは、平成20(2008)年の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用事例リファレンスサービスに「すべての人が力を出し切れる平等の社会」という内容で紹介されている。
当社の障害者雇用を一口で言えば、アールビーと同じ「平等」となる。知的障害者が3名、精神障害者が6名いるが、知的・精神の色分けもなく、そういうことを社員一同意識したこともない。
当然ハンディキャップ部分は認識しているが、「障害のない人と同じ働きをしてもらう」という前提で雇用を進めている。また、障害のあるなしに関係なく、個性・特性・得手不得手に合った仕事を探し、指導をしていれば、誰でもピッタリの仕事に巡り合えて成長すると、自信を持って取り組んでいる。
(3)障害者雇用の経緯
障害者の雇用は、平成22(2010)年に特別支援学校の生徒の現場実習を受け入れることから始まった。当初は社会的な責任を果たすという意味合いもあったが、障害者に接して個人個人の長所を見ていくうちに、ハンディキャップはあるが適職に配置できれば障害のない人と変わらない仕事ができるのではないかと思うようになった。
雇用の流れは、特別支援学校生徒の現場実習を経た卒業後の雇用と障害者就労支援センターからの推薦者のトライアル雇用の2通りである。現場実習の延べ2週間~8週間、トライアル雇用の3か月間、いずれも実際の現場でお互いを理解することができ、安定した雇用につながっている。
2. 取組の内容
(1)偏見、先入観がない
残念ながら多くの会社では、障害者に偏見、先入観は付きものという感じがある。しかし、親会社のアールビーでも当社でも「全員が平等」という認識で一致しており、偏見、先入観のカケラも見当たらない。偏見、先入観をなくすよう特別配慮しているわけではなく、ごく自然にこれができていることに優しさと思いやりを持った人たちの姿が浮かんでくる。
後述5項の「アンケート結果」にも、みなさん満足して働いていることがはっきり出ているが、偏見、先入観がないということが大きな理由になっていると思う。
(2)ローテーションなど、人事面でカバー
この仕事ができないのであれば、ほかの仕事もダメだろうという考えは捨てる。能力がないのではなく、その人に合わなかっただけのことであり、別の仕事ならその人に合うかもしれないと考え実行している。そのためには、現場の全ての仕事を知ることが大切である。その人の長所や障害を理解し、現場を熟知していれば、必ずピッタリの仕事は見つかると言う。
ア.複雑な作業から単純継続作業へ
特別支援学校のAさんは、バリ取り作業で実習し、入社後は、スポット溶接加工作業を担当した。
Aさんは礼儀正しくまじめであるが、変化に対応する能力が不足していた。しかし、Aさんが担当したスポット溶接加工は、製品ごとに溶接する位置が違うなど、複雑な作業を20~30種類もマスターしなければならない。障害のあるなしに関係なく大変な作業である。7~8か月間、粘り強く努力したが、障害のない人の3割程度の作業量しかできなかった。
作業効率が上がらないのは、本人の能力というより、仕事の選定が間違っていたと考え、梱包作業への配置換えを行った。梱包作業といっても、梱包するだけでなく、ねじ加工、組付も行う。その上、4種類の部品を正しい順序で梱包しないと、市場に出てからクレームがついてしまう大変責任の重い仕事である。いかに粘り強く間違いのない作業をするかがポイントであるが、覚えなければならない作業の数は、スポット溶接加工に比べれば、かなり少なく負担も軽減した。
ジョブコーチを交えてマニュアル(手順書)を作成し作業指導をしたところ、梱包作業がAさんの個性に合っていたのだろう、僅か3日ほどで完璧にこなせるようになった。信じ難いほど早期に仕事をマスターした上、この5年間、市場クレームはゼロである。
Aさんは、仕事をマスターしたことが自信となって、普通自動車の免許も取得し、会社行事にも積極的に参加するようになり明るく元気になった。スポット溶接加工を担当していたころに比べると別人の観があるほどに大化けした。
 梱包作業 | 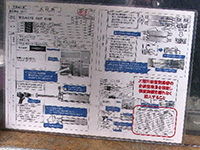 写真・図入りのマニュアル |
イ.単純継続作業から変化の多い作業へ
トライアル雇用を活用したBさんは、浴槽ライン梱包オペレーターとなったが、飽きっぽいところがあり、同じ仕事を続けることが苦手であった。そこで変化の多いパイプ加工にローテーションした。この作業は、パイプに穴を開ける仕事であるが、製品ごとに穴を開ける場所や数も異なり、神経を使う。しかし、変化を好むBさんにはピッタリの仕事で、すっかり自分を取り戻し、活き活きと作業に取り組んでいる。
 パイプ加工作業 |  洗浄作業 |
ウ.補助作業から1人作業へ
Cさんは、洗浄作業の補助を担当したが、洗浄カゴへの入れ方が製品により異なり複雑な作業であり、入社当初は、満足な仕事ができなかった上、無断で休むことも度々あった。
しかし、成長する可能性もあり、責任感を持たせるため、思い切って1人作業に変えてみた。7か月間、マンツーマンの指導を粘り強く続けた結果、障害のない人の8割程度の作業をこなせるまでになった。また、1人作業になったので、甘えがなくなり休みも減った。
(3)ビジュアル化されたマニュアル、ポンチ絵の活用
障害者を雇用するまでマニュアルはなかったが、仕事を理解してもらうためには、分かりやすいマニュアルが必要であると考え、マニュアル作りをスタートさせた。
写真、絵、図などをふんだんに取り入れ、どのように作業したら効率的な作業ができるか、製品不良の防止や安全な作業をするためには、どこに注意しなければならないかを一目で分かるようにマニュアルを作成し、これをテキストとして何回も繰り返し教育した。
マニュアル作りは現在も継続中で、膨大な時間がかかっているが、作業の問題点の把握、改善など障害のない人にも役立つテキストになっている。
作業する場所にもたくさんのポンチ絵やマニュアルが張ってあり、誰でもすぐに効率的かつ安全に仕事ができるようになっている。
 プレス作業 |  現場で活用されているポンチ絵 |
(4)障害者の雇用に合わせて作業を改善
ア.記憶力から目で見る仕事へ
出荷品を倉庫から引き出すピッキング作業は、1,500以上の部品の出入れがあり、個人の長年の経験、記憶力に頼っていたが、これでは障害者にはかなり難しい仕事であると、複雑な作業の仕組みを改善して障害者に限らず、誰でも簡単に作業ができるようにした。その結果、担当のDさんは、2か月の経験で障害のない人の7割の作業をこなせるまでになった。バーコードの読取りシステムを導入すれば、障害者ばかりでなく高齢者もミスのない仕事ができるようになるのではないかと、現在検討中である。
イ.工程の細分化
覚えることを少なくするため、できるかぎり工程を細分化している。細分化した工程を担当させると、より短期間に仕事を覚えることができて自信がつく。これをマスターしたら次のステップへと、新たな工程を少しずつ担当させ、担当範囲を無理なく広げている。
(5)長所を活かす
検査員のEさんは読み書きが苦手で、ひらがな、カタカナしか読めない。しかし、検査業務は目視検査であり、視力の高いことが一番の条件である。字は読めなくても、ポンチ絵をテキストにしてマンツーマンで3~4か月指導したところ、今では頼りになり欠かせない存在となっている。
(6)教育
ア.根気
教育は手順等を説明して、実際にやってもらい、根気よくできるまで何度も繰り返す。覚えるまでの時間はかかっても、体に染み込むように覚えたことは、ほとんど忘れない。
イ.コミュニケーションを取るための声かけと会社行事
コミュニケーションを取るために頻繁に声をかけるようにしている。それを証明するように、社長、工場長ともに現場で気軽に頻繁に声をかけていた。また、私たちも現場のみなさんから笑顔で元気に挨拶され、パワーをもらった。
会社行事は、一泊旅行、家族も含めた花見、バーベキュー大会、暑気払い、忘年会と盛んであり、参加率も高い。障害者のみなさんも体調に問題がないかぎり積極的に参加している。
ウ.仕事の自信が症状の改善につながる
精神障害者は、コミュニケーションを取ることが苦手な人が比較的多いが、仕事をマスターするにつれて、苦手な対人関係も克服しスムーズに会話できるようになっている人もいる。
(7)「社内満足度アンケート」の結果
障害者9名全員に最近アンケートした結果は次のとおり。勤続年数が短いこともあり、これからというところもあるが、大変満足していると考えてよいだろう。
ア. やりたい仕事をやっていますか?
5人が満足。得意と不得手の仕事があるが1名。まだよくわからないが3名。
イ. 当社で成長、自己実現できていますか?
できているが7名。これからが2名。
ウ. 直属の上司に満足していますか?
親切および評価不能(短期間の勤務)がほとんど。目下のところ問題はない。
エ. 給与・賞与に満足していますか?
満足が4名。評価されるような仕事までいっていないが5名。
オ. 仕事量が多くてきつすぎると思いますか?
「問題ない」と「慣れてくれば問題ない」が大半。「残業は2時間以内に」が1名。
カ. 当社に一体感はありますか?
;一体感がない人はゼロ。もっとストレートにものを言ってほしいが1名。
キ. 当社の将来についてどう思いますか?
安心と不安が各2名、わからないが4名。心配は親がいなくなった後の生活。
ク. 当社が好きですか?
好きが7名と大半。「これから」と「もっと自由にやりたい」が各1名。
ケ. 当社にこれからもいたいと思いますか?
思うが7名で大半。これから判断が2名。
3. 今後の課題と展望
(1)賃金と生活設計
全員、最低賃金をクリアしている。いずれは親元を離れて暮らすようになるので、希望者には一人暮らしを経験させることも考えている。
(2)家族とのコミュニケーション
家族とのコミュニケーションは不足しているとのことであるが、連絡を取らなければならないことがないだけの話であり、それだけ問題がないといえる。
ただし、障害者が長く勤めていく中で、生活環境の変化など必要性が生じる可能性もあるので、その際は家族としっかりコミュニケーションを取っていきたいと考えている。
(3)将来設計
ア.症状の変化対応
精神障害は、症状が変化することがある。目下のところは全員問題はなく、薬の服用を怠らないかぎりは大きな問題は出てこないと思われる。しかし、通院している人もいるので、健康状態については上司、仲間が気を使っていく必要がある。
イ.定年以降の生活設計
「定年は60歳、希望者全員65歳まで雇用」となっている。まじめに一生懸命やっていれば、65歳までの雇用は確保されるので、安心して働くことができる。そのためには、気力と体力の維持向上のための自助努力が必要である。また、障害がある人もない人も同様であるが、定年以降も安定した生活を送るため、今から生活設計をしっかり描けるように関わっていきたい。
代表取締役:米田一夫氏の話
「障害者のあるなしに関係なく、従業員を活かせないのは、会社が悪いと経営陣を含め幹部は思うべきです。『障害者を雇用することは大変でしょう?』という方もいますが、障害のあるなしにかかわらず仕事を覚えるまで教育することは当たり前のことです。その成長を見たときには、大変というより感動すら覚えるはずです。大切なことは、本人を信頼し、期待することだと思っており、『人間は期待されたとおりの人間になる』ということを実感しています。障害者に限らず誰でも『努力した甲斐』という達成感が必要だと思います。達成感は、自分の能力+αの負荷に付随して生まれてくると考えています。」

米田代表取締役
「人を活かせないのは会社の責任です。」 |
取締役工場長:横山正人氏の話
「障害者に対しても障害のない人と同じように、常に期待し能力を発揮するよう指導してきました。ポイントは、障害者も十人十色であり、器用な人もいますし、そうでない人もいます。ほとんどの会社には、その人に合った仕事が必ずあるはずです。一度の失敗で懲りないで、その人の個性に合わせた指導を、手を変え品を変えて続けることです。
配属が失敗したこともありましたが、あきらめずにローテーションで再チャレンジしてきました。このときは、障害者も指導者も大変だったと思いますが、それを乗り越えたとき、本人も指導者も達成感を味わうと同時に、成長を実感し、自信がついたと思います。」

横山取締役工場長
「失敗を乗り越えて成長があります。」 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。











